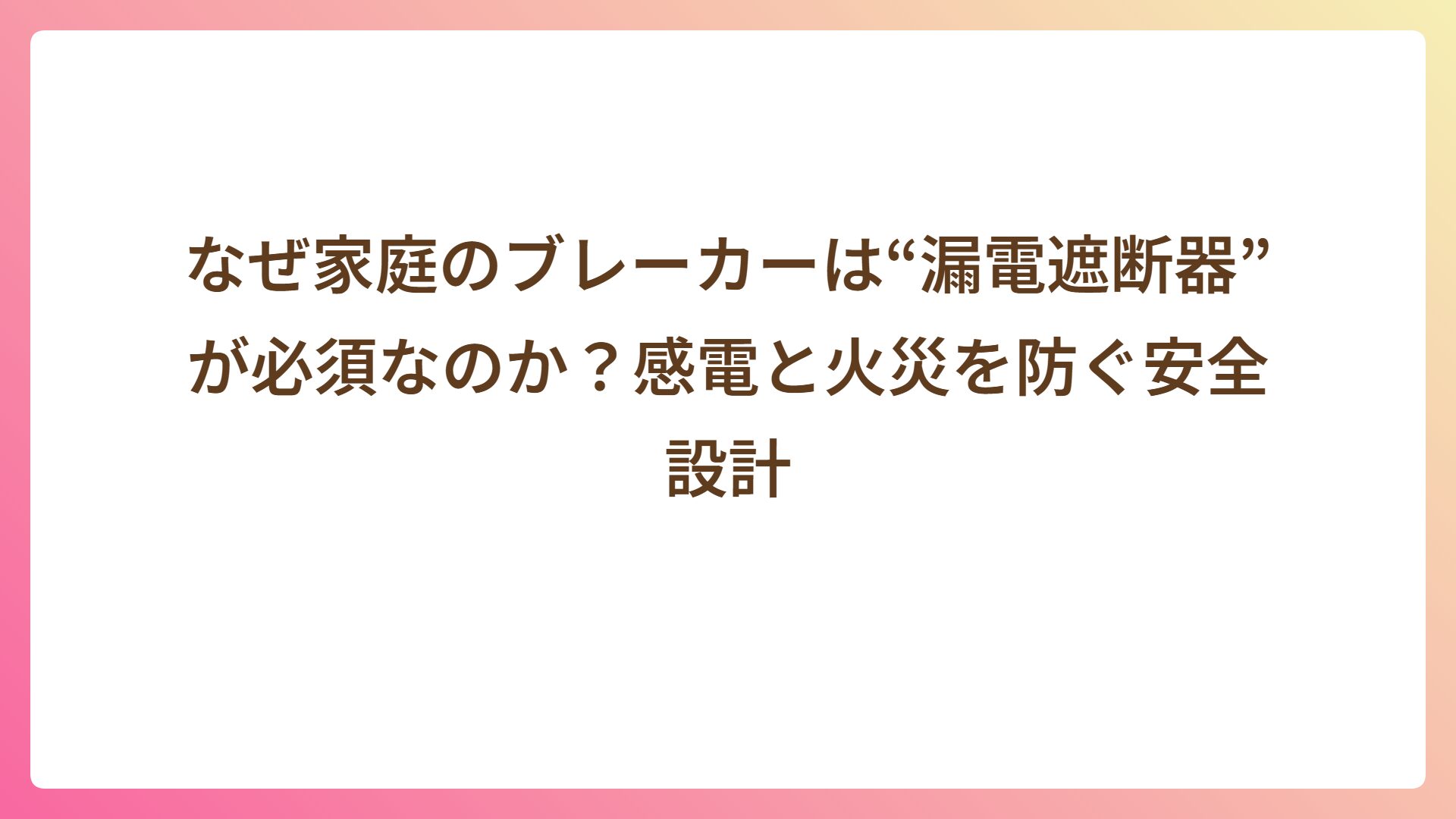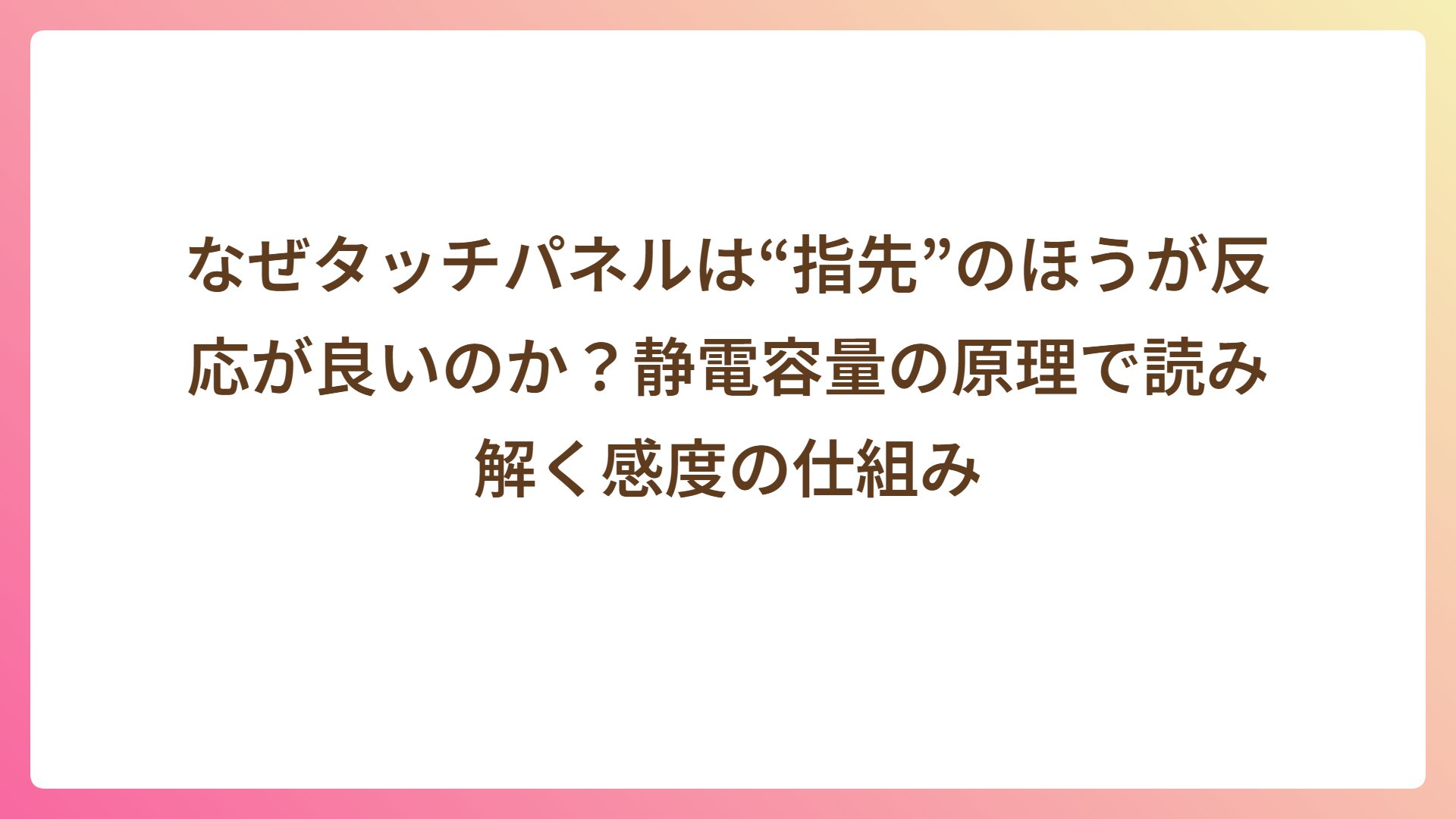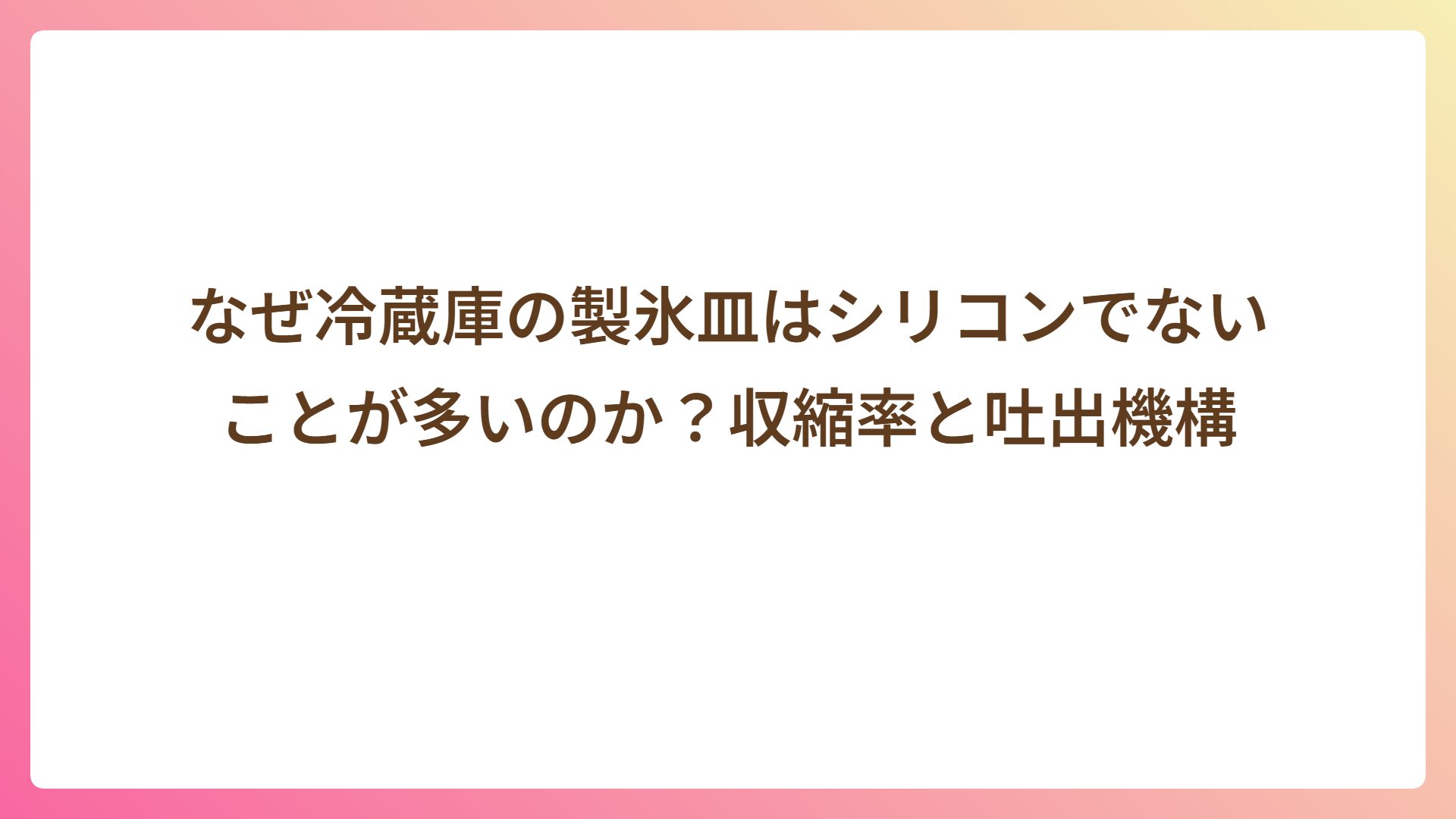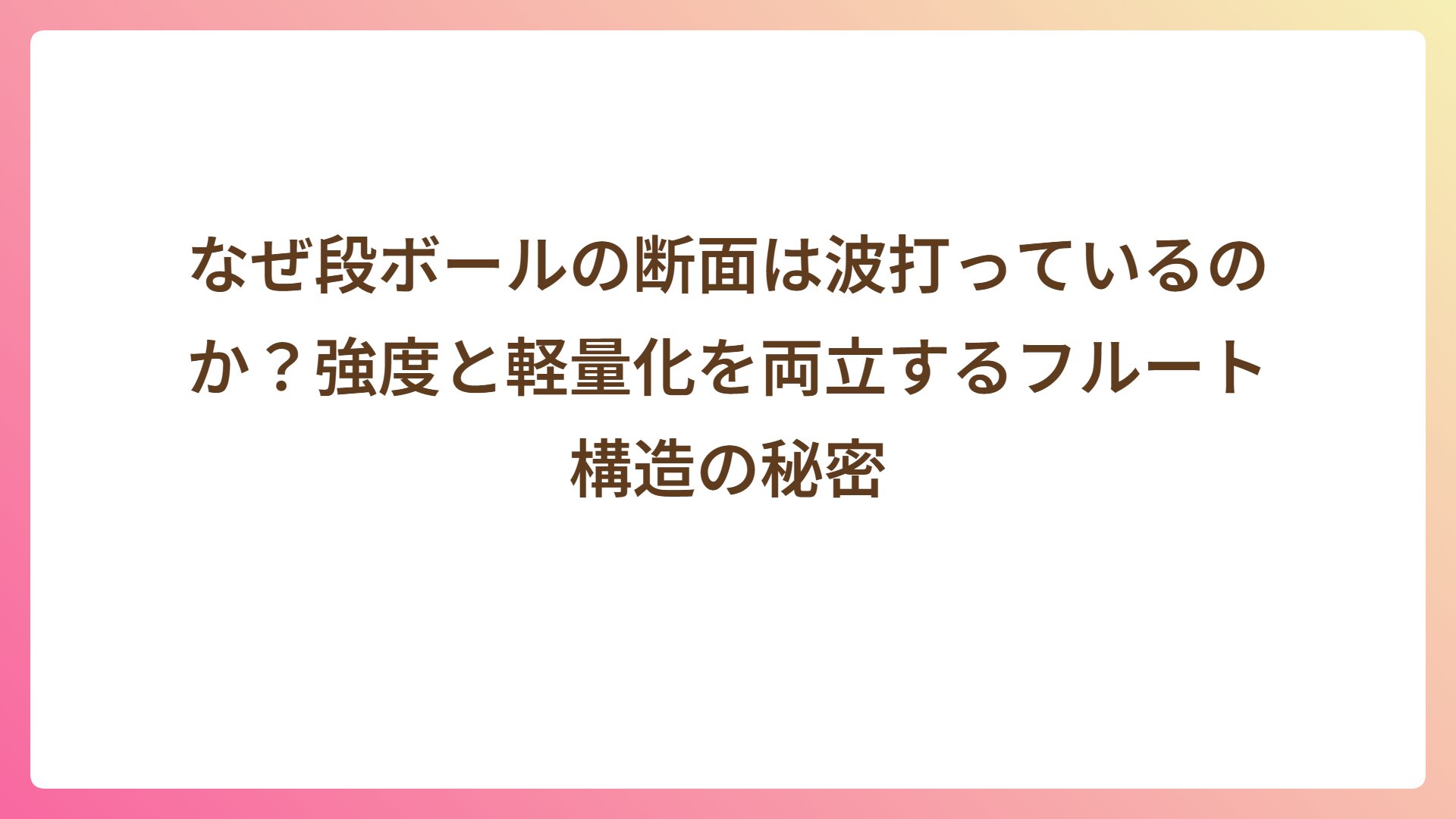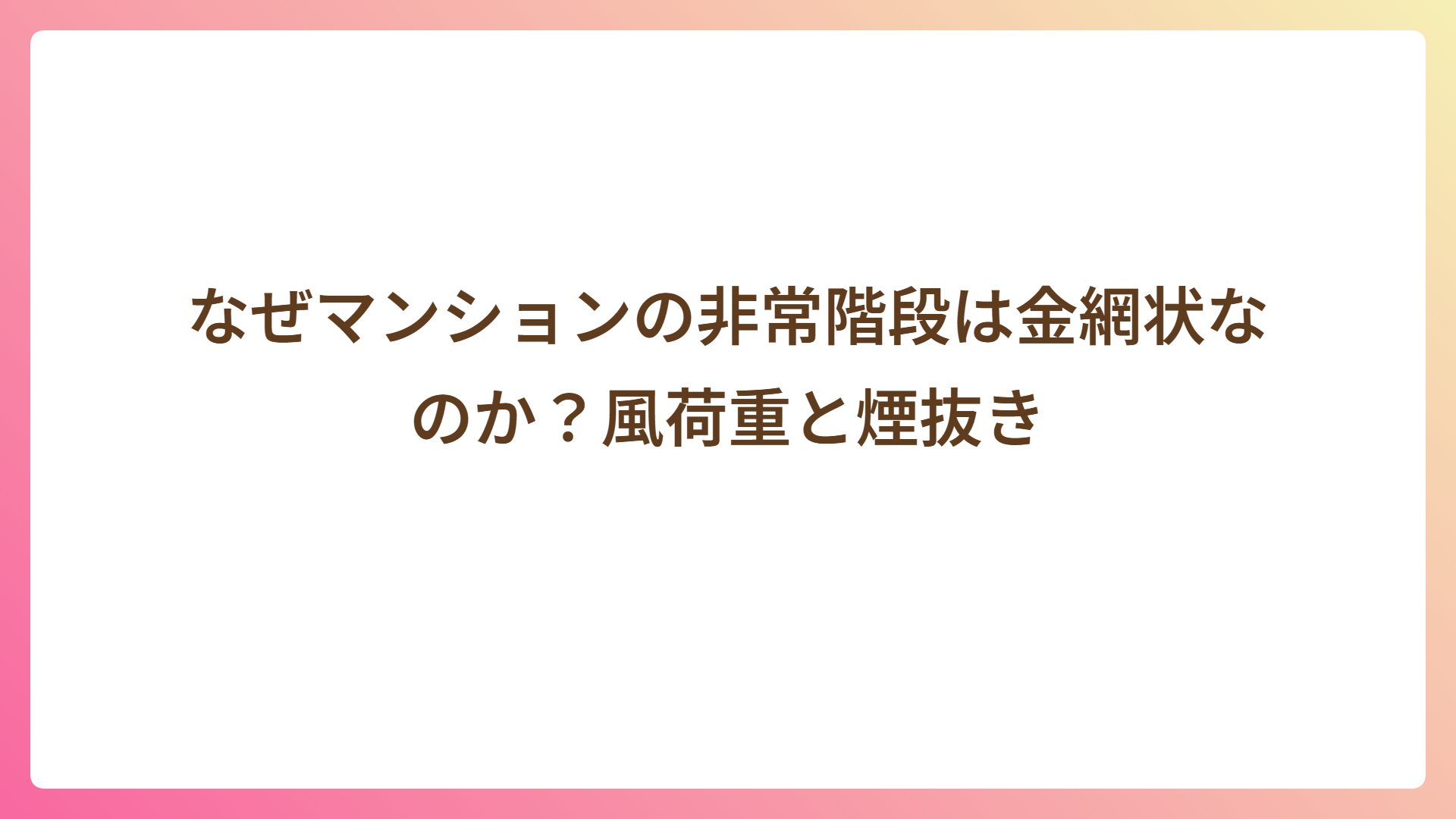なぜ日本の紙幣はサイズが違うのか?視認性と偽造防止のための設計
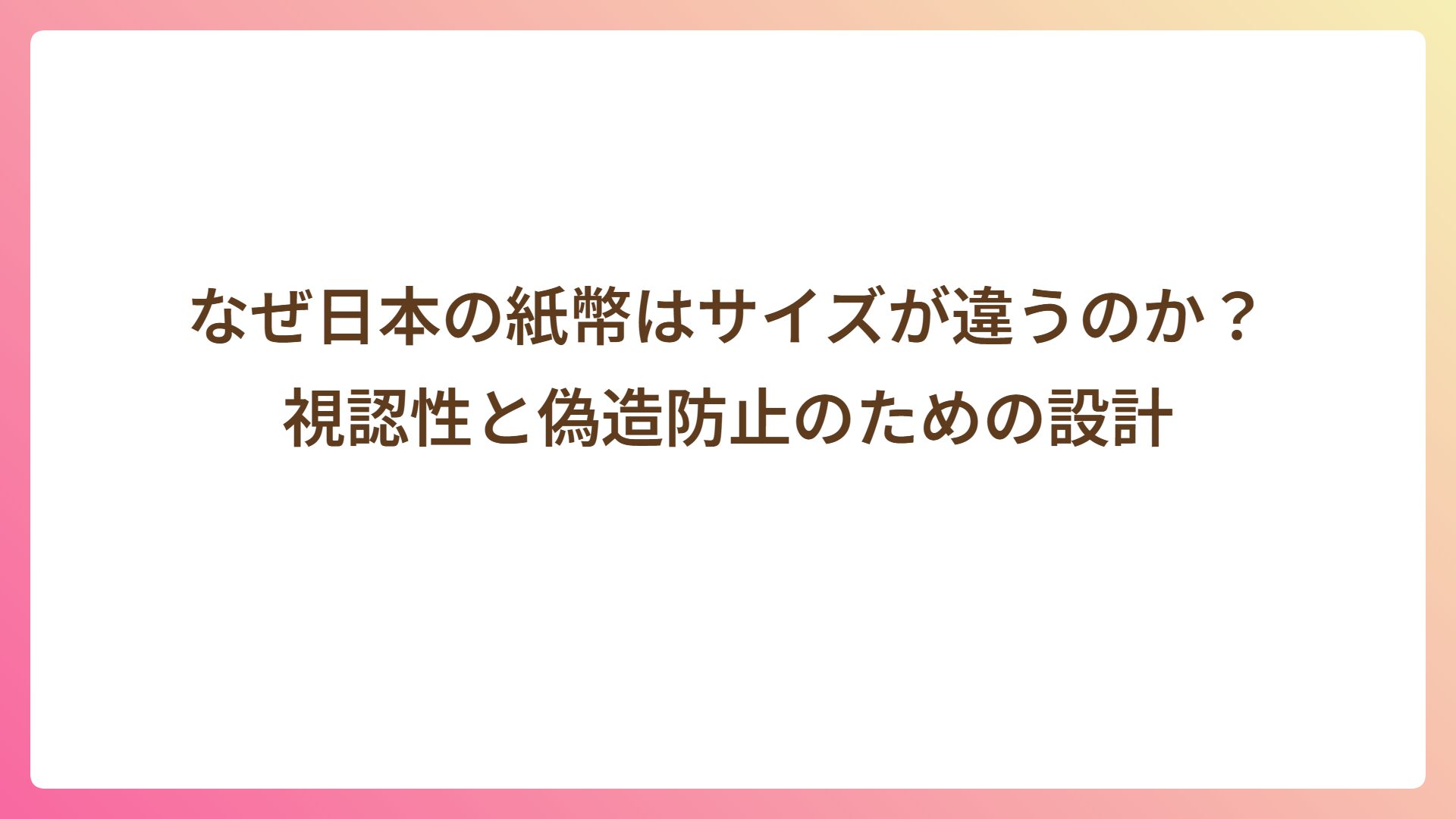
1万円札、5千円札、千円札──日本の紙幣を並べてみると、実はすべて微妙にサイズが違います。普段何気なく使っているお金ですが、なぜわざわざ金額ごとに大きさを変えているのでしょうか?その理由には、私たちの「使いやすさ」と「安全性」を両立するための工夫が隠されています。
視覚的・触覚的に区別しやすくするための工夫
紙幣のサイズが異なる最大の理由は、金額の区別を誰にでもわかりやすくするためです。
特に視覚に障がいのある人や高齢者でも判別しやすいように、額面が高くなるほど紙幣のサイズも少しずつ大きくなっています。
これは視認性だけでなく、手触りでも違いがわかるようにするための工夫です。
また、日本銀行は紙幣のデザインを決定する際に、ユニバーサルデザインの観点を重視しています。触っても判別できる「識別マーク(記号)」や、数字の大きな表示、濃淡の強い印刷なども組み合わせて、誰もが安心して使えるように設計されているのです。
偽造防止の観点からも異なるサイズが有効
紙幣のサイズが異なるもうひとつの理由は、偽造を防ぐためです。
もしすべての紙幣が同じサイズであれば、1万円札のデザインを千円札にすり替えるなどの“変造”が容易になってしまいます。
しかし、金額ごとにサイズが異なれば、印刷や裁断の工程で一致しないため、単純なすり替えでは偽札を作れなくなります。
さらに、日本の紙幣には高度な偽造防止技術が施されています。
ホログラム、すかし、深凹印刷、パールインキなど、複数の要素を組み合わせており、サイズ差もその一部として偽造防止に寄与しています。
海外の紙幣との比較:世界的にも主流の設計思想
紙幣のサイズを額面ごとに変える仕組みは、日本だけでなく多くの国でも採用されています。
例えばユーロ紙幣も、5ユーロから500ユーロまで段階的にサイズが大きくなります。
これにより視覚障がい者や高齢者が簡単に区別でき、紙幣の自販機・ATM判定の精度も向上します。
一方、アメリカのドル紙幣はすべて同じサイズです。そのため視覚障がい者への配慮が課題とされ、専用の識別ツールやアプリが開発されています。
この点で、日本の紙幣設計は「人に優しく、安全性にも優れた仕組み」といえるでしょう。
次回の紙幣刷新でも継承される“サイズ差”の意義
2024年発行の新紙幣(渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎の肖像)でも、従来と同じサイズ比が維持されます。
新たな偽造防止技術として3Dホログラムなどが導入されますが、金額ごとのサイズ差という基本設計は変わりません。
それだけ、この仕組みが視認性と安全性を両立させる上で最適だと認められているのです。
まとめ:サイズの違いは「安心して使うためのデザイン」
日本の紙幣が金額ごとに大きさを変えているのは、単なるデザイン上の違いではありません。
そこには、
- 誰にでも見分けやすくするためのユニバーサルデザイン
- 偽造や変造を防ぐためのセキュリティ設計
という2つの目的が込められています。
見た目や手触りの違いには、日々の安心を支える知恵と技術が詰まっているのです。