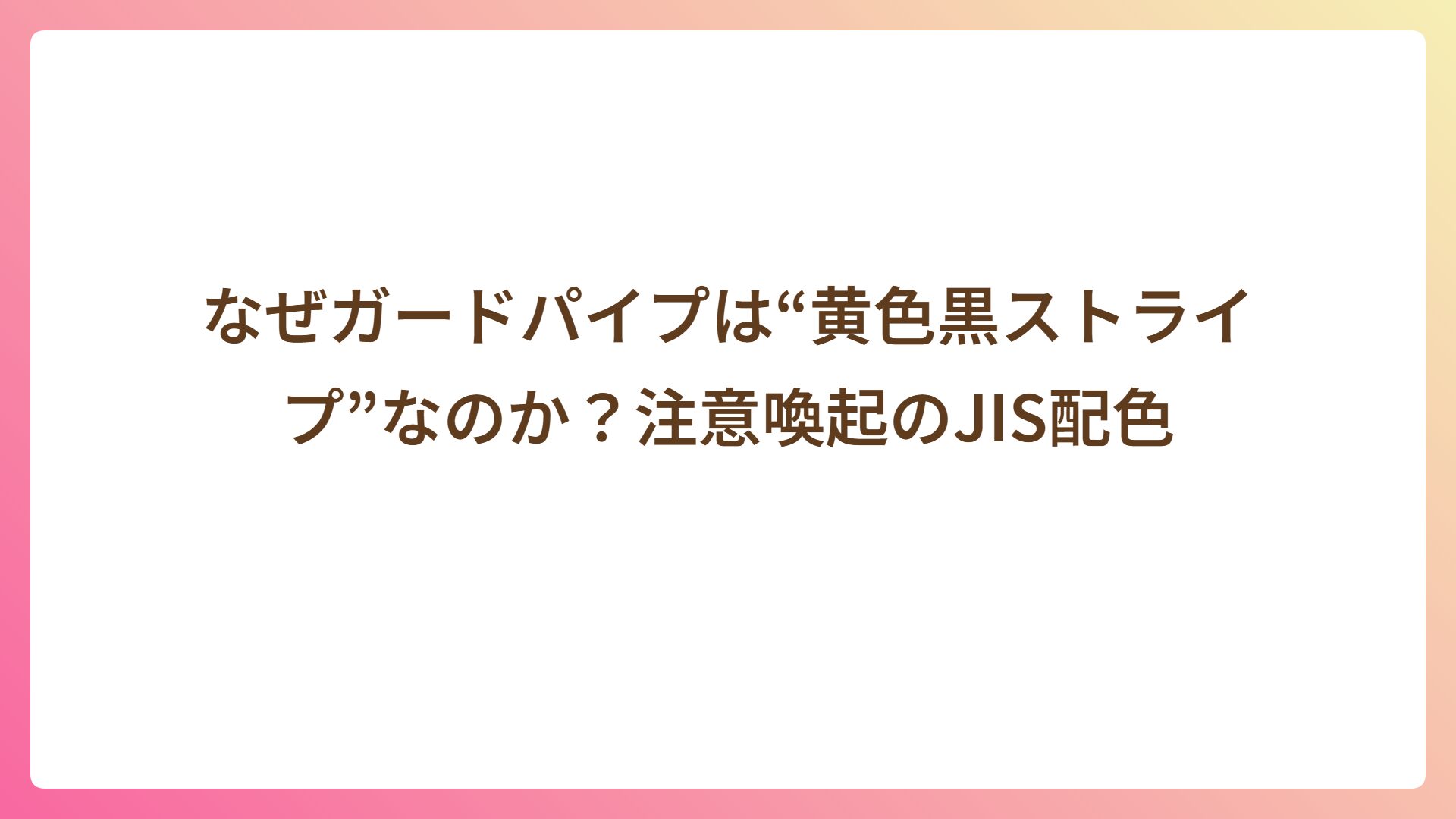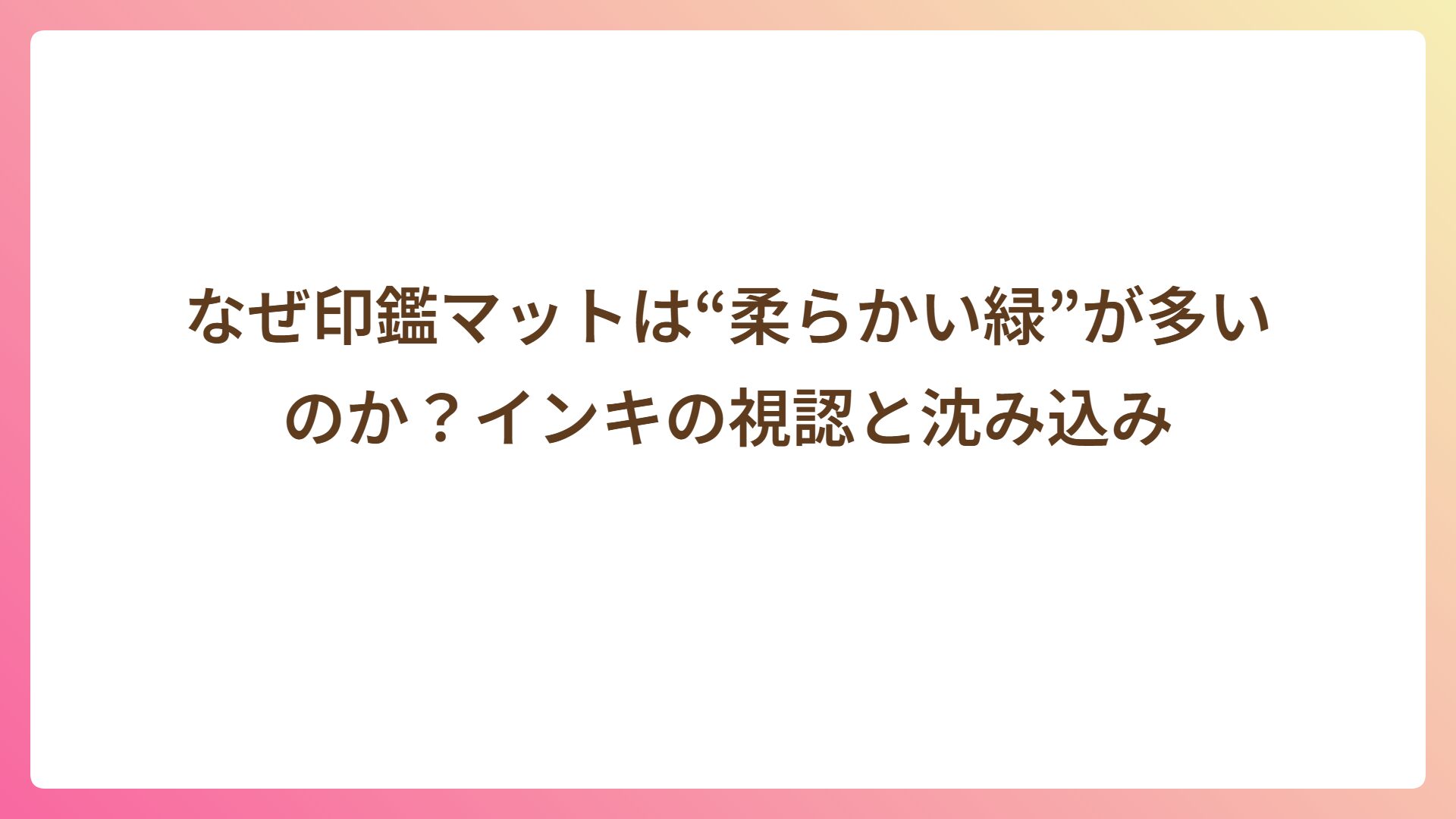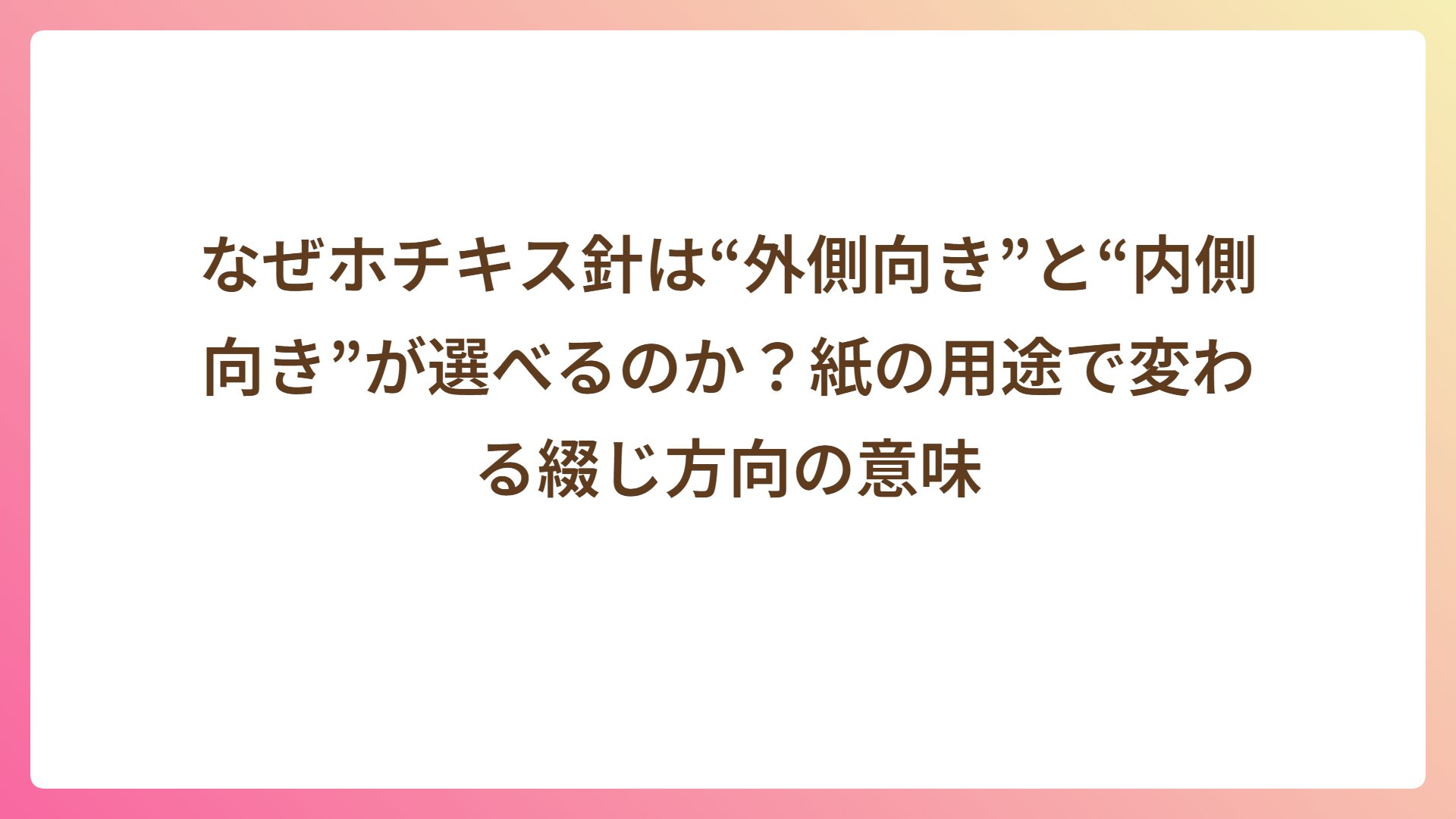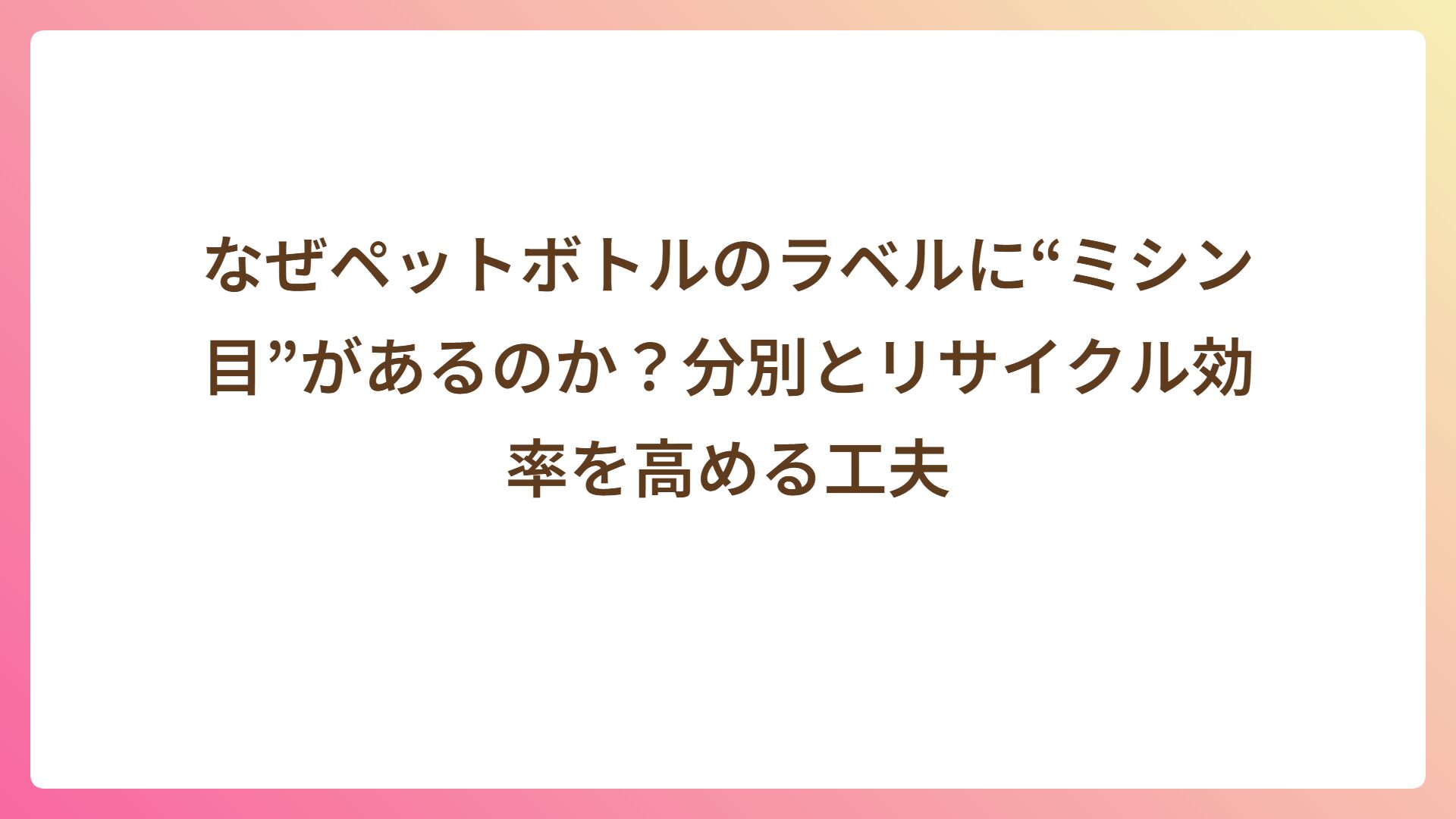なぜ信号の高さは場所によって違うのか?視認距離と車線数の関係
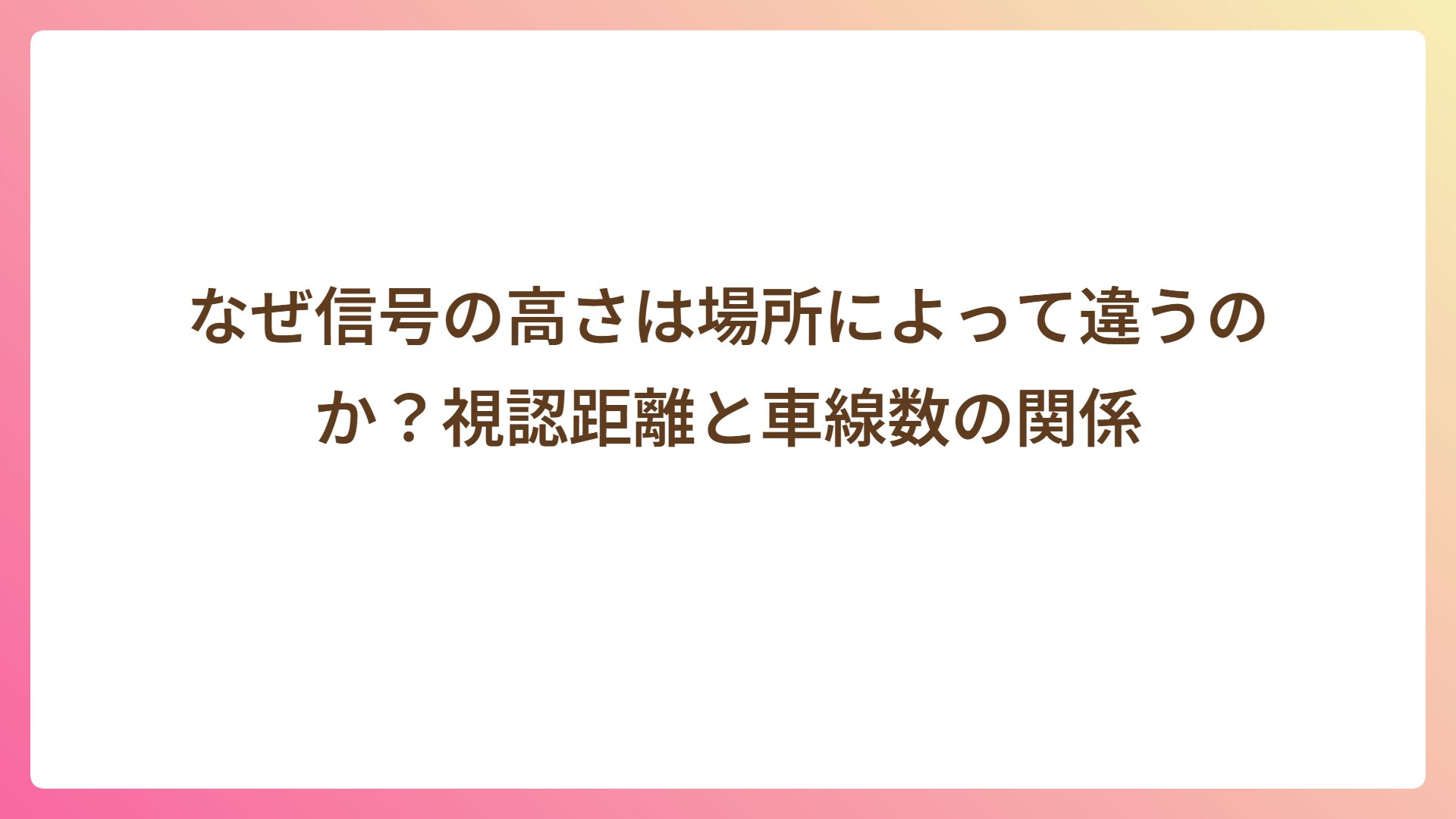
街を歩いたり車を運転していると、信号機の高さが交差点によって微妙に違うことに気づくことがあります。
高いものもあれば、歩行者信号のように低いものも。
実はこの違いは偶然ではなく、道路構造や車線数、運転者の視線位置をもとにした綿密な設計に基づいています。
この記事では、信号機の高さが場所によって異なる理由を、視認性・安全性・道路設計基準の観点から解説します。
理由①:信号の高さは“視認距離”を基準に決められている
信号機の高さは、道路を走るドライバーが適切な距離から視認できることを最優先に設計されています。
日本の道路標識・信号機の設置基準(警察庁「道路交通信号機設置基準」など)では、
- 一般道では 約4.5〜5.0m
- 幹線道路では 5.5〜6.0m前後
が標準高さとされています。
ただしこの高さは「車から見やすい位置」で決められており、
車線数や勾配などによって柔軟に調整されます。
理由②:車線が多いほど“高く設置”される
多車線道路や国道などでは、運転者が遠くから信号を確認できるように高めの設置が必要です。
たとえば:
- 片側1車線の道路 → 約4.5m程度
- 片側3〜4車線の幹線道路 → 約6m前後
- 高速道路の料金所手前など → 7m以上
これは、車線が増えるほど「視線の角度が浅く」なり、低い位置の信号が他の車に隠れて見えにくくなるためです。
理由③:勾配やカーブの“見通し条件”によっても変わる
上り坂やカーブの先に信号がある場合、通常の高さでは視界に入らないことがあります。
そのため、
- 上り坂の頂上付近 → 高めに設置
- 下り坂の終点付近 → 低めに設置
- カーブ外側 → 高め、内側 → 低め
といったように、ドライバーの視界角度を考慮して最適化されています。
理由④:歩行者用・車両用で“目的の高さ”が異なる
信号機は車用だけでなく、歩行者や自転車向けにも設置されています。
それぞれで求められる視線高さが違うため、構造も異なります。
| 種類 | 主な高さ | 理由 |
|---|---|---|
| 車両用信号 | 約4.5〜6m | 車の運転席から見やすい高さ |
| 歩行者用信号 | 約2.1〜2.5m | 歩行者や車いす利用者の視線高さに合わせる |
| 自転車専用信号 | 約2.3〜2.7m | 走行時の目線と同じ高さ |
つまり、信号の「種類」によっても高さが意図的に分けられているのです。
理由⑤:周囲の建物・街路樹・看板などの“遮蔽物”を避けるため
都市部では、信号の視認性を確保するために周囲の構造物との干渉が考慮されます。
- 看板や信号が重なる → 高さを変えて区別
- 木の枝で見えにくい → ポールを延長
- 高架橋や歩道橋が近い → 低めに設置
このように、信号機は「見やすい位置」に個別調整されているため、
交差点ごとに高さが違うのです。
理由⑥:補助信号(手前信号)との“視線分担”
大きな交差点では、停止線付近で信号が見えなくなることを防ぐため、
補助信号(低い位置のサブ信号)が設置されます。
メイン信号を高く設置し、補助信号を低く設置することで、
- 遠くからでも早めに確認できる
- 停止線の直前でも見上げずに確認できる
という距離別の視認最適化が可能になります。
理由⑦:設置環境(道路構造物・配線条件)の制約
信号機はポールやアームで支えられており、
その構造上の制約によっても高さが決まります。
- 電柱共用型 → 高さ制限あり(5m前後)
- 横断歩道上アーム型 → 設置位置の制約で高め
- 吊り下げ型 → 架線・風荷重を考慮して位置調整
つまり、電線や構造物の位置関係も高さのばらつき要因なのです。
まとめ:信号の高さは“道路環境に合わせた設計解”
信号機の高さが場所によって違うのは、
- 車線数や視認距離に応じた最適化
- 勾配やカーブなど地形条件への対応
- 歩行者や自転車との視線差
- 建物や木などの遮蔽物を避けるため
といった安全と視認性の両立設計によるものです。
つまり、あの高さの違いは単なる設置ミスではなく、
「その場所で最も見やすく安全に止まれるための調整」なのです。