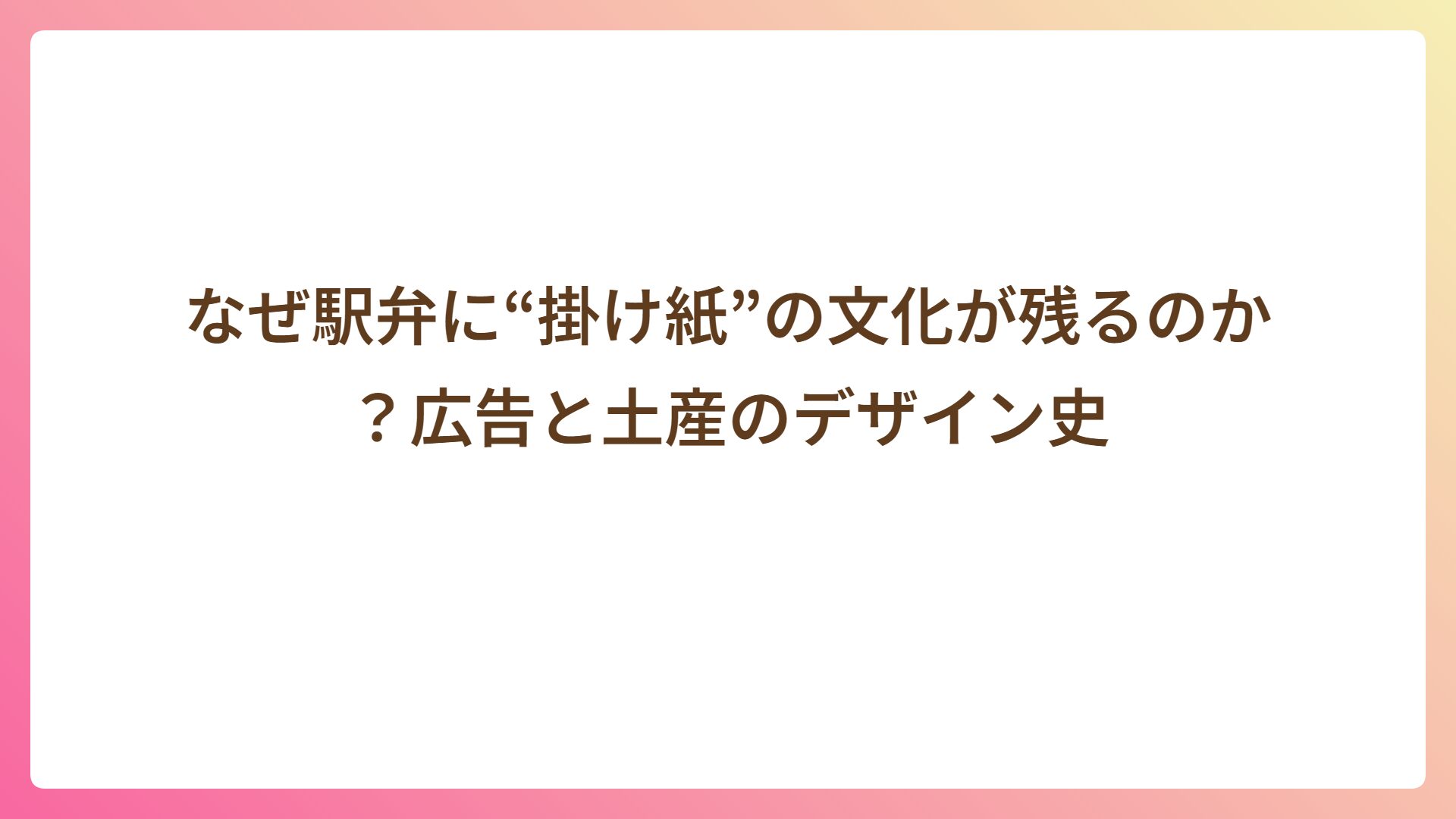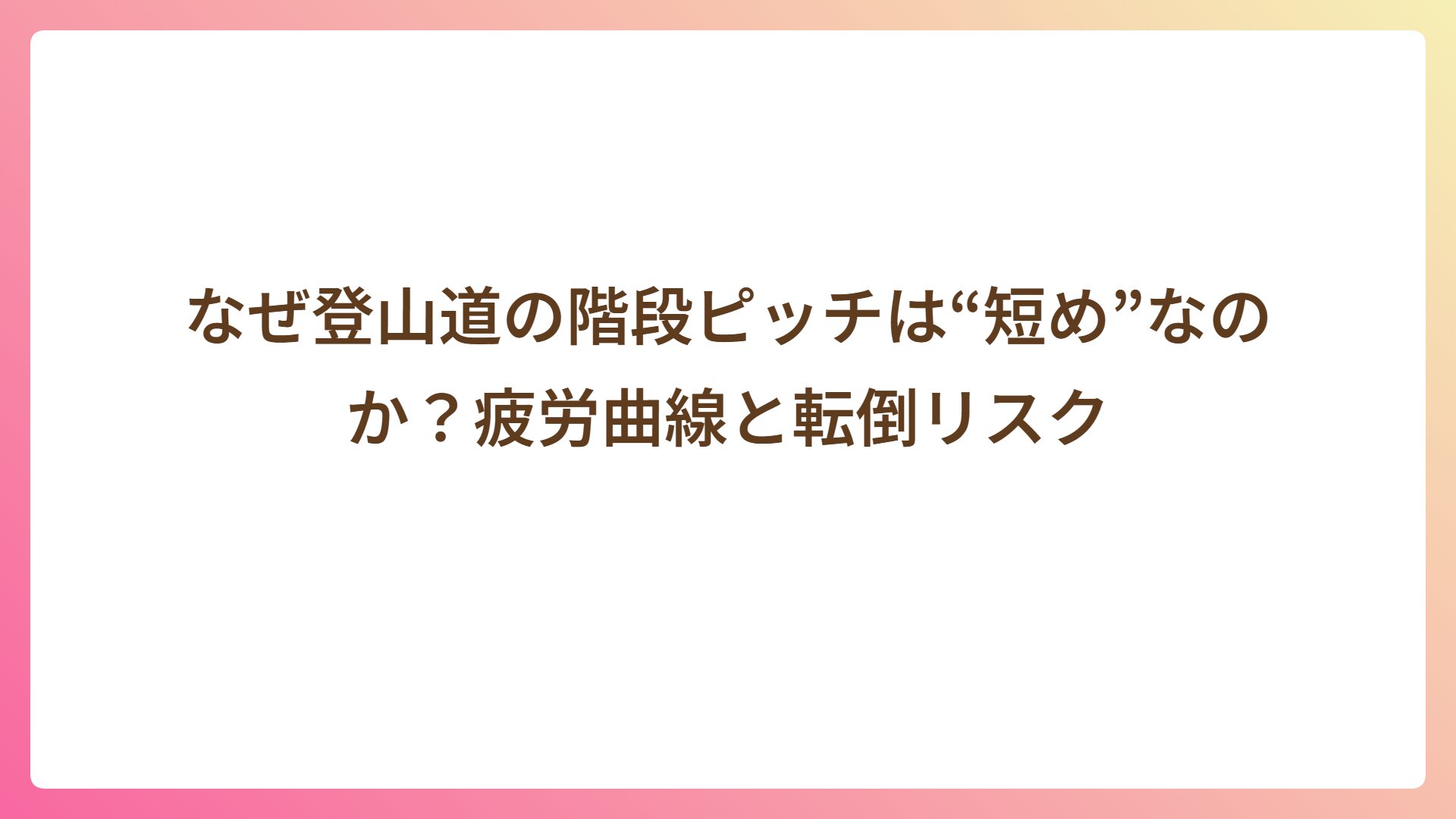なぜ新幹線は“トンネル”で耳が痛くなるのか?圧力波と気密構造の科学
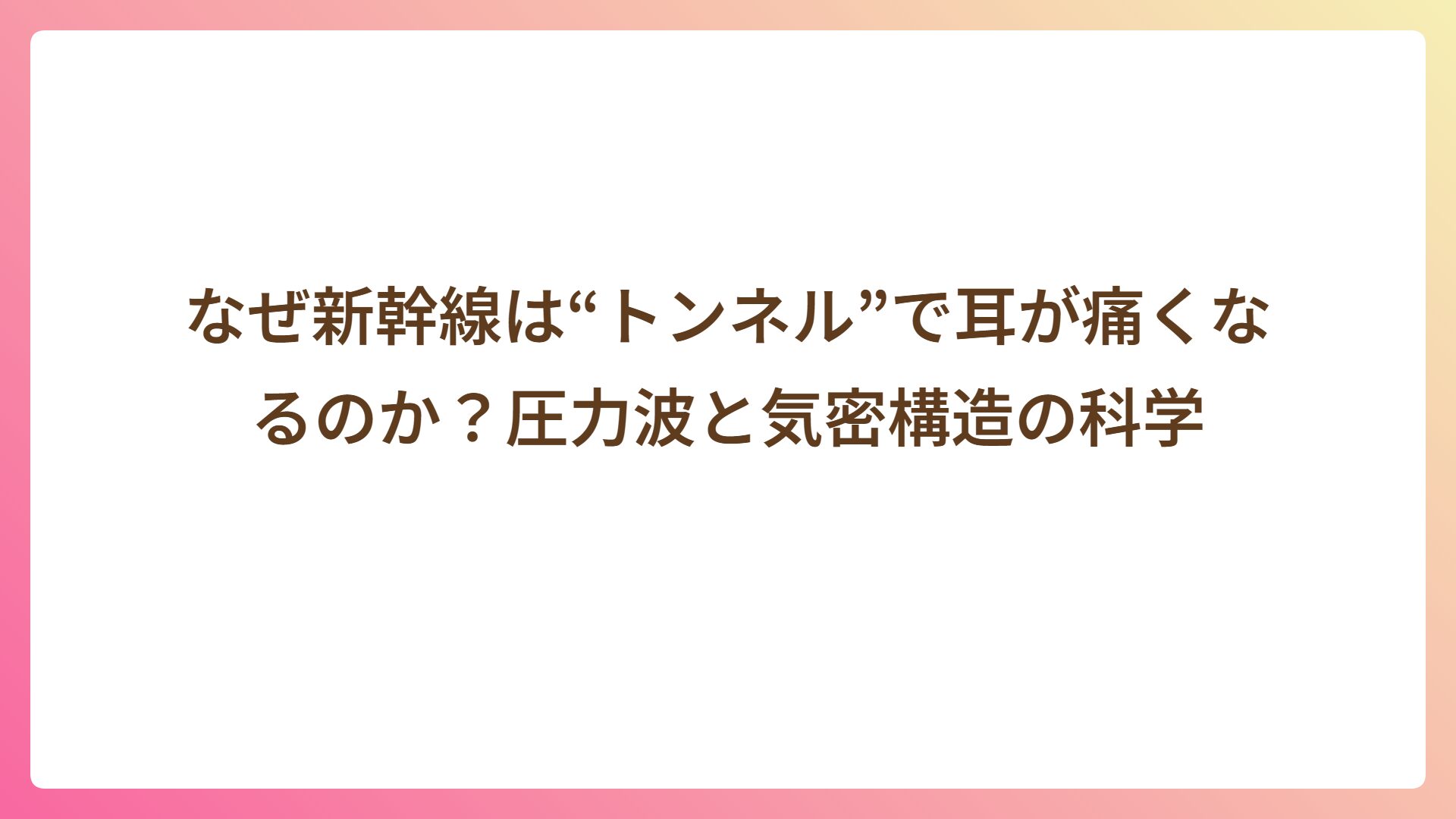
新幹線に乗っていて、トンネルに入ると「キーン」と耳が詰まるような感覚を覚えたことはありませんか?
あれはスピードのせいだけではなく、空気の圧力変化(圧力波)による生理的な反応です。
この記事では、トンネル内で起こる圧力波の正体と、それを緩和するための新幹線の気密構造をわかりやすく解説します。
トンネルに入ると“圧力波”が発生する
新幹線がトンネルに突入すると、空気の逃げ場がなくなるため、
列車の先頭が空気を押し込み、前方に“圧力の波”が発生します。
この波を「トンネル圧縮波(圧力波)」と呼びます。
列車は時速300km近い速度で進むため、わずか0.1〜0.2秒の間に大きな気圧変化が起きます。
その変化が車内にも伝わり、私たちの鼓膜を内外から押すことで耳に違和感を生じさせるのです。
耳が痛くなるのは“鼓膜の気圧差”が原因
人間の耳は、外気と中耳(鼓膜の内側)の圧力を耳管(じかん)という管で調整しています。
飛行機や山道でも耳が「ポン」となるのは、耳管が開いて圧力を均等にしているためです。
しかし、新幹線のトンネル進入時のように急激な気圧変化が起こると、
耳管の反応が追いつかず、鼓膜の内外にわずかな圧力差が発生。
これが「詰まったような」「押されるような」痛みとして感じられます。
特に、鼻づまりや風邪などで耳管が狭くなっていると、
圧の逃げ道がなくなり、痛みを感じやすくなります。
圧力波の物理的仕組み:空気が“壁”のように詰まる
圧力波をもう少し詳しく見ると、
トンネルの入り口で列車が空気を押しのけた瞬間、
その空気の塊が“壁”のように前方へ押し出され、音速に近い速度で伝わります。
そして、トンネルの出口に到達した瞬間、
外の空気とぶつかって「ドン!」という音(トンネルドン)を発生させることもあります。
これを防ぐために、トンネルの出口には緩衝坑(スリット)や緩やかな形状の抗口が設けられています。
つまり、私たちの耳が感じる“痛み”は、
この圧力の変化が車内空間にわずかに伝わることによって起きているのです。
新幹線の車体は“気密構造”で圧力変化を緩和
この問題を軽減するために、新幹線は飛行機と同じような気密構造を持っています。
- ドアや窓の隙間を極力なくす
- 空調システムで車内気圧をゆっくり調整する
- 客室と車外の圧力差を一定速度で緩和する
たとえば東海道新幹線のN700系以降では、
トンネル進入時の圧力変化を0.2kPa/秒以下に抑えるよう設計されています。
この制御により、乗客の鼓膜への負担が大きく軽減されているのです。
トンネル形状も“耳対策”に関係している
新幹線のトンネルは、実は形状そのものにも工夫があります。
- 出口付近を広げる「フレア構造」
- 天井にスリットを設けて圧力を逃がす「スリット坑」
- トンネル入口に緩衝空間を設ける「緩衝坑」
これらの構造によって、圧力波が一気に外気へ放出されず、
空気の流れを緩やかに分散することができます。
その結果、列車内部で感じる圧力変化も穏やかになり、耳への負担が減少します。
乗客ができる耳のケア方法
もしトンネルで耳が痛くなったときは、以下の方法で緩和できます。
- あくびやツバを飲み込む(耳管を開く)
- 飴をなめる・ガムを噛む(咀嚼で耳管が開く)
- 鼻をつまんで軽く息を出す(バルサルバ法)
これらはいずれも、鼓膜内外の圧力を調整するための自然な反応を促す方法です。
特に子どもは耳管が狭く圧力変化に弱いため、
親が声をかけてあげることも効果的です。
まとめ:耳の痛みは“空気の波”の副作用
新幹線で耳が痛くなるのは、
- トンネル進入時に発生する圧力波(空気の衝撃波)
- それによる急激な気圧変化が鼓膜を刺激する
- 車体やトンネルの構造で徐々に緩和している
という物理現象と人体反応の組み合わせです。
つまり、あの「キーンとする感覚」は、
時速300kmで走る列車が空気と戦っている証拠。
最先端の気密技術とトンネル設計は、
“耳が痛くならない新幹線”を目指して今も進化を続けているのです。