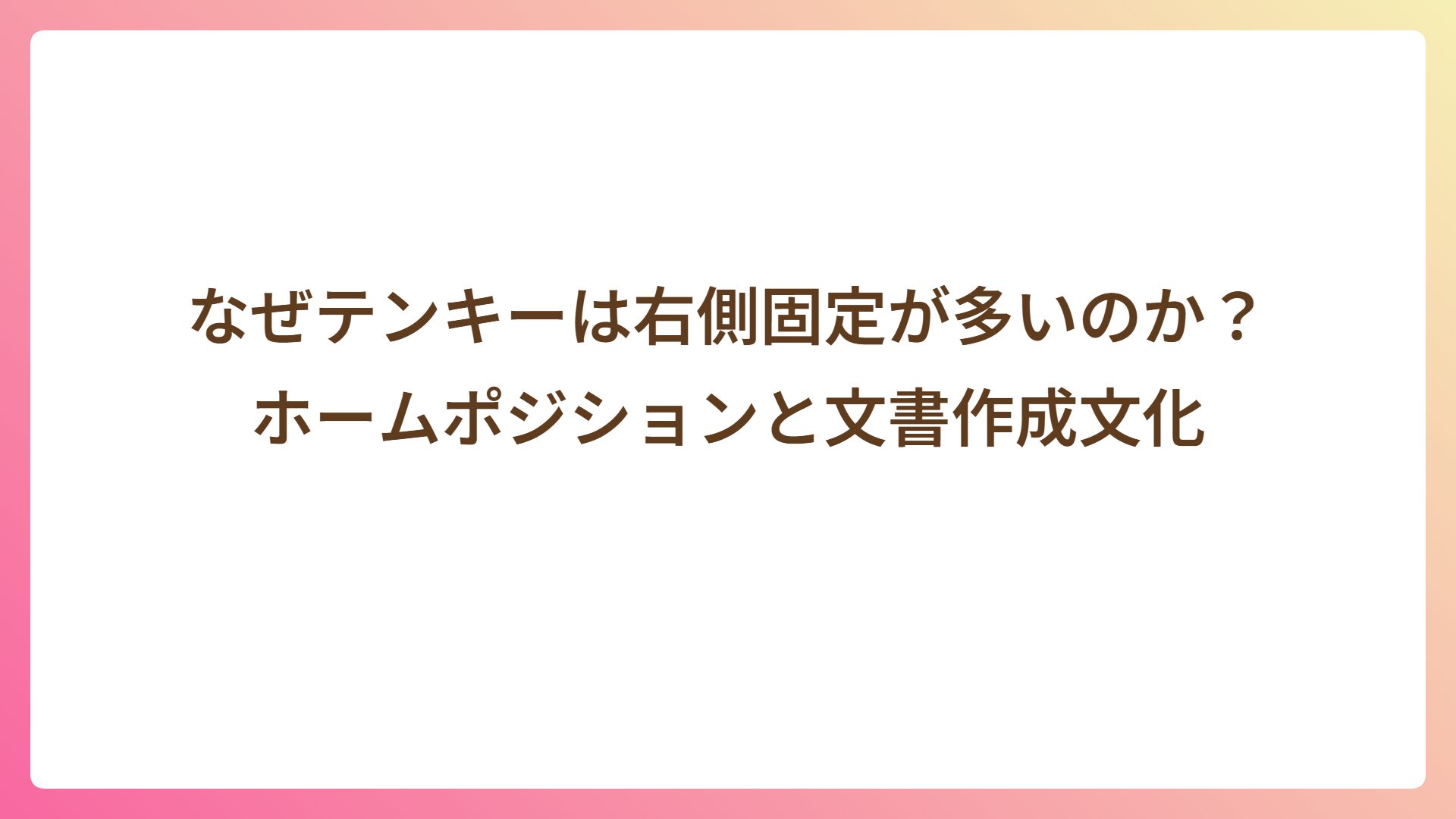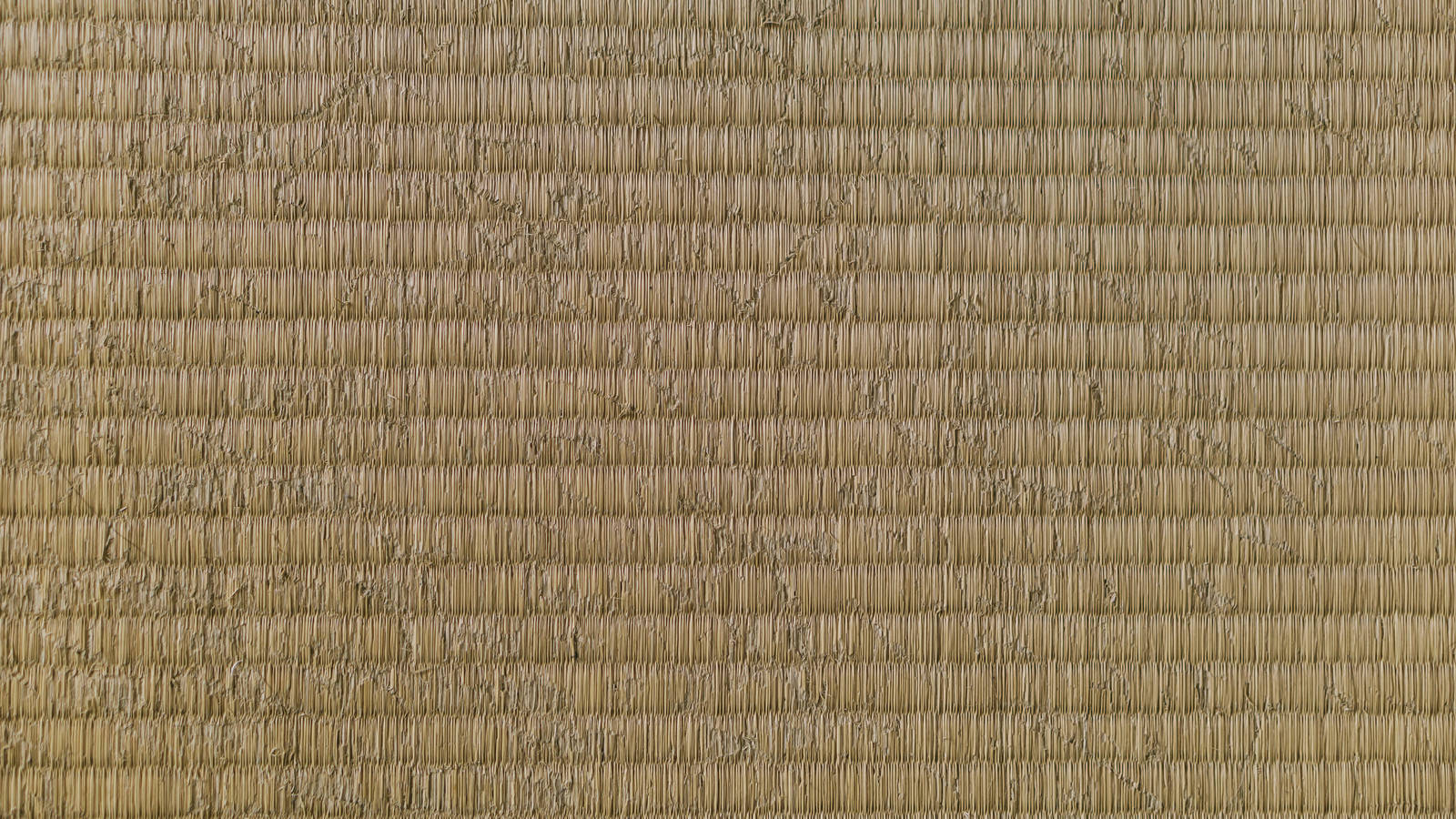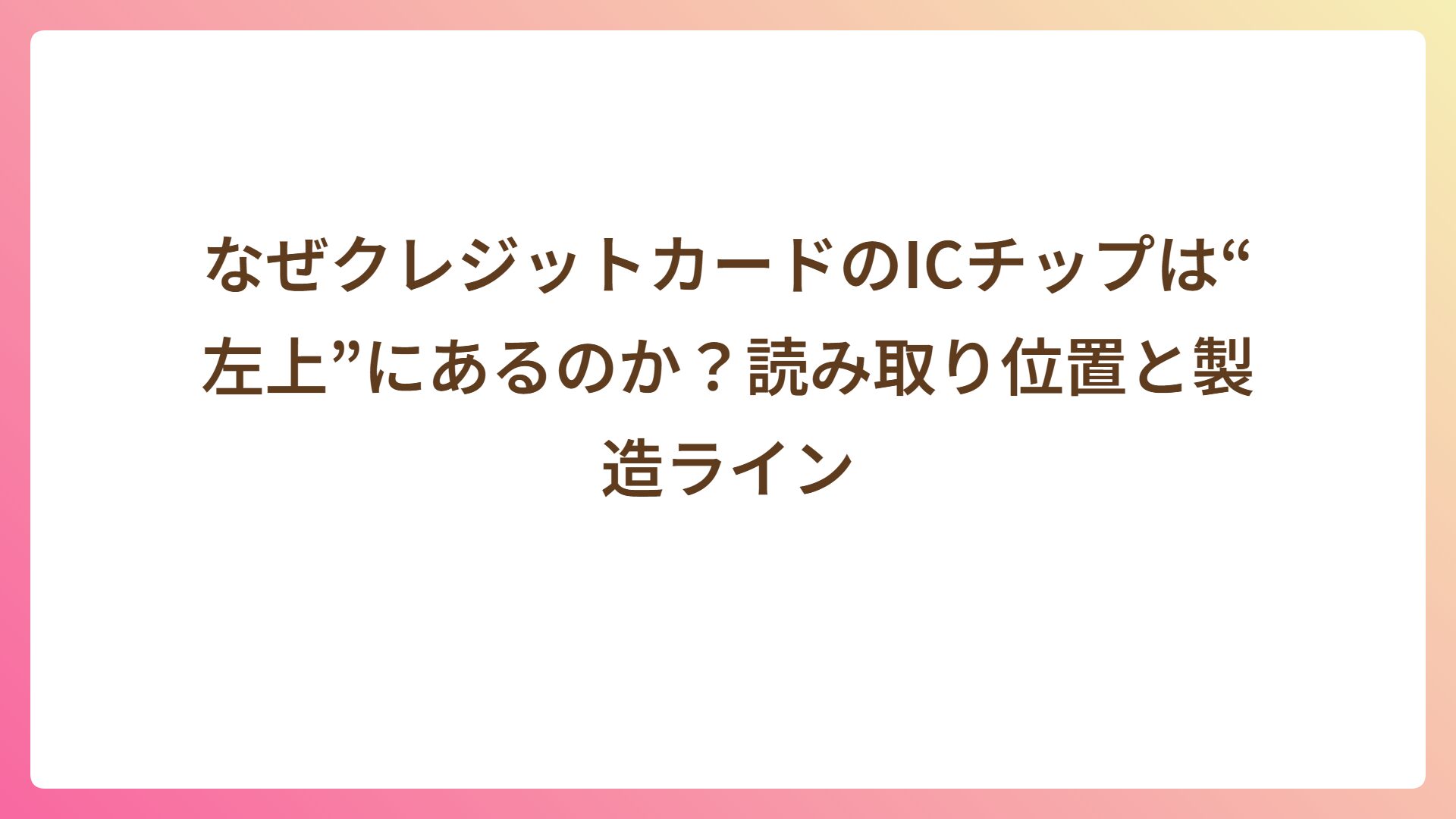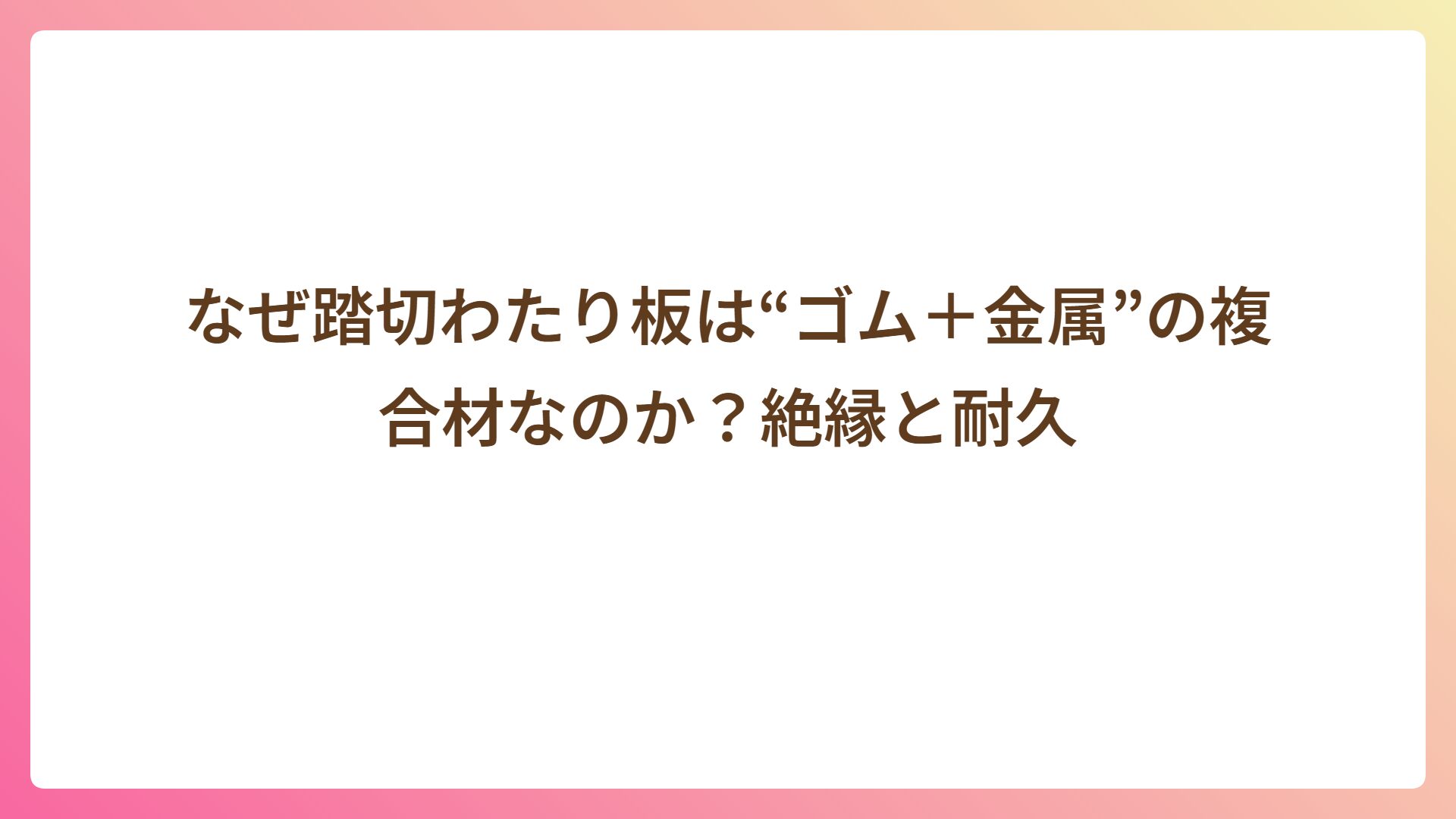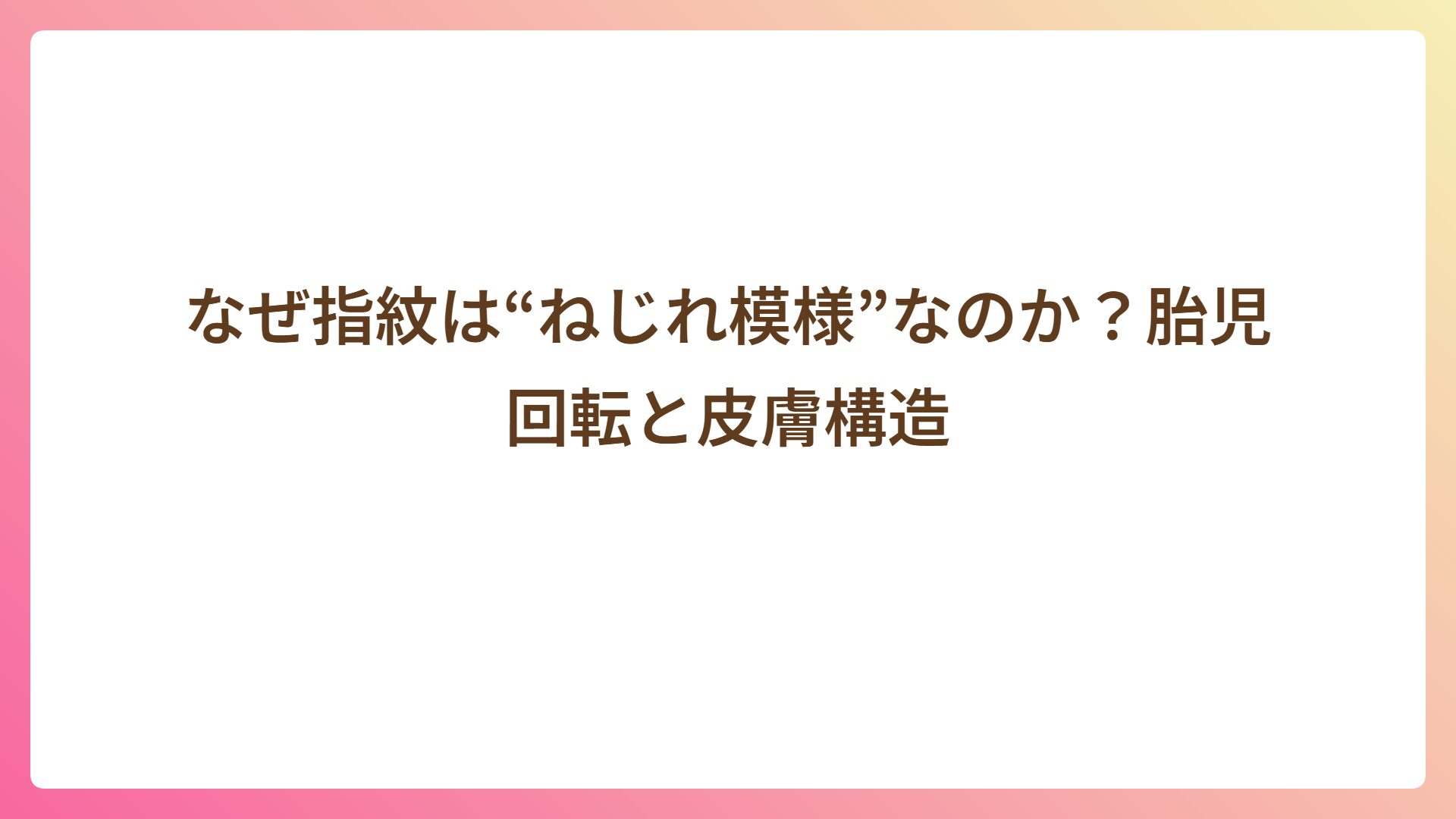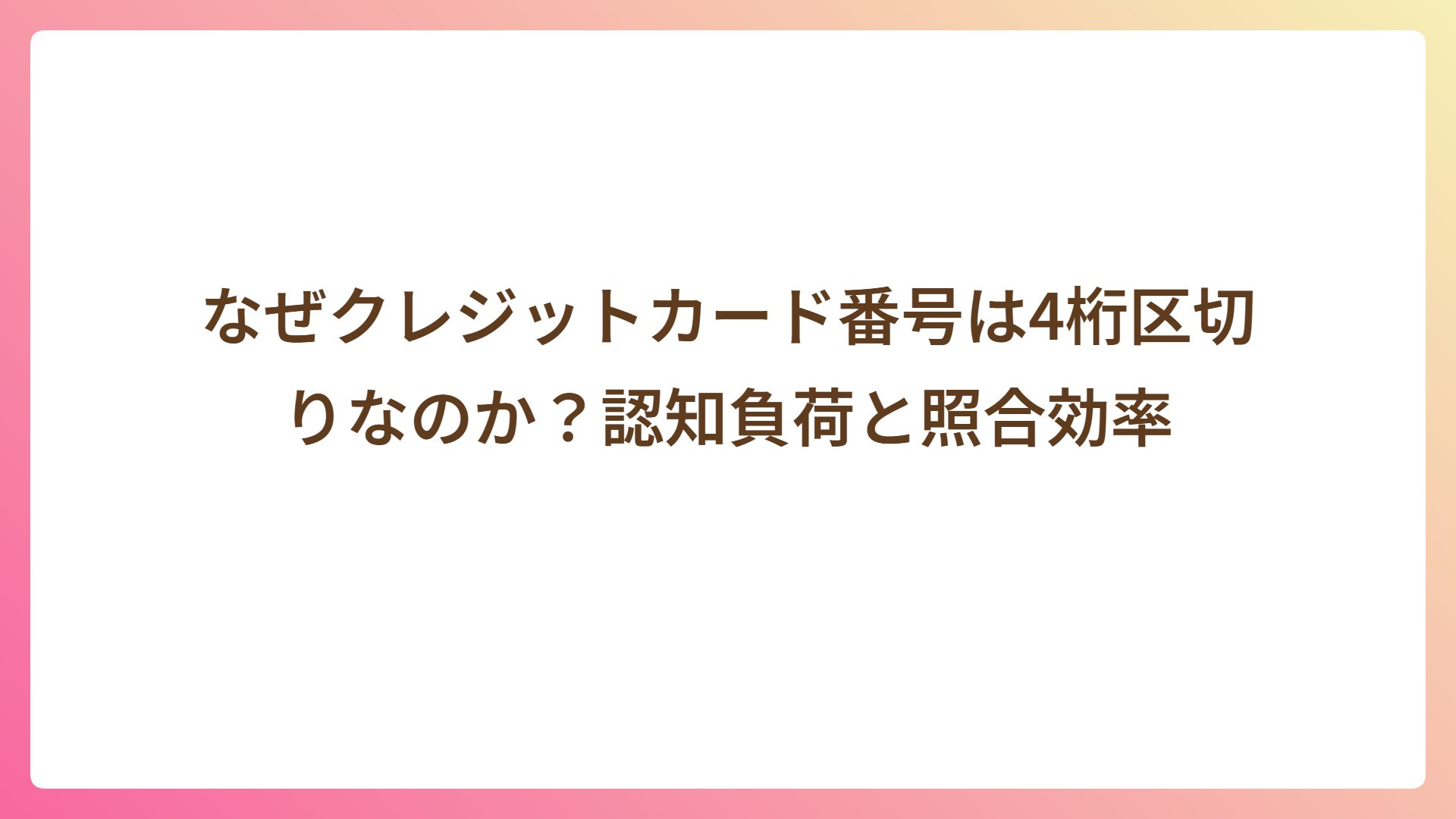なぜスライサーの刃は“斜め”が切れやすいのか?せん断角の理屈
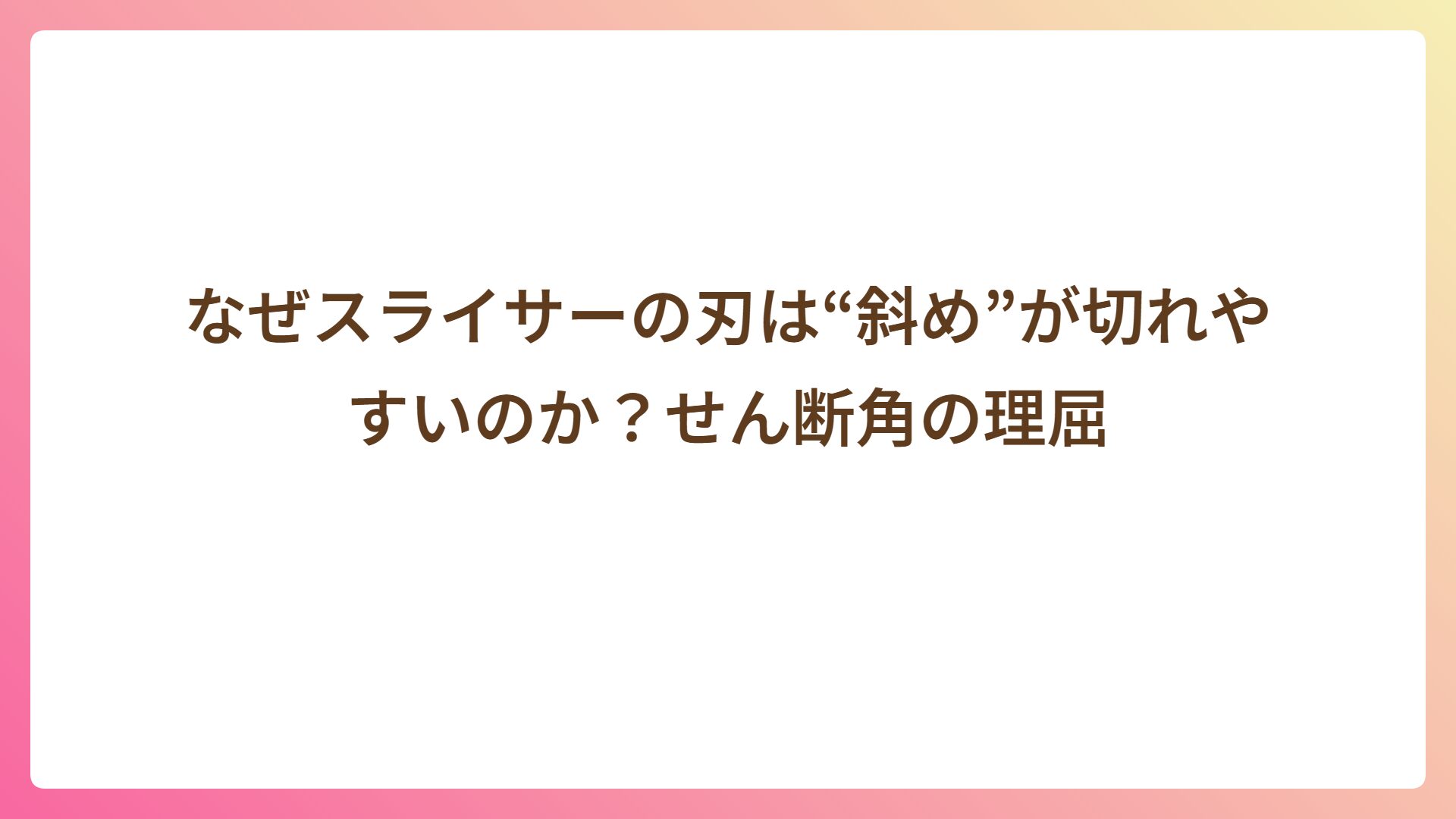
野菜スライサーや包丁の刃をよく見ると、まっすぐではなく斜めに配置されていることがあります。
まっすぐ押し当てるよりも、斜めに動かすほうがなぜかスッと切れる——。
実はこれ、偶然ではなく、力を分散して切断効率を上げる「せん断角」の原理によるものなのです。
「押す」より「滑らせる」ほうが切れる
まっすぐ押し切ると、刃全体に一度に大きな力が必要になります。
しかし刃を斜めに動かすと、接触している部分が常に一点に限定され、食材にかかる力が集中して切れ込みやすくなるのです。
いわば、斜めの刃は「スライドカット」を自動的に生み出す構造。
この動きによって、摩擦や抵抗を減らしながら効率的に切断できます。
せん断角が生む“滑らかな切れ味”
機械工学でいう「せん断角(shear angle)」とは、物体を切るときに刃と材料の間で生じる角度のことです。
刃を斜めにすることで、この角度が適切に保たれ、材料が押し潰される前に滑らかに分離します。
まっすぐ刃を当てると、圧縮力が強すぎてつぶれやすくなりますが、斜めにすると力が横方向に分散し、「削ぐように切る」状態が生まれるのです。
野菜スライサーやハムスライサーでは、このせん断角を数度〜十数度の範囲に設定することで、
最も少ない力で最大の切断効率を発揮できるように設計されています。
食材の変形を抑えて「断面がきれい」に
斜め刃は、食材を押し潰さないという利点もあります。
力が分散されるため、柔らかいトマトやハムなどでも断面がつぶれず、滑らかに切れるのです。
この原理は、包丁で“引き切り”をするのと同じ。料理人が刃を前後に動かして切るのも、
せん断角を意図的に作り出し、繊維をつぶさず切るための動作なのです。
工業製品にも応用される「斜め刃の理論」
このせん断角の考え方は、実は工場の金属加工や紙の断裁機などにも応用されています。
たとえば断裁機の刃がナナメについているのは、紙の全体を一度に押し切るのではなく、
一点ずつ順番に切ることで必要な力を小さくし、摩耗や振動を減らすためです。
つまりスライサーの斜め刃は、身近な生活用品に落とし込まれた「工学的な最適解」なのです。
まとめ
スライサーの刃が斜めなのは、せん断角を利用して切断抵抗を減らすためです。
斜めの角度が生む“滑らせる力”によって、少ない力でなめらかに切れる構造になっています。
私たちが日常的に使うスライサーにも、力学と工学の知恵がしっかりと生かされているのです。