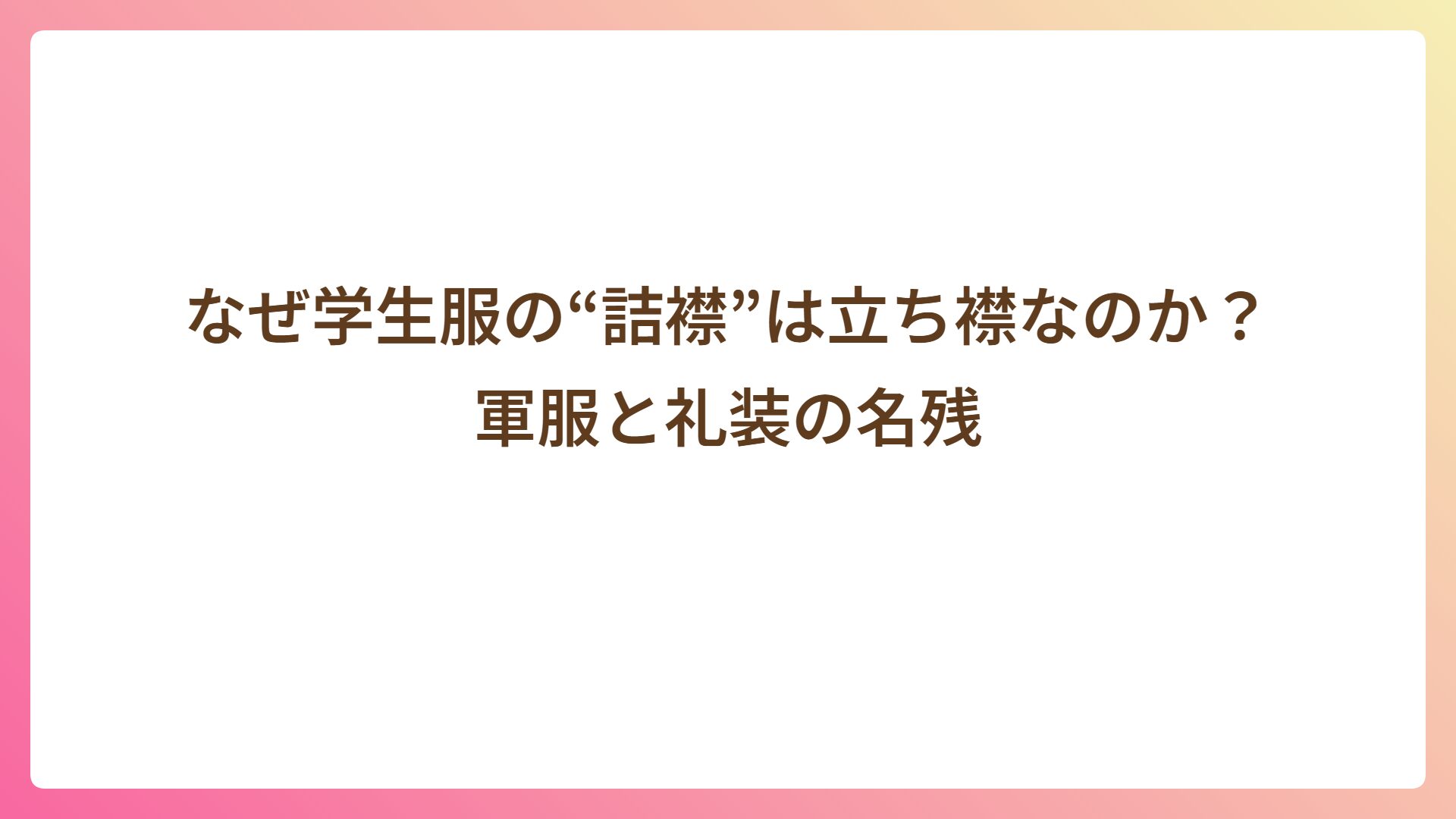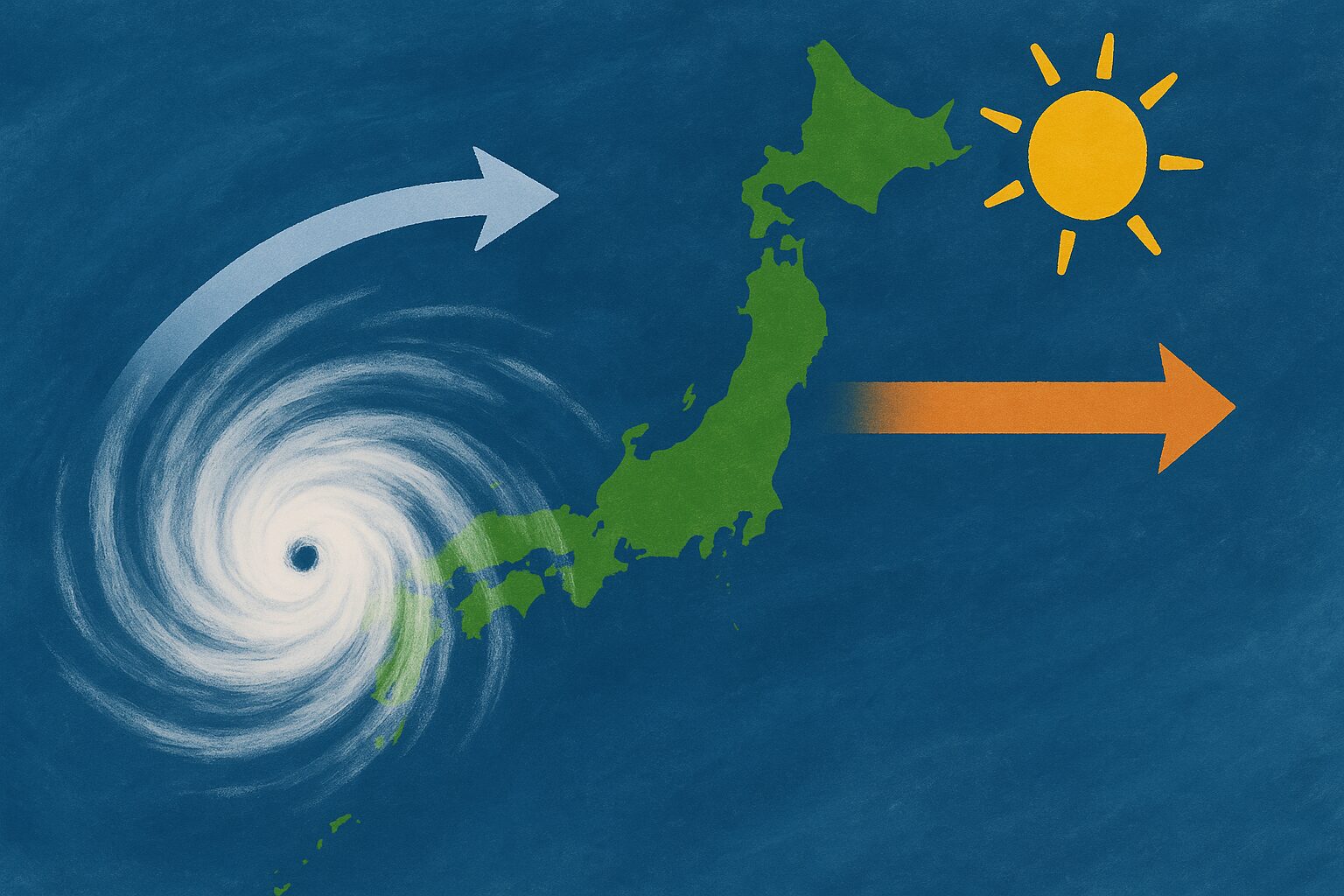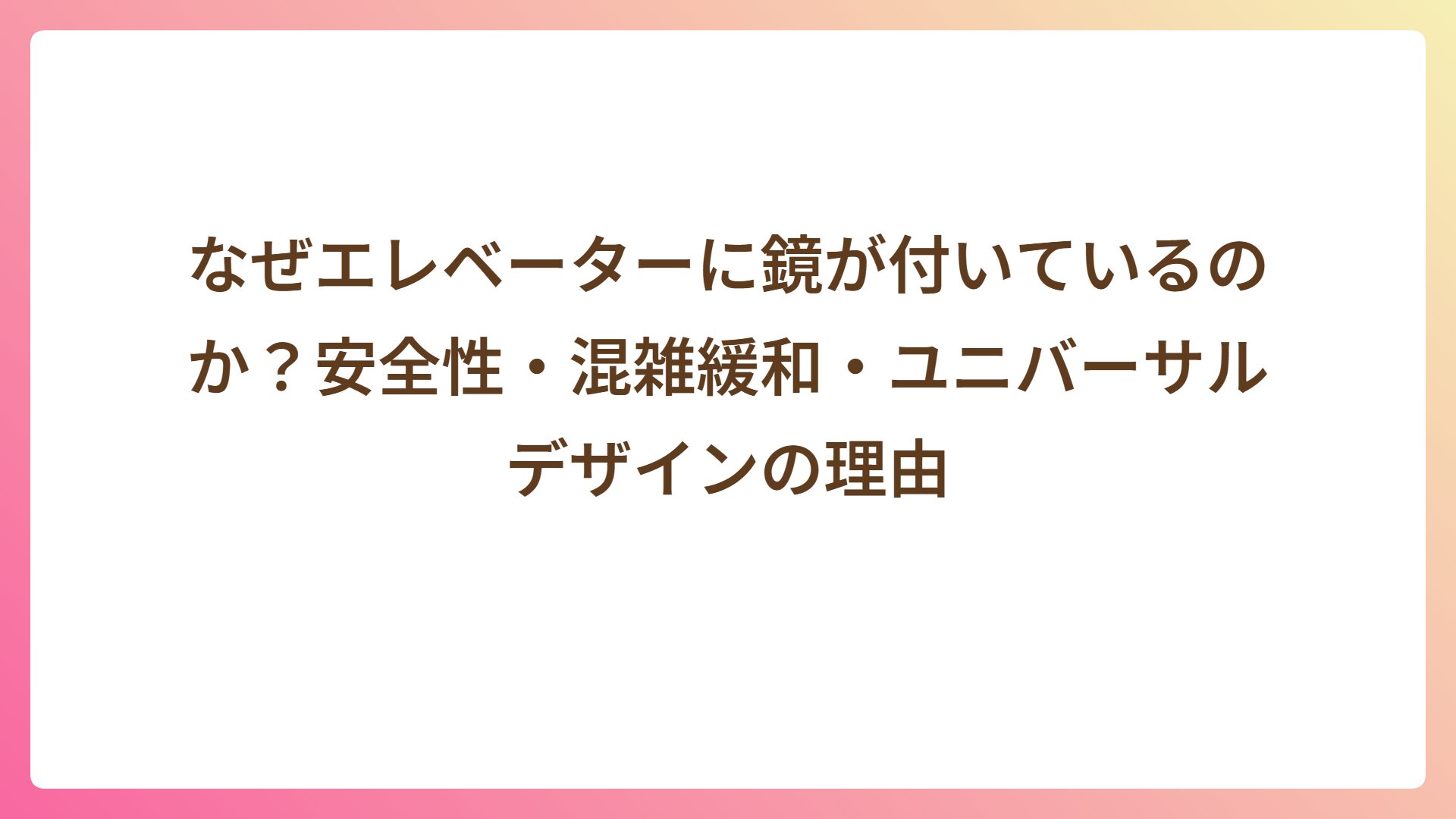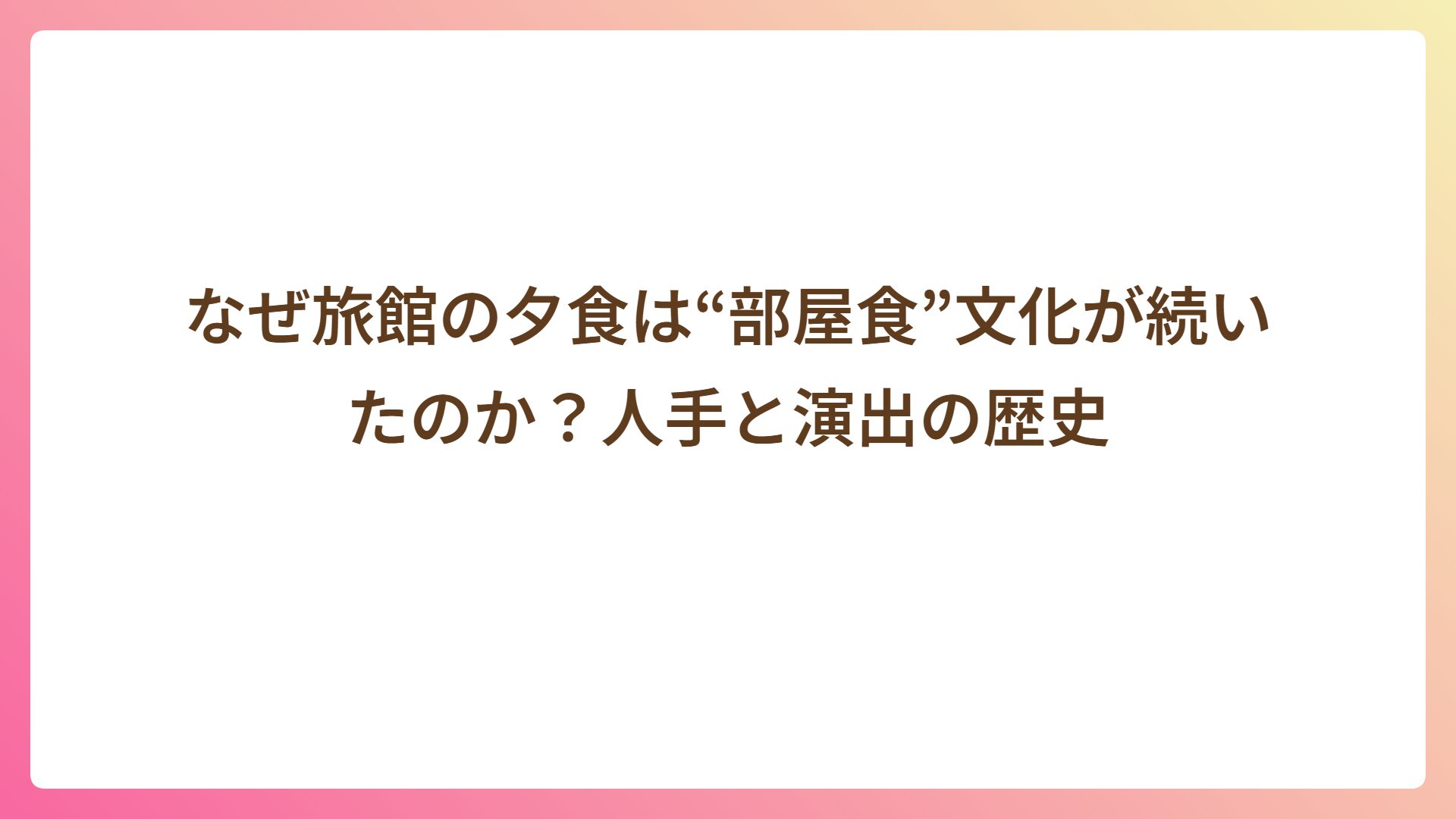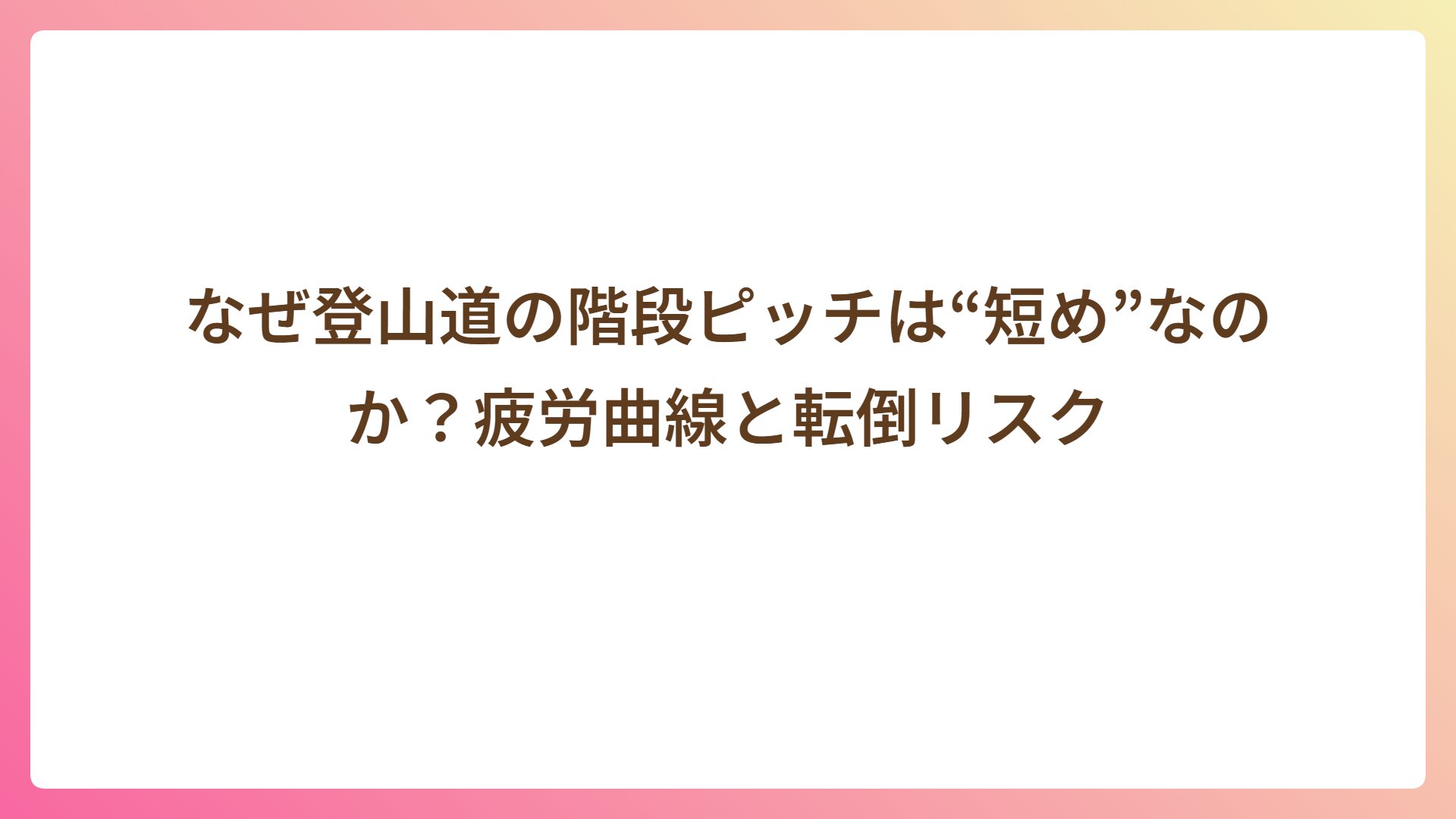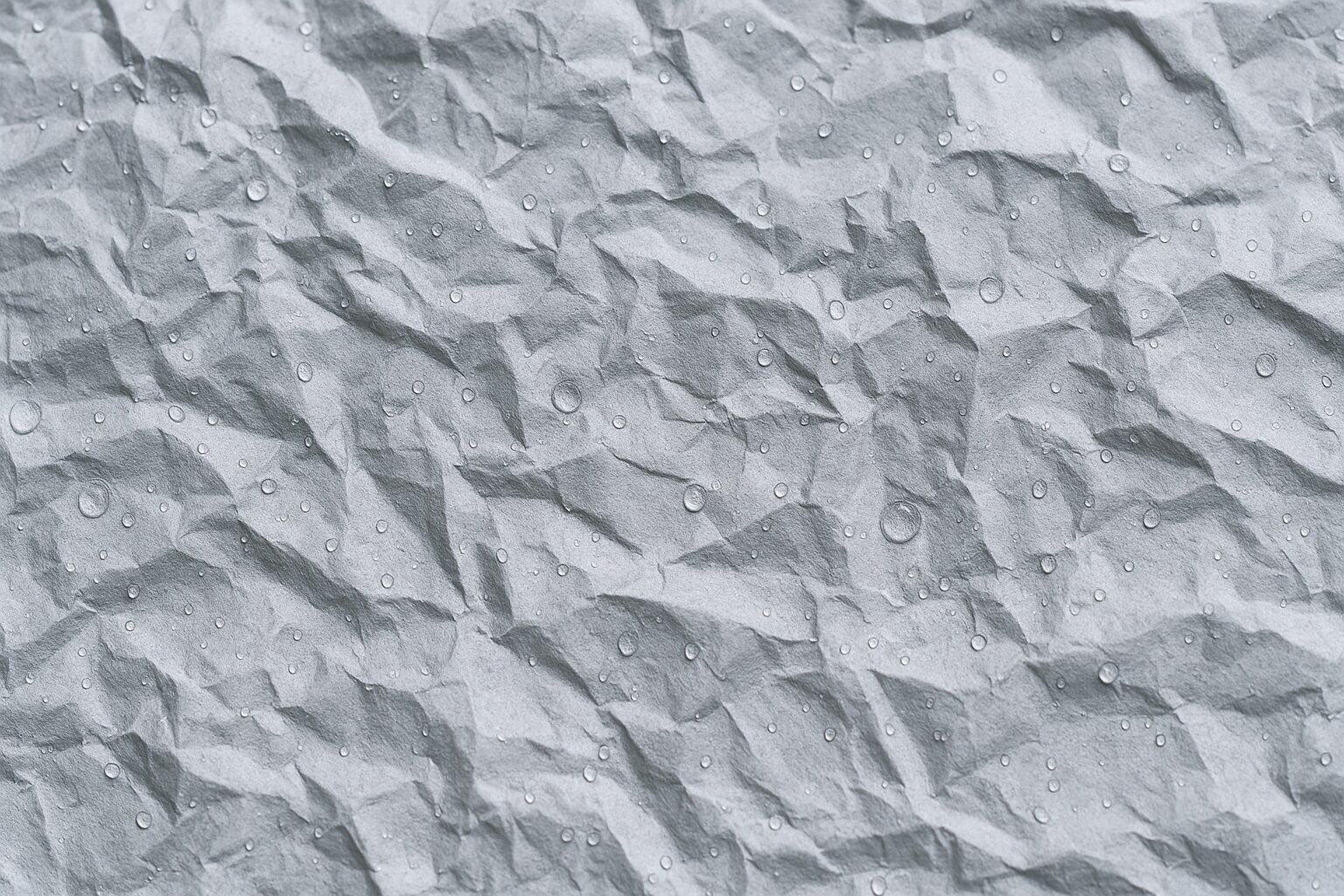なぜスイカの縞模様があるのか?成長抑制と光合成の影響
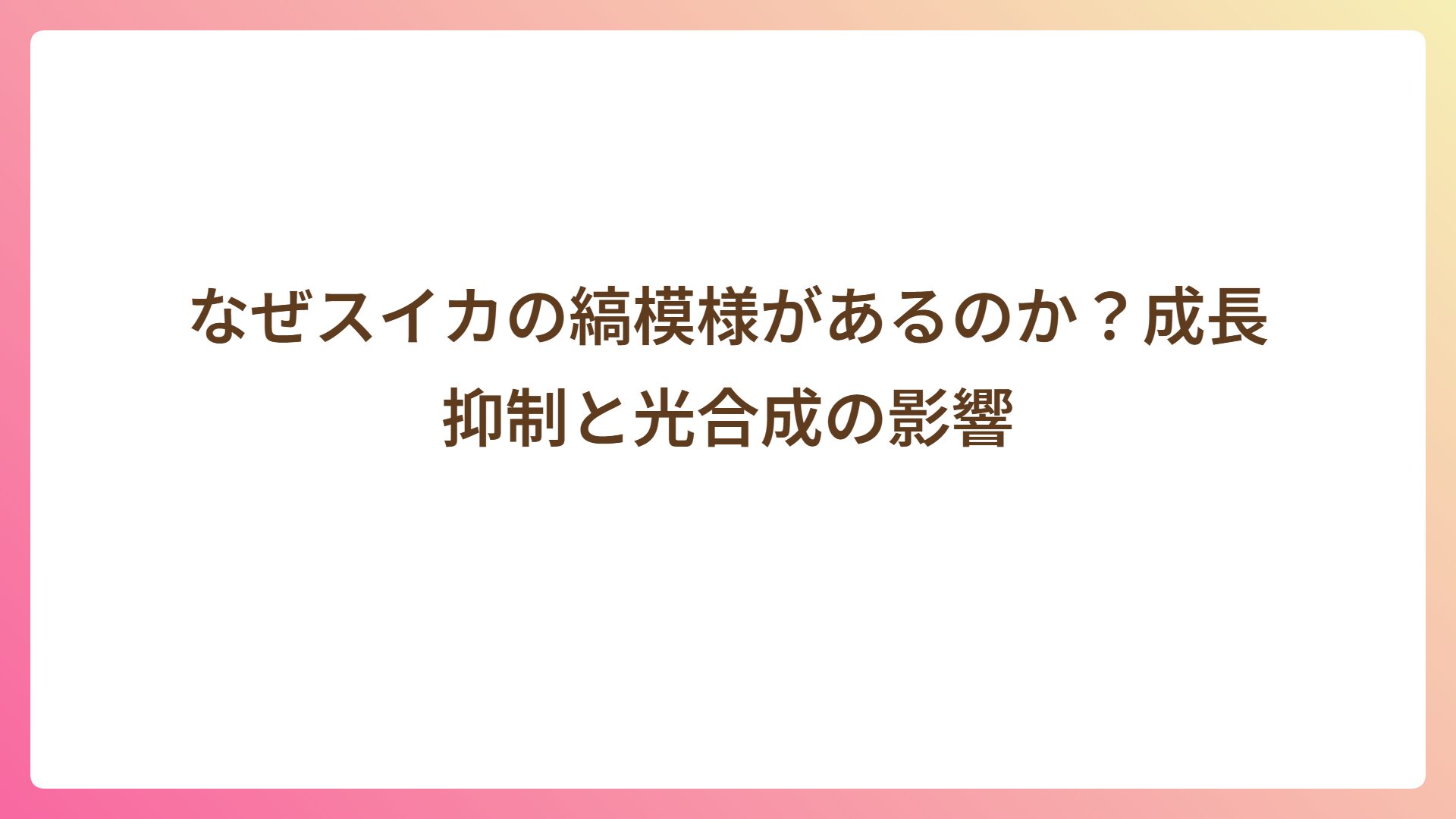
夏の風物詩スイカ。その表面に走る緑と黒の縞模様は、まるで手で描いたように整っています。
品種による違いはあるものの、この模様はどのスイカにもほぼ共通して現れます。
いったい、スイカの縞模様はどのようにして生まれているのでしょうか?
成長速度の差による「表皮の伸びムラ」
スイカの果皮は、もともと淡い緑色の表層に、濃い緑の部分が筋状に現れる構造になっています。
この濃淡の差は、果実が成長する過程で生じる細胞の伸長速度の違いによって生まれます。
濃い緑の部分では、果皮の細胞分裂や膨張がわずかに抑えられており、表面がわずかに沈み込みます。
逆に明るい部分は細胞が活発に成長して膨らみ、光をより反射するため明るく見えます。
つまり縞模様は、果実表面の“成長ムラ”が色として視覚化されたものなのです。
光合成と色素生成のバランス
スイカの表皮には、クロロフィル(葉緑素)が含まれています。
光がよく当たる部分では光合成が活発に行われ、クロロフィルの分解や再生が繰り返されるため、色がやや淡くなります。
一方、光がやや届きにくい部分ではクロロフィルが濃く残り、より暗い緑色になります。
このように光の当たり方による色素濃度の変化も、縞模様を形成する一因です。
特に野外で育つスイカでは、果実の向きや葉の影によって微妙な光環境の差が生じ、縞模様がよりくっきりと現れます。
品種改良によって固定された「縞パターン」
もともと野生種のスイカには薄い筋がある程度でしたが、品種改良によって縞のコントラストが強い系統が選抜されてきました。
見た目の識別性が高く、熟度判定にも役立つため、農家や消費者にとってメリットが大きかったのです。
現在では、縞の幅・濃さ・パターンが遺伝的に安定しており、「縞あり(縞スイカ)」と「縞なし(無地スイカ)」という分類が存在します。
つまり縞模様は、自然現象が遺伝的に固定された結果でもあるのです。
まとめ
スイカの縞模様は、
果皮の成長速度の違い・光の影響・遺伝的選抜が組み合わさって生まれるものです。
見た目の美しさの裏には、植物の成長リズムと環境応答が隠されています。
スイカの模様は、自然が描いた“成長の記録”といえるのです。