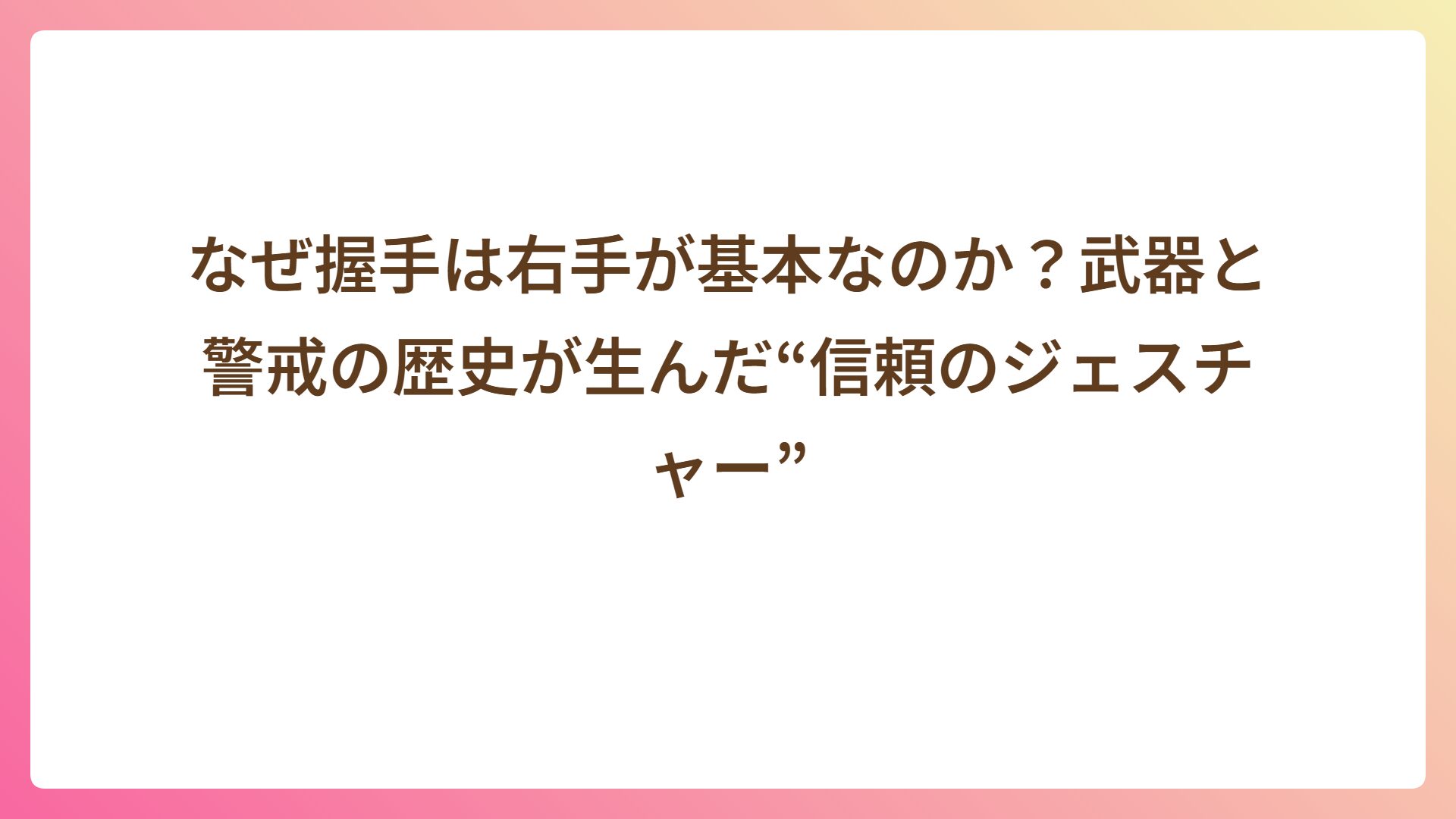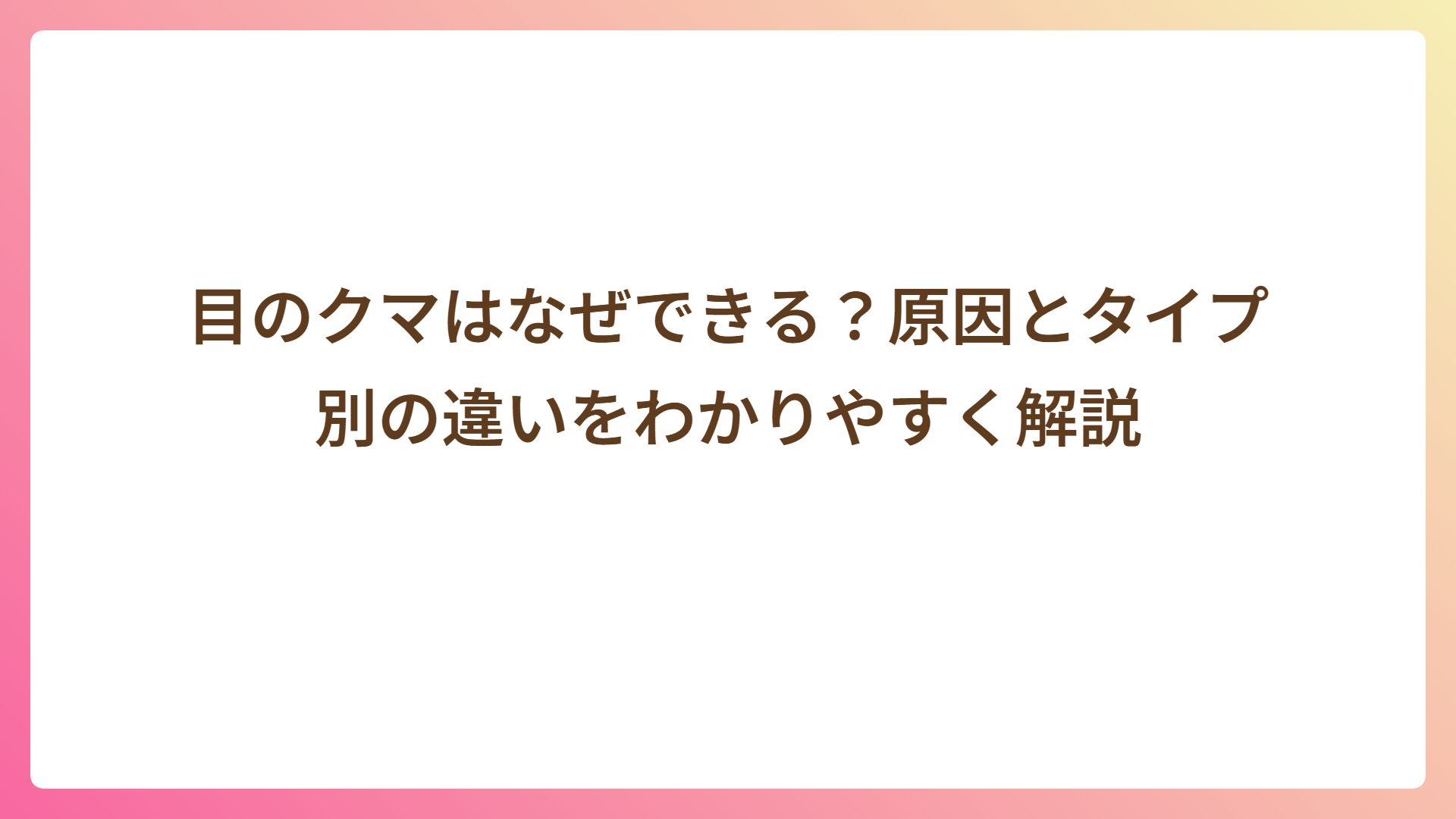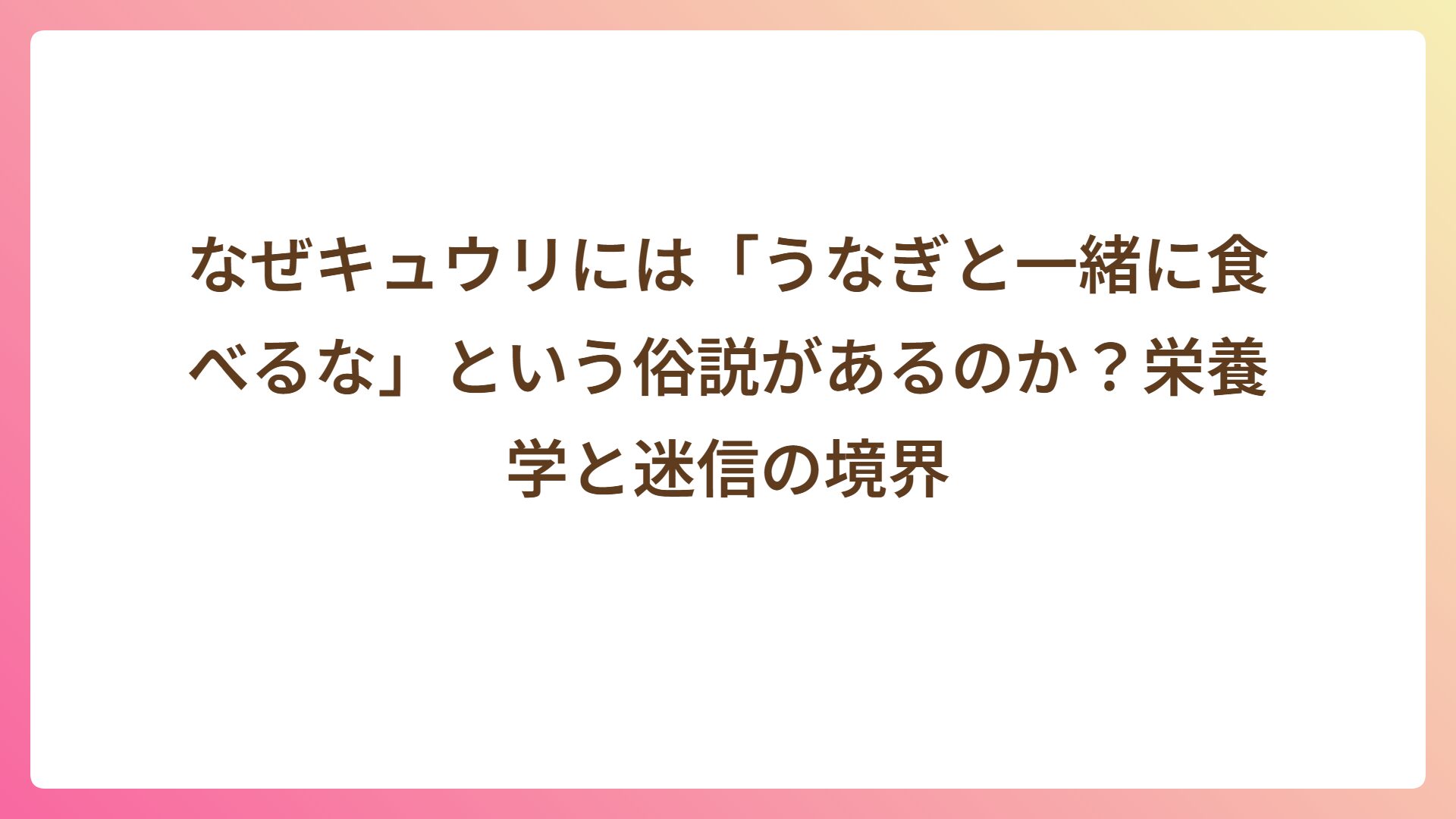なぜスーパーマーケットの通路は“一方通行になりがち”なのか?回遊率の最適化
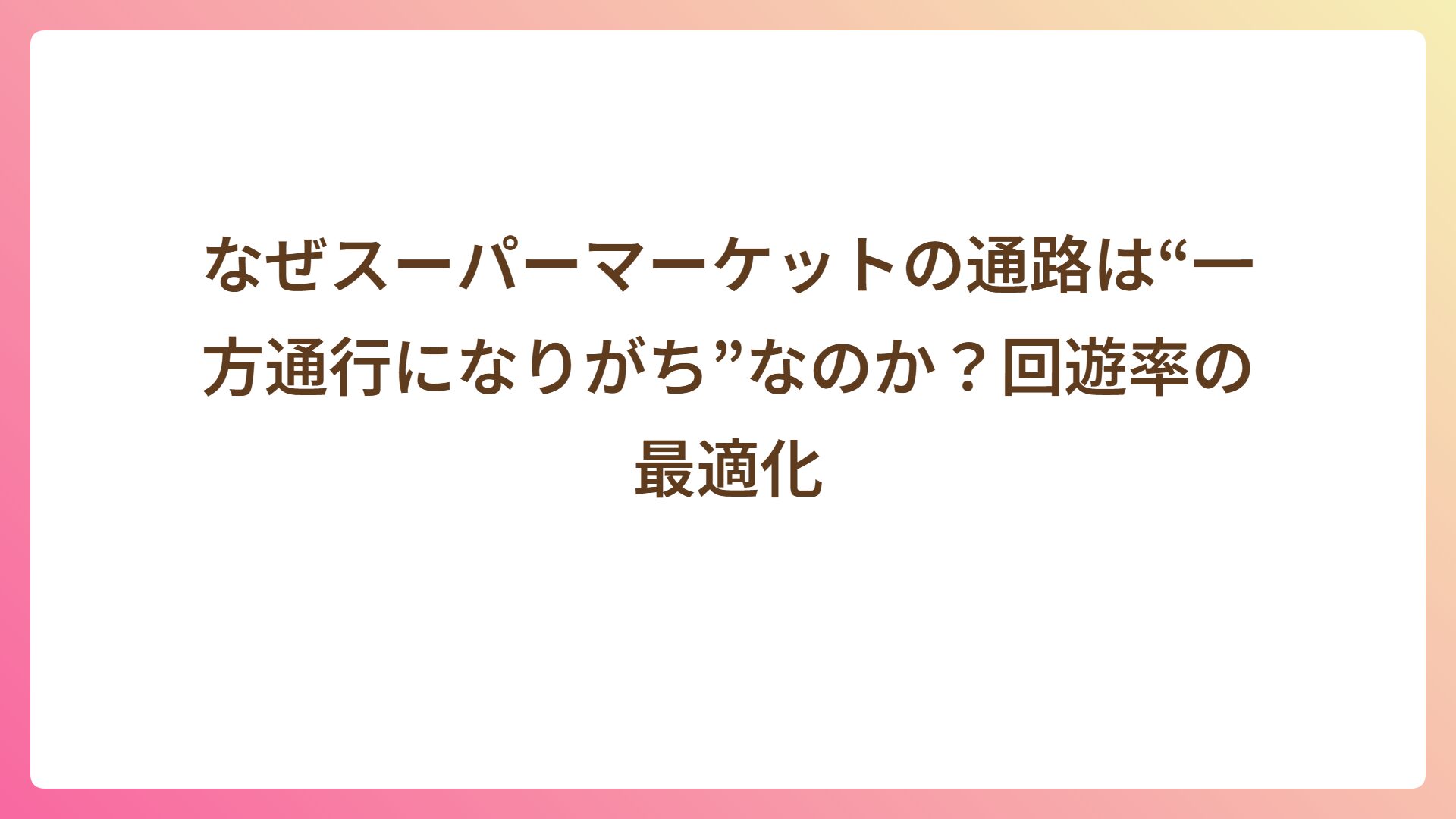
スーパーマーケットで買い物をしていると、気づけば店内の通路をみんな同じ方向に歩いています。
決められてはいないのに、自然と一方通行のように動線が形成される――これは偶然ではなく、売上を最大化するための店舗設計によるものです。
この記事では、スーパーの通路が“一方通行になりがち”な理由を、心理学と経済学の両面から解説します。
スーパーマーケットの“基本動線”は右回りが多い
日本の多くのスーパーでは、入口を入ってすぐに果物や野菜があり、店内を反時計回り(右回り)に進む構造が一般的です。
これは、買い物客が右利きであること、そして人の流れが自然に右方向へ向きやすいという行動心理に基づいています。
右回り設計にすると、
- 買い物かごを左手に持ち、右手で商品を取りやすい
- 右側の棚に商品を陳列すれば視線が自然に誘導される
- 通路内で客同士のすれ違いが減り、流れがスムーズになる
といった効果があります。つまり、通行方向を“決めずに誘導する”デザインなのです。
一方通行に見える理由①:買い物動線の“最短化”
スーパーでは、できるだけ多くの商品を見せつつ、買い物を効率よく進めてもらうことが求められます。
そのために設計されているのが「ワンウェイコントロール(One-Way Control)」という考え方です。
入口から出口までの流れを一本化し、
- 行き止まりを作らず、自然に進める
- 前の通路に戻りにくくする(Uターンしづらいレイアウト)
- 会計までの導線で主要カテゴリーをすべて通過させる
ことで、買い忘れを減らし、回遊率(どれだけ多くの売場を通ったか)を最大化する仕組みです。
一方通行に見える理由②:カートの向きとすれ違い防止
スーパーマーケットでは、通路幅が「カート2台+人1人がすれ違える程度」に設定されています。
これはあえて広すぎず狭すぎない設計。
広すぎると売り場効率が悪くなり、狭すぎると混雑が生じます。
しかし同じ方向に進むことで、
- すれ違いが減ってストレスが少ない
- 立ち止まって商品を選んでも後ろの人に迷惑をかけにくい
といったメリットが生まれます。
結果的に、客同士の“自然な譲り合い”が一方向の流れを作り出しているのです。
一方通行に見える理由③:購買心理を活かした配置戦略
通路設計には心理的な仕掛けもあります。
たとえば、
- 入口付近に生鮮食品を置く(鮮度の印象で店全体の好感度を上げる)
- 奥に日配・惣菜・精肉など“目的買い”商品を配置(途中で他商品を見せる)
- 出口付近にレジ横商品やスイーツなど“衝動買いエリア”を設ける
こうしたレイアウトはすべて、一方向の流れを前提に設計されています。
途中で逆走すると、通路の幅や棚の向き、照明の角度まで「逆向きに歩きづらく」感じるようになっているのです。
一方通行に見える理由④:視線誘導と照明効果
実は、照明や床のパターンも人の流れに影響を与えます。
通路の奥が明るく、手前がやや暗くなるよう照明を配置すると、人は明るい方向へ進みたくなるという心理が働きます。
また、床や棚の配置がわずかに斜めになっている店舗もあり、無意識に一方向へ誘導されるよう設計されています。
こうした“見えない誘導”によって、店内は自然と一方通行の流れになるのです。
一方通行設計のメリット:売上と顧客体験の両立
スーパーの一方通行的レイアウトには、次のようなメリットがあります。
- 客が店内の多くの売場を通過するため、購買機会が増える
- 混雑や接触が減り、快適な買い物体験が維持できる
- 補充スタッフの動線も分かりやすく、作業効率が上がる
つまり、顧客満足度と売上効率を両立させる“静かな最適化”なのです。
まとめ:スーパーの一方通行は“心理と設計”の融合
スーパーマーケットの通路が一方通行になりがちなのは、
- 行動心理に基づいた右回り設計
- 回遊率と効率を高めるワンウェイ動線
- 視線・照明・棚配置による誘導効果
といった複数の要素が組み合わさっているためです。
意識せずとも私たちは、店舗設計に導かれて理想的な買い物ルートを歩いているのです。