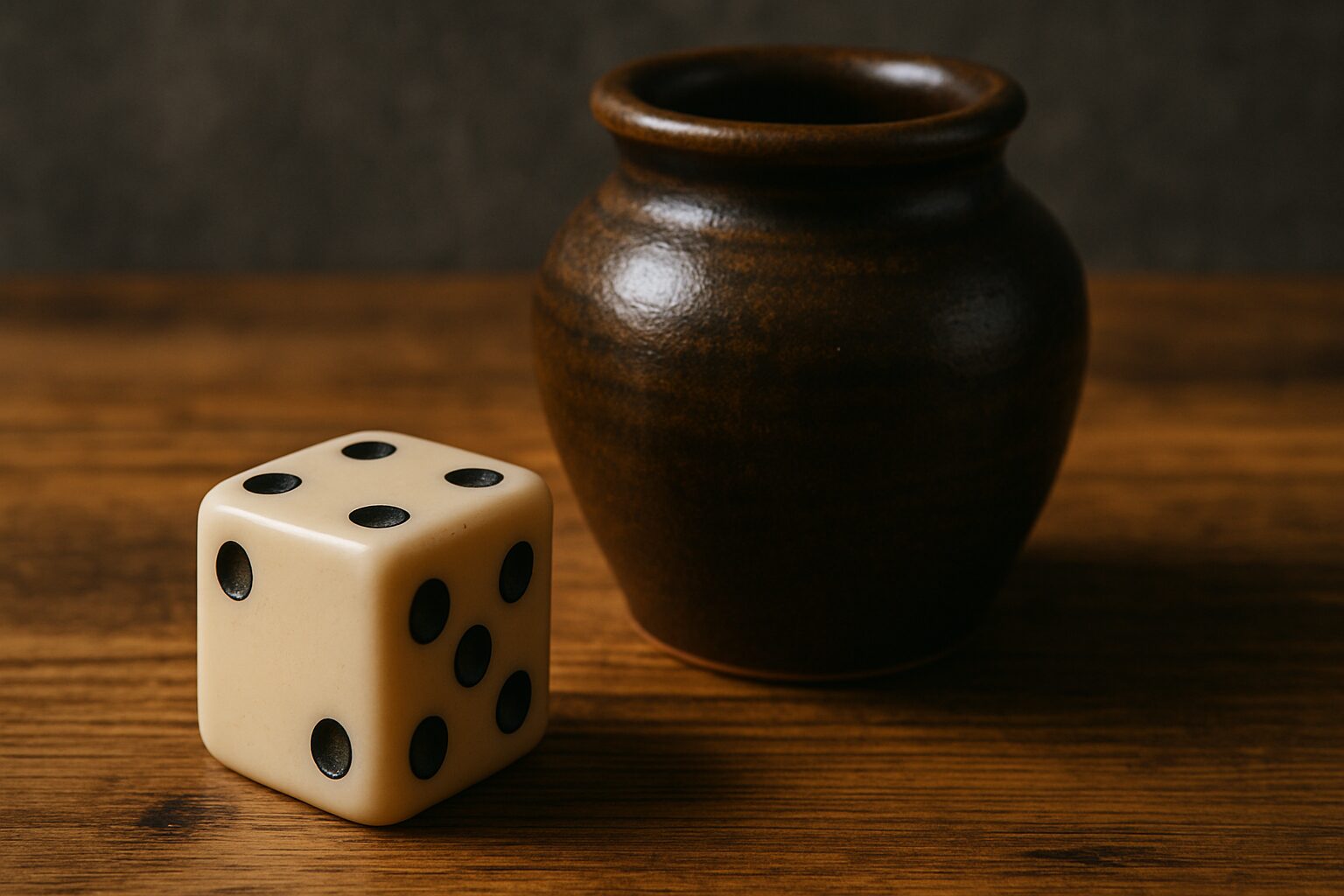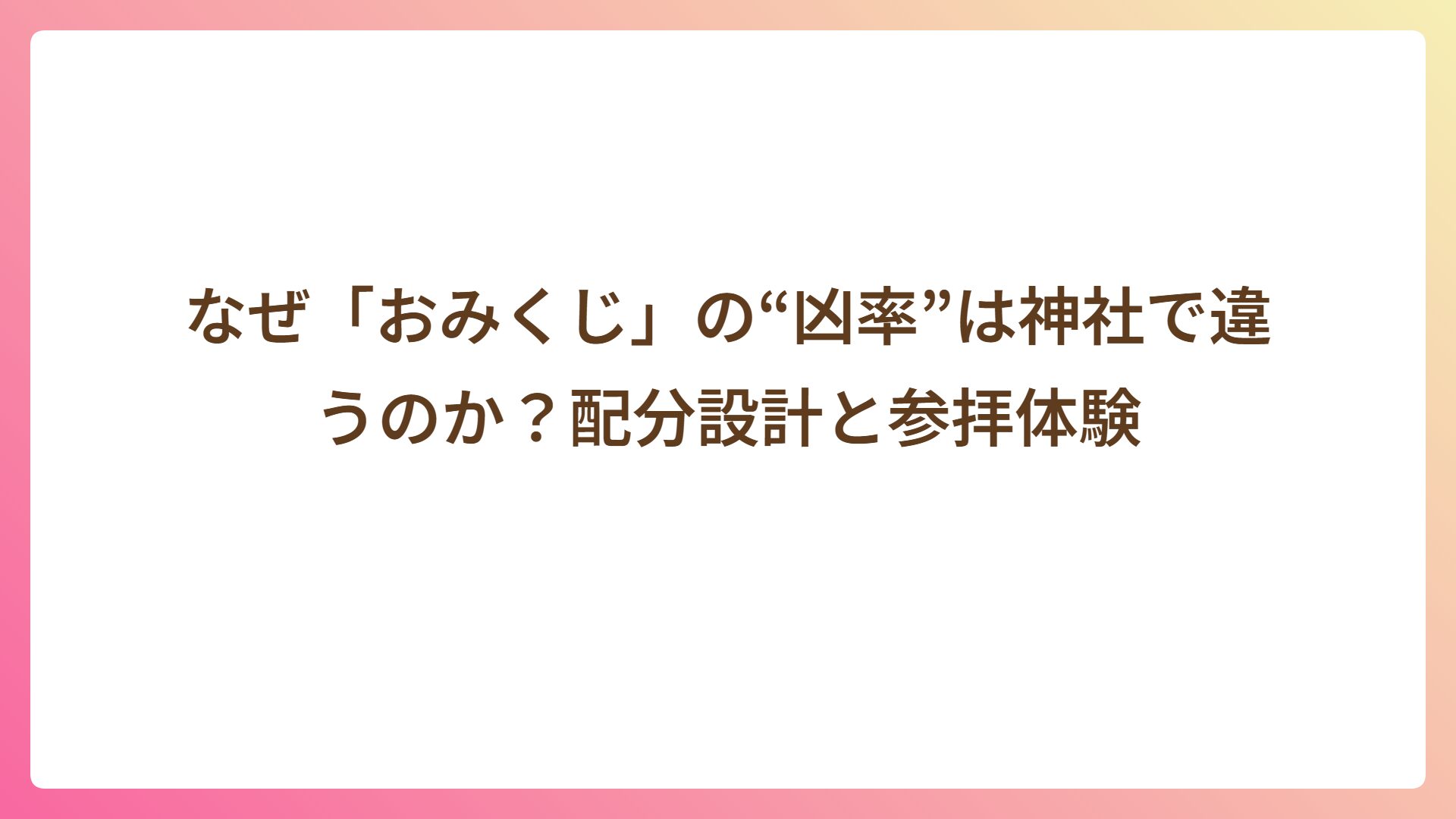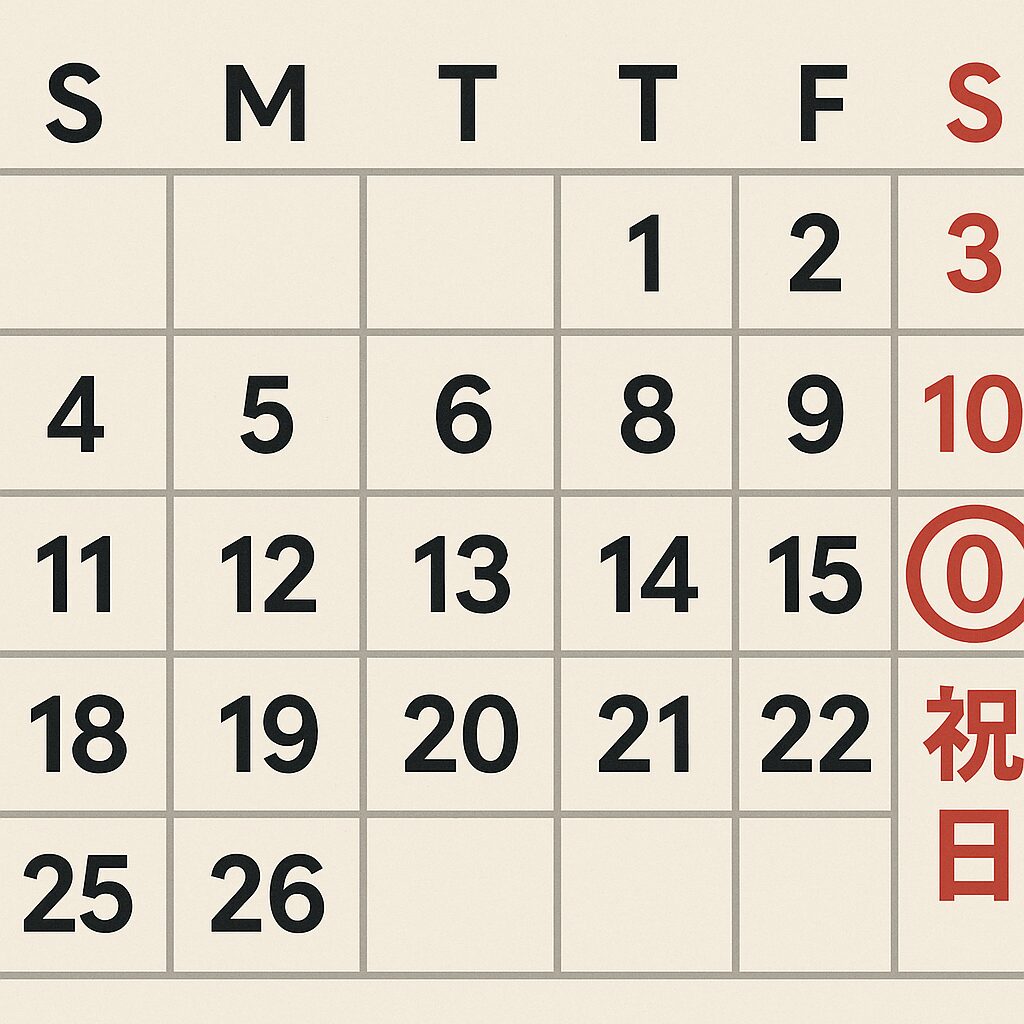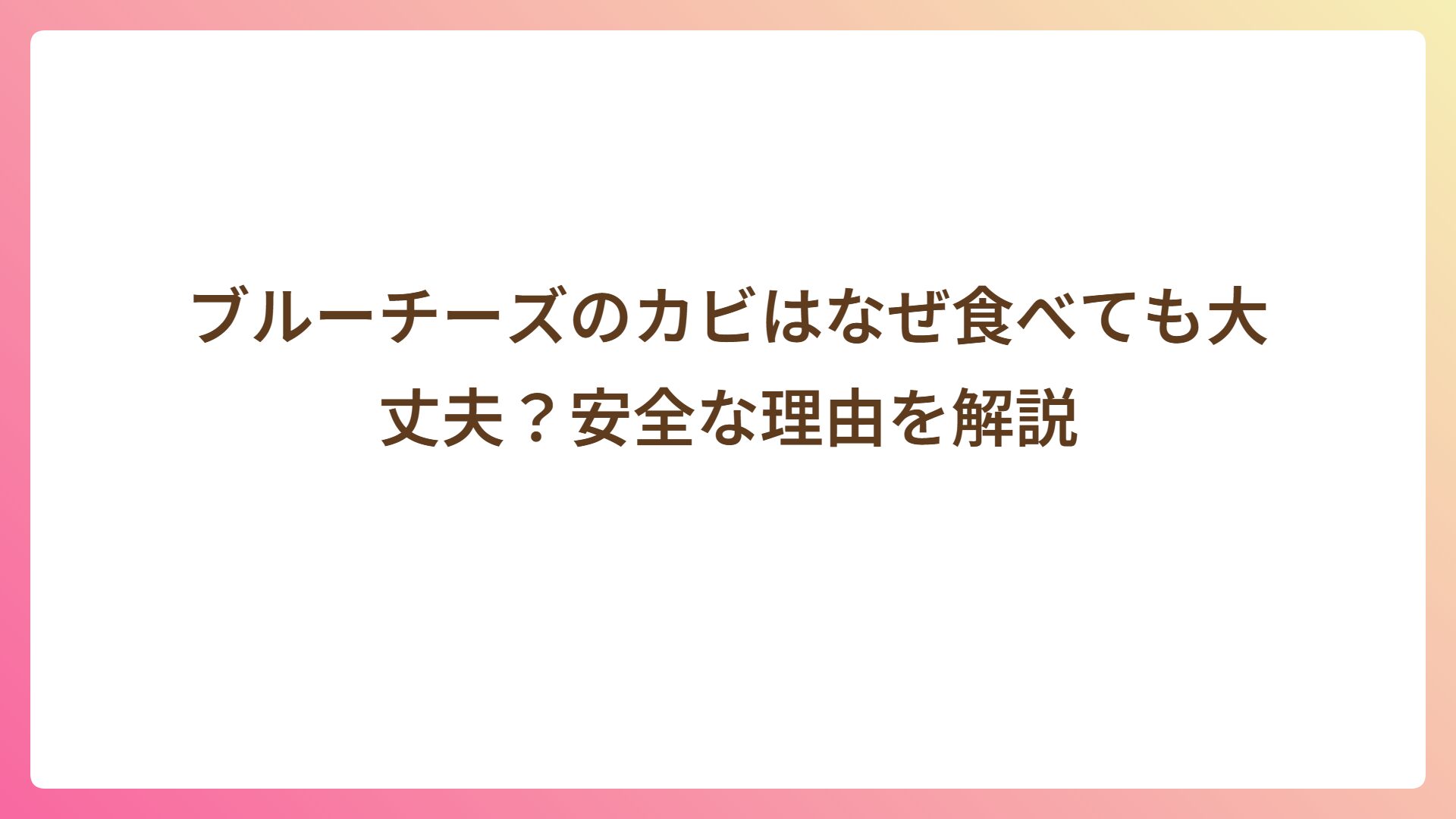なぜ卵焼きは甘い派と塩派に分かれるのか?江戸前文化と保存技術
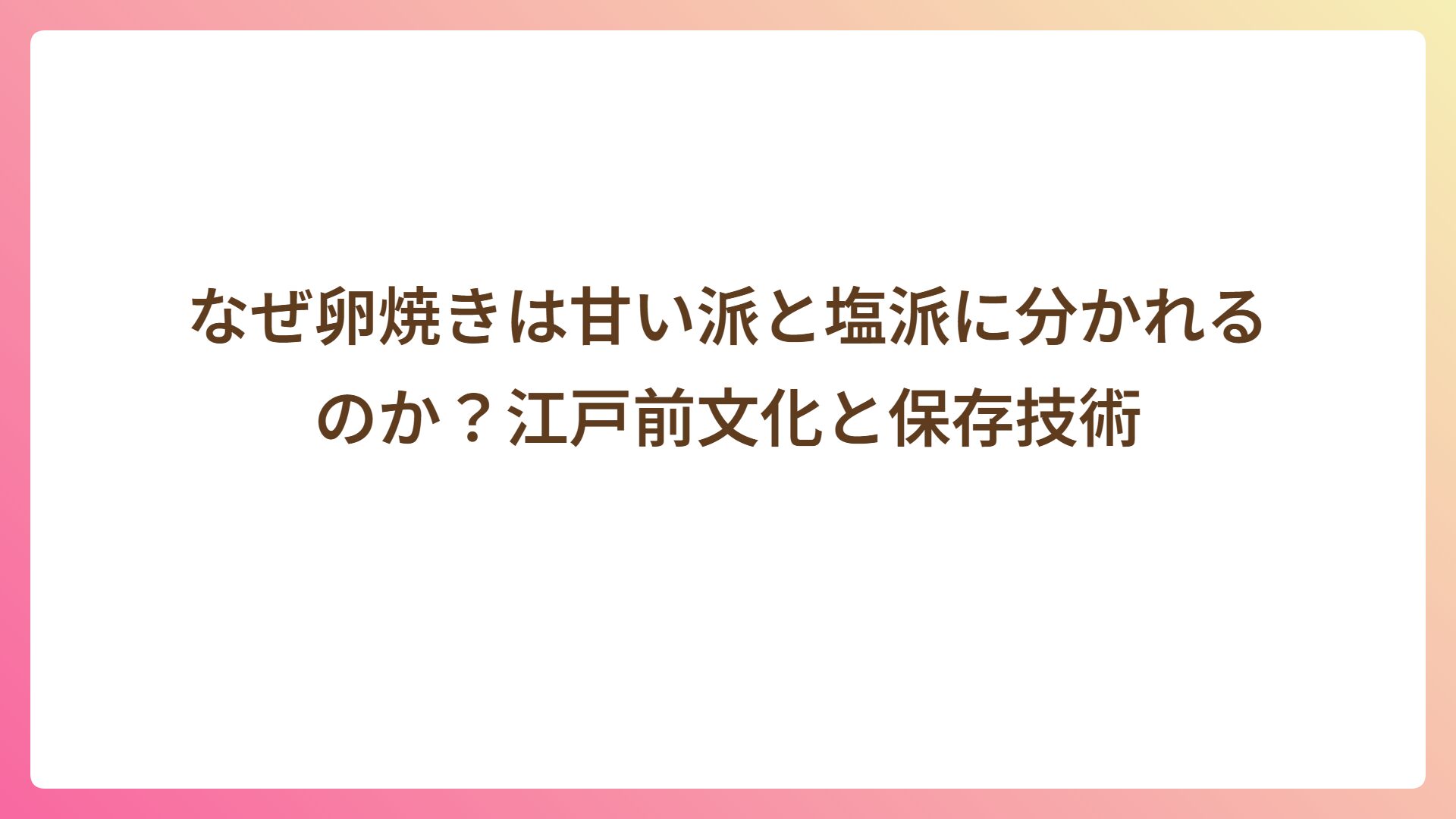
お弁当や朝食の定番「卵焼き」。
しかし、食べてみると甘い卵焼きと塩味の卵焼きがあり、地域によって好みが分かれます。
なぜ同じ料理なのに、ここまで味の傾向が違うのでしょうか?
その背景には、江戸時代の食文化と保存技術の違いが深く関係しています。
江戸前寿司から広まった「甘い卵焼き」
関東で主流の甘い卵焼きは、実は江戸前寿司の影響によるものです。
江戸時代、寿司は「握り寿司」よりも「屋台の早飯」に近い存在で、
調味料でしっかり味付けされた甘辛い料理が好まれた時代でした。
また、当時の寿司屋では魚介を酢や煮切りで保存していたため、
卵焼きにも砂糖と醤油を多めに入れて日持ちを良くする工夫がなされました。
この「甘くてコクのある厚焼き卵」は寿司の締めとして人気を集め、
江戸の味として定着していきます。
さらに砂糖は当時の高級品。
甘味をふんだんに使う卵焼きは、豊かさと粋を象徴する料理でもありました。
関西では「出汁巻き」が主流
一方、関西では古くから出汁文化が発達していました。
昆布だしを中心にした料理が多く、素材の味を活かすことが重視されたため、
卵焼きにも砂糖を使わず、出汁と塩で上品に仕上げるスタイルが好まれました。
この「出汁巻き卵」は、ふわりとした口当たりとだしの香りが特徴で、
茶碗蒸しや吸い物と同じく“だし文化”の延長線上にある料理です。
保存よりも出来立てを味わう贅沢が重んじられた地域性が反映されています。
甘味=保存と価値の象徴
現代では嗜好の違いと見られがちですが、
本来、甘味の強い卵焼きには保存性を高める実用的な目的がありました。
砂糖には浸透圧による防腐効果があり、
高温多湿な江戸の気候でも食材を長持ちさせる役割を果たしました。
また、当時の甘味料は高価だったため、
甘い卵焼きは「贅沢な一品」「ごちそう」の象徴として発展したのです。
現代に残る「地域の味の名残」
現在でも、東京の惣菜店や寿司屋では甘い卵焼きが多く、
大阪・京都では出汁巻きが定番。
これは単なる好みの違いではなく、食文化のルーツの名残です。
東日本では「濃い味・保存重視・砂糖文化」、
西日本では「薄味・素材重視・出汁文化」といった傾向が、
卵焼きの味の違いにそのまま現れているのです。
まとめ
卵焼きが甘い派と塩派に分かれるのは、
江戸の保存食文化と関西の出汁文化が並行して発展したためです。
甘い卵焼きは「江戸前の実用と粋」、
塩味の出汁巻きは「京の風味と繊細さ」。
一見小さな違いのようでいて、
その一口には日本の食文化の二大潮流が詰まっているのです。