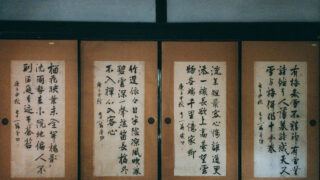「出産は命懸け」は本当か?周産期死亡率を交通事故・労災と比較して徹底検証
mixtrivia_com
MixTrivia

「田んぼ」という言葉、みなさん何気なく使っていると思いますが、「んぼ」ってよく考えると不思議な響きじゃないですか?
「田」だけでも意味は通じるのに、わざわざ「んぼ」がつくのはなぜなのでしょうか?
今回は、そんな「田んぼ」の語源と、日本語特有の言葉の変化について解説します。
「田んぼ」という言葉のルーツは、「田面(たのも)」または「田面(たおも)」とされており、「田んぼの表面」や「田の土地の面」を意味します。
この「田面(たのも)」が徐々に口語で崩れていき、
と変化していったのが「田んぼ」だと考えられています。
つまり、「んぼ」はもともとあった「のも(面)」という言葉が変化した結果なのです。
「たのも」が「たんぼ」になるのは不自然に思えるかもしれませんが、実は日本語ではこのようにま行とば行が入れ替わる音変化はよく見られます。
たとえば、
など、音の濁りや変化によって言葉が柔らかく、また地域に合わせて使いやすくなっていくことがあります。
「んぼ」もこの一種と考えると、それほど特殊ではないのです。
「たんぼ」のように、「んぼ」で終わる日本語は確かに珍しいですが、完全に唯一というわけではありません。
たとえば、
など、地方の方言や古語の中では同様の響きが見つかることがあります。
ただし、標準語の中では非常にレアな言葉の構成といえるでしょう。
「田んぼ」の「んぼ」は不思議な響きですが、言葉の歴史や音の変化を知ると意外と自然に思えてきます。
身近な言葉にこんな奥深い背景があるとわかると、日本語って面白いですよね。
この他にも日本語に関する豆知識をたくさん紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。