なぜ“引き戸”は日本で定着したのか?気候と住宅構造が生んだ開口文化の理由
mixtrivia_com
MixTrivia
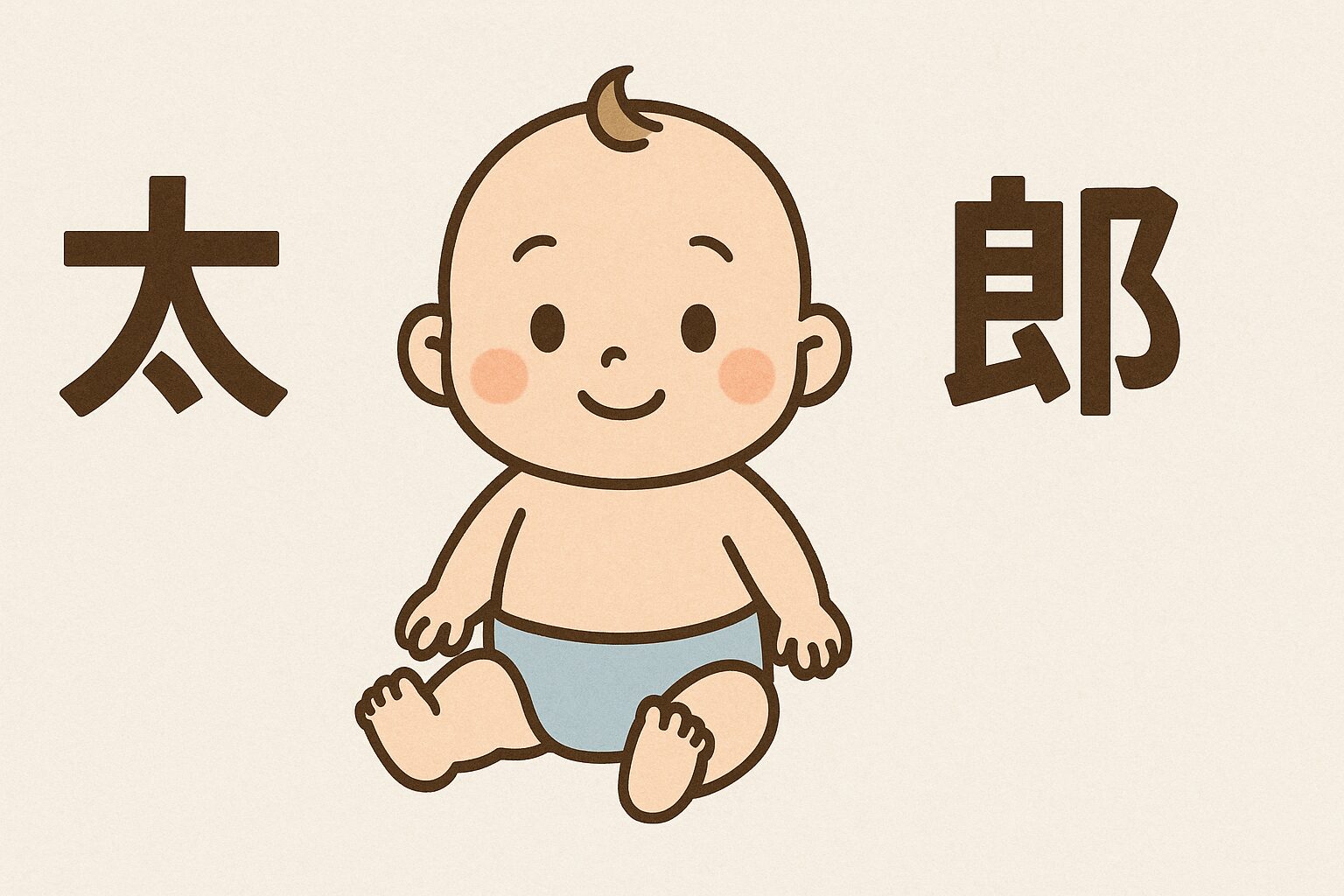
日本の男性名でよく見かける「太郎」。
次男なら「次郎」、三男なら「三郎」といったパターンは理解できますが、「太郎」だけは「太」が数字でも順序でもなく、不思議に思ったことはありませんか?
実はこの「太」には、古くから特別な意味が込められているのです。
「太郎」を分解すると、「郎」は男性を指す漢字で、「新郎新婦」の「郎」と同じです。
問題は「太」の部分ですが、漢和辞典を調べると以下のような意味が見つかります。
特に重要なのは「物事のはじめ」という意味です。これにより、「太郎」は**「最初の男子」「最初の子」**を表す名前として使われるようになったのです。
「太」を「物事のはじめ」という意味で使った熟語は少なくありません。
たとえば——
こうした用法から、「太郎」が「最初の男子=長男」と結びついたことが理解できます。
長男を「太郎」、次男を「次郎」と呼ぶ風習は、平安時代の後半に武士が台頭した時期から盛んになったといわれます。
当時は「諱(いみな)」と呼ばれる本名を日常的に呼ぶことは避けられており、代わりに
などをもとに通称を用いる習慣がありました。その中で「太郎」「次郎」が広まり、武士の名乗りとして定着していったのです。
有名な例が、源義家(みなもとのよしいえ)です。
彼は源頼義の長男であったことから「太郎」と呼ばれ、さらに「石清水八幡宮で元服した」ことと合わせて「八幡太郎義家」の通称を持ちました。
このように「太郎」は単なる名前ではなく、「家の長男であること」を示す記号的な役割を持っていたのです。
「太郎」は単なる名前ではなく、漢字の意味と社会の風習が合わさって生まれた長男の象徴だったのです。






