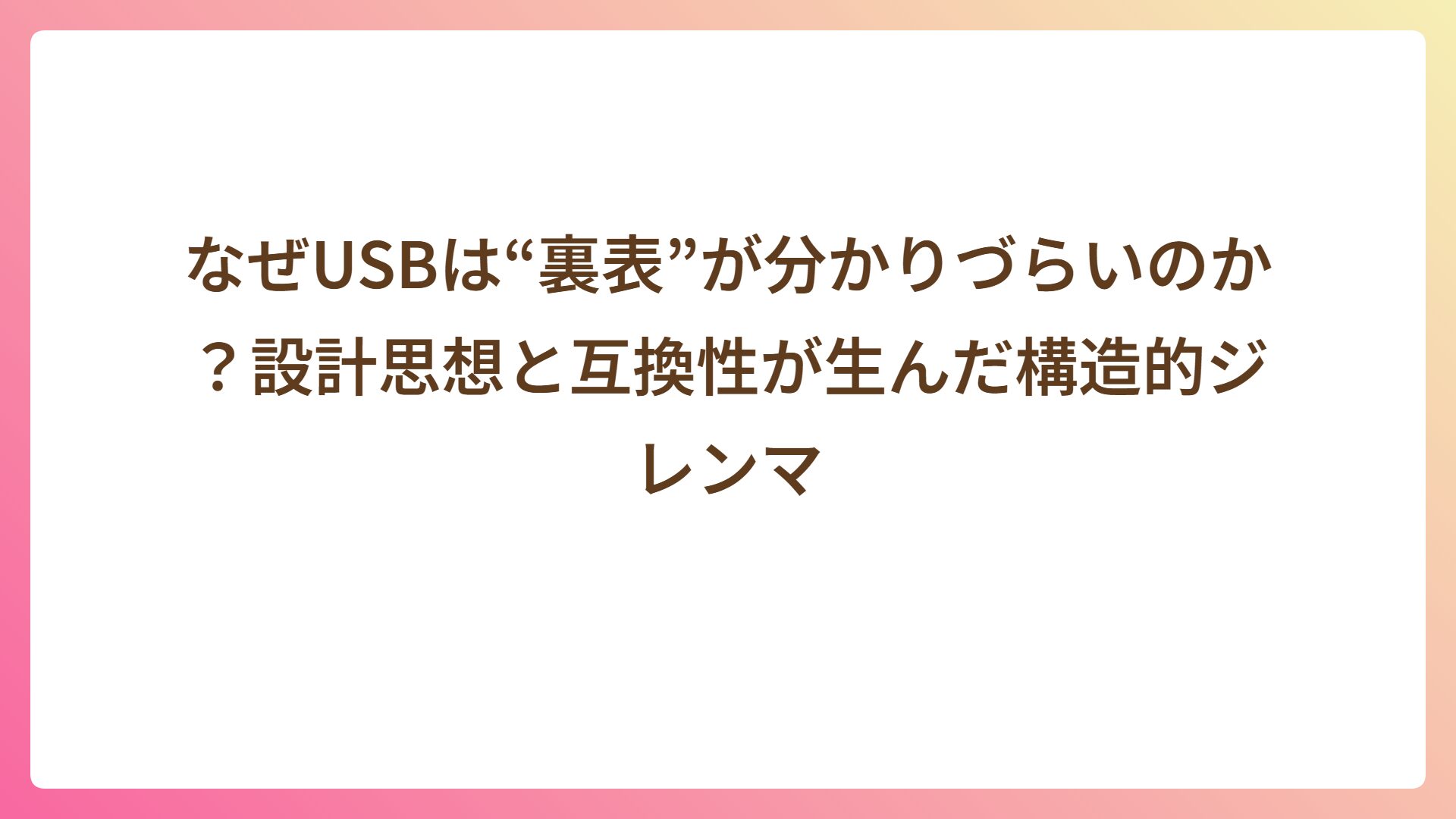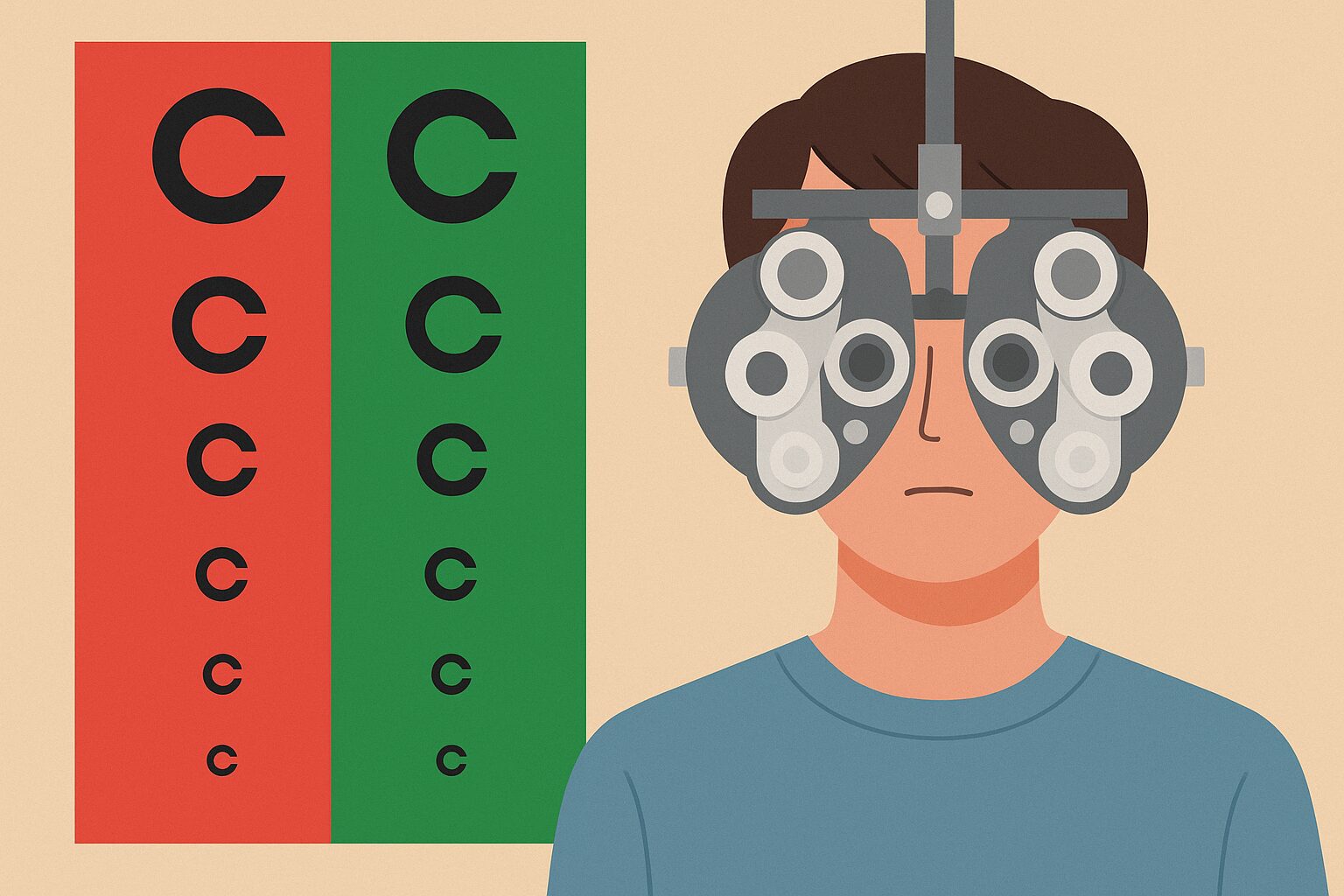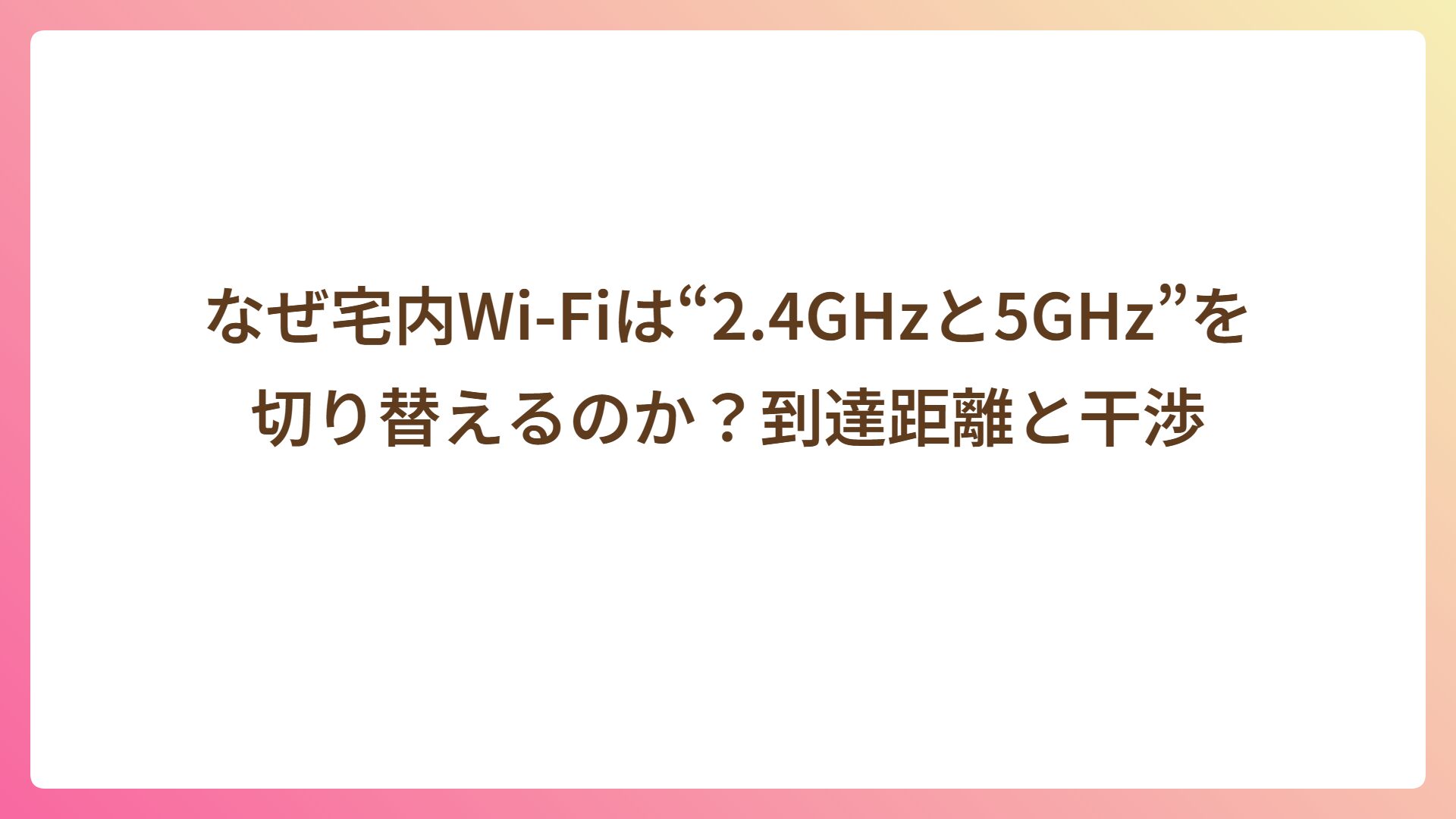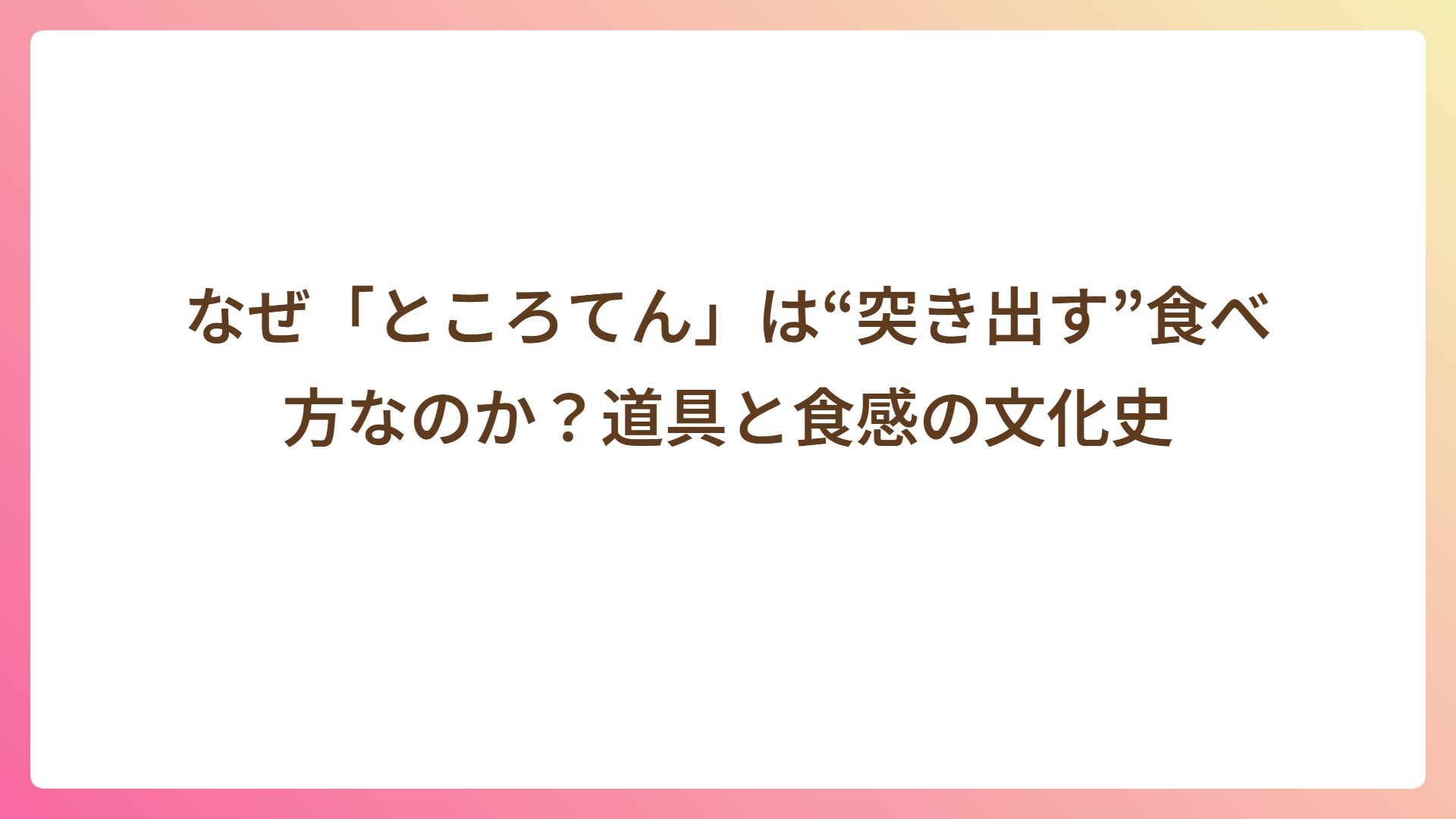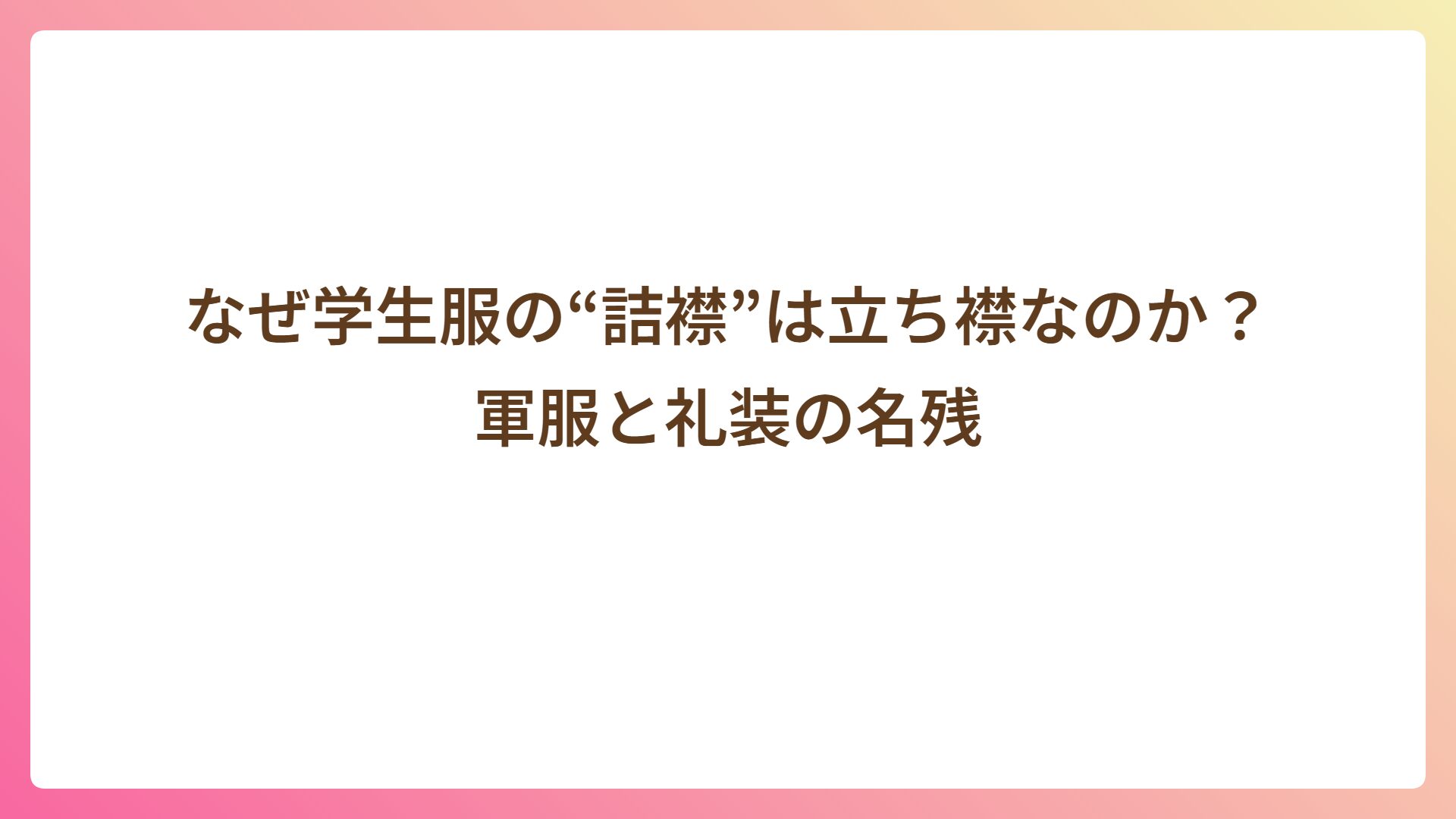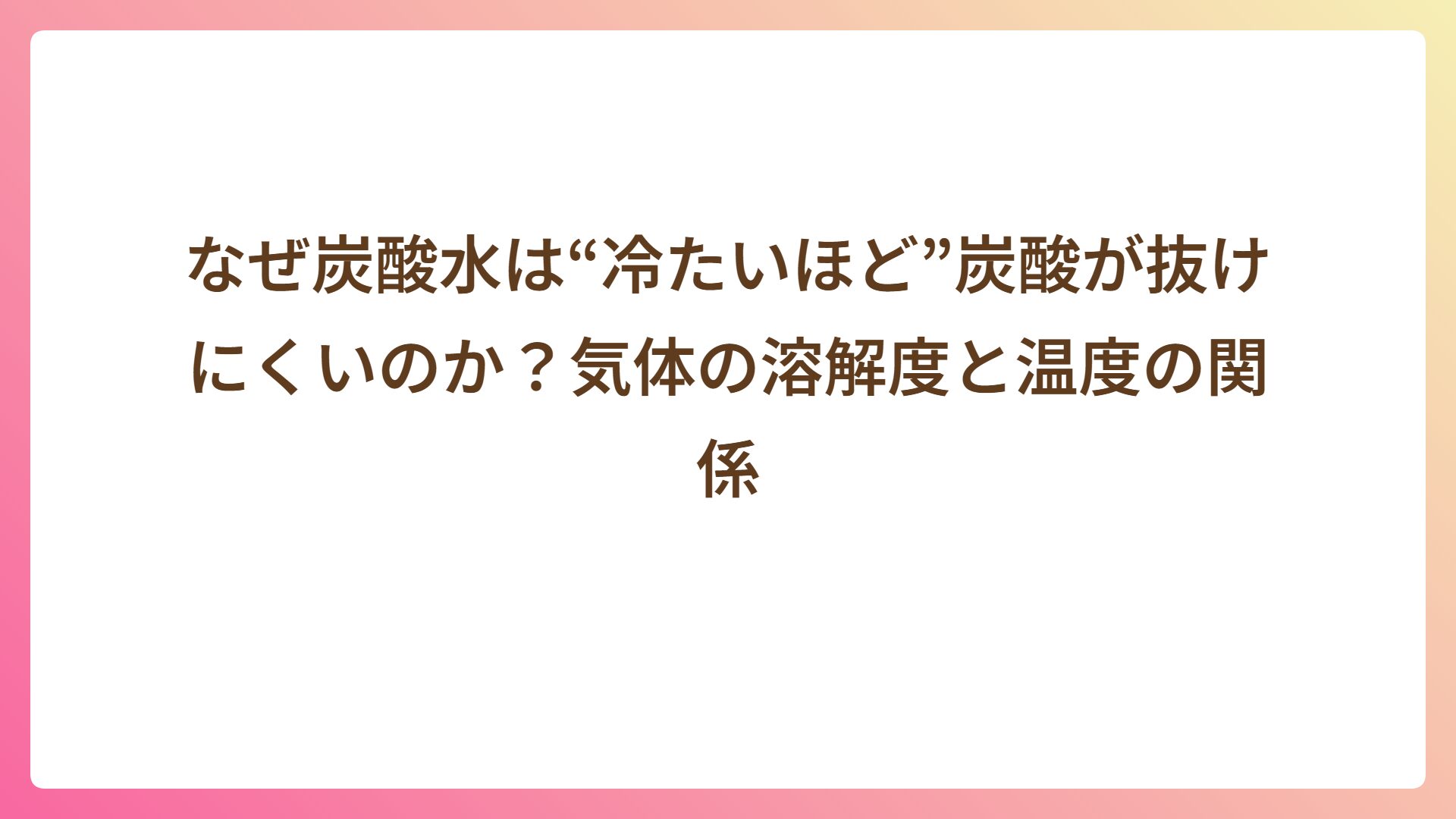なぜ歩道の点字ブロックには2種類あるのか?誘導ブロックと警告ブロックの役割の違い
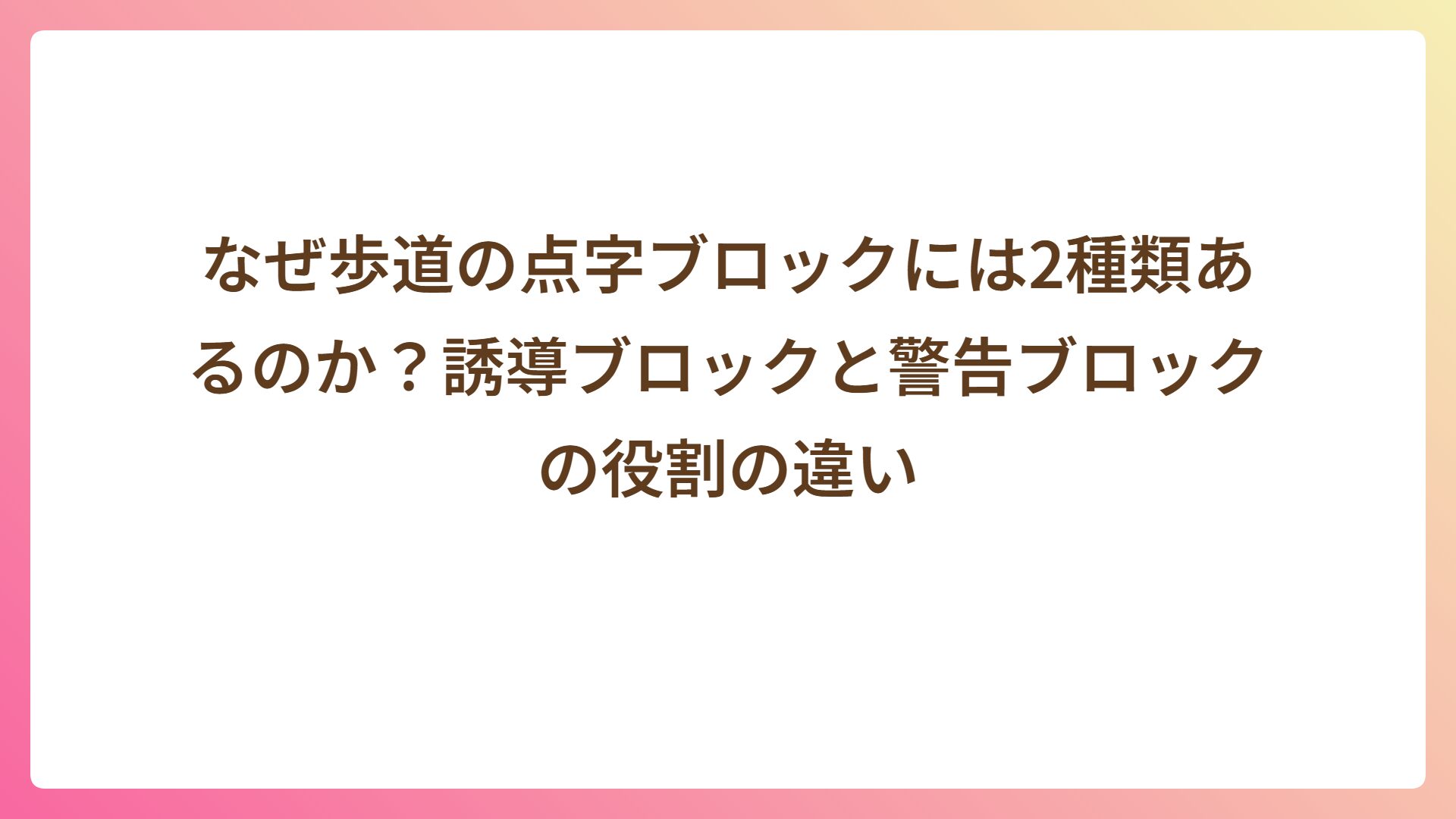
街を歩いていると、歩道や駅のホームに敷かれた黄色いブロックをよく見かけます。
実はこの「点字ブロック」には、線の形をしたものと点が並んだものの2種類があります。
どちらも視覚障がい者のための安全設備ですが、果たす役割がまったく違うのです。
点字ブロックは“岡山発祥”の日本の発明
点字ブロックは、1967年に岡山県の三宅精一氏が考案しました。
目の見えない人が安全に歩けるよう、足裏で情報を感じ取れるように工夫されたものです。
この発明は高く評価され、現在では世界100か国以上で採用。
黄色いブロックが「視覚障がい者を守る道しるべ」として国際的に広まっています。
「線状ブロック」=進む方向を示す“誘導”
細い線が何本も並んでいるタイプは、「誘導ブロック」と呼ばれます。
正式名称は「線状ブロック」または「誘導表示」。
これは足裏の感触で「この方向に進めば安全」ということを伝えるもので、
- 駅のホームの通路
- 歩道の真ん中
- 施設入口までの経路
などに設置されています。
視覚障がい者は白杖(はくじょう)や靴の裏でこの凹凸を感じ取り、
線の方向に沿ってまっすぐ進むことで目的地へ安全に誘導される仕組みです。
「点状ブロック」=注意を促す“警告”
一方、丸い点が並んでいるタイプは「警告ブロック」または「点状ブロック」。
これは“ここで立ち止まって注意が必要”という意味を持ちます。
設置される場所の例としては:
- 駅ホームの端(線路の直前)
- 横断歩道の手前
- エレベーターや階段の前
- 自動ドア・券売機などの前
つまり、「危険・変化・交差点」を知らせるためのストップサインなのです。
「線」から「点」へ──安全の切り替えポイント
多くの場所では、線状ブロックの誘導路が途中で点状ブロックに切り替わる構造になっています。
これは「ここから先は注意して進んでください」という区切りのサイン。
たとえば駅構内では、
ホームへの誘導ラインが点状ブロックの位置で止まり、
その先が線路の直前であることを知らせます。
この“線から点への切り替え”こそ、
点字ブロックの最も重要なメッセージの一つなのです。
見た目が黄色いのは“視覚補助”のため
点字ブロックが黄色いのは、単なるデザインではありません。
弱視(視力の一部が残っている)人にも見やすいよう、
コントラストが強く目立つ色として採用されています。
ただし、背景が黄色っぽい場所(白線の多い道路やベージュの床など)では、
灰色や濃い色の点字ブロックが使われることもあります。
目的はあくまで「視認性の確保」であり、
“黄色=義務”ではなく“見えやすい色を選ぶ”のが原則です。
点字ブロックを邪魔する行為は“危険”
近年、点字ブロックの上に自転車や荷物を置いたり、
歩行者が立ち止まったりするケースが問題視されています。
点字ブロックは「視覚障がい者の命綱」。
わずか数センチの障害物でも進路を失わせ、
事故につながる危険があります。
歩道や駅構内では、ブロックの上を塞がない意識が求められます。
まとめ:2種類のブロックで“歩行の安全”を守る
点字ブロックが2種類あるのは、
- 線状ブロック:進む方向を示す(誘導)
- 点状ブロック:注意・危険を知らせる(警告)
という明確な役割分担があるからです。
この2つが連携して、
視覚障がい者が「どこへ進むべきか」「どこで止まるべきか」を
足の裏で感じ取れるようになっています。
つまり、点字ブロックとは“街に組み込まれた見えない言葉”。
それを正しく理解することが、誰にとっても安全な街づくりの第一歩なのです。