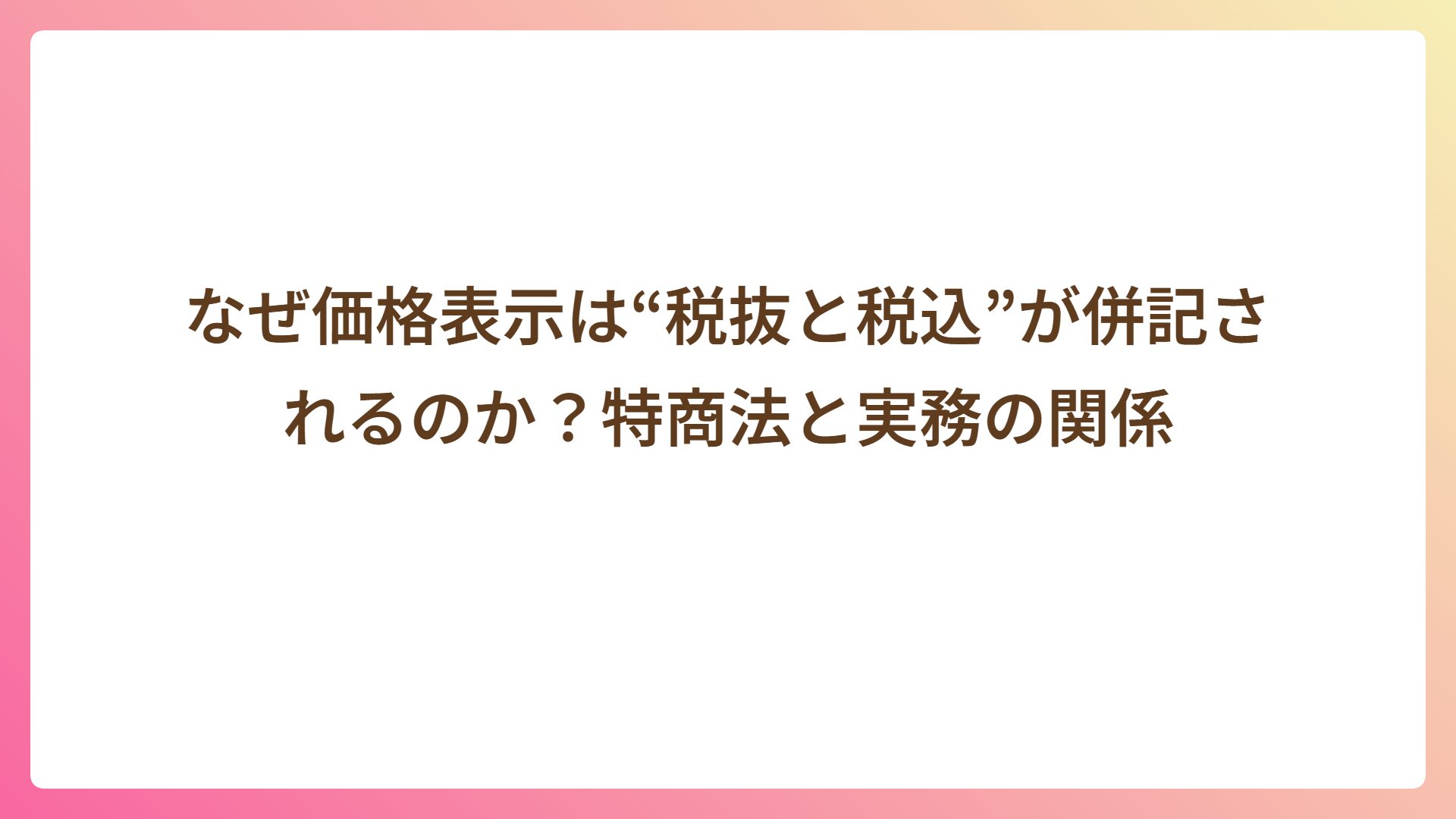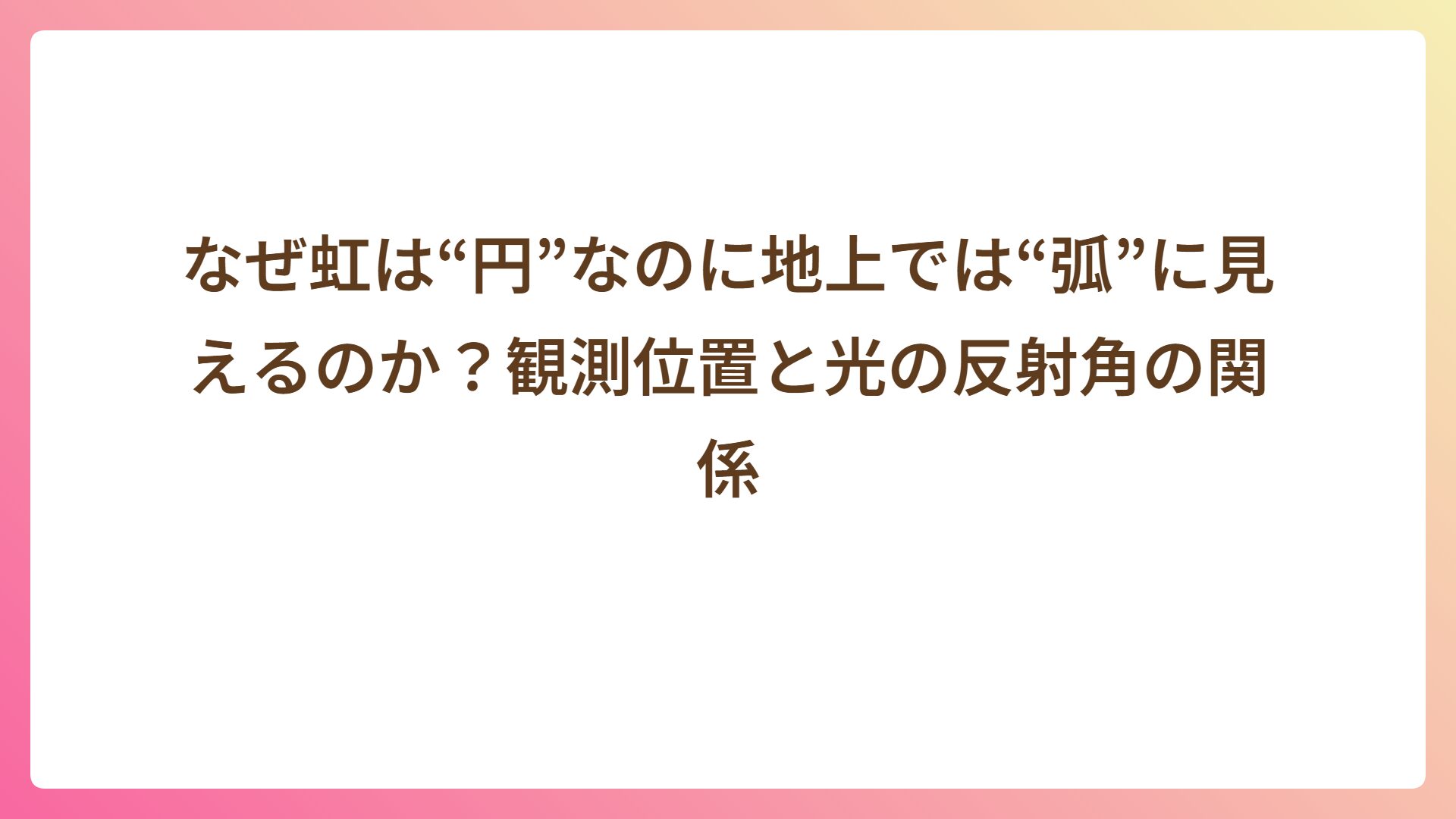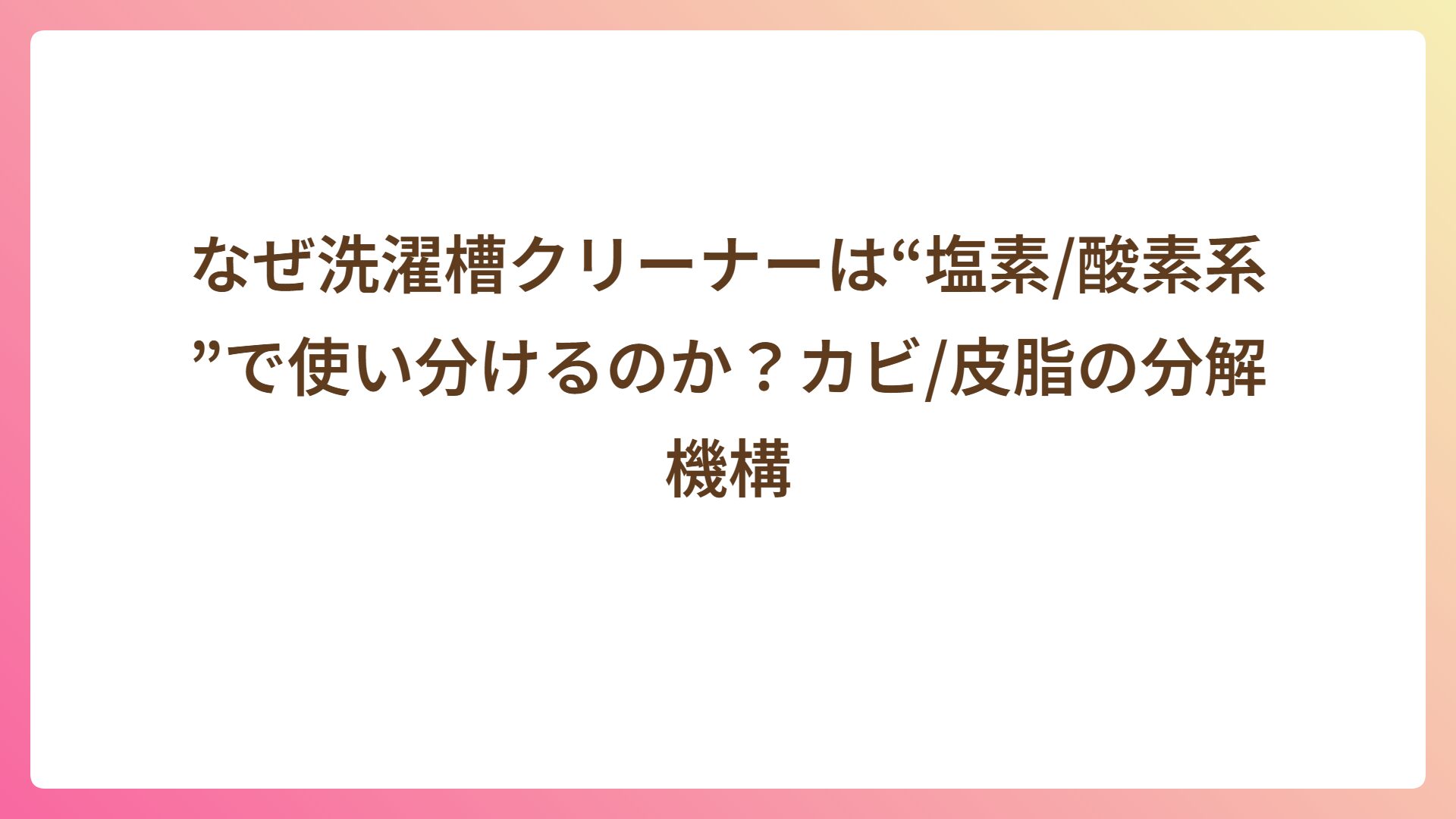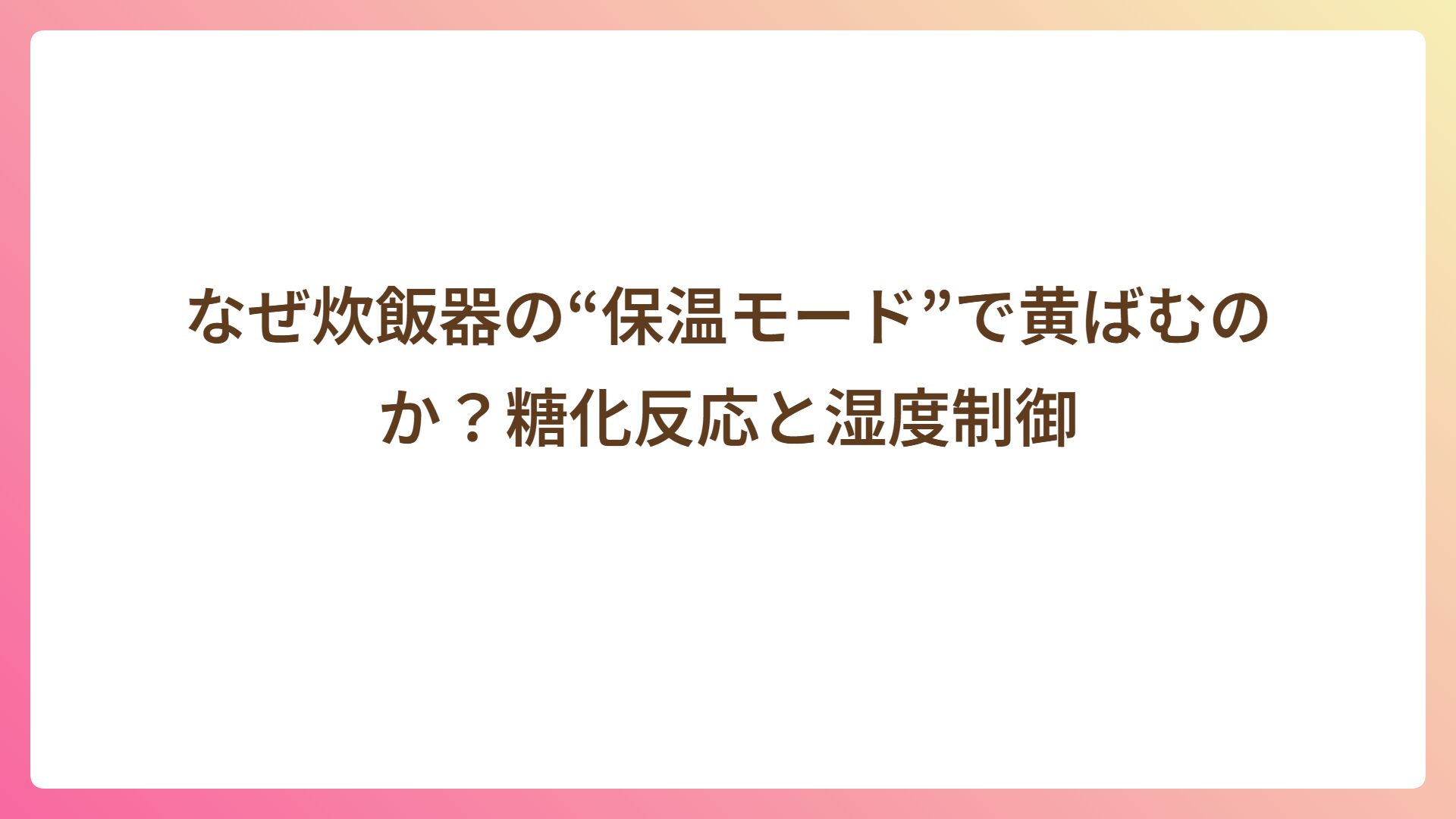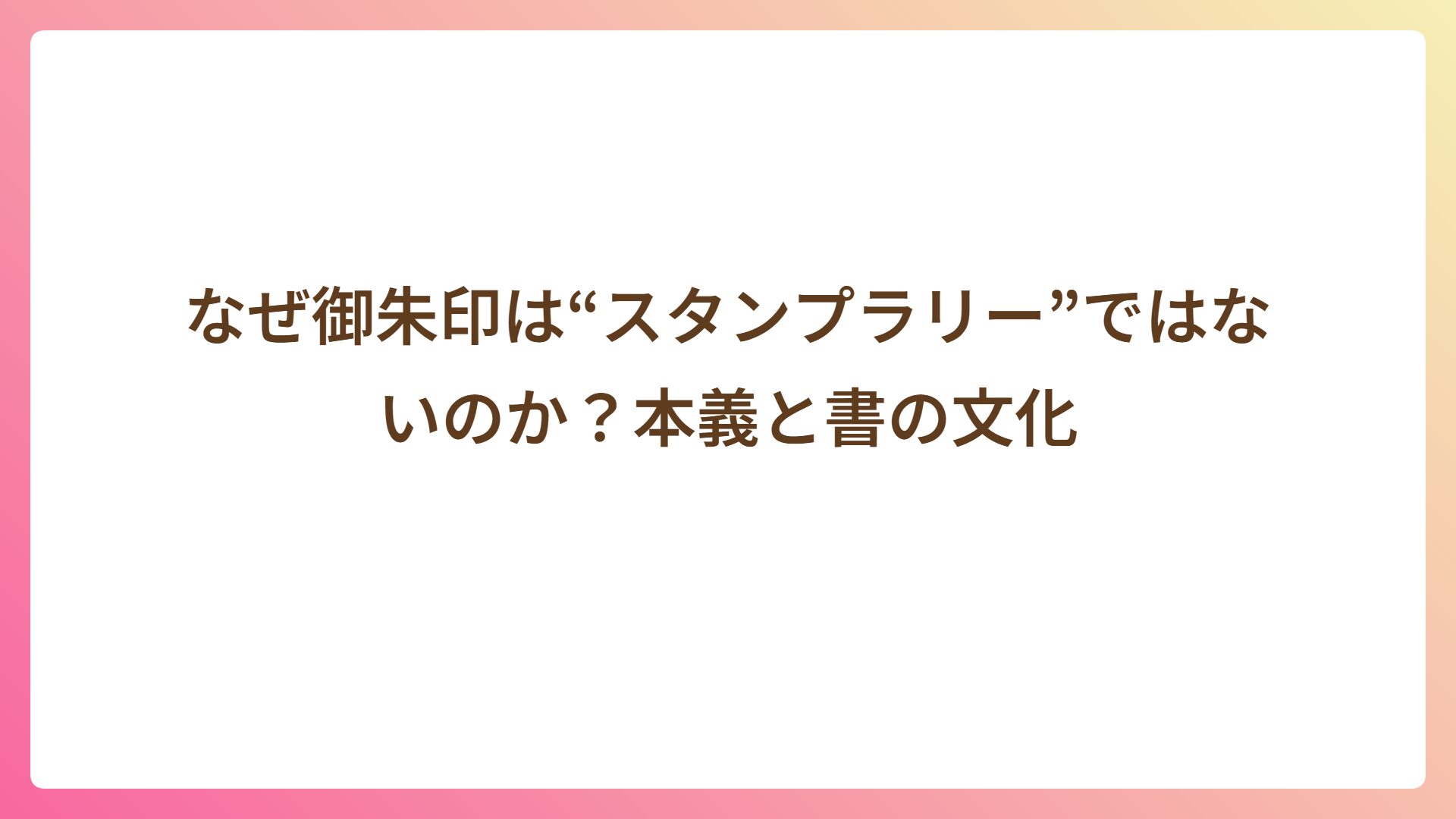なぜ点字ブロックの端部は斜めカットなのか?つまずき低減の形状
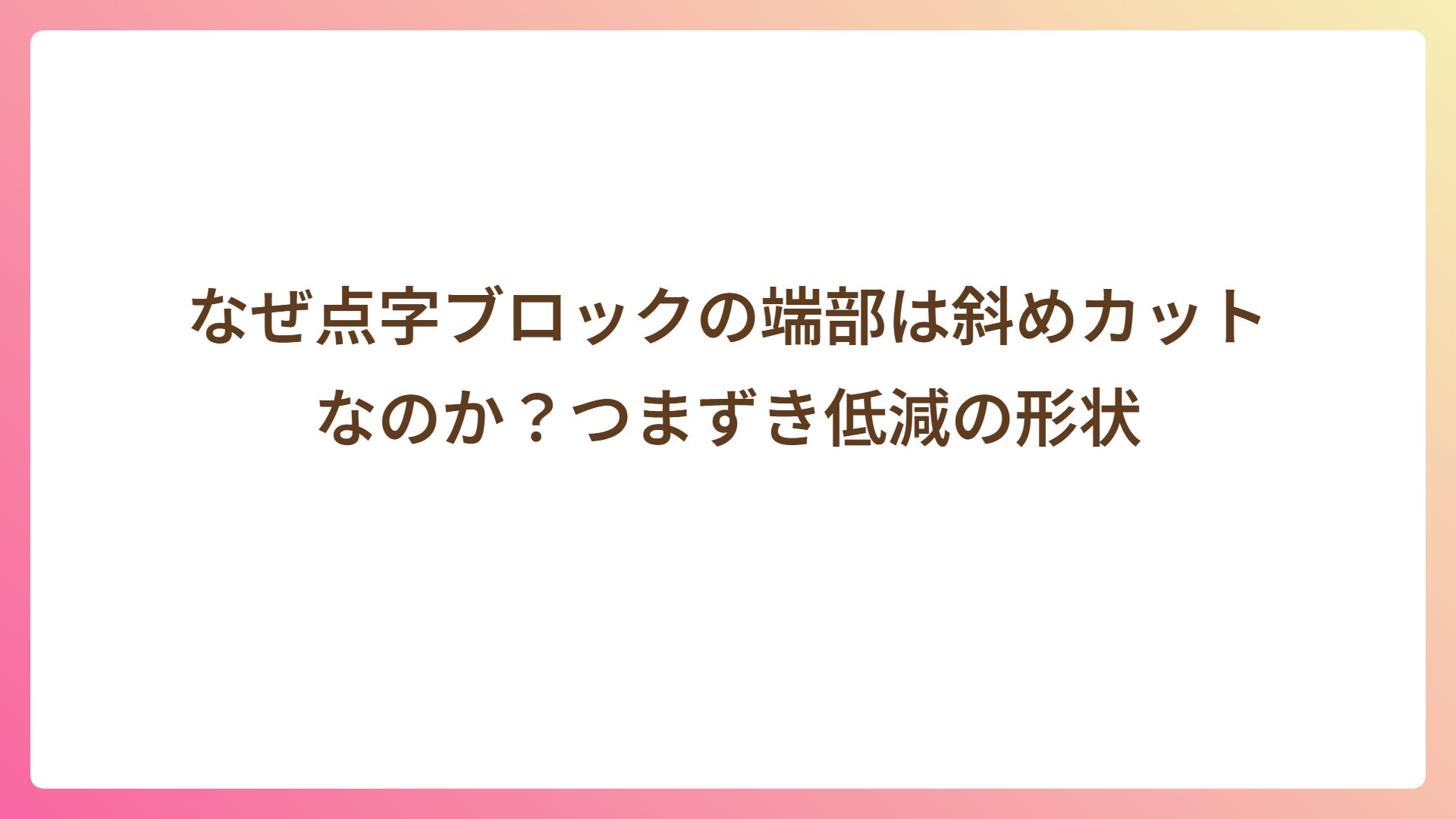
駅や歩道で見かける黄色い点字ブロック。
よく見ると、その端の部分が“すぱっと斜め”にカットされていることがあります。
なぜわざわざ平らにせず、傾斜をつけているのでしょうか?
それは、安全性と歩行性を両立するための形状設計なのです。
斜めカットは“つまずきを防ぐため”
点字ブロックの端を斜めにする最大の理由は、
健常者・高齢者・車いす利用者が段差につまずかないようにするためです。
点字ブロックは厚さが約5mmほどあり、
端が直角だと歩行時に靴底や杖の先が引っかかりやすくなります。
特に、白杖(はくじょう)を使う視覚障害者は、
杖先がブロック端に“コツン”と当たる感触を頼りに位置を確認しています。
このとき、端が急角度だと杖が引っかかり、誤って方向を変えてしまう危険があります。
そこで、端を斜めに削り、自然に乗り越えられる傾斜にすることで安全性を確保しているのです。
規格で定められた“傾斜角”
点字ブロックの形状はJIS(日本産業規格)により細かく定められています。
「JIS T 9251(視覚障害者誘導用ブロック)」では、
端部を斜めに加工する場合、傾斜角は10〜30度以内が望ましいとされています。
この角度は、歩行時に靴底が自然に滑り上がる最適値であり、
高齢者の歩幅や白杖の接触角度などをもとに決められています。
つまり、あの斜め形状は「つまずかず・気づける」ための実験的根拠に基づくデザインなのです。
車いす・ベビーカーへの配慮
車いすやベビーカーは、わずかな段差でも進行抵抗が大きくなります。
点字ブロックを直角のまま敷設すると、
前輪が引っかかり、乗り越える際に前傾してしまう危険があります。
斜めカットを採用することで、段差を滑らかに乗り越えられ、
さらに車輪が傾斜面で安定するため、安全でスムーズな通過が可能になります。
このため、駅構内や公共歩道では、車いす動線上のブロック端に傾斜加工が義務化されている場合もあります。
雨水や汚れの“たまり防止”にも効果
端が直角だと、ブロックと床面の間に雨水や砂ぼこりが溜まりやすく、
滑りやすくなったりカビが生えたりする問題がありました。
斜め形状にすることで水が自然に流れ落ちる排水効果が生まれ、
清掃やメンテナンスの面でも有利なのです。
この“排水勾配”の考え方は、道路舗装やマンホールの縁設計などにも応用されています。
段差を“感じつつ安全に越えられる”設計思想
斜めカットは「完全に段差をなくす」ためではなく、
あくまで段差の存在を感じつつ安全に越えられるようにするための設計です。
点字ブロックは、視覚障害者にとって進行方向や危険箇所を知らせる“触覚サイン”ですが、
健常者にとっては“つまずきや滑り”のリスクにもなり得ます。
その双方を両立するために生まれたのが、緩やかで連続的な端部傾斜。
触れて気づける“段差”と、転ばない“滑らかさ”の中間をとった形状なのです。
まとめ
点字ブロックの端部が斜めにカットされているのは、
つまずき防止・白杖操作・車いす走行・排水性といった多方面の安全要件を満たすためです。
段差をなくすのではなく、「感じて安全に越えられる」設計を目指した結果、
あの独特な斜めラインが生まれました。
見た目以上に緻密なその傾斜には、誰もが安心して歩ける歩道づくりの工学的知恵が詰まっているのです。