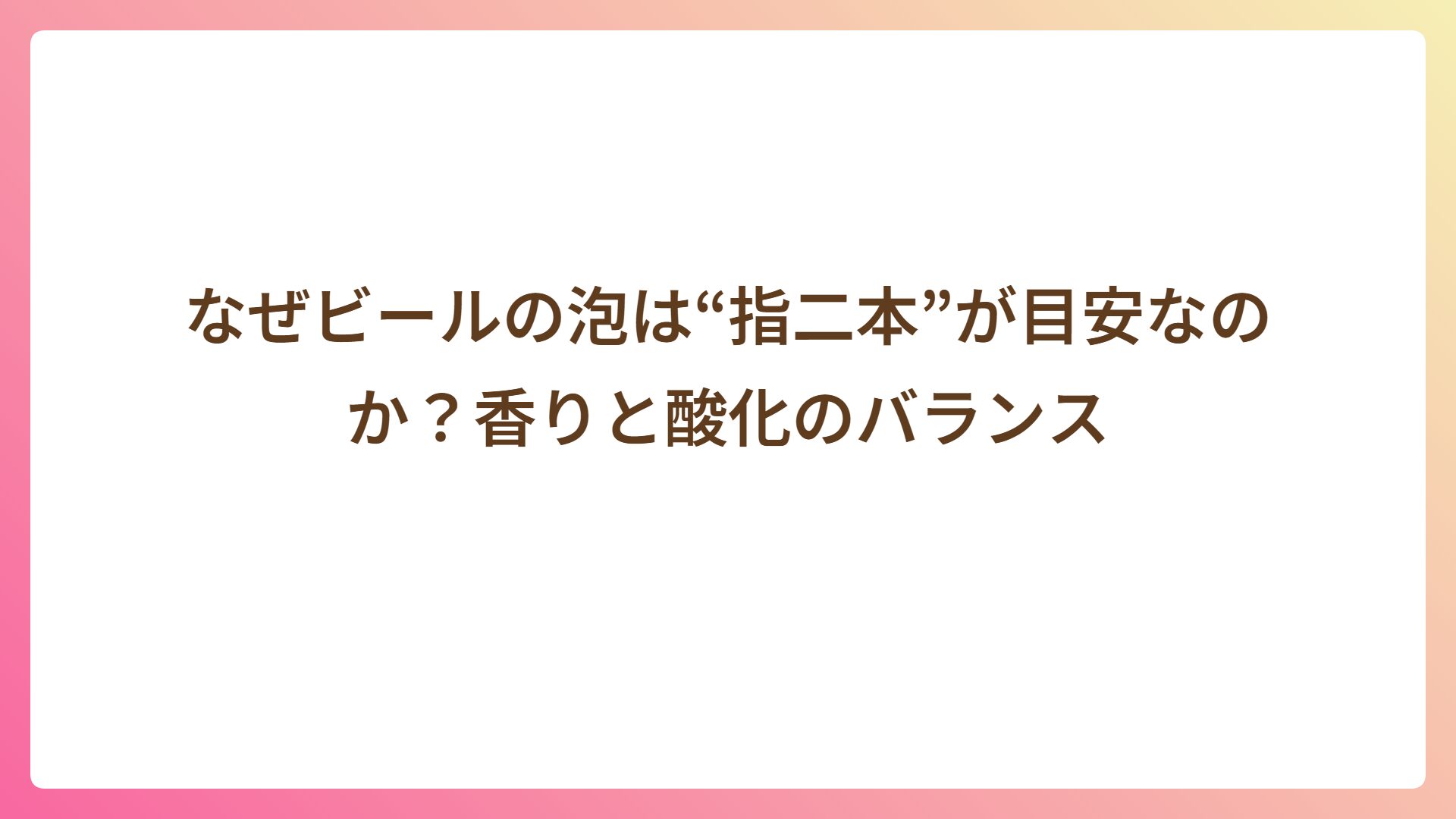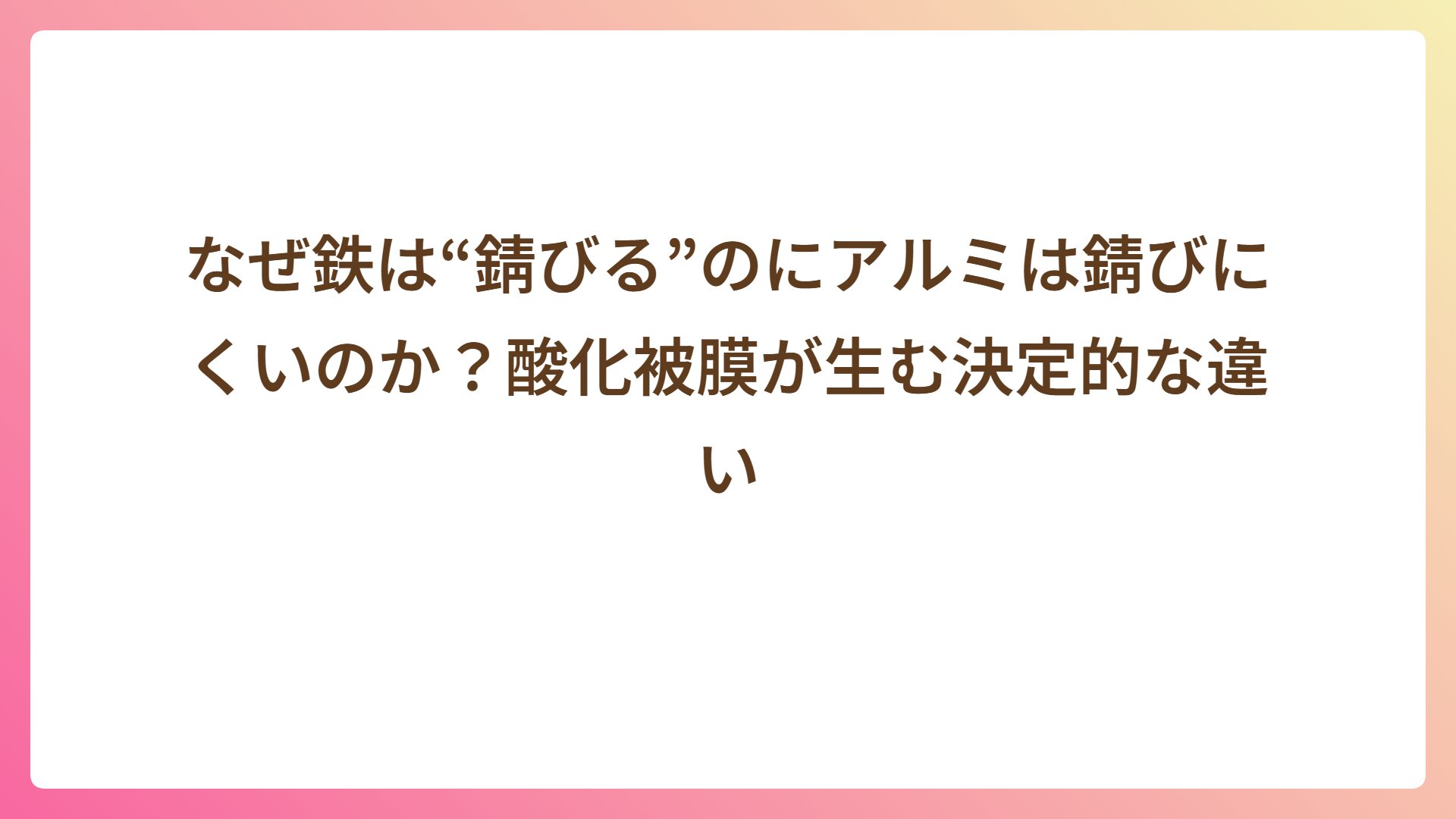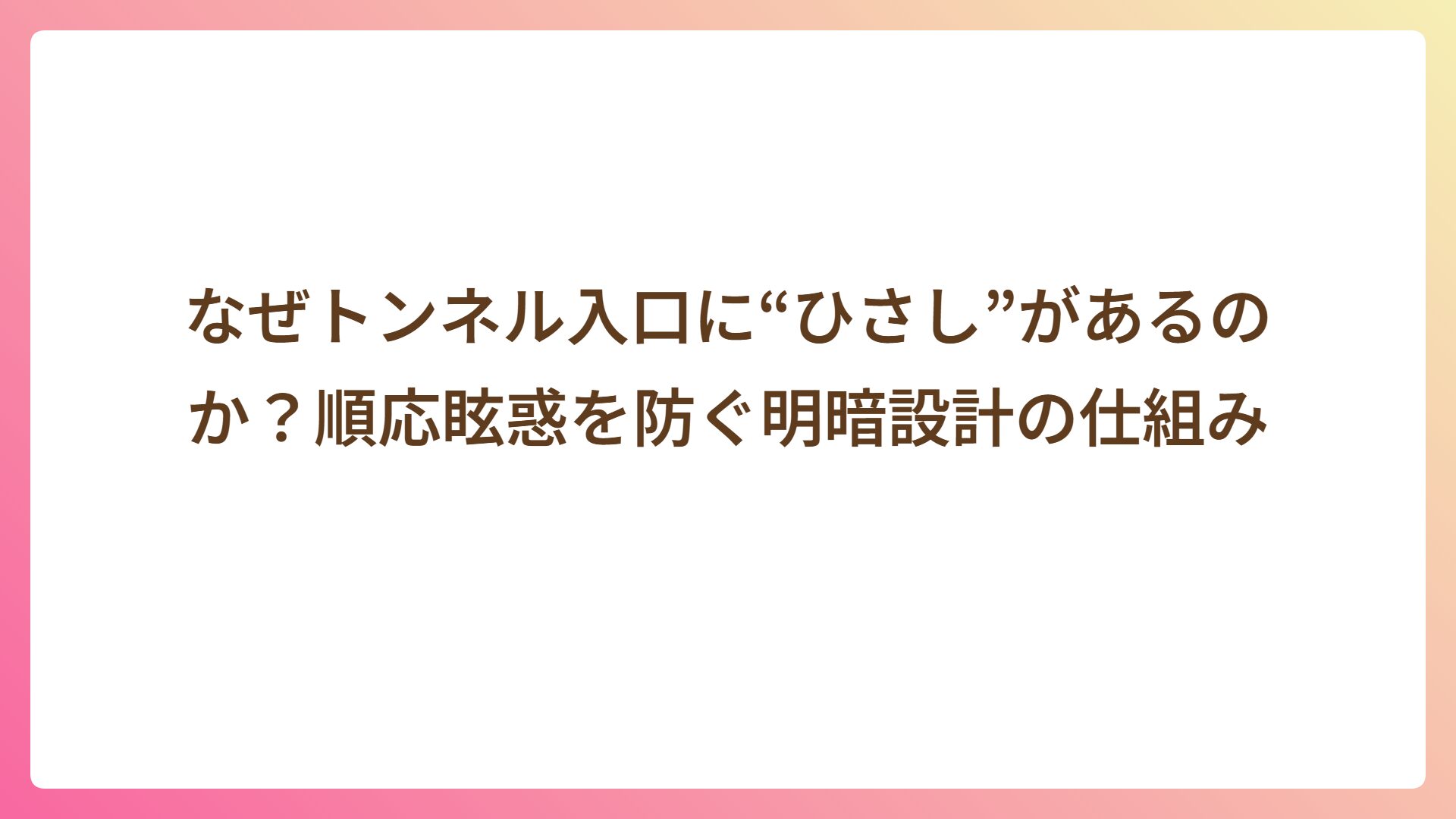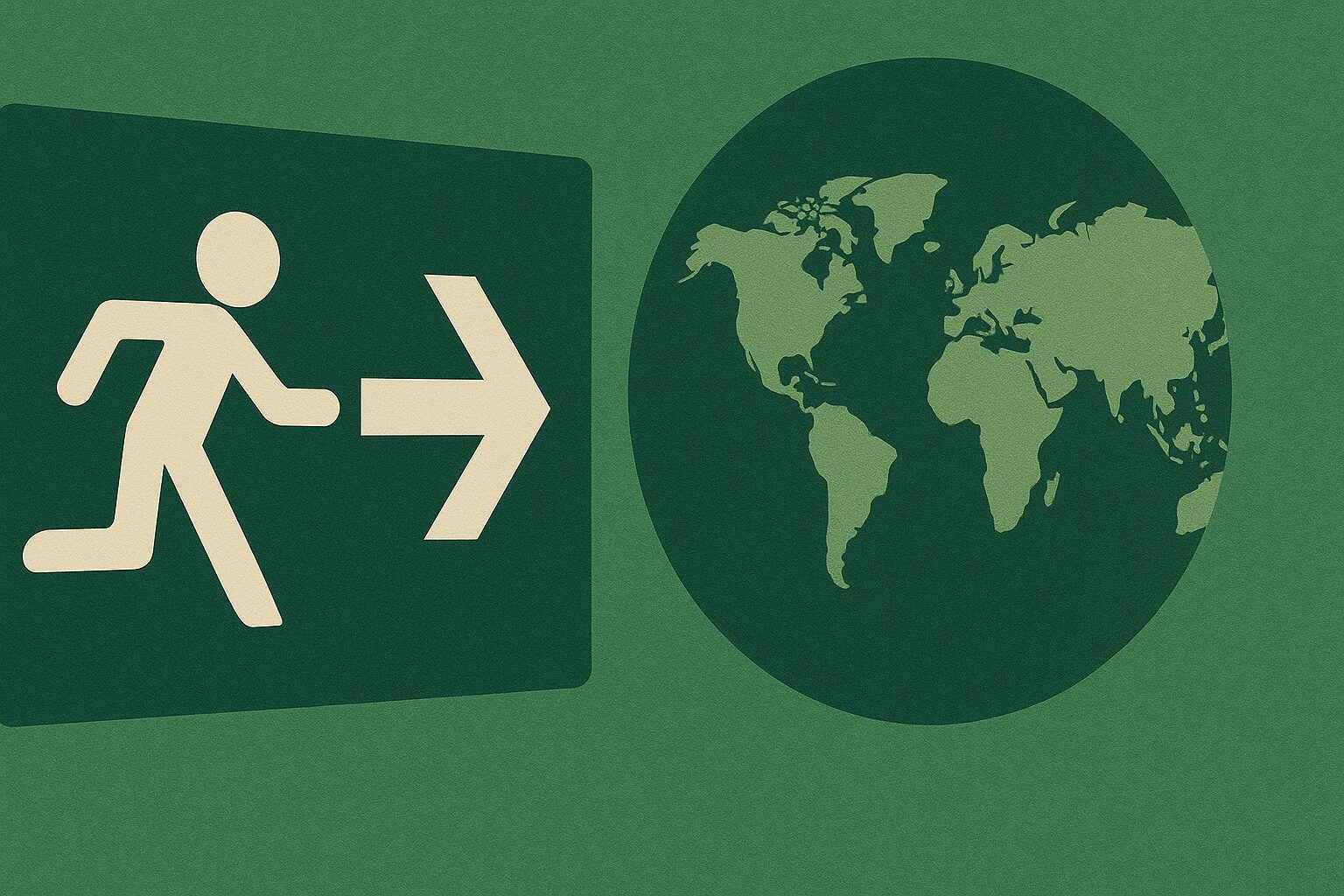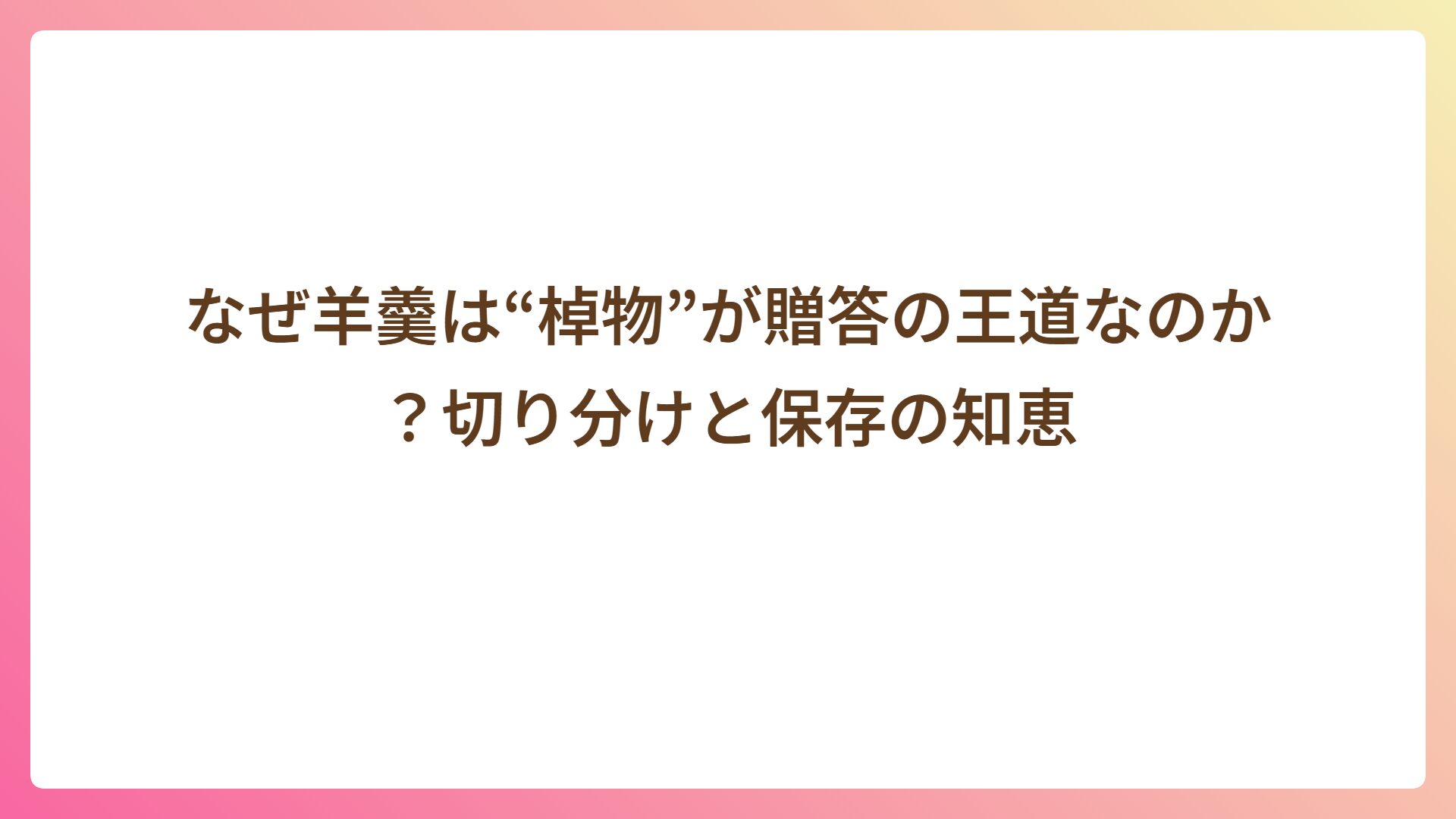なぜエスカレーターの手すりは“少し速い”のか?体のズレを防ぐ安全設計

エスカレーターに乗っていると、ふと気づくことがあります。
「手すりが少し速い?」——そう感じたことはありませんか?
実はそれ、設計ミスではなく意図的な設計です。
この記事では、エスカレーターの手すりが本体よりわずかに速く動く理由を、
構造・安全・人間工学の観点から解説します。
エスカレーターは“本体と手すりが別駆動”になっている
まず前提として、エスカレーターのステップ(足場)と手すりは、同じモーターで動いているものの、
実際には別々の経路・部品構造で動いています。
- ステップ:チェーン駆動(金属リンクで一定速度)
- 手すり:ベルト駆動(ゴム製で摩擦による伝達)
つまり、両者は物理的には同期していないため、
構造上どうしても微妙な速度差が生じるのです。
理由①:手すりを“わずかに速く”して体のズレを防ぐ
人がエスカレーターに立つとき、体は手すり側に少し重心を預けています。
もし手すりがステップより遅かった場合、
- 握っている手が後ろへ引かれる
- 上半身だけ遅れる
- 体が前に倒れそうになる
といった危険な「ズレ」が発生します。
そのため、メーカーは意図的に手すりをわずかに速く動かすことで、
手と体の位置関係を自然に補正するよう設計しています。
この“ほんの少し速い”設計が、
利用者が感じる「安定している」「姿勢が崩れない」感覚を生み出しているのです。
理由②:摩擦伝達だからこそ“わずかな余裕”が必要
手すりベルトはモーター直結ではなく、摩擦ローラーで回されています。
このため、
- 温度変化による伸び縮み
- ゴム表面の摩耗
- 湿度や油分による滑り
といった影響で、速度が微妙に変わります。
もし本体と完全に同速に設計すると、
わずかな摩擦低下で手すりが遅れる(ズレる)危険があります。
そこで、安全側に倒して「常にやや速く」設定することで、
ズレが後方方向に生じないようにしているのです。
理由③:人間の感覚上“遅いほうが不安定”に感じる
人の体は、前方への支えが速い場合よりも、後ろに引かれる状況のほうが不安を感じやすいといわれます。
これは、重心の制御と視覚の不一致による前方転倒リスクが高いためです。
そのため、手すりが少し速いほうが、
利用者は「引っ張られている」よりも「支えられている」感覚になり、
心理的にも安定感が増すのです。
理由④:国際規格でも“手すり+2〜5%”が標準
この速度差はメーカーや国ごとに基準が定められています。
- JIS(日本工業規格):手すり速度はステップ速度より最大+5%まで許容
- EN(欧州規格):±2〜5%以内の範囲で設計
- ANSI(米国規格):ステップより速い方向の差を推奨
つまり、「少し速い」は国際的に意図された標準仕様なのです。
理由⑤:利用者の位置維持を助ける“微小な力”
上りエスカレーターでは重力が後ろ方向に働くため、
人は自然とステップの後方へずれがちです。
このとき手すりが少し速いと、
前方方向に軽く引く力がかかり、
結果として立ち位置が安定しやすくなる効果があります。
下りエスカレーターでも同様に、
体が前に倒れすぎるのを前向きの摩擦力で抑える働きをします。
理由⑥:メンテナンス上の“速度誤差の吸収”
手すりのゴムベルトは長年使用すると伸び、速度が遅くなりがちです。
そのため、最初から少し速めに設計しておくことで、
経年劣化を見越した安全マージンを確保しています。
定期点検時には「ステップとの速度差3%以内」が維持されているかを測定し、
ベルト交換や調整を行います。
理由⑦:逆に“速すぎても危険”──許容範囲の制御
もちろん、手すりが速すぎると、
- 手が引っ張られてバランスを崩す
- 子どもや高齢者が転倒する
という危険が生じます。
そのため、速度差は「人が気づかない程度の微差(1〜3%)」に設定され、
常に体の自然な動きを補助するレベルに保たれています。
まとめ:わずかな速度差が“安全と快適”を生む
エスカレーターの手すりが少し速いのは、
- 手と体のズレを補正するため
- 摩擦駆動の遅れを防ぐため
- 利用者に安定感を与えるため
- 国際的に定められた安全基準に沿うため
といった理由によるものです。
つまり、あのわずかなスピード差は人間の感覚に合わせた安全設計。
“ピッタリ同じ”ではなく、“ほんの少しズレている”ことこそが、
エスカレーターを快適で安心な乗り物にしている工学的工夫なのです。