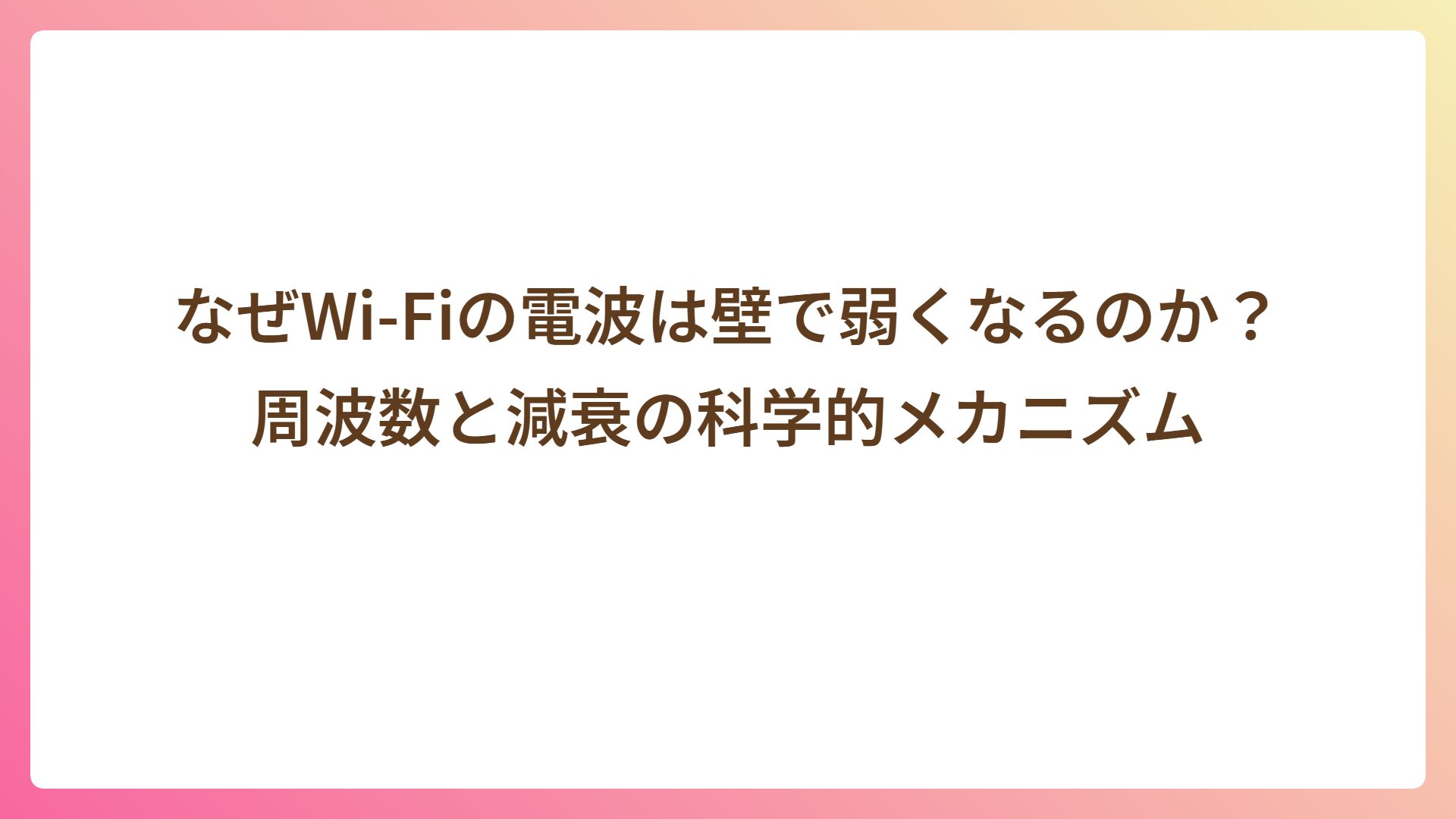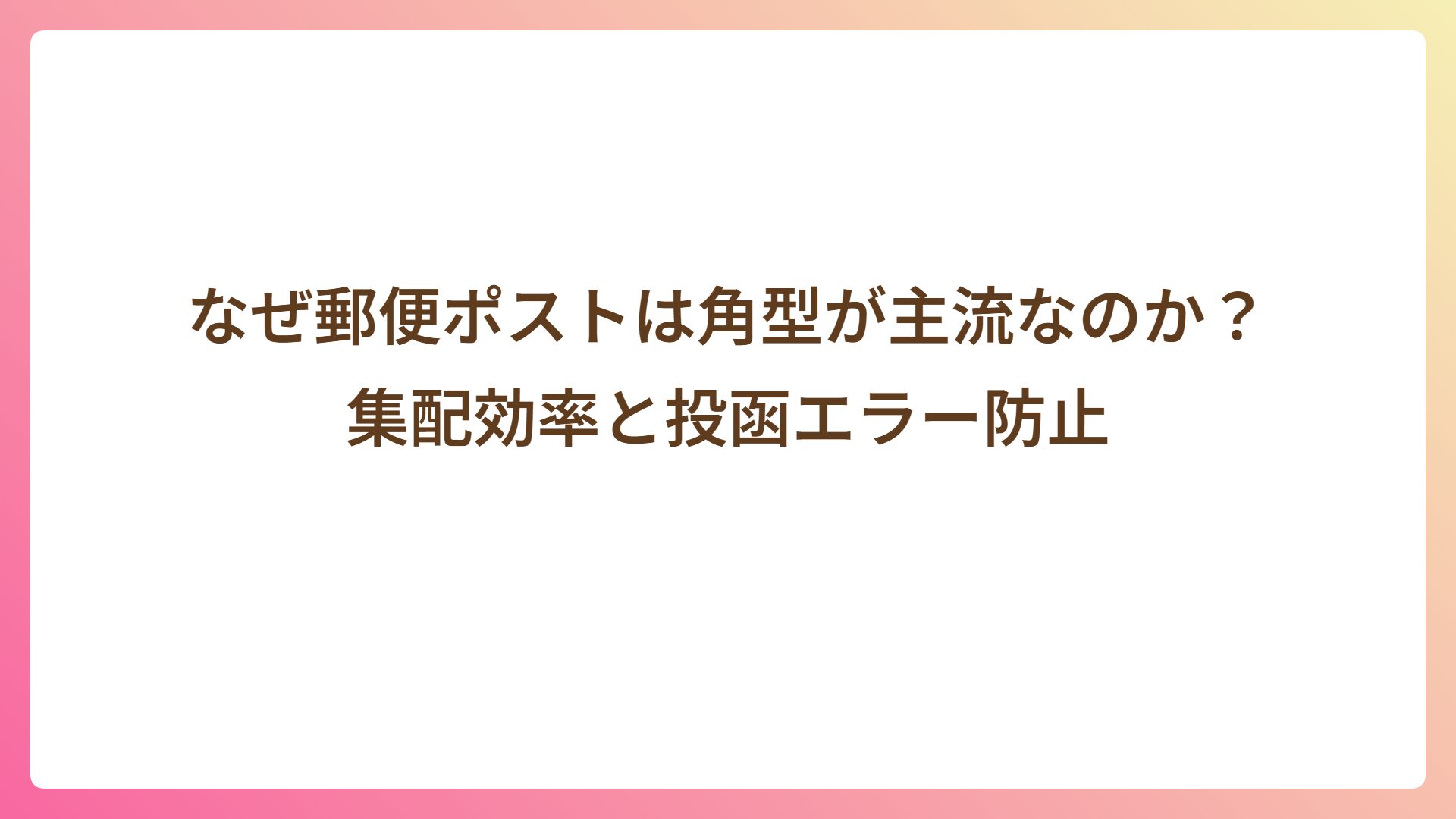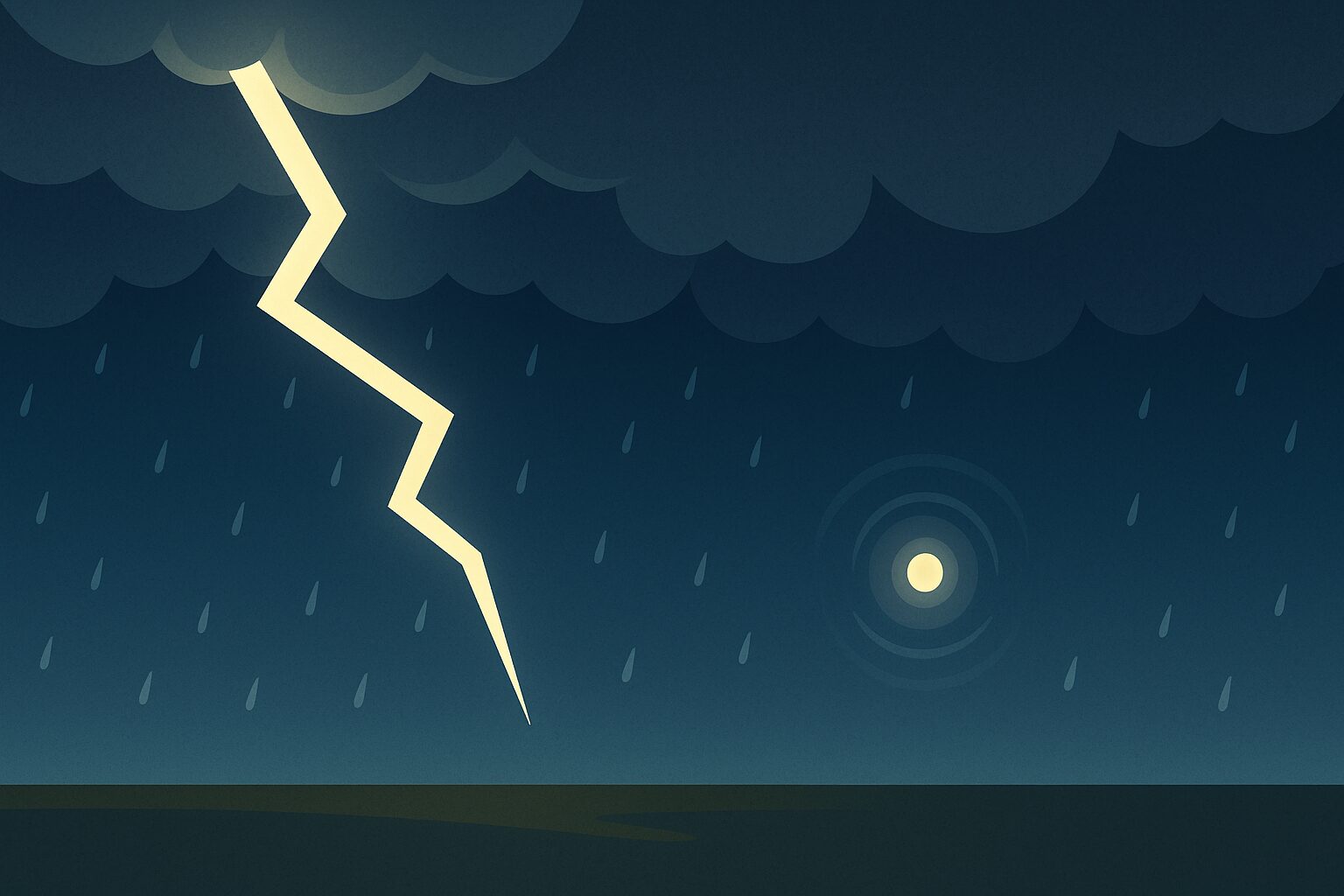なぜティッシュは“取り出し口”で破れにくいのか?滑りと抵抗を計算した箱の設計
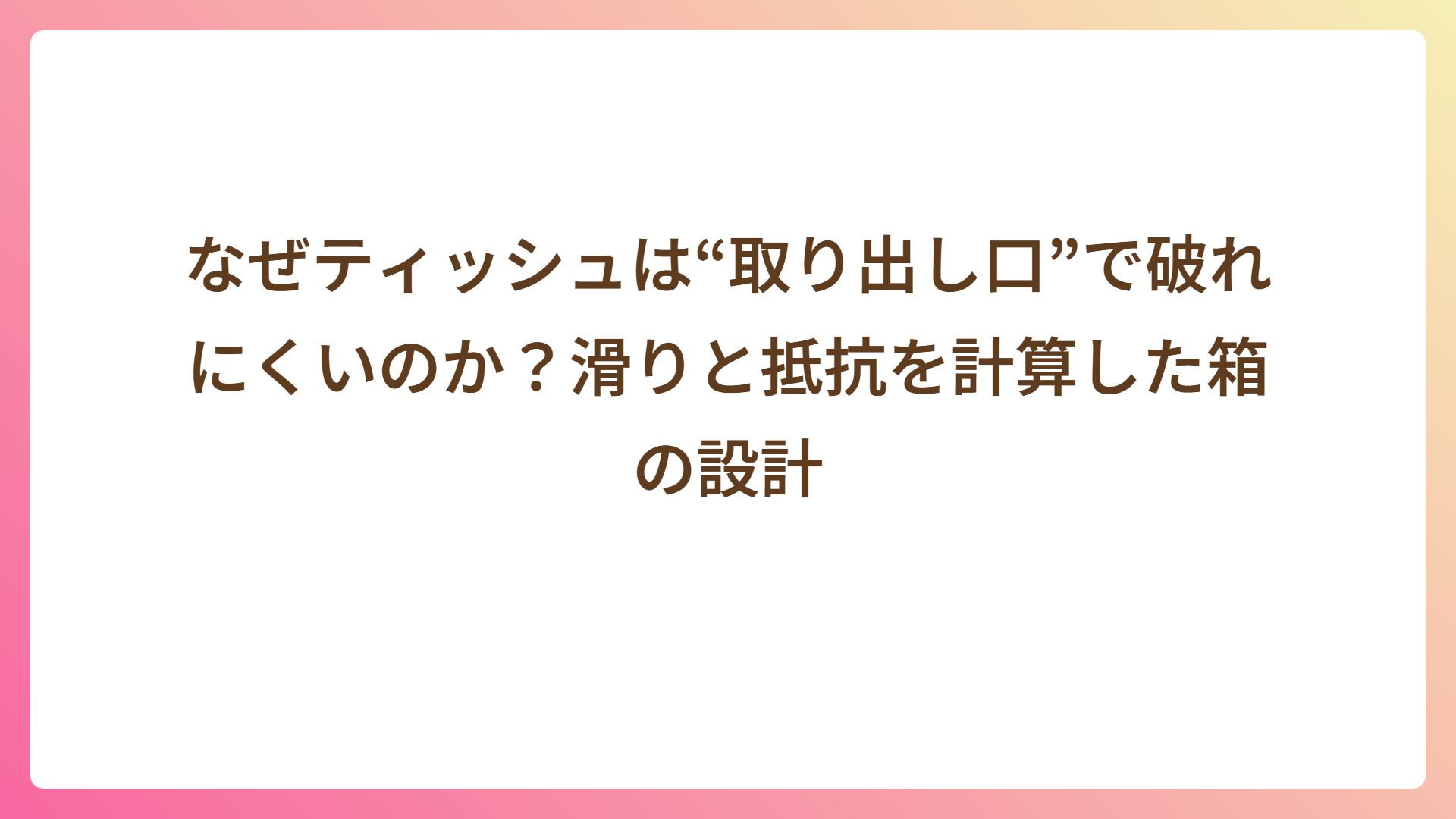
何気なく引き出しているティッシュペーパー。
勢いよく引っ張っても破れず、1枚だけスッと出てくる――実はこれ、精密に計算された箱の設計によるものです。
この記事では、ティッシュが“取り出し口で破れない”理由を、紙の摩擦・箱の構造・人の動作設計の観点から解説します。
ティッシュが破れにくい理由は「摩擦と抵抗のバランス」
ティッシュ箱の取り出し口は、
単に紙を取り出す穴ではなく、“適度な抵抗を与える機構”として設計されています。
この仕組みのカギは、
- 紙の強度(引っ張り強さ)
- 取り出し口の形状と摩擦係数
- 次のティッシュを引き出すための連動構造
の3点にあります。
つまり、破れないのは“柔らかい紙”ではなく“適切な抵抗”が作られているからなのです。
理由①:取り出し口の“フィルム”が力を分散する
ティッシュ箱の取り出し口には、
薄いポリエチレンや紙製のフィルムが貼られています。
このフィルムには、中央に“花びら型”や“楕円形”の切り込みが入っており、
ティッシュを取り出す際に指と紙の力が一点に集中しないようになっています。
これにより、
- 引っ張る力が面全体に分散される
- 紙が一方向に裂けにくくなる
- 摩擦が一定になり、スムーズに引き出せる
という効果が生まれます。
つまり、取り出し口の形状そのものが、紙を守る“クッション”の役割を果たしているのです。
理由②:紙と紙の“重なり構造”が連動して動く
ティッシュは1枚ずつバラではなく、山折り・谷折りを交互に重ねた「インターフォールド」構造になっています。
この構造により、
1枚を引き出すと次の1枚の端が自動的に引っかかって顔を出す――という仕組みになっています。
取り出し口の抵抗が適度にあることで、
- 引っ張る際に次のティッシュを“持ち上げる力”が発生
- 次の紙が自然に顔を出す(1枚ずつ連続)
- 力が分散して1枚目が破れない
という“連動のバランス”が保たれているのです。
理由③:紙の強度と“取り出し角度”の最適化
ティッシュは非常に薄い紙ですが、
実際には繊維方向(縦方向)には強く、横方向には弱いという性質があります。
メーカーはこの繊維方向を考慮し、
「引き出す力が紙の強い方向に働くよう」箱の角度と取り出し口を設計しています。
たとえば、
- 箱の高さを低めにして引き出し角度を浅くする
- 紙の繊維方向を“引っ張り方向”に合わせる
ことで、最小限の力で破れずに引き出せるよう最適化されています。
理由④:摩擦を“少しだけ”残すことで安定性を保つ
取り出し口の抵抗がまったくないと、
ティッシュが数枚まとめて飛び出したり、引き出す時に箱の中でぐちゃぐちゃになります。
そのため、メーカーは「摩擦係数の最適値」を実験的に決めています。
- 抵抗が強すぎる → 紙が破れる
- 抵抗が弱すぎる → 複数枚出てしまう
このバランスを取るために、フィルムや箱素材の表面処理・開口形状・弾性が調整されています。
この“ほんの少しの引っかかり”こそが、1枚ずつきれいに取り出せる秘密なのです。
理由⑤:使用者の“動作”に合わせた設計
人がティッシュを取るとき、
多くの場合は指先で軽くつまんで斜め上方向に引くという動作をします。
この動作パターンを想定し、箱の取り出し口は水平よりやや下に傾いた構造になっています。
この角度により、
- 紙に無理な力がかからず破れにくい
- 次の紙が自然に引っ張り出される
- 箱全体が安定して倒れにくい
という“人間工学的デザイン”が実現しています。
まとめ:破れにくさは“偶然”ではなく“設計の成果”
ティッシュが取り出し口で破れにくいのは、
- フィルム開口部が力を分散している
- 紙の折り方が連動を生む
- 摩擦と角度が最適化されている
- 紙の繊維方向と人の動作が計算されている
という複数の設計要素の組み合わせによるものです。
つまり、「破れないようにできている」のではなく、
“破れにくく、次が出やすい”という理想の引き出し動作を設計しているのです。
普段の何気ないティッシュ1枚にも、驚くほどの“人と紙の工学”が詰まっているのです。