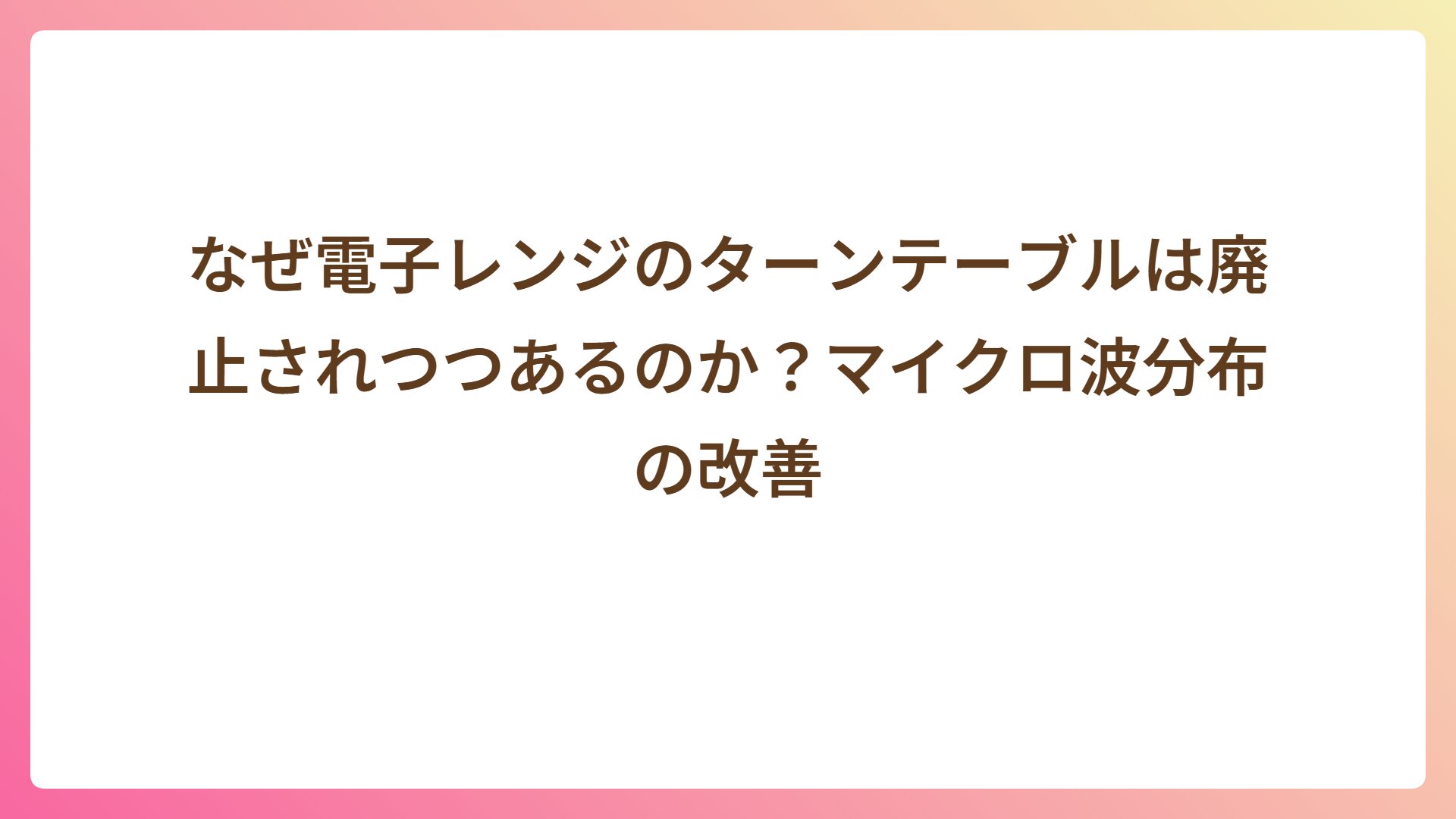なぜ茶道の“床の間”は少し高く作られているのか?主役位置と畳傷み防止
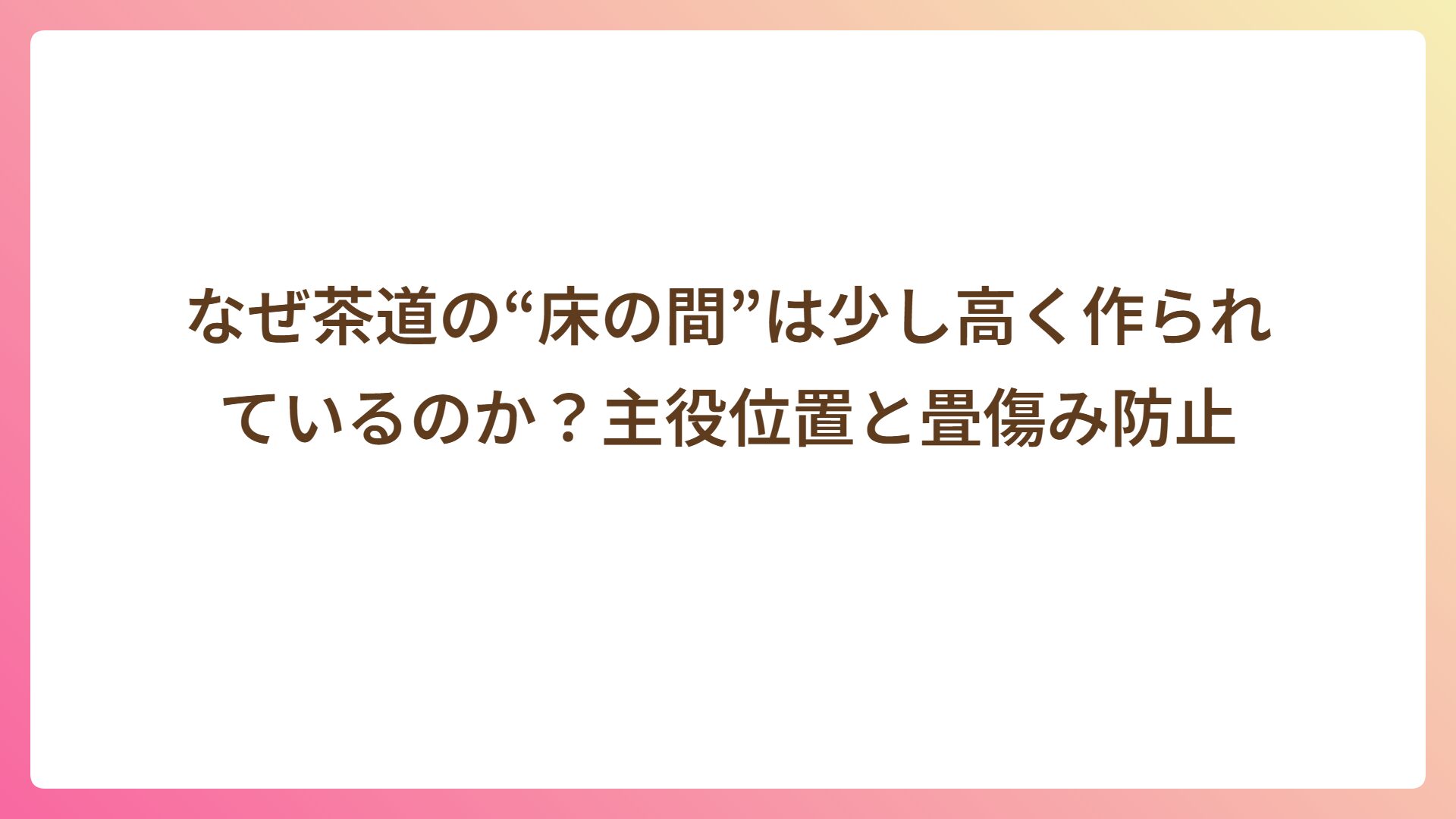
茶室に入ると、正面の壁際に掛け軸や花が飾られた「床の間」があります。
よく見ると、その床は他の畳よりわずかに高く作られています。
なぜ茶道では、床の間を少し高く設計しているのでしょうか?
そこには、格式と実用を両立させた日本建築ならではの理由があります。
格式を示す「主役の場所」だから
床の間は、もともと客人に敬意を示すための“主役の空間”です。
掛け軸や花入れなど、主人(亭主)の心を表す品が飾られ、客はそれを正面から拝見します。
床を一段高くすることで、その空間を他と明確に区別し、神聖で特別な場所であることを示す意味があります。
この「一段上げる」構造は、神社の内陣や上座の座敷にも通じる伝統的設計で、
人が直接上がることを避け、飾られたものを敬う日本的な礼法の表現でもあります。
掛け軸や花入れを守る「物理的な工夫」
茶室では湯を沸かし、湯気や湿気がこもりやすくなります。
そのため、床の間を少し高くしておくことで、湿気や水気が直接伝わりにくくなり、道具や軸を傷めにくくする効果があります。
また、畳の上に直接花台や陶器を置くと、重みで畳がへこんだり、湿気で変色したりします。
床を板張りにして高くすることで、畳の傷みを防ぎ、清潔さを保つ実用的な意味もあるのです。
茶室設計の「見えないバランス」
茶室では、すべての構造に「控えめな非対称の美」があります。
床の間の高さもその一つで、過度に目立たず、しかし確かに格式を感じさせる微妙な段差(約3〜5cm程度)に調整されています。
これは、見る人に“主客の境界”を意識させつつ、空間全体の調和を崩さないための設計。
まさに、茶道の精神である「和敬清寂」を形にした建築的表現です。
まとめ
茶道の床の間が少し高いのは、
主役空間としての格式と、道具を守る実用性の両立によるものです。
わずかな段差の中に、敬意と調和を重んじる日本の美意識が息づいています。
それは単なる構造ではなく、「もてなしの心」を形にした空間設計なのです。