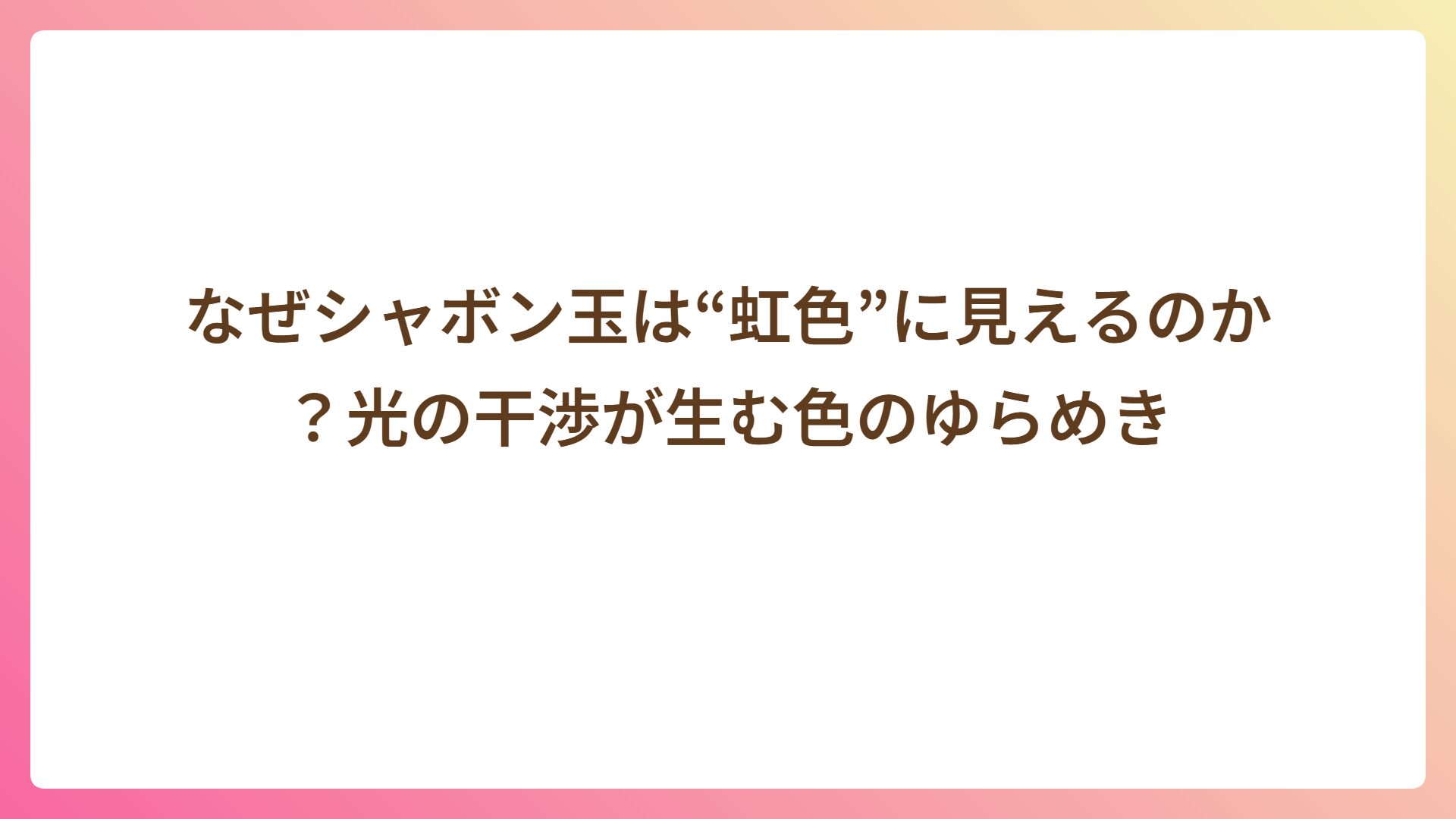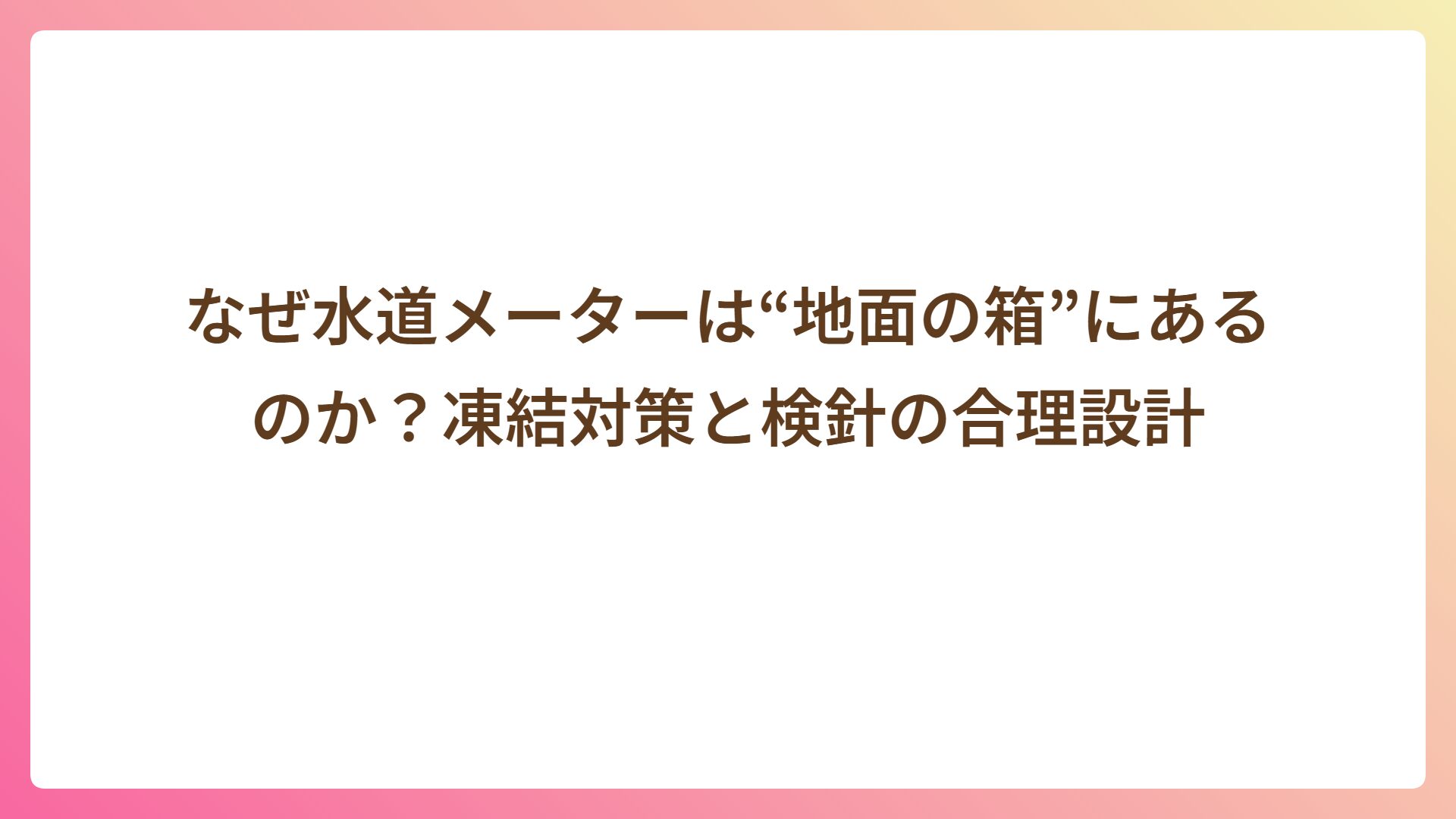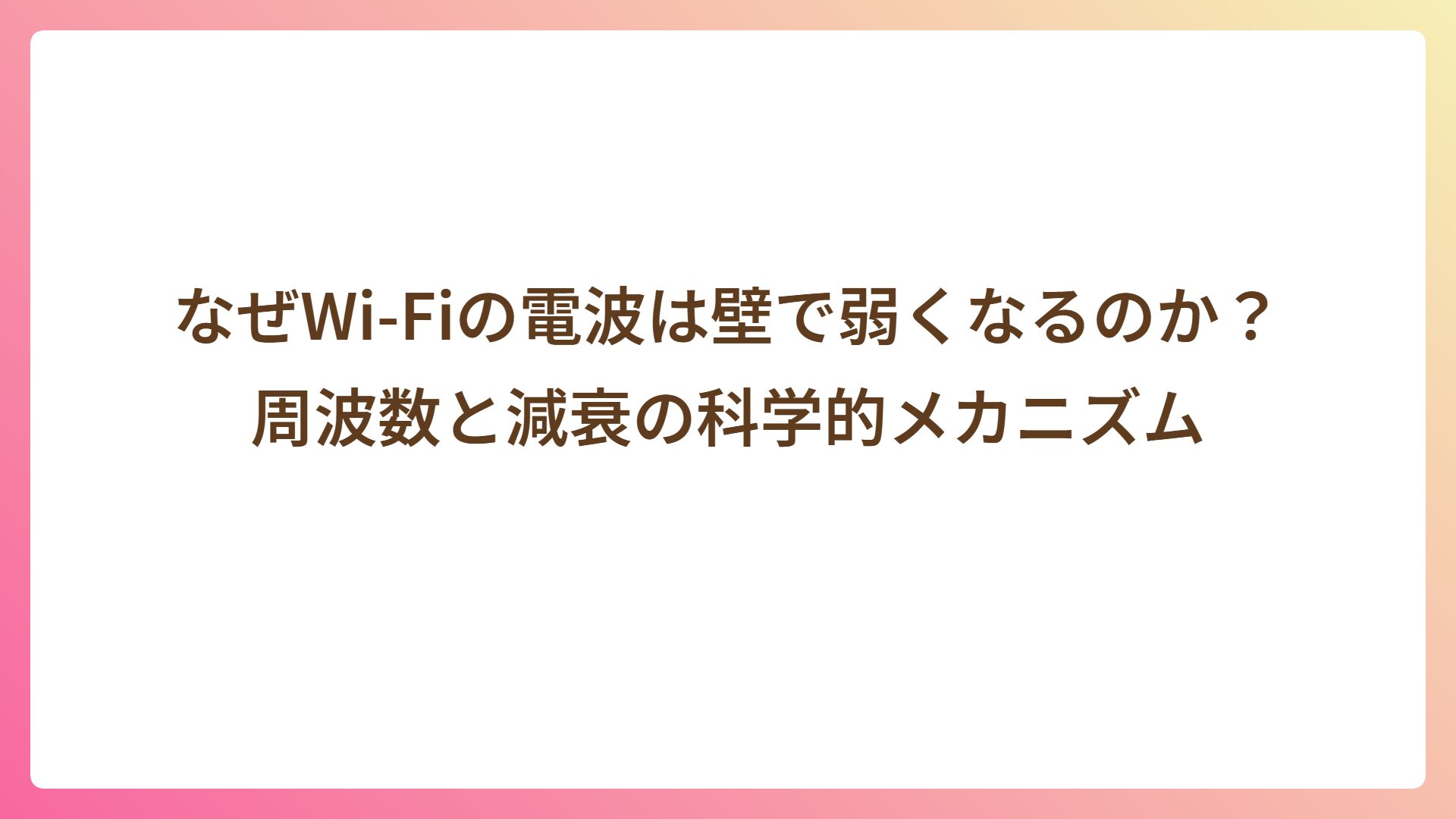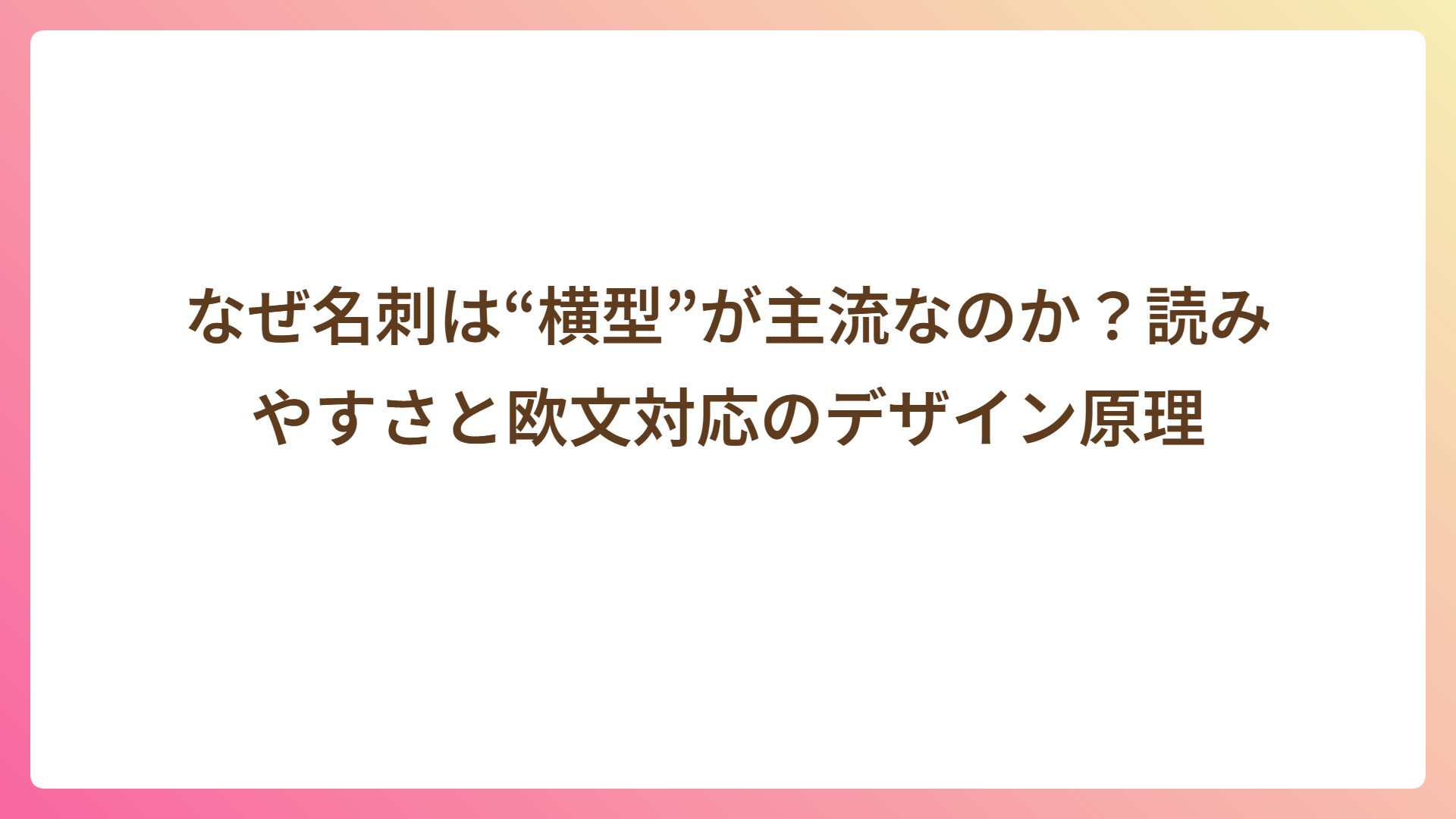なぜ月見団子は十五個並べるのか?月齢と供え物の数理
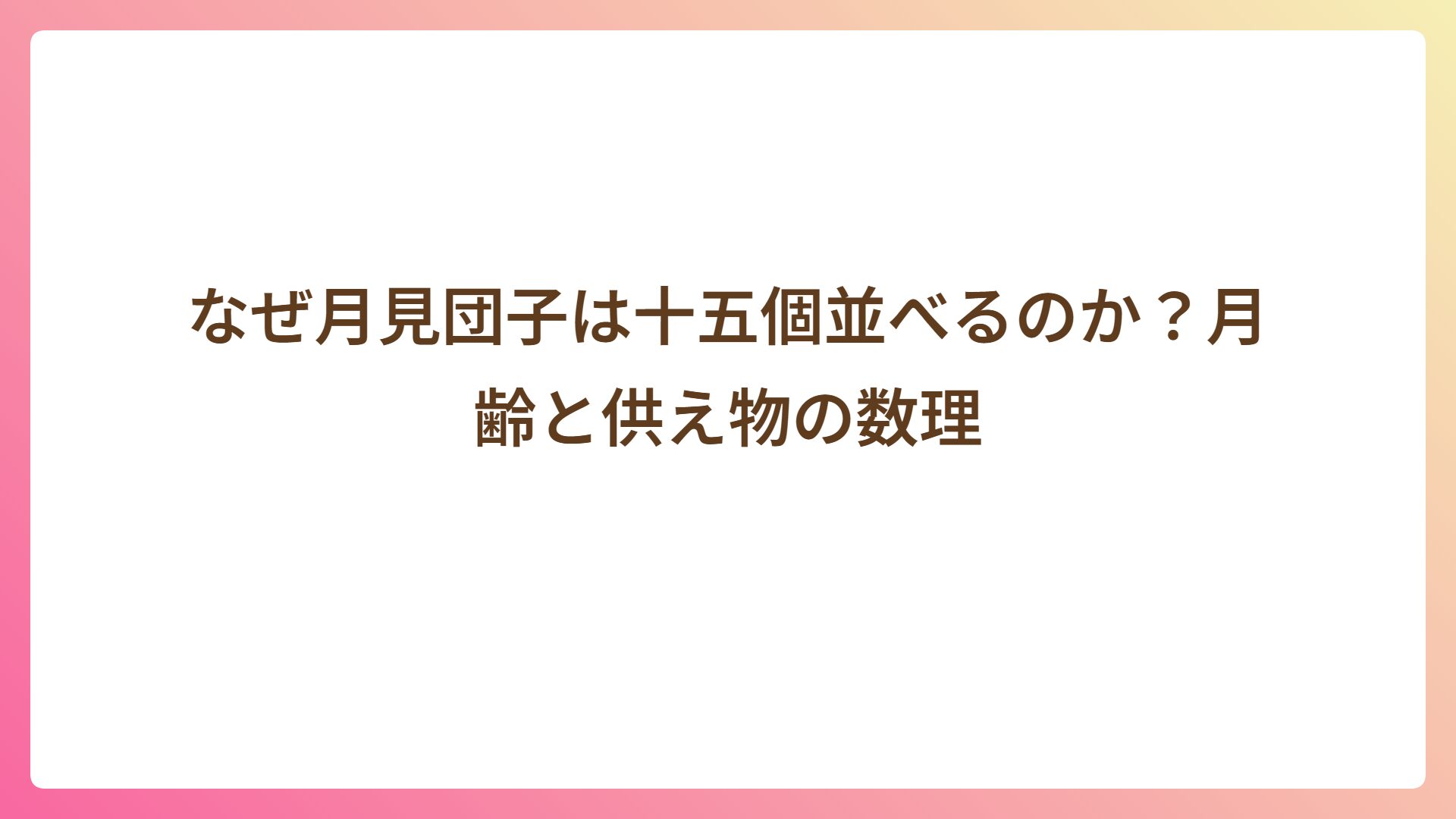
中秋の名月といえば、ススキと月見団子。
まん丸の団子を十五個、段々に並べてお供えする光景は、
秋の風物詩として日本人に深く親しまれています。
しかし、なぜ「十五個」なのか?
そこには、月の満ち欠けの周期を重んじる古代の時間感覚と、神への供え物の数理的な意味が隠されています。
「十五夜」は“満月の夜”を意味する
「十五夜」とは旧暦の八月十五日、すなわち満月に最も近い夜のこと。
旧暦では新月を1日目と数え、十五日目が月齢15前後、
つまり月が最も満ちた状態になる時期です。
人々はこの“満ちる瞬間”を、
自然界の完成・収穫・生命の充足と重ね合わせ、
その喜びを神に捧げる行事として月見を行ってきました。
十五個の団子は、まさに十五夜=十五日目=満月を象徴する数字なのです。
「十五」という数に宿る“満ちる”意味
古来、日本では奇数が「陽数」とされ、
とくに“十五”は「十(完全)+五(生成)」の組み合わせで、
完全にして生まれ変わる数と考えられていました。
これは月の周期(約29.5日)の半分にあたり、
十五夜を境に“満ちて欠ける”サイクルが始まることから、
十五という数は「自然の一巡=完全な周期」を意味します。
そのため、十五個の団子を供える行為は、
「月が満ちたことを祝い、再び巡る命に感謝する」
という象徴的な儀式なのです。
並べ方にも“天と地”の意味がある
十五個の団子は、通常「1段目に9個・2段目に4個・最上段に2個」とピラミッド状に並べます。
この配置には、天地の調和を意識した神饌(しんせん)形式が反映されています。
- 下段:地を表す(人の世界・大地の恵み)
- 中段:天を表す(月の世界・神の領域)
- 上段:神への祈りを届ける最頂点
つまり、供え方そのものが月への祈りを形にした祭壇構造なのです。
また、関西など一部地域では十三夜(後の月)には十三個の団子を供える習慣もあり、
月の数(十五・十三)をそのまま供物の数にするという「数理信仰」が全国的に見られます。
月見団子は“収穫と再生”の供え物
十五夜の月見は、もともと稲の実りを感謝する収穫祭でした。
団子が丸いのは月の形をかたどると同時に、
稲の籾(もみ)や魂(たま)を象徴する“満ちた形”を意味します。
また、十五個という数は「稲穂の粒」をも連想させ、
収穫の豊かさと家族の円満を祈る願いが込められています。
つまり、月見団子は単なる飾りではなく、
「自然のリズムを食として受け入れる神饌(しんせん)」なのです。
地域による数の違いも「月齢信仰」から
東日本では十五個、西日本では十二個や十三個を供える地域もあります。
これは、月見が「十五夜(満月)」だけでなく「十三夜(後の月)」も祝う行事として広がったため。
十三夜は旧暦九月十三日、十五夜からおよそ一か月後に訪れる“次の月”。
十五夜と十三夜の両方を拝むことを「二夜の月見」と呼び、
どちらか片方だけ行うのは「片見月」として縁起が悪いとされました。
こうした地域差も、月齢の節目を丁寧に数える日本人の時間観のあらわれといえます。
まとめ
月見団子を十五個並べるのは、
十五夜の満月=自然の完全周期を象徴する“数の信仰”によるものです。
- 十五夜=月齢15の満ちた夜
- 十五個=自然の完成と再生の数
- 並べ方=天地の調和を表す供え形
- 丸い形=満ちた生命と収穫の象徴
月見団子は、ただの甘味ではなく、
月と人の命のリズムをつなぐ“数理の供物”として今も受け継がれているのです。