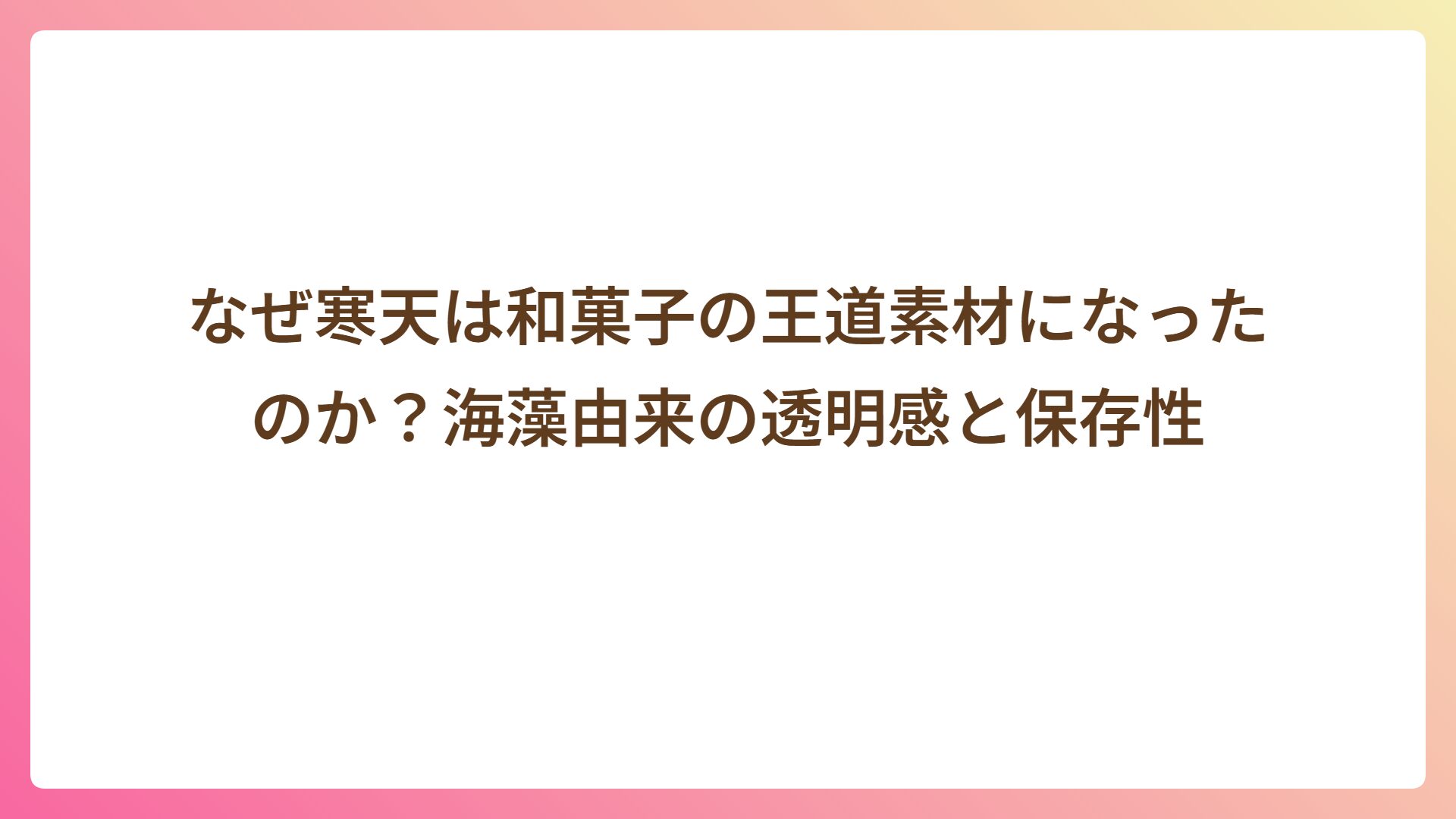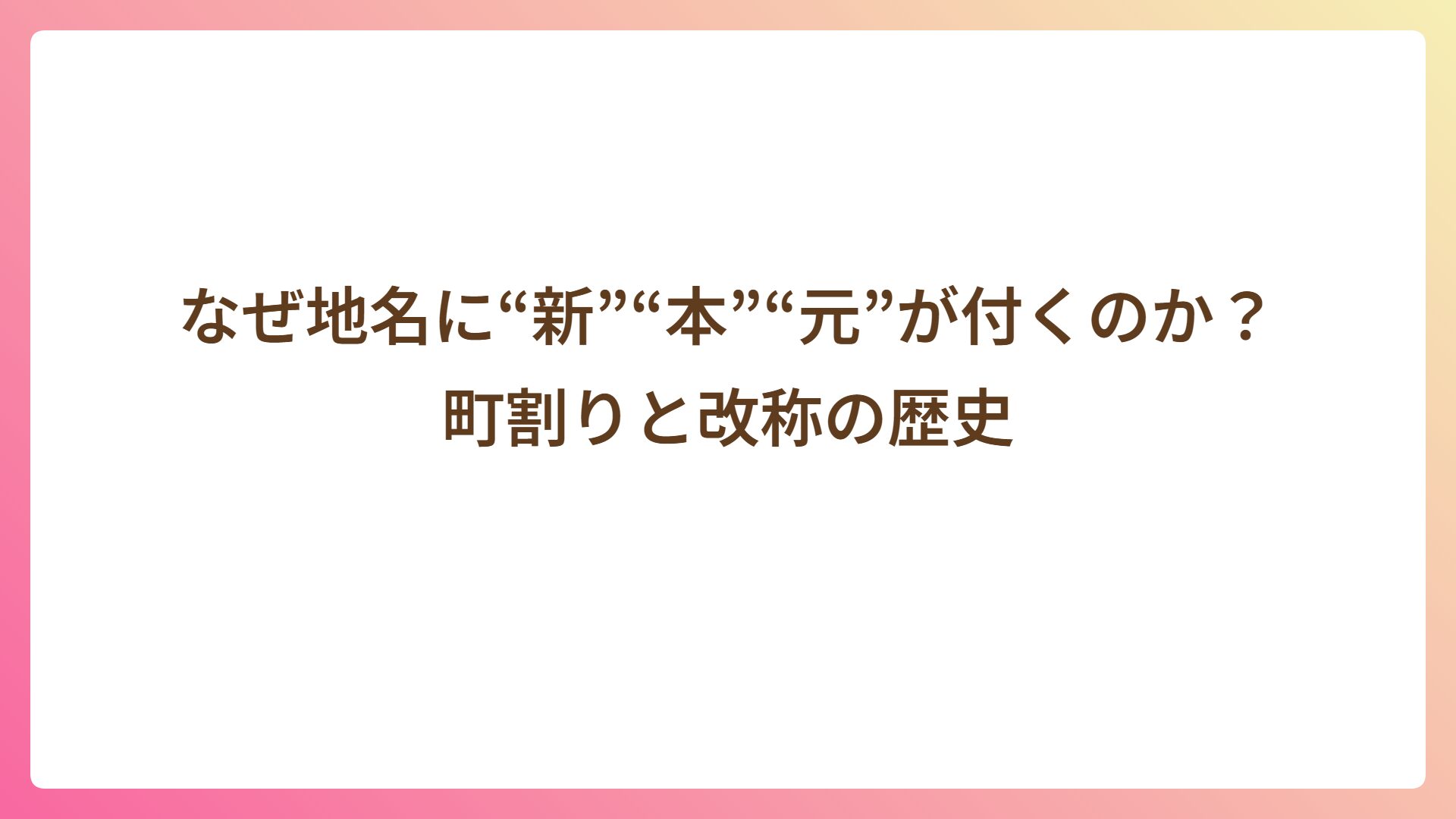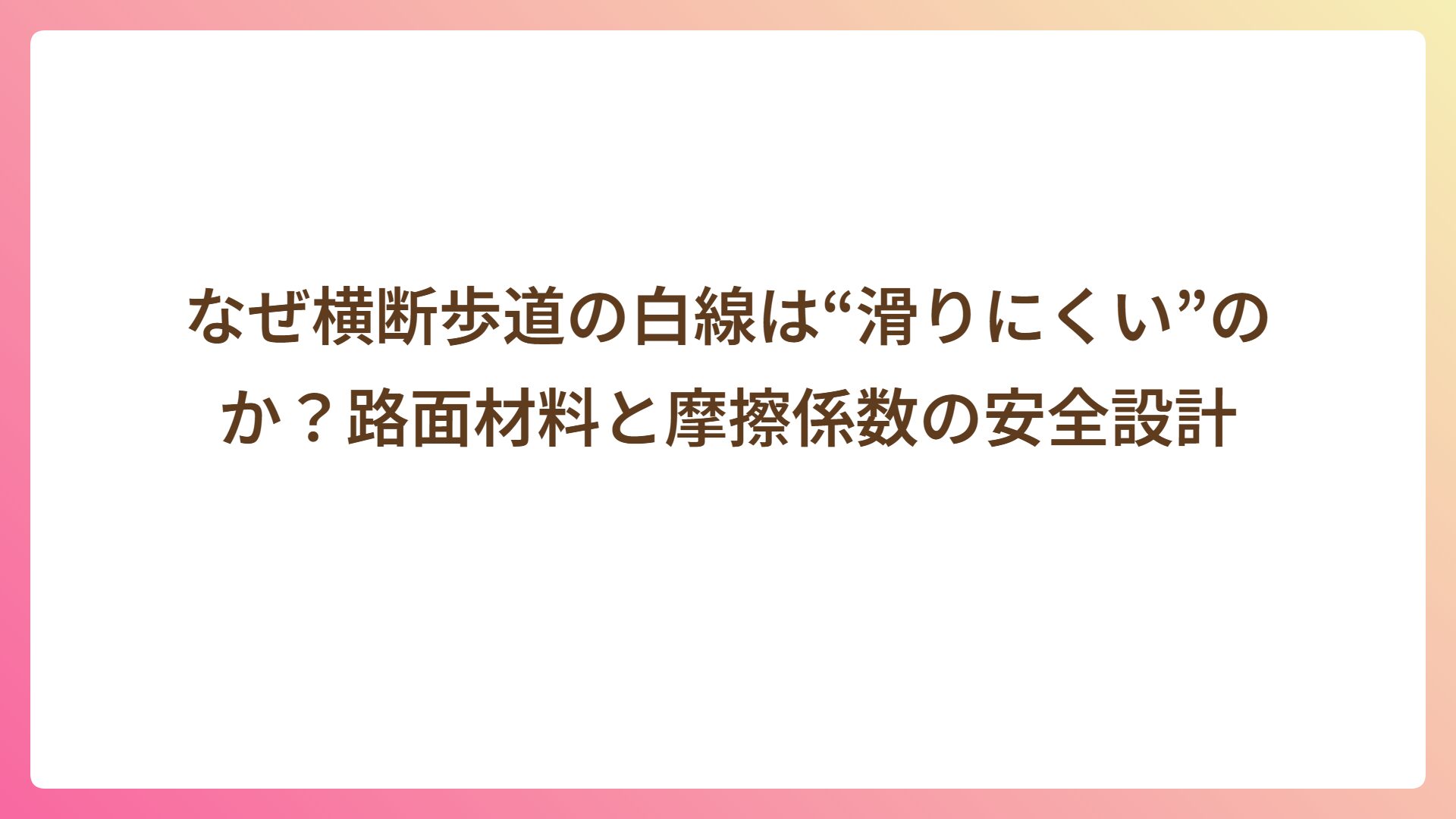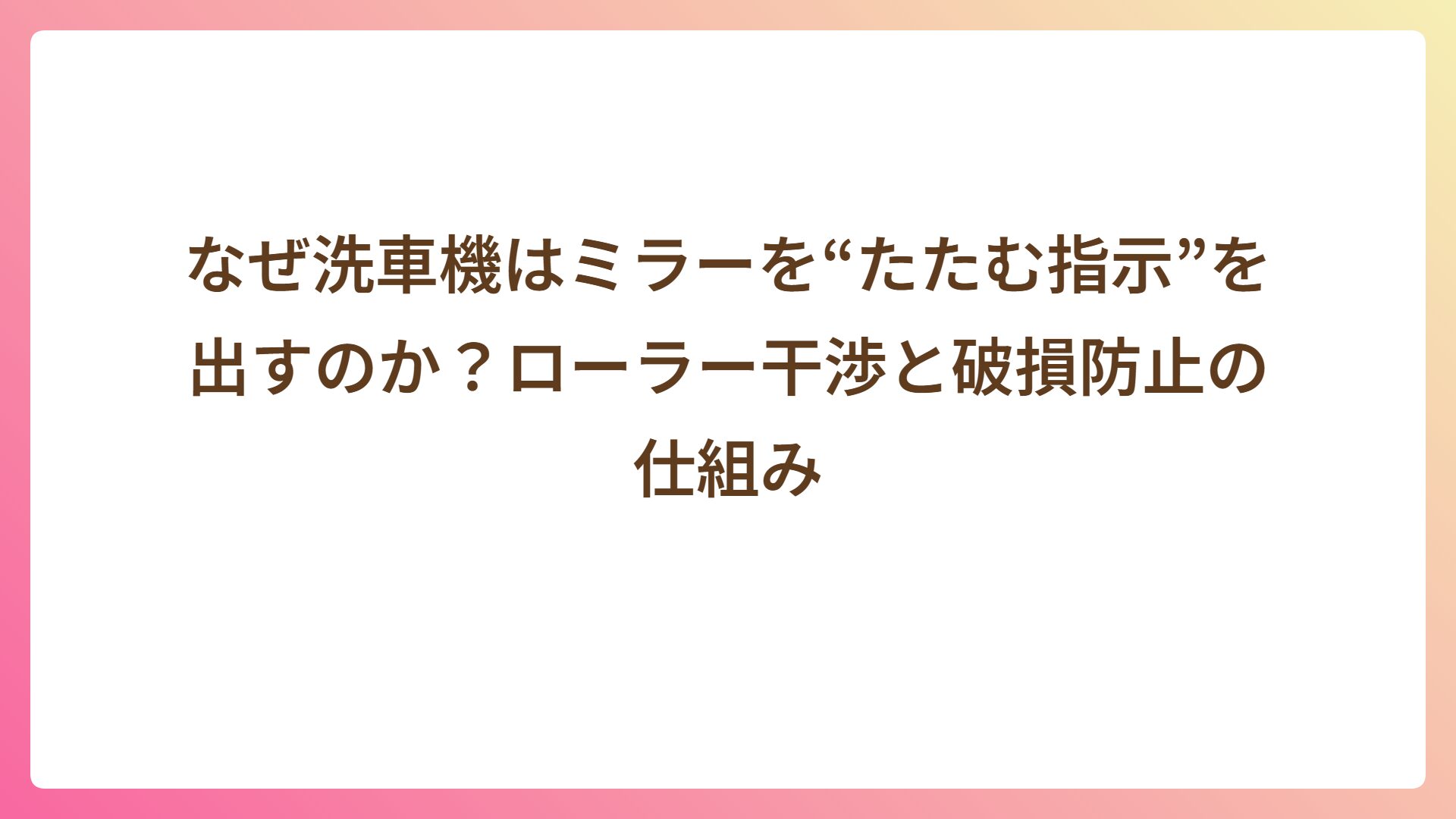なぜテレビ番組の放送時間は“54分”など中途半端なのか?CM枠と編成ルールの仕組み
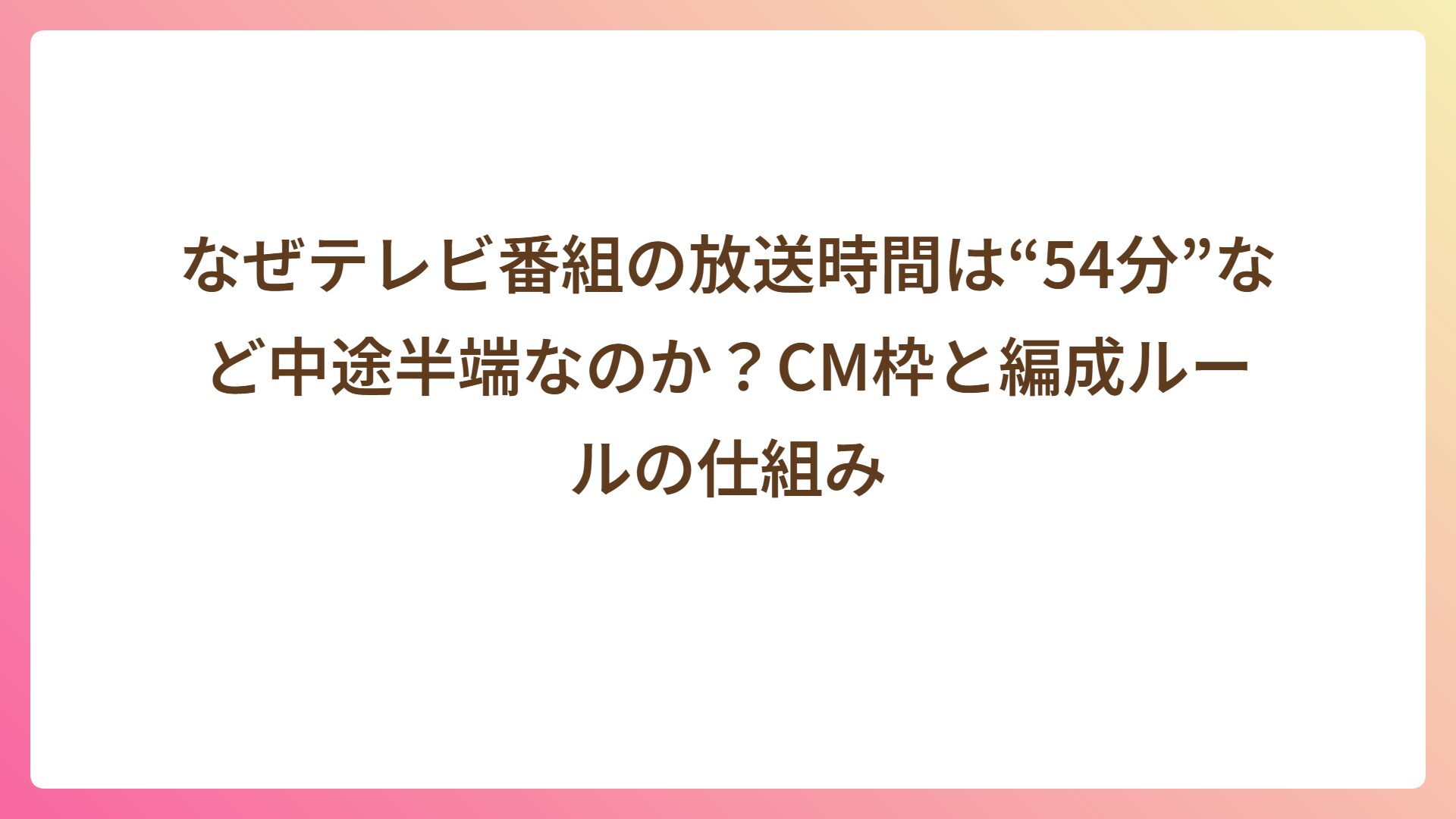
テレビ番組を見ていると、ドラマやバラエティの放送時間が「54分」「57分」「58分」など、きっかり1時間ではないことに気づきます。
なぜ、どの局も中途半端な時間設定にしているのでしょうか?
その理由は、CM(コマーシャル)の枠の構成と、放送局の編成ルールにあります。
この記事では、番組の放送時間が“きっかり60分”ではない理由を、広告・放送制度・編成の実務から解説します。
理由①:60分のうち“実際の番組部分”は約54分だから
1時間番組と言っても、実際に番組内容が流れているのは約54分ほど。
残りの6分前後は、CMや番宣(番組宣伝)、ステーションIDなどが挿入される時間です。
テレビ局は1時間を「番組+CM」で構成しており、
- 54分:番組本編
- 6分前後:CM・局アナウンス・次番組予告など
という内訳になっています。
そのため、番組表に「19:00〜19:54」と書かれていても、実際は1時間枠をフルに使っているというわけです。
理由②:広告主の“CM枠販売”単位が決まっている
テレビ局の収益は広告収入に依存しており、CMは秒単位で販売されています。
一般的に、30分番組では4〜5分、1時間番組では6〜8分がCM枠。
この時間配分は、広告主との契約上の基準になっており、
番組放送時間(実質54分)は、CM枠を差し引いた「残り時間」として設計されているのです。
つまり、「54分番組」は「60分枠からCMを除いた結果の放送時間」にすぎません。
理由③:“ステーションブレイク(SB)”のための時間が必要
テレビ局は番組の合間に、
- 局のロゴ表示
- ニュース速報
- 天気情報や次番組の案内
といった局独自の告知タイム=ステーションブレイク(SB)を挟みます。
この時間を確保するために、番組本体を54分・57分などに調整しており、
番組と番組の間に約3分のSB枠を挿入できるようにしています。
理由④:全国ネットとローカル局の“時報合わせ”のため
地上波放送では、キー局(東京)と地方局(系列局)が同じ番組を同時放送しています。
このとき、放送時間を毎時0分や30分にピッタリ合わせる必要があります。
番組を「19:54終了」とすれば、
- 19:54〜19:57:ローカル局のCMやお知らせ
- 19:57〜20:00:次の全国ネット番組の準備
といった形で、全国すべての放送局が時間を合わせやすい構成になります。
そのため、「中途半端な終了時刻」は全国ネットワークを同期させるための調整時間でもあるのです。
理由⑤:“またぎ番組”や“特番編成”との整合を取るため
テレビ局は、1日中綿密に番組を編成しており、
- 特番(2時間・3時間枠)
- 生放送番組
- ニュース枠
などがあるため、きっかり60分単位では収まらないことも多いです。
そこで、54分や57分などの微調整を行うことで、
- 番組同士のつなぎを滑らかに
- 1日の放送全体を無駄なく配置
できるようになっています。
理由⑥:広告放送の“法的ルール”にも基づいている
日本では、CM放送の時間や構成は放送法および総務省のガイドラインで制限されています。
たとえば:
- 1時間あたりの広告放送は「最大12分まで」
- CMと番組の区別を明確にすること
などが定められています。
このため、局はその範囲内で最大限効率よくCMを配置できるよう、
番組時間を調整しているのです。
理由⑦:CM構成の“慣習的フォーマット”が定着している
実際の編成では、以下のような時間割が一般的です。
| 番組枠 | 番組本編 | CM・告知 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 30分番組 | 約24分 | 約6分 | 30分 |
| 60分番組 | 約54分 | 約6分 | 60分 |
| 90分特番 | 約81分 | 約9分 | 90分 |
この「6分=1時間の1割をCMに充てる」構成は、
視聴者の集中力・広告効果・編成効率のバランスが取れた長年の業界慣習として定着しています。
まとめ:放送時間が“中途半端”なのは精密な編成の結果
テレビ番組の放送時間が「54分」や「57分」と中途半端なのは、
- 1時間の中にCM・局告知・ステーションブレイクを含むため
- 放送局ネットワーク全体の時間を同期させるため
- 広告枠や法令上の放送時間制限に合わせているため
といった編成上の合理性によるものです。
つまり、「54分番組」とは単に短いのではなく、
“1時間枠を最大限活かすための精密な放送設計”なのです。