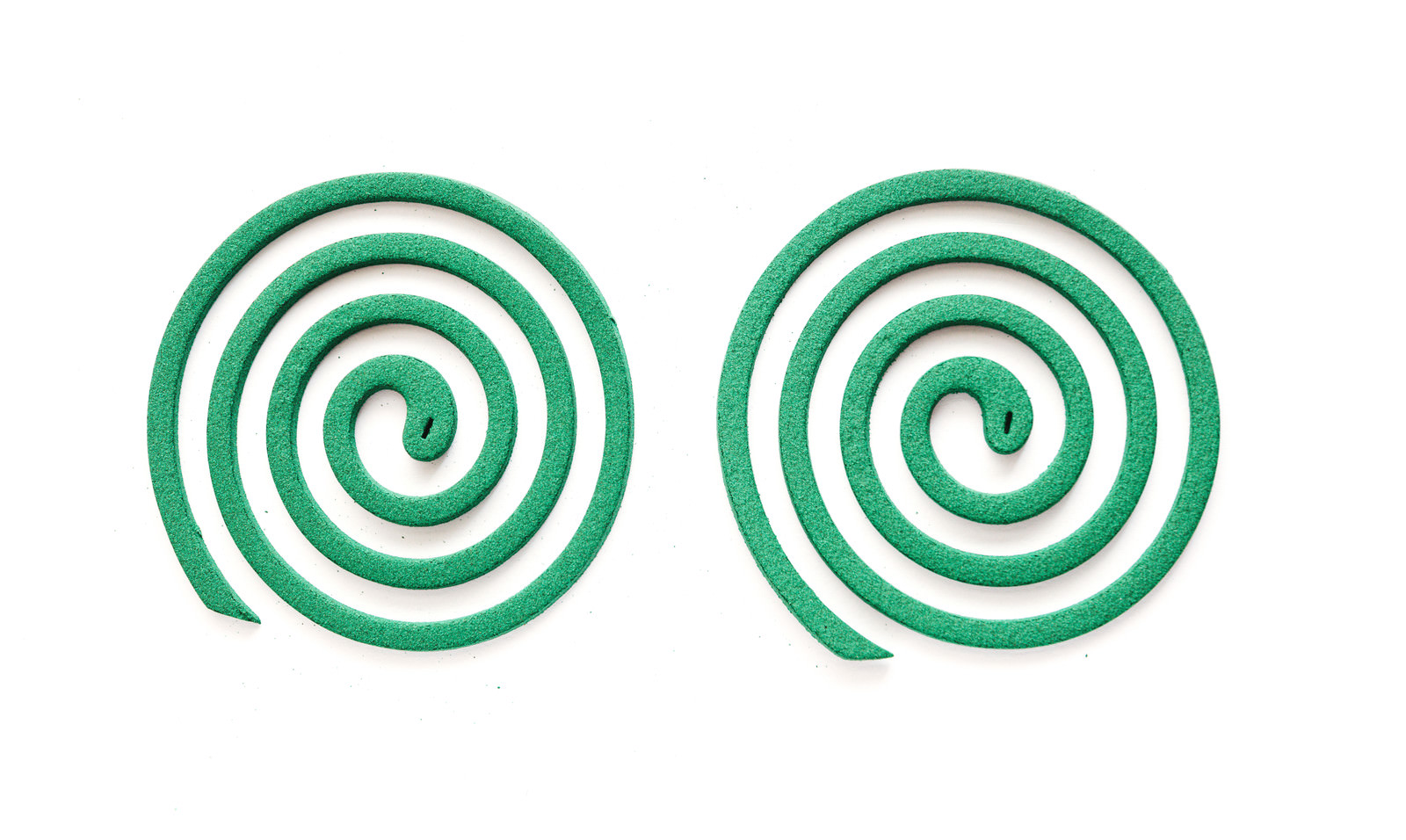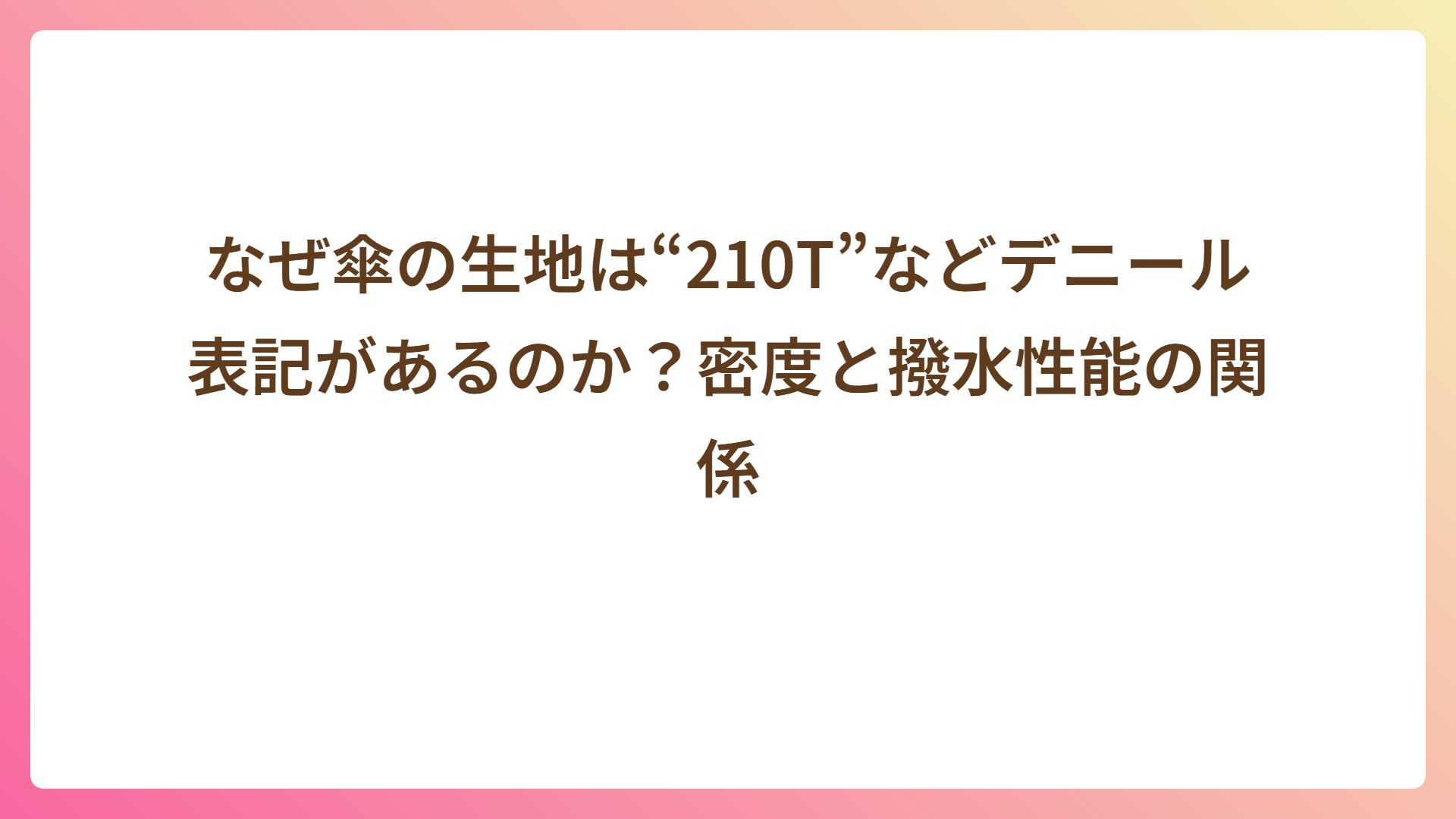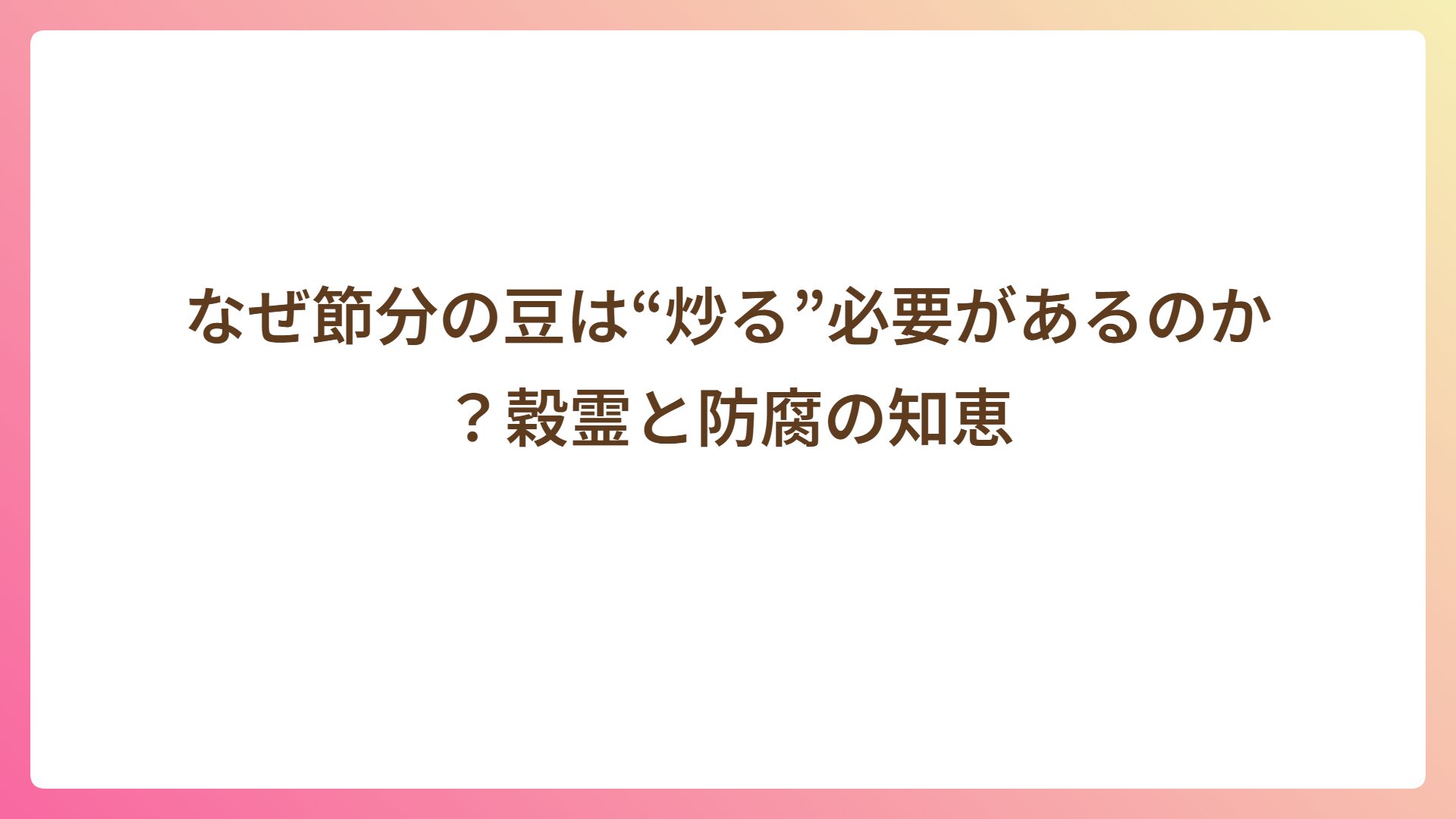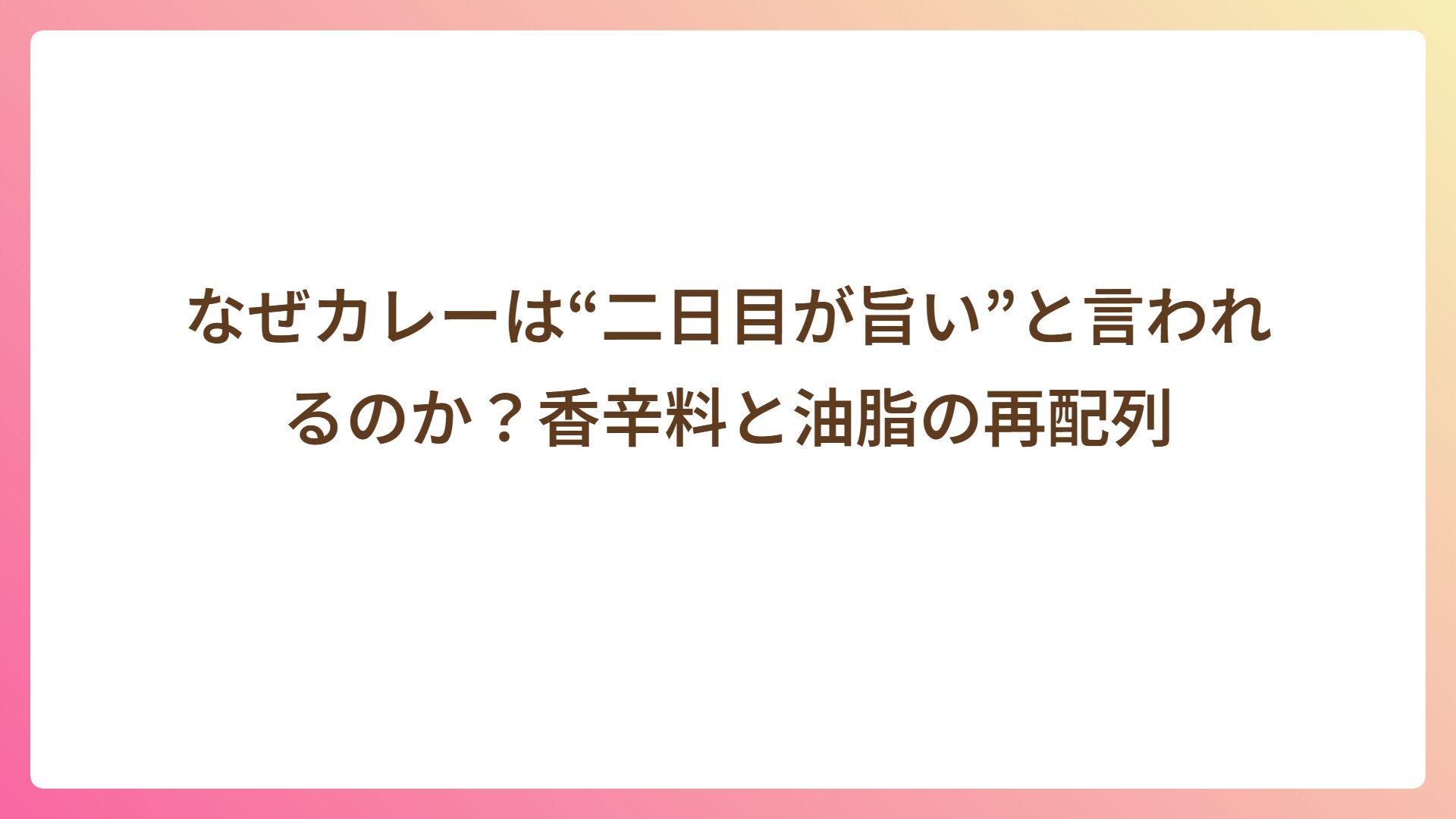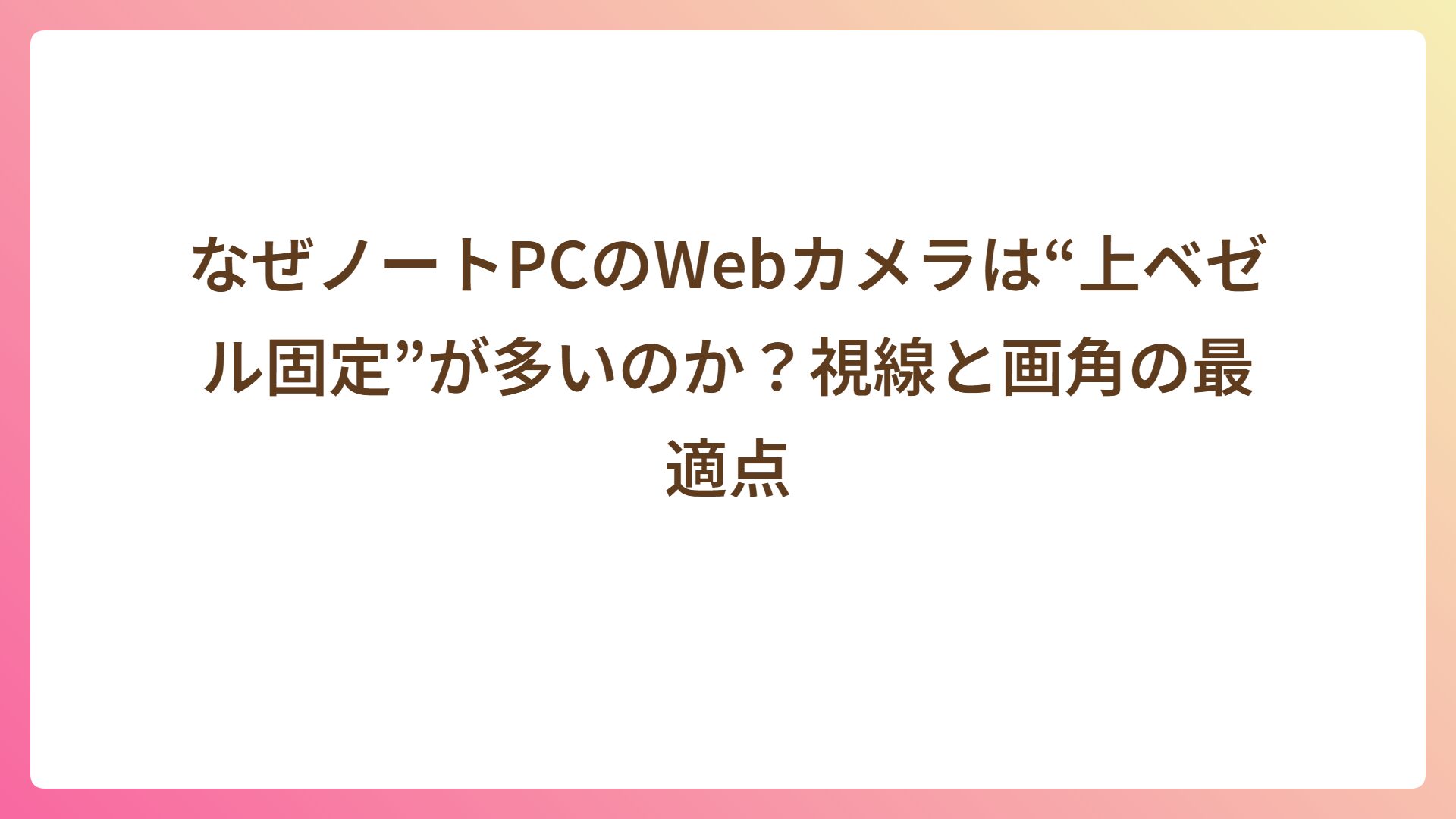なぜ梅干しは「白飯の友」の代表格になったのか?保存と戦の食文化史
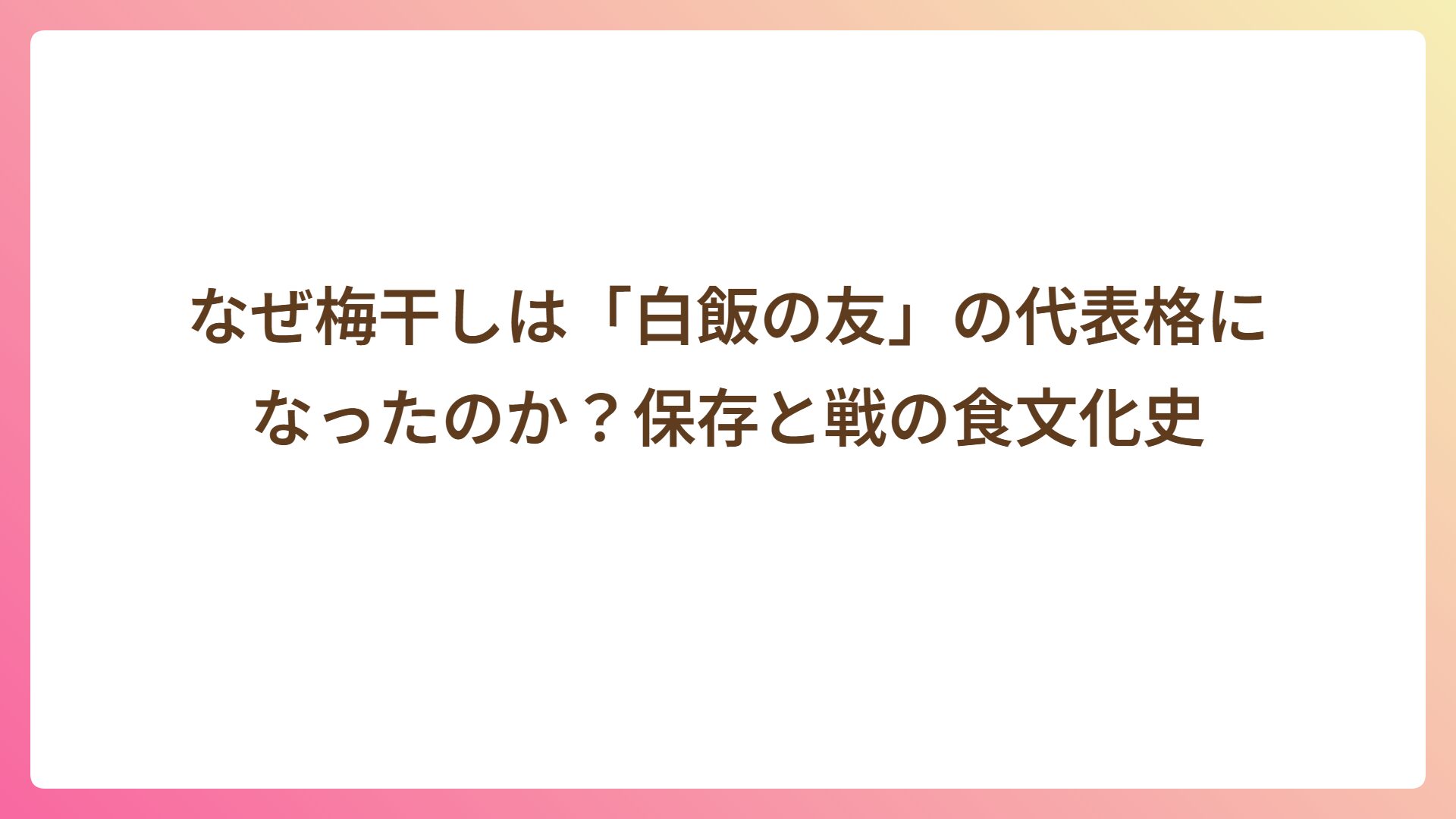
お弁当やおにぎりの定番といえば梅干し。
白いご飯の中央に置かれた赤い梅干しは、日本の食卓を象徴する存在です。
なぜ梅干しはこれほどまでに“白飯の友”として愛されてきたのでしょうか?
その背景には、保存技術・戦の食文化・健康思想が深く関係しています。
塩分と酸による「最強の保存食」
梅干しは、梅を塩と紫蘇で漬け込み、天日で干して作られます。
このときの塩分濃度は15〜20%と高く、さらにクエン酸による強い酸性環境が加わります。
この二重の作用により、細菌が繁殖できない環境が作られるのです。
そのため、常温でも腐りにくく、長期間保存が可能。
冷蔵庫のない時代において、梅干しはまさに天然の防腐剤として重宝されました。
ご飯と一緒に詰めた「日の丸弁当」も、
中央の梅干しが防腐効果をもたらす実用的な保存設計だったのです。
戦国時代の兵糧食としての梅干し
梅干しが広く普及したのは戦国時代。
戦場では水が汚れていることも多く、塩分・酸を含む梅干しは食中毒防止・疲労回復・防腐の三拍子そろった貴重な携行食でした。
また、武士たちは干飯(ほしいい)とともに梅干しを持ち歩き、
水で戻したご飯に梅干しを入れて食べていたとされています。
これが後の「梅干し×白飯」の組み合わせの原型となりました。
戦国の兵糧から、やがて庶民の弁当へと受け継がれたこの食習慣が、
梅干しを“白飯の友”へと押し上げたのです。
疲労回復と防臭効果 ― 科学的にも理にかなう組み合わせ
梅干しに多く含まれるクエン酸は、エネルギー代謝を促す働きがあり、
肉体労働や暑さによる疲労回復に効果的です。
また、酸味が唾液の分泌を促し、食欲を引き出すため、
白飯のような淡白な食材と組み合わせると旨味が引き立ち、消化も良くなるという科学的メリットもあります。
さらに梅干しの酸は抗菌作用があり、
常温で弁当を持ち歩く際にもご飯の腐敗を防ぐ役割を果たします。
色と形の“日の丸効果”
白いご飯の中央に赤い梅干しを置いた弁当は「日の丸弁当」と呼ばれ、
戦時中には日本の象徴的な食文化として広まりました。
この色の対比は見た目にも美しく、
「質素でも心は豊か」という日本的美意識を表しています。
単なる保存食を超え、梅干しは精神性と文化性を備えた食の象徴へと変化したのです。
まとめ
梅干しが“白飯の友”となったのは、
保存性・栄養性・戦場由来の実用性という三つの要素が結びついた結果です。
腐らず、疲れを癒し、味も引き立てる。
そして、赤と白のコントラストが美しい。
梅干しは、日本人の知恵と美意識が凝縮された「文化としての保存食」なのです。