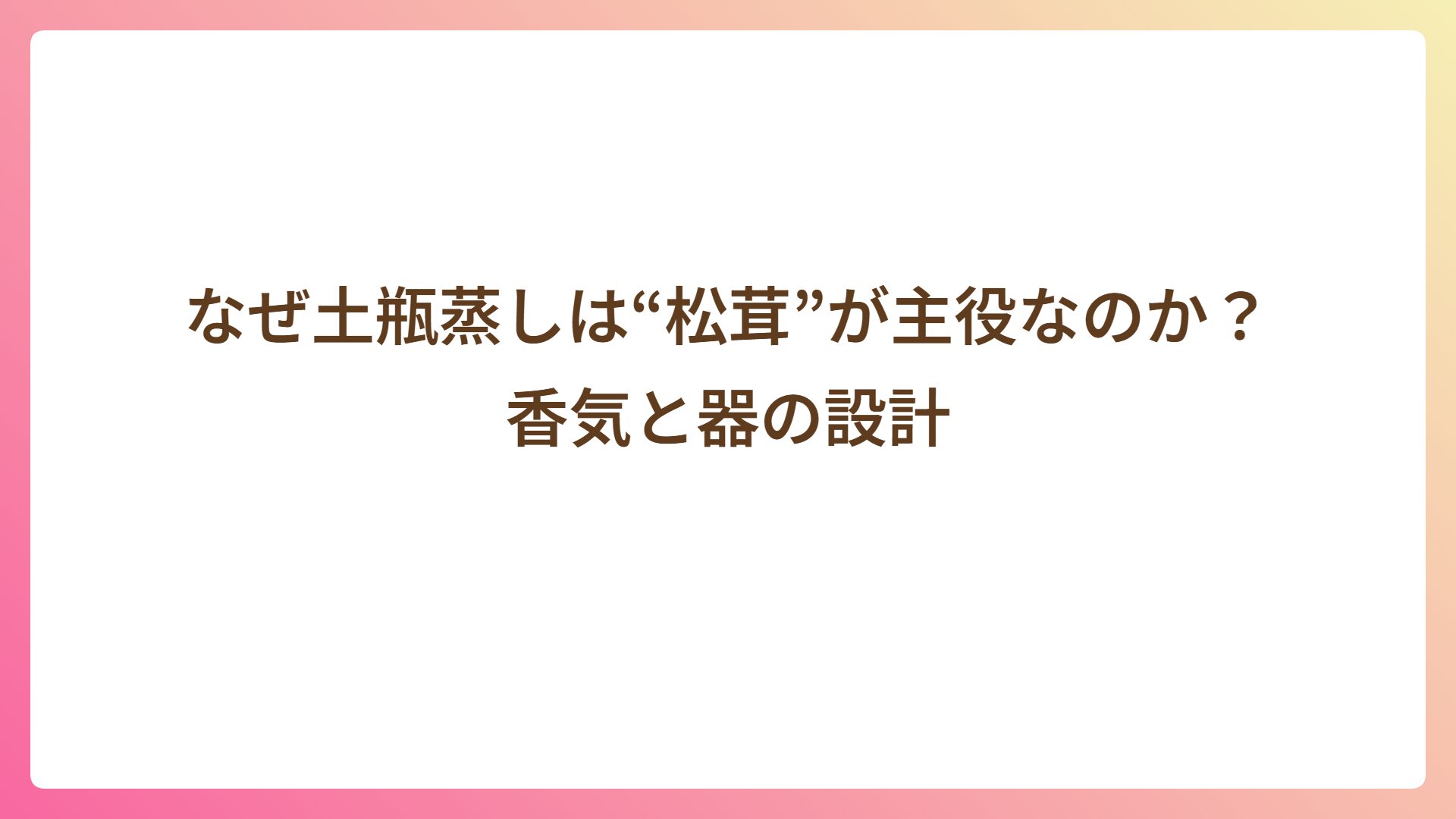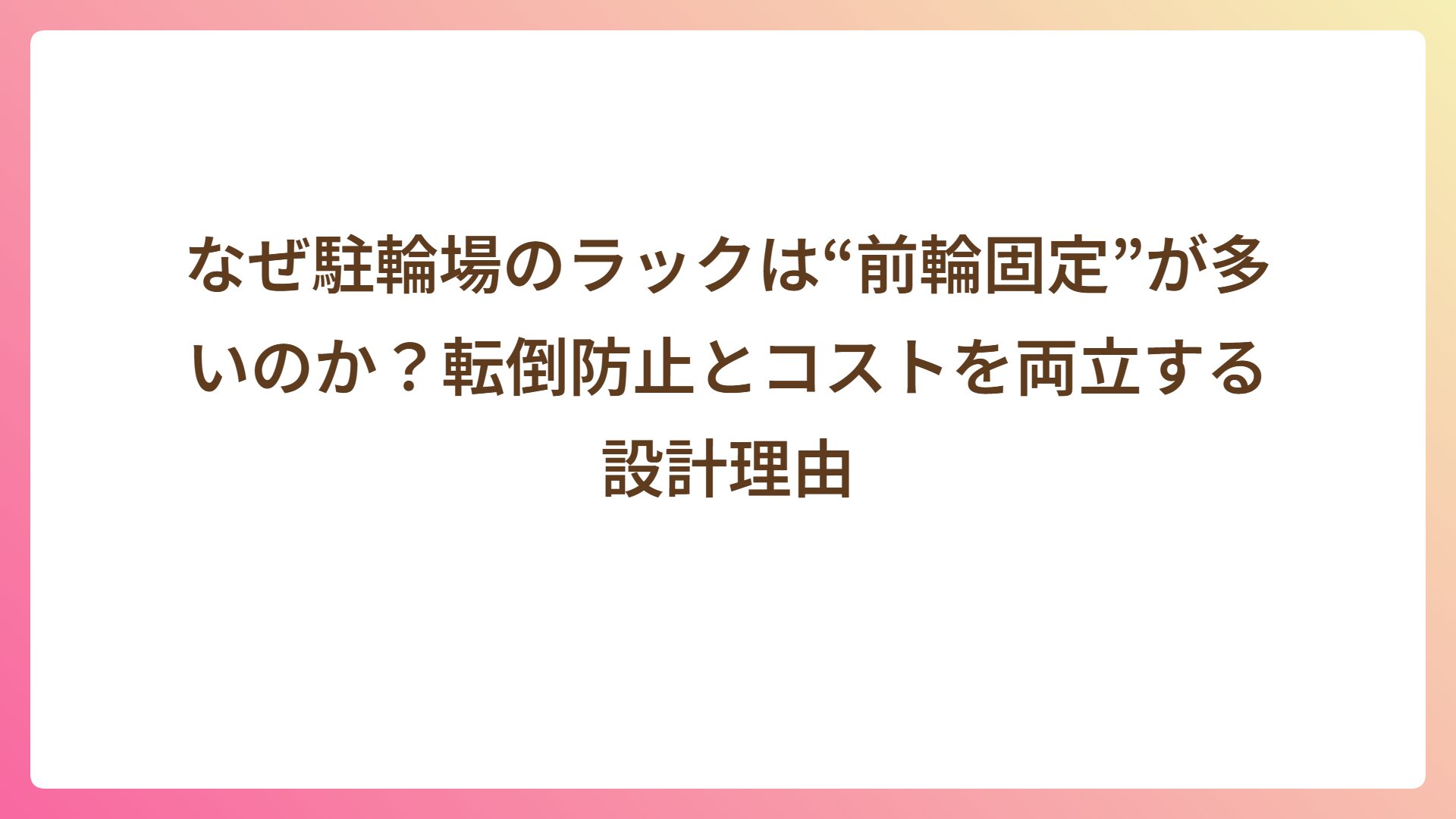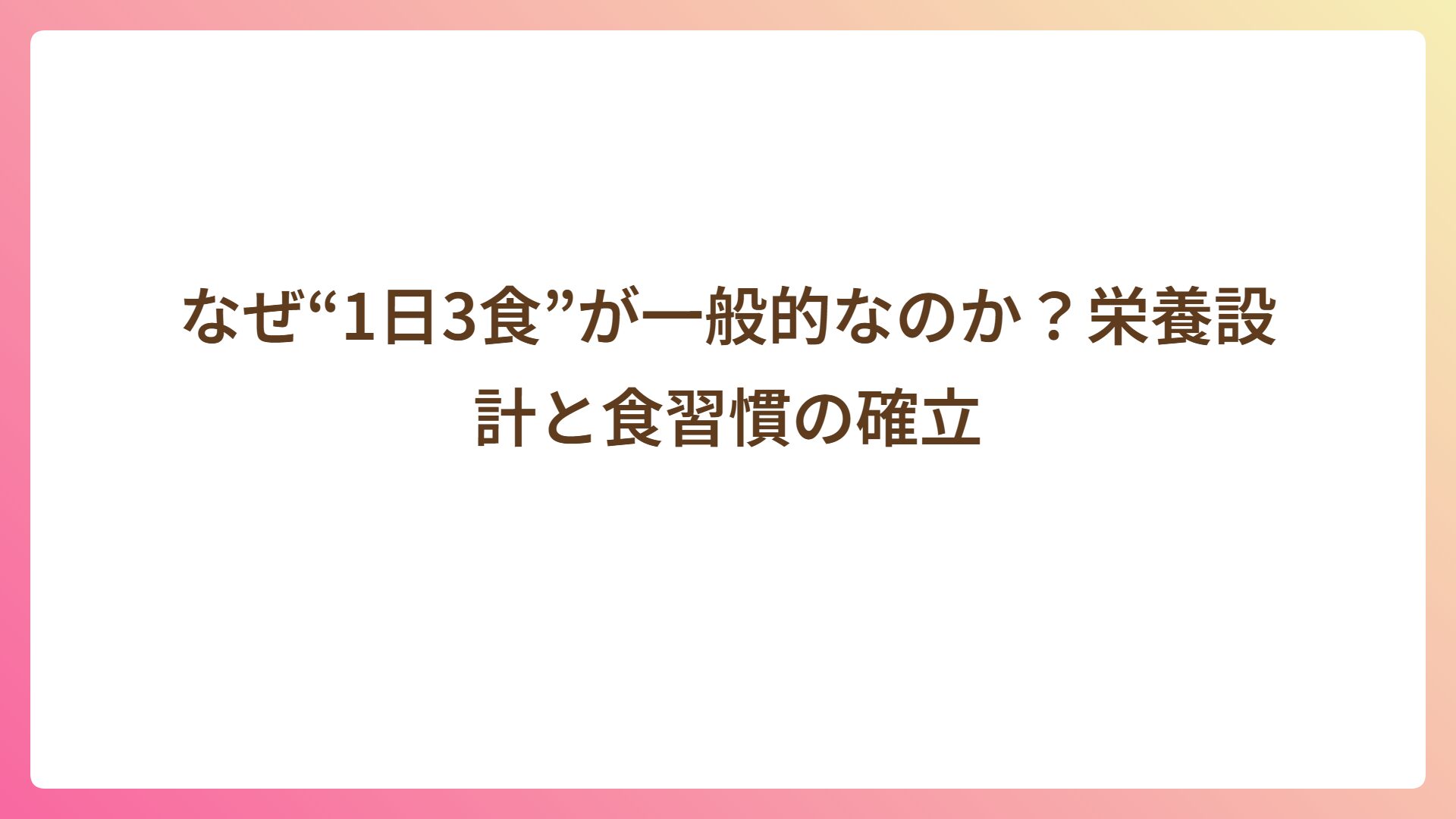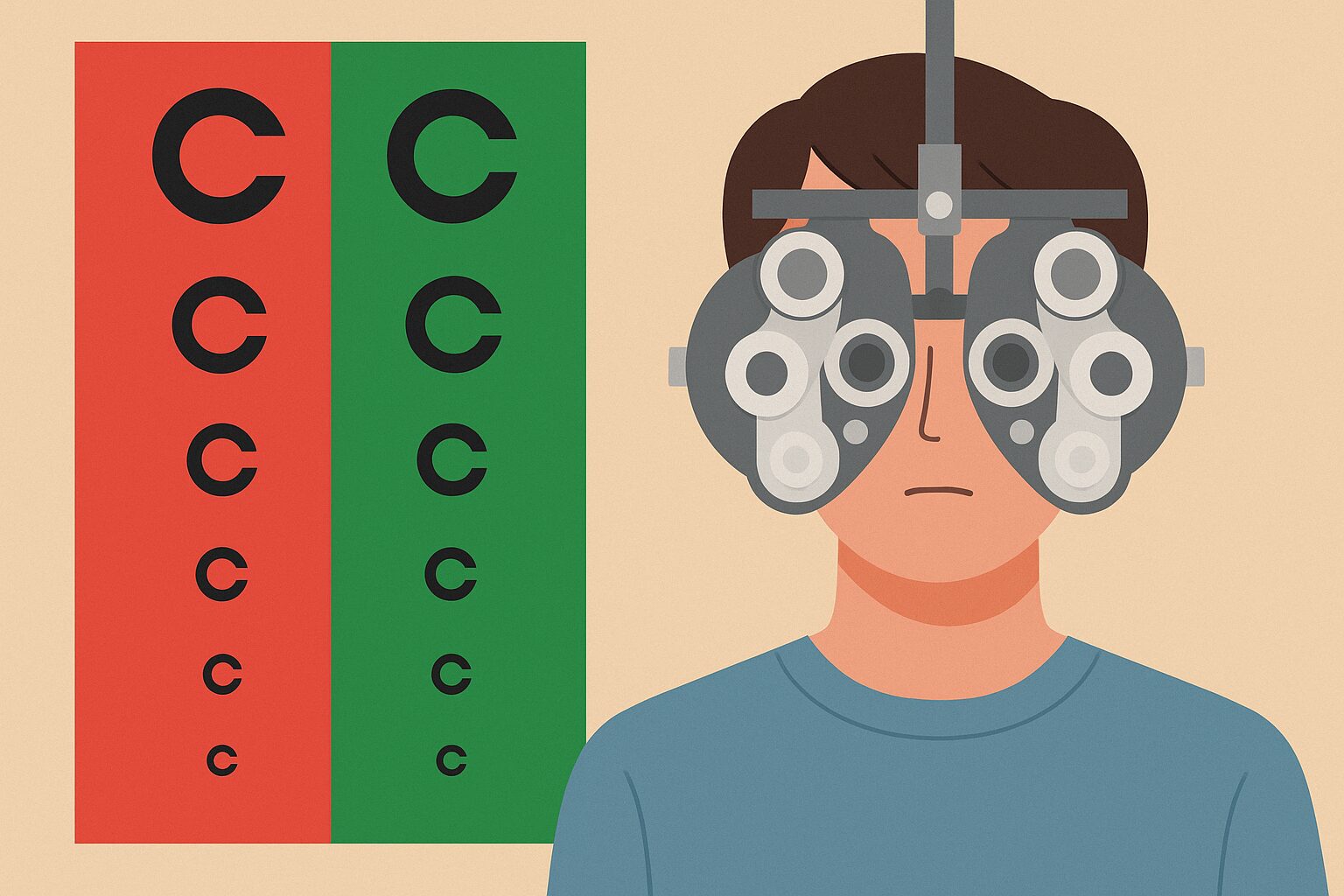なぜ宅内Wi-Fiは“2.4GHzと5GHz”を切り替えるのか?到達距離と干渉
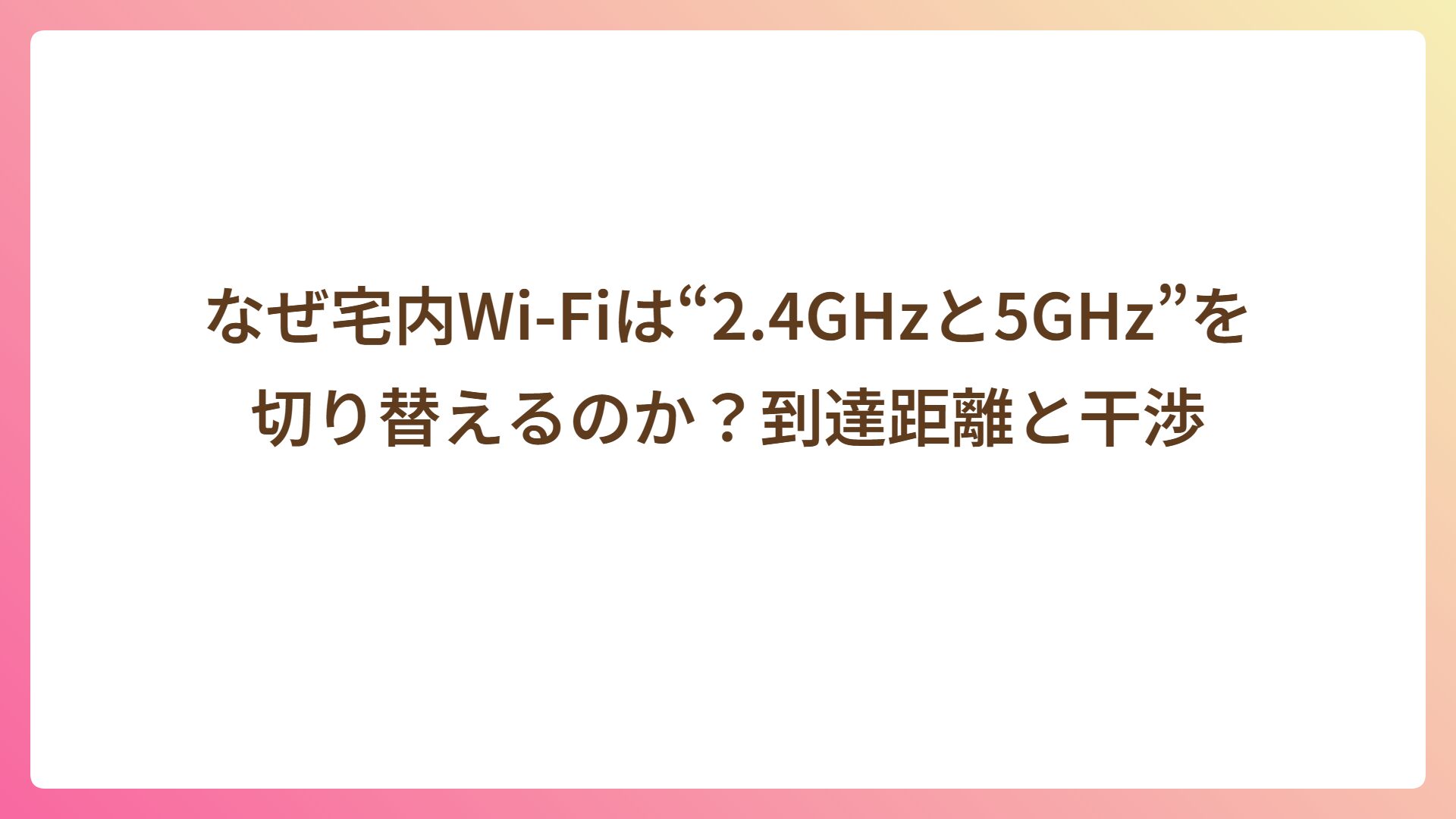
自宅のWi-Fiに「2.4GHz」と「5GHz」という2種類の電波があるのを見たことがあるでしょう。
どちらも同じインターネットに接続するのに、なぜわざわざ2種類が存在するのでしょうか?
実はこの違い、電波の届き方・速さ・干渉のしやすさという物理特性に基づいて使い分けられているのです。
2.4GHzは「遠くまで届く」電波
2.4GHz帯は、波長が長く障害物を回り込みやすいという特徴があります。
そのため、壁や床を隔てた別の部屋にも電波が届きやすく、広い範囲で安定した通信が可能です。
ただし、同じ周波数帯は電子レンジやBluetooth機器なども使用しているため、電波干渉が起きやすいという欠点があります。
つまり2.4GHzは、「広く届くけれど混み合いやすい」電波といえるのです。
5GHzは「速いが届きにくい」電波
一方、5GHz帯は波長が短く、直進性が高いため、より多くのデータを高速に送ることができます。
高画質動画のストリーミングやオンラインゲームなど、速度が求められる通信に向いています。
しかし、壁や家具などの障害物に弱く、距離が離れると急に電波が弱くなるという弱点があります。
つまり5GHzは、「速いけれど遠くまでは届かない」電波です。
自動切り替え(バンドステアリング)の仕組み
最近のWi-Fiルーターは、状況に応じて2.4GHzと5GHzを自動で切り替えるバンドステアリング機能を備えています。
たとえば、近距離では5GHzで高速通信を行い、離れた部屋では2.4GHzに自動的に切り替わるようになっています。
これにより、ユーザーが意識しなくても速度と安定性のバランスを最適化できるのです。
また、混雑状況を判断して空いている周波数帯へ誘導する機能もあり、同じ家の中でも時間帯や接続数に応じて通信効率を維持しています。
干渉を避けるための工夫
2.4GHz帯は家電製品との干渉が避けられないため、ルーターは**チャンネル(周波数の細かい区分)**を切り替えて干渉を最小限に抑えています。
一方、5GHz帯はチャンネル数が多く、空いている帯域を選びやすいため、混線しにくく安定した通信が実現できるのです。
また、最新規格のWi-Fi 6では「OFDMA」や「MU-MIMO」などの技術で複数機器の同時通信効率も改善されており、2.4GHzでも干渉の影響を受けにくくなっています。
まとめ
Wi-Fiが2.4GHzと5GHzを切り替えて使うのは、電波の到達距離と通信速度、干渉のしやすさが異なるためです。
2.4GHzは遠くまで届くが干渉に弱く、5GHzは速いが距離に制限がある。
この2つを自動で使い分けることで、家庭内のどの場所でも安定した通信を確保できるのです。
つまり、「2つの電波帯」は不便さではなく、最適な通信を維持するための仕組みなのです。