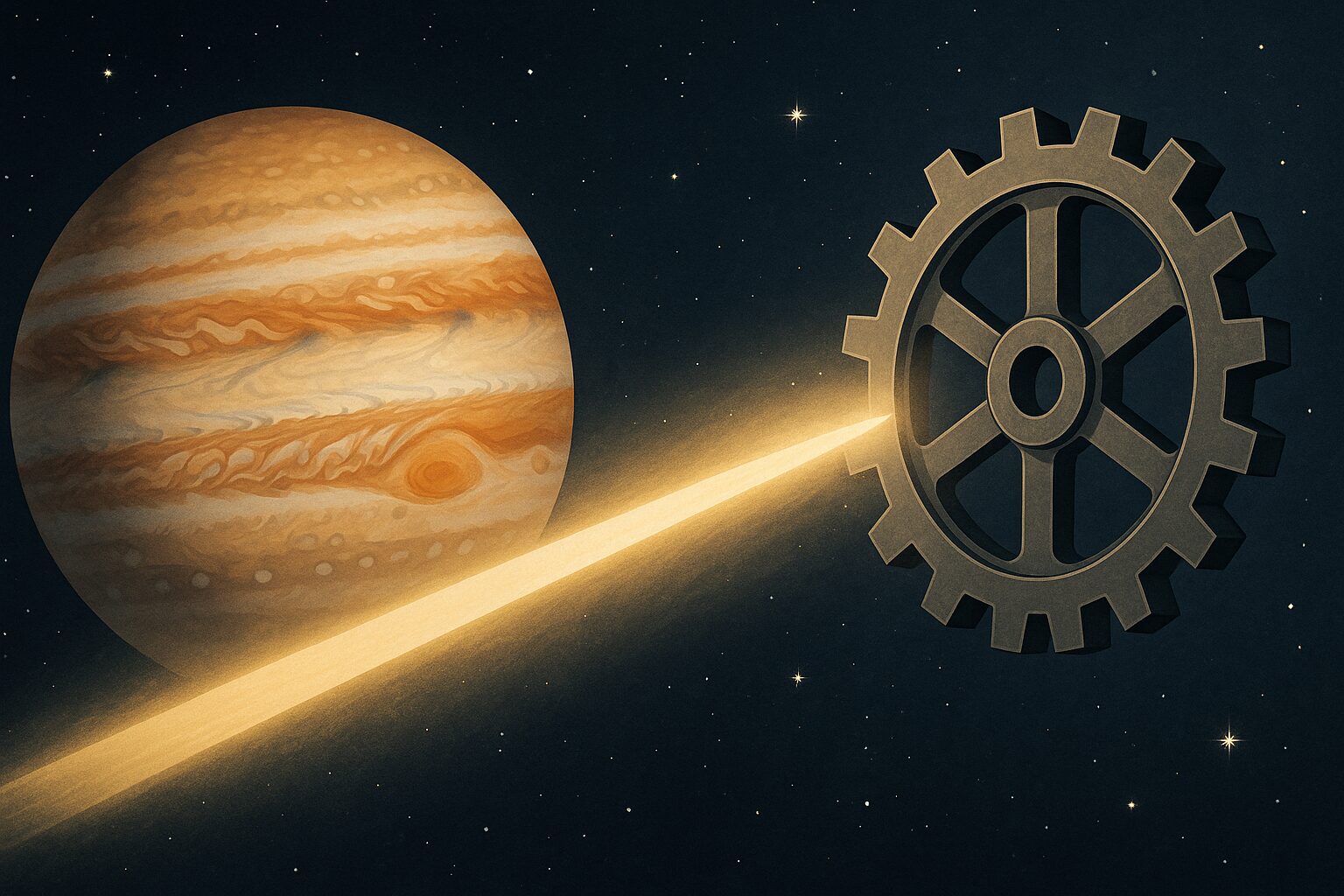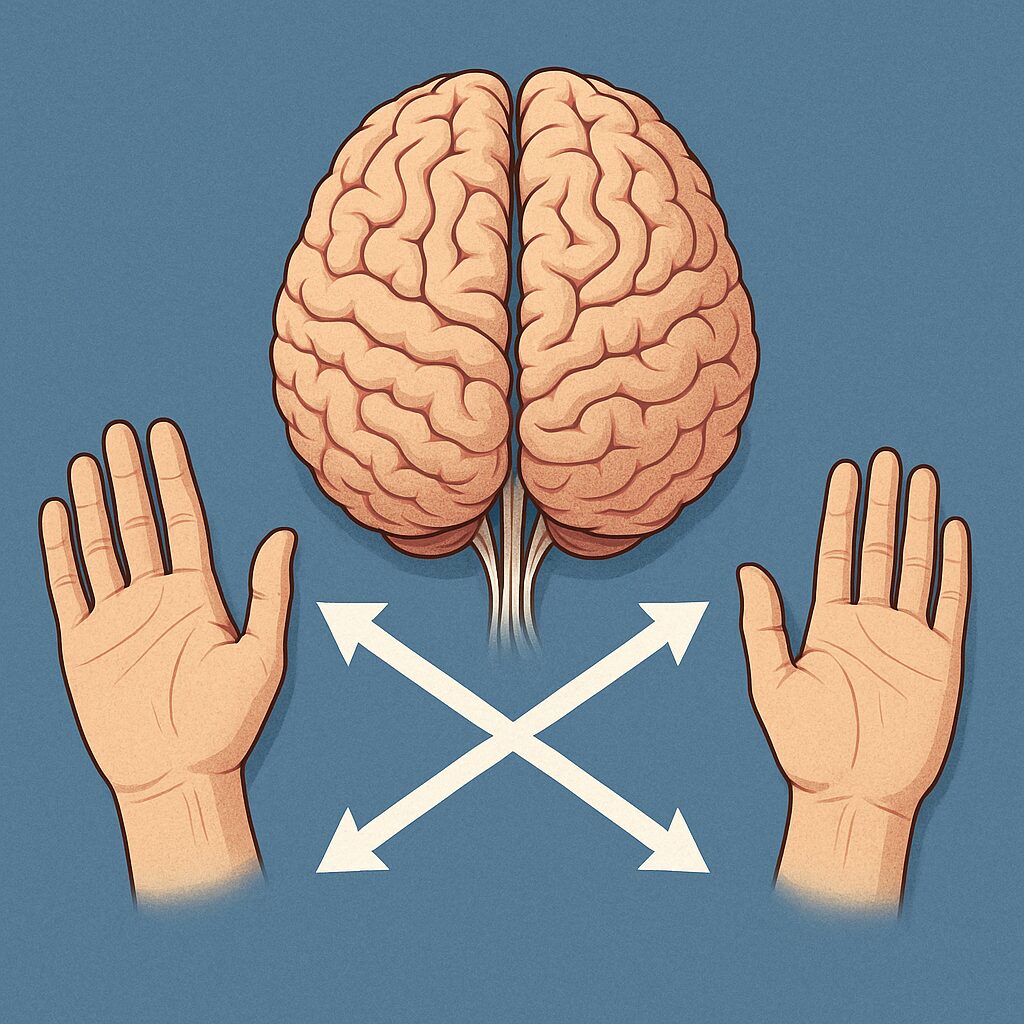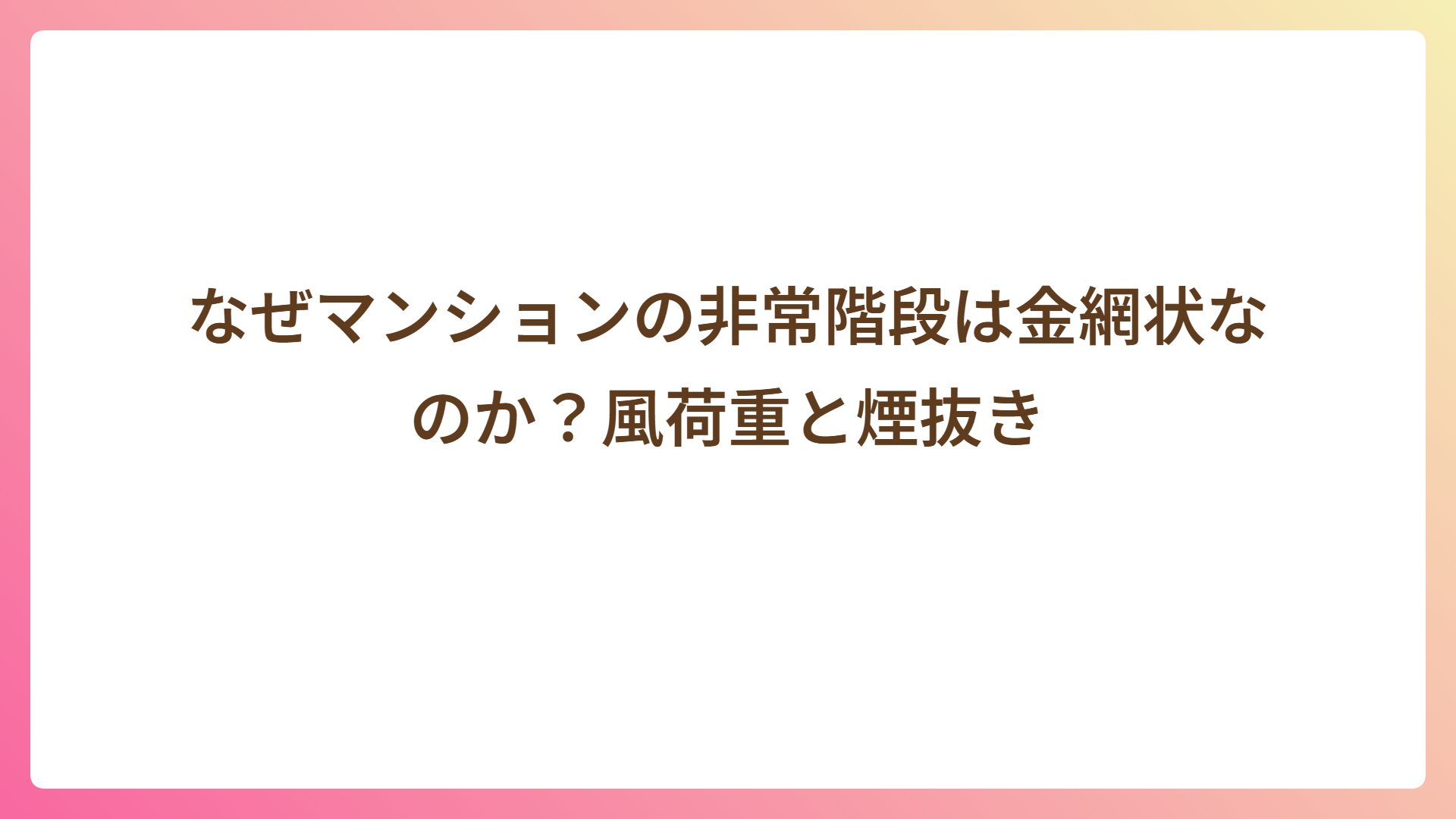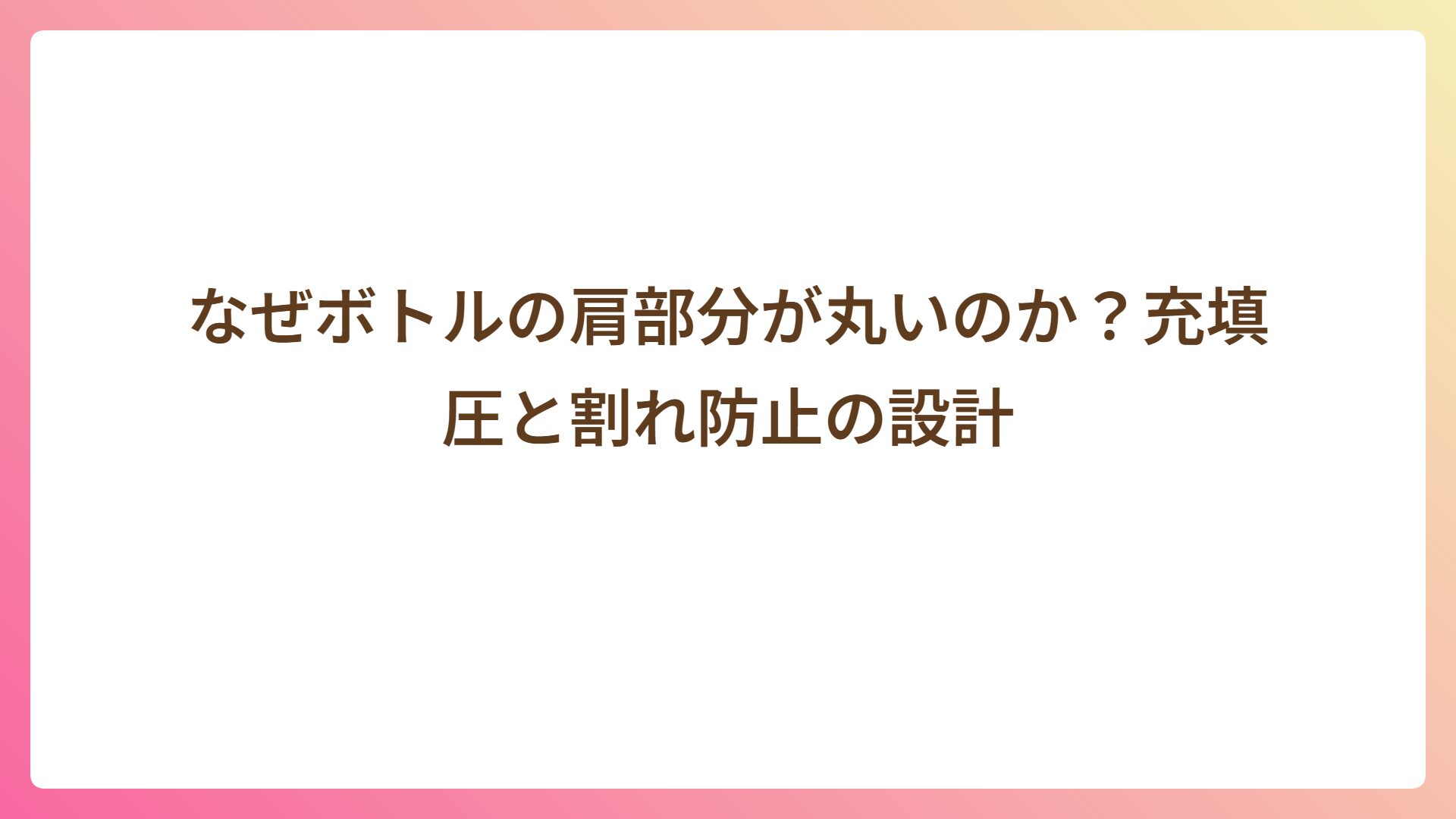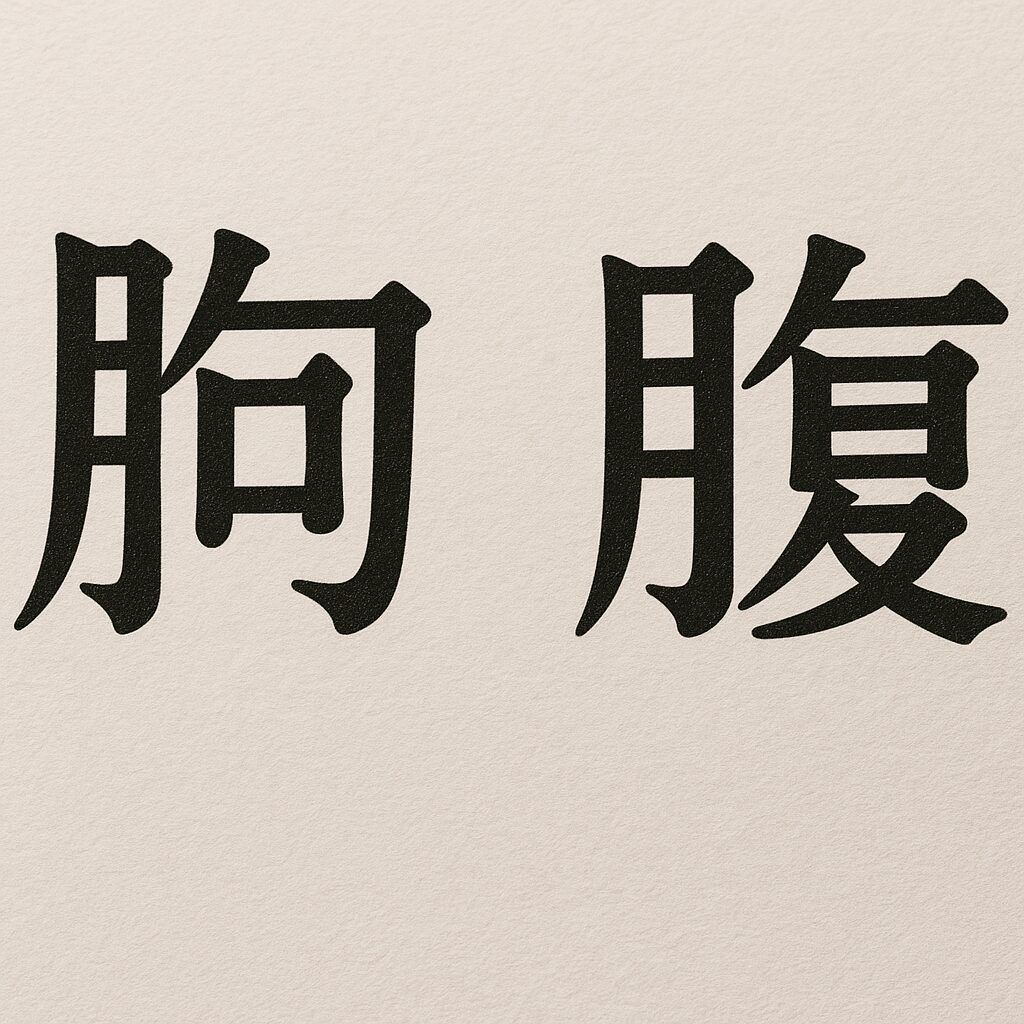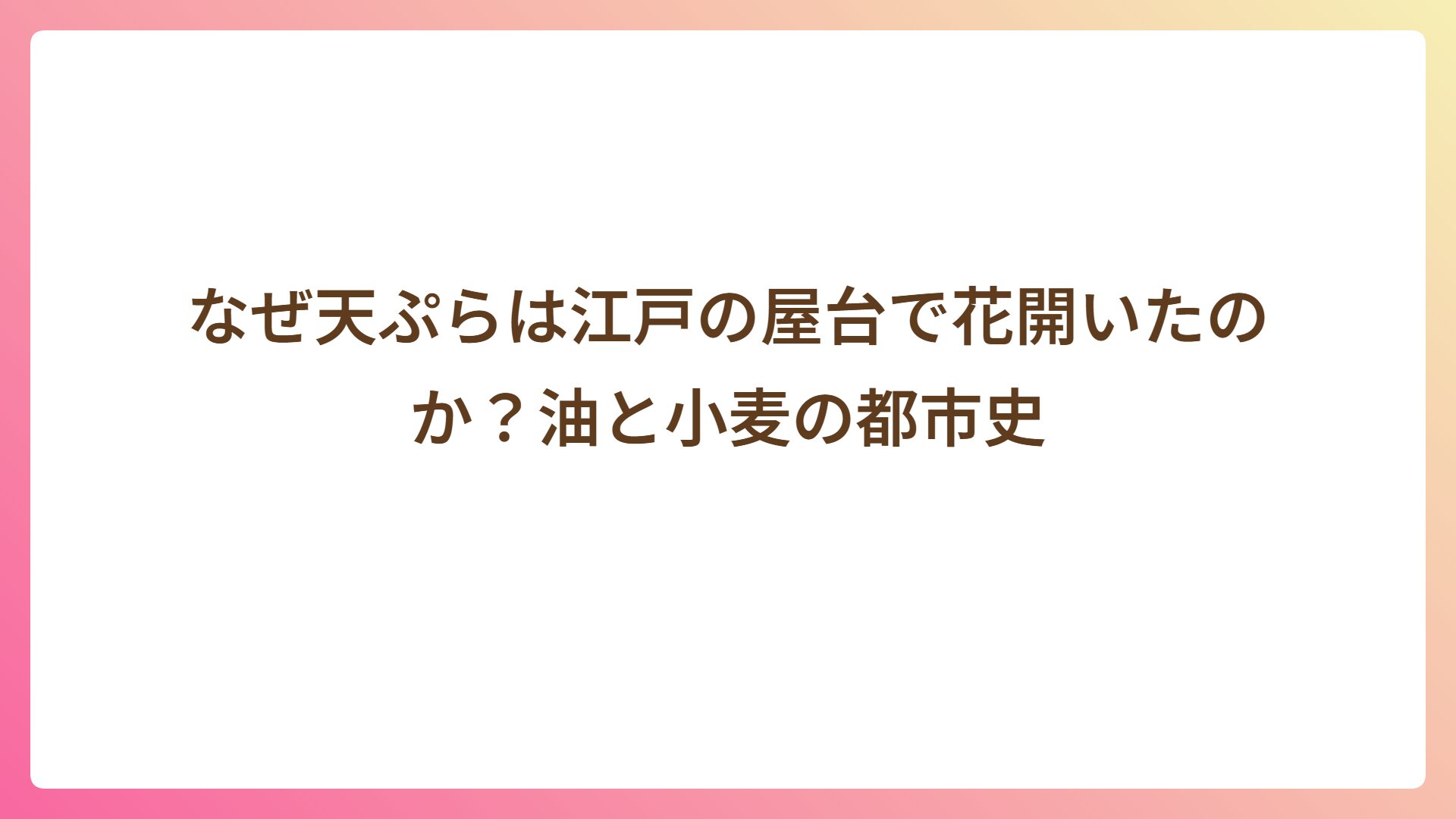なぜ価格表示は“税抜と税込”が併記されるのか?特商法と実務の関係
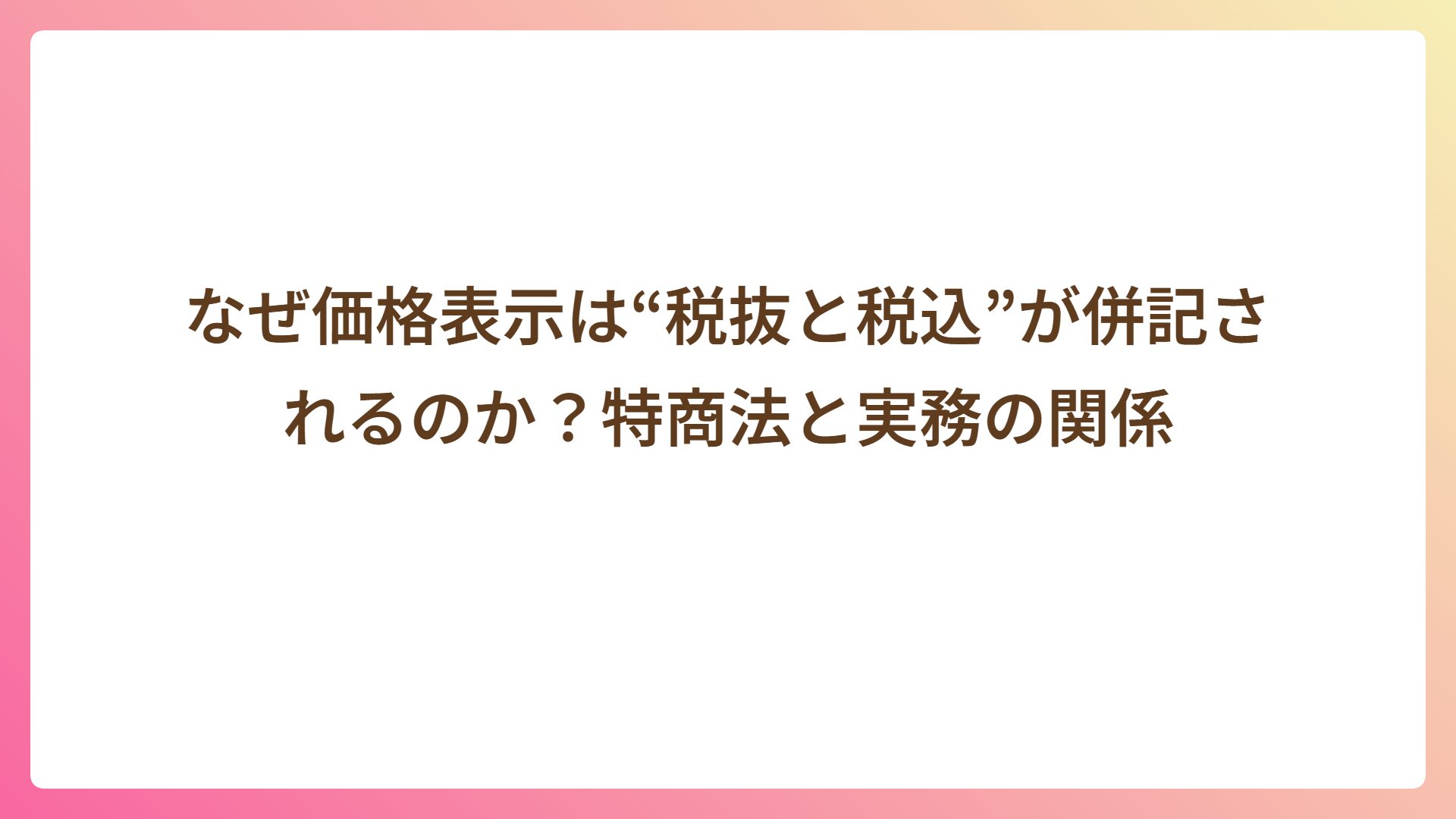
スーパーやネット通販の商品ページで「1,000円(税抜 909円)」のような表示を見たことはありませんか?
一見わかりにくいこの“併記表示”ですが、実は法的なルールと販売現場の事情が複雑に絡んでいます。
この記事では、価格表示に「税抜」と「税込」が併記される理由を、特商法・消費税法・実務上の運用という3つの視点から整理して解説します。
総額表示義務とは?すべての「税込価格」を明示するルール
まず前提として、日本では消費税を含めた「支払総額」を表示する義務があります。
これは「総額表示義務」と呼ばれ、消費税法第63条に基づいて消費者に誤解を与えないためのルールとして2004年に導入されました。
たとえば、
- ✕「1,000円+税」
- ○「1,100円(税込)」
のように、購入時に実際に支払う金額が一目で分かる表示が求められています。
この義務は、消費者が「レジで思っていたより高かった」と感じることを防ぐためのものです。
それでも“税抜併記”が残る理由①:事業者の経理・価格設定の都合
一方で、多くの店舗やECサイトでは税込価格と税抜価格が併記されています。
これは、事業者側の経理・販売戦略上の都合によるものです。
企業の仕入れ・会計処理では税抜価格が基本単位として扱われます。
特にBtoB(企業間取引)では税抜でのやり取りが主流のため、税抜額を併記することで社内処理や原価管理がしやすくなります。
また、税率が変動した際にも税抜価格をベースに再計算できるため、価格改定の手間が少なく済むというメリットもあります。
税抜併記が残る理由②:特定商取引法の「誇大表示」防止
オンラインショップなど通信販売では、特定商取引法(特商法)の表示義務も関係しています。
特商法では「実際に支払う金額を誤認させる表示」を禁止しており、税込価格を明記することが求められています。
ただし、消費者が“税金を除いた本体価格”を知りたい場合も多いため、
- 「本体価格(税抜)」
- 「支払総額(税込)」
を併記すれば誤認を招かずに両立できるため、実務上よく採用されています。
つまり、税抜表示は「内部の管理用」だけでなく、「消費者に価格構造を明確に伝えるため」の一面もあるのです。
税抜併記が残る理由③:小売現場での“価格印象”コントロール
心理的な側面もあります。
税込価格だけを大きく表示すると、見た目の価格が上がったように感じられ、購買意欲が下がる傾向があります。
そこで、
- 大きな文字で「税抜価格」
- その下に小さく「税込価格」
というデザインを採用し、「お得に見せる」心理的演出を行っている店舗もあります。
これは法的にグレーな領域ですが、「税込価格がどこかに明示されていればOK」という消費税法の運用上、一定の範囲で許容されています。
総額表示義務の“例外”と緩和措置
実は、2021年4月までは「総額表示義務の特例」が一時的に認められており、
「税抜価格+税」などの表示も容認されていました。
コロナ禍による景気変動などを踏まえ、価格改定の混乱を避けるためです。
しかし、現在は原則として税込価格の明示が必須に戻っています。
ただし、カタログ・チラシ・ECサイトの仕様上、
「税抜価格( )内に税込価格」などの併記は合法的な表現として残っています。
まとめ:税抜・税込併記は“法令遵守+実務合理性”の結果
価格表示に税抜と税込が併記されるのは、
- 消費税法による総額表示義務を守るため
- 事業者の経理・価格管理の合理化
- 特商法の誤認防止と消費者への情報提供
- 販売心理・デザイン面での調整
といった複数の理由が重なった結果です。
見た目にはやや煩雑ですが、その裏には法令遵守と実務の最適解が存在しています。
今後、税率変更やデジタルインボイス制度の普及に伴い、表示方法が再び見直される可能性もあるでしょう。