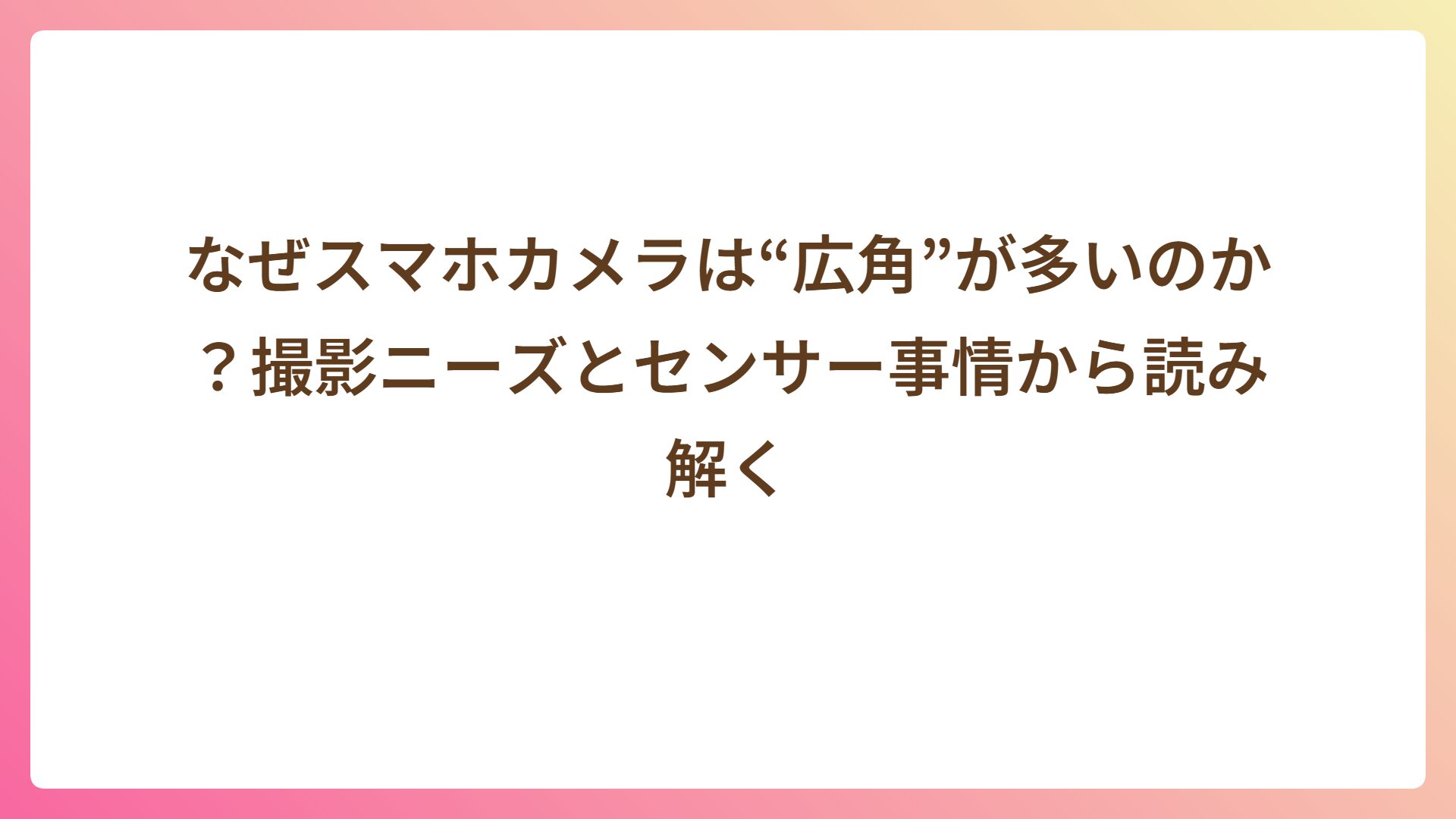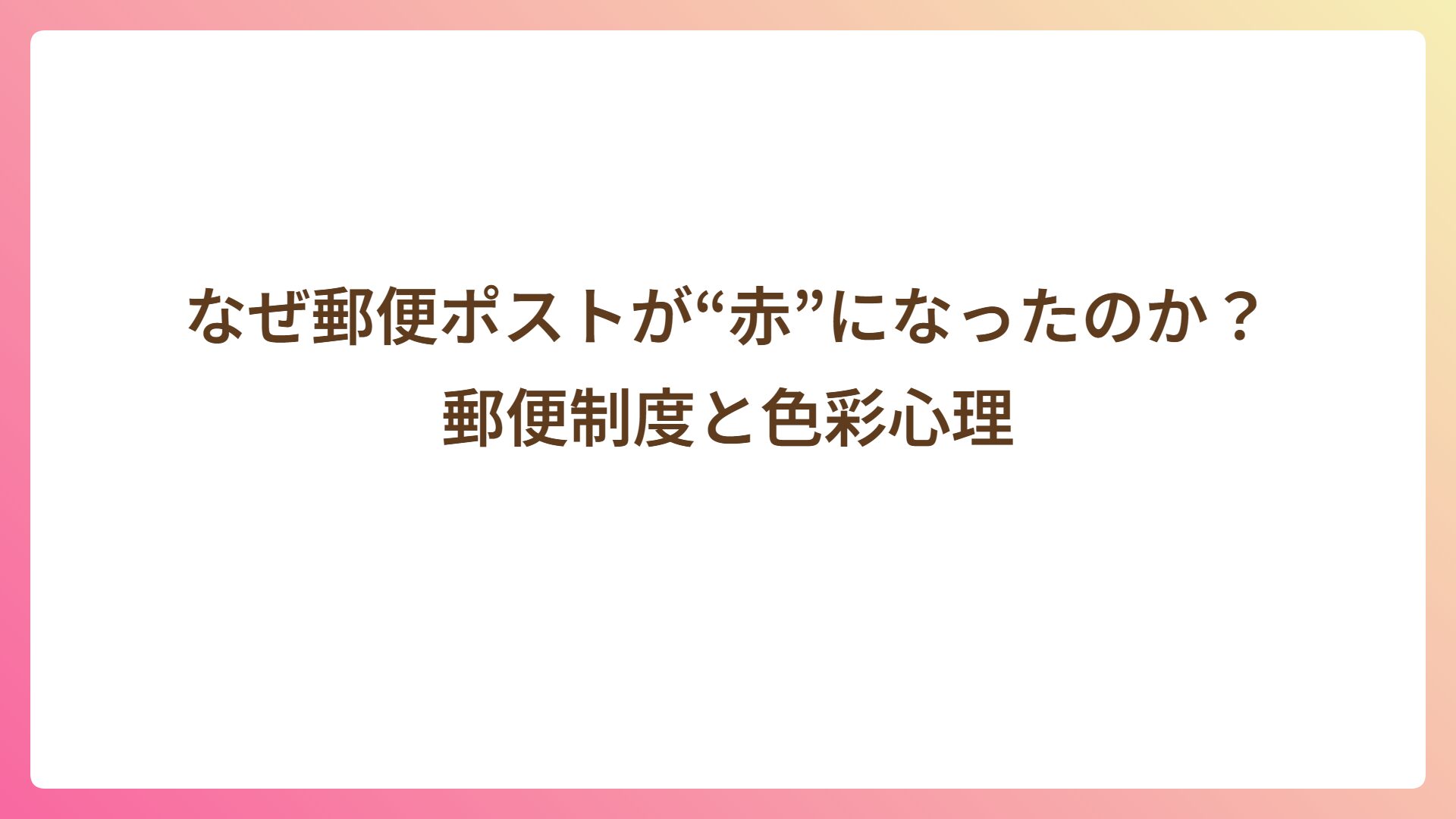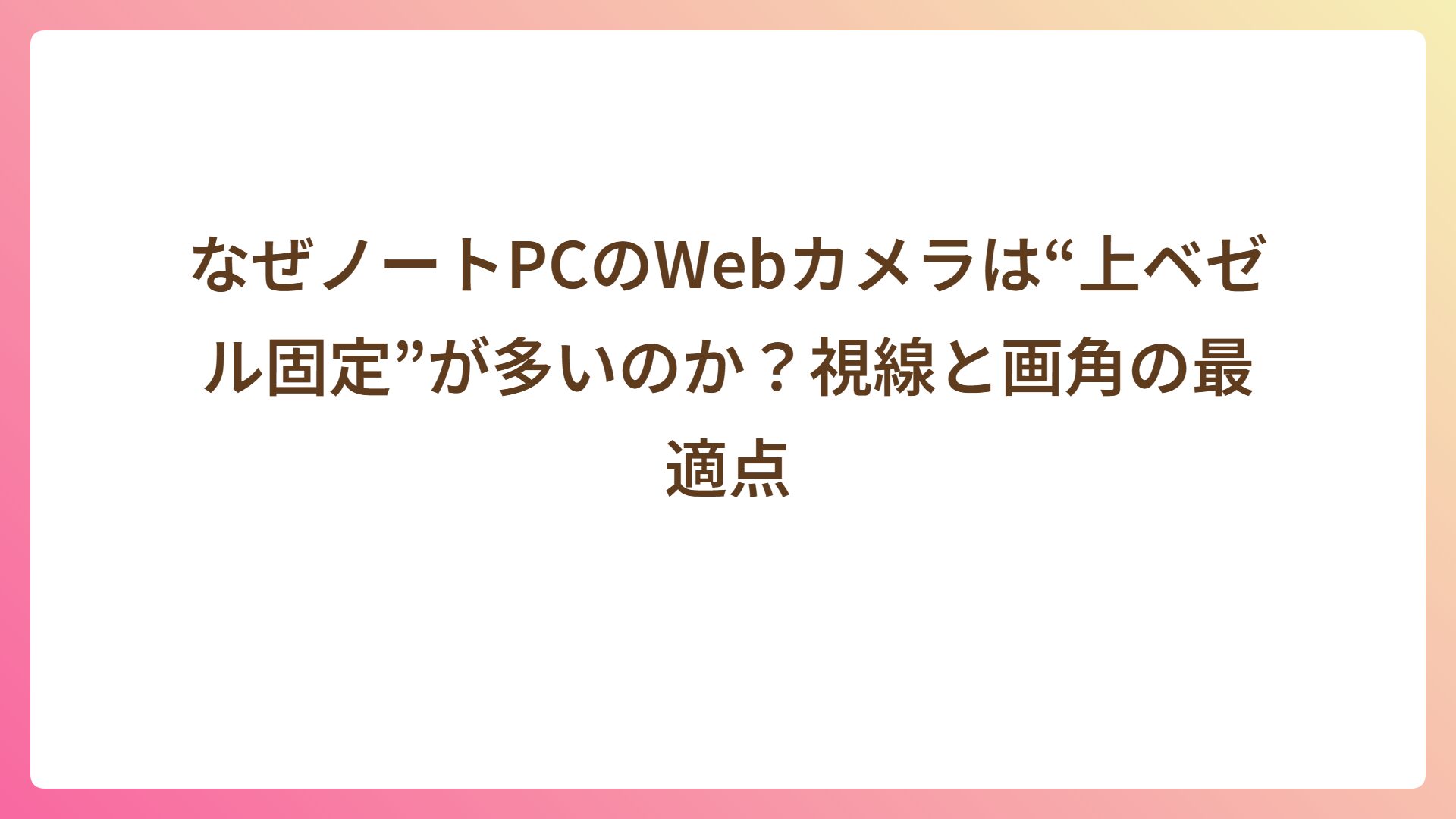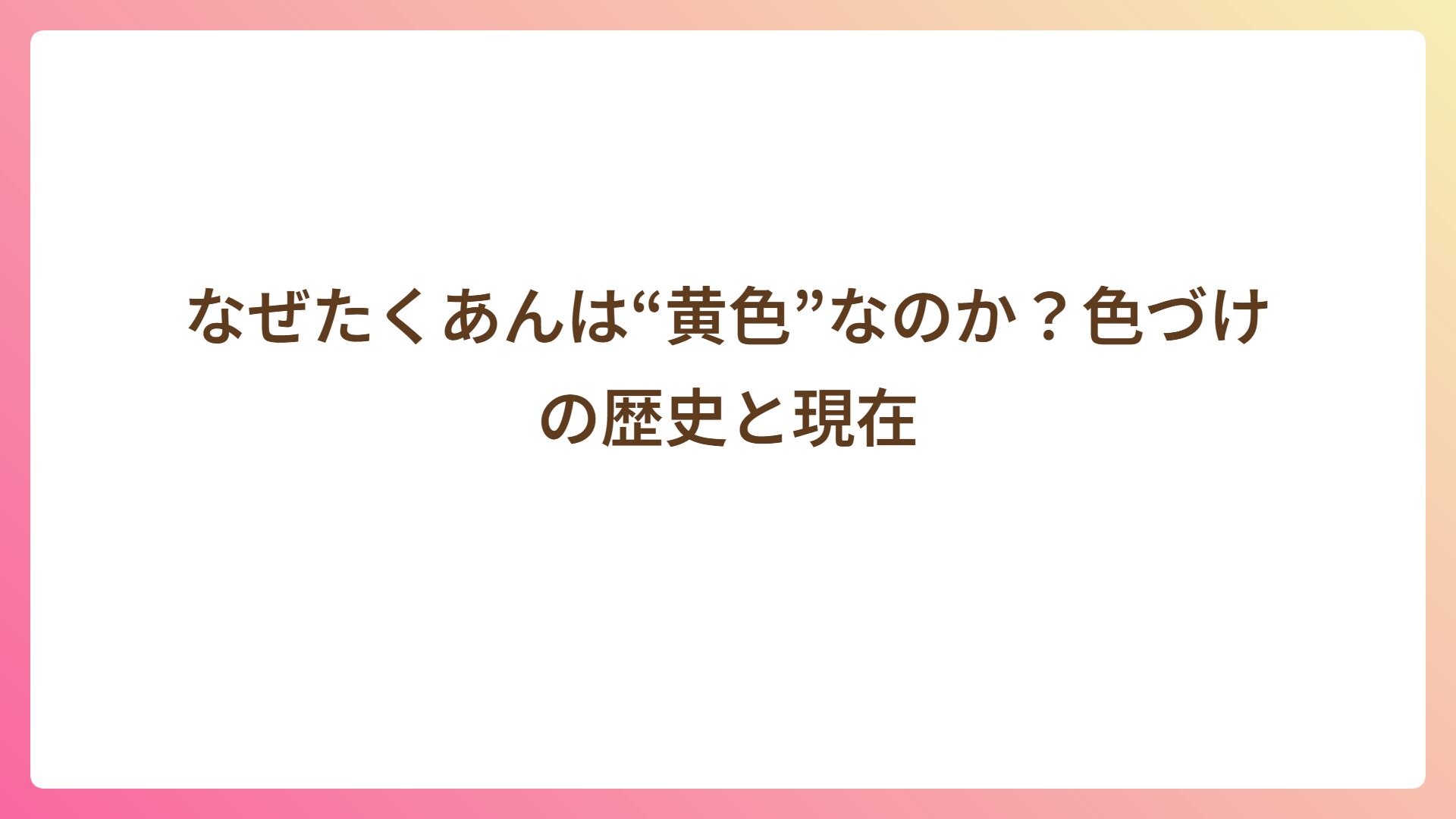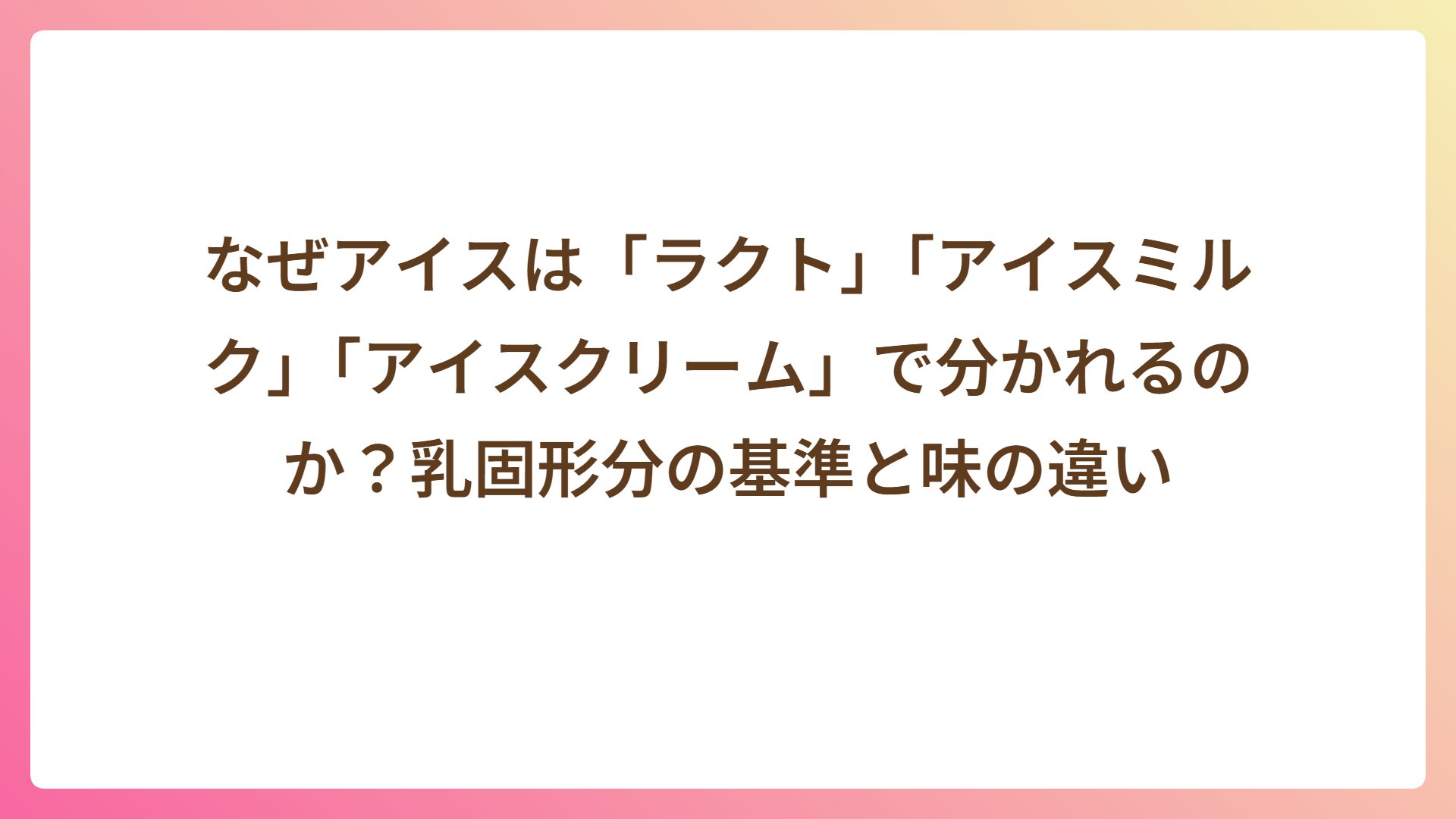「みどりの窓口」の名前の由来は?なぜ緑なのかをわかりやすく解説
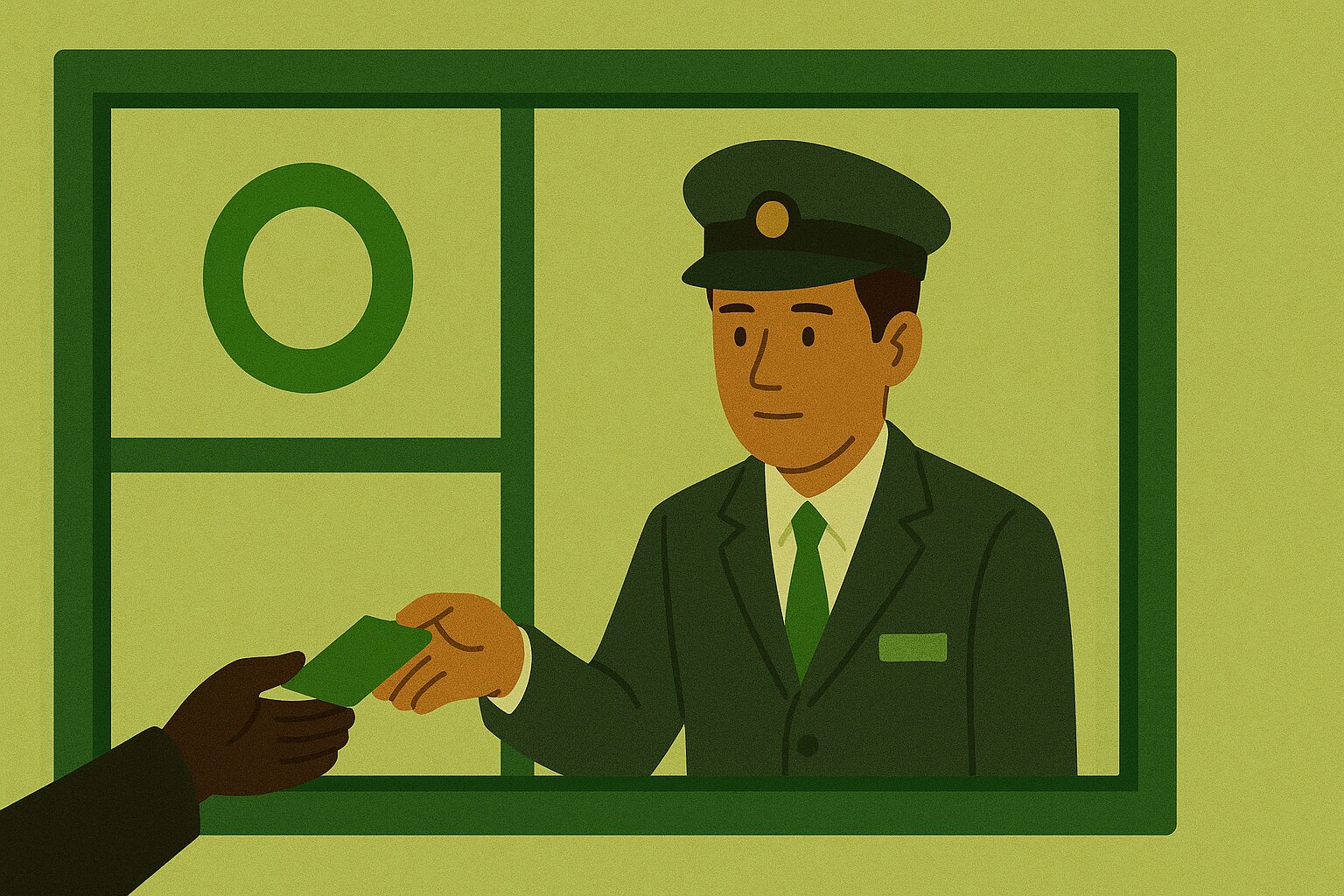
今ではSuicaやPASMOなどのICカードが普及し、きっぷを買う機会は減ってきました。それでも、新幹線や特急を使う旅行や帰省の際には、駅で乗車券や指定席を購入する人も多いでしょう。
そんなときに利用するのが、「みどりの窓口」。でも、よく考えると不思議です。なぜ「みどり」なのでしょう? 目立つ色なら黄色でもピンクでもよさそうですし、単純に「きっぷの窓口」としても問題なさそうです。
ではなぜあえて「みどり」が使われているのでしょうか。
「みどり」は発券されたきっぷの色だった
「みどりの窓口」とは、JRが設置している指定券などを扱う窓口のこと。この窓口には「マルス端末」と呼ばれるオンライン予約システムが導入されており、その場できっぷの発券や座席指定が可能です。
※マルス(MARS)=Multi Access seat Reservation System(旅客販売総合システム)
このマルス端末によって発券されたきっぷは、他の券と区別するため緑色の紙が使われていました。
一方で、自由席や定期券を扱う窓口ではマルス端末を使用しておらず、きっぷの色も青や赤など別の色でした。
こうした違いを明確にするため、マルス端末を備えた窓口が「みどりの窓口」と呼ばれるようになったのです。
マルス以前は手作業で大混乱
「みどりの窓口」が初めて設置されたのは、マルスが全国の駅に導入された1965年のことです。
それ以前、指定席の予約は非常に煩雑でした。すべての指定券は、中央の管理センターにある台帳で管理されており、各駅の窓口は電話で空席を問い合わせ、予約手続きを行っていました。
この作業は手作業で、回転式の台帳から対象の列車を探し、空席状況を確認してから記帳。電話が混雑すれば、発券まで半日以上待たされることもありました。また、記録ミスによる二重予約(ダブルブッキング)も頻発していたのです。
この非効率さを改善するために開発されたのが、オンライン予約システム「マルス」でした。当時はインターネットも普及しておらず、コンピュータ自体が珍しい時代。開発は困難を極めましたが、1960年には商用運用が開始され、発券の効率が飛躍的に向上しました。
「みどりの窓口」は色と技術の歴史の象徴
「みどりの窓口」の“みどり”は、もともとマルス端末できっぷを発券した際の用紙の色に由来しています。そしてその裏には、紙の台帳からオンライン予約への進化という、鉄道業界の大きな変革の歴史がありました。
今やオンラインでの予約が主流になりつつありますが、駅で「みどりの窓口」を見かけたときは、そんな技術革新の背景に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。