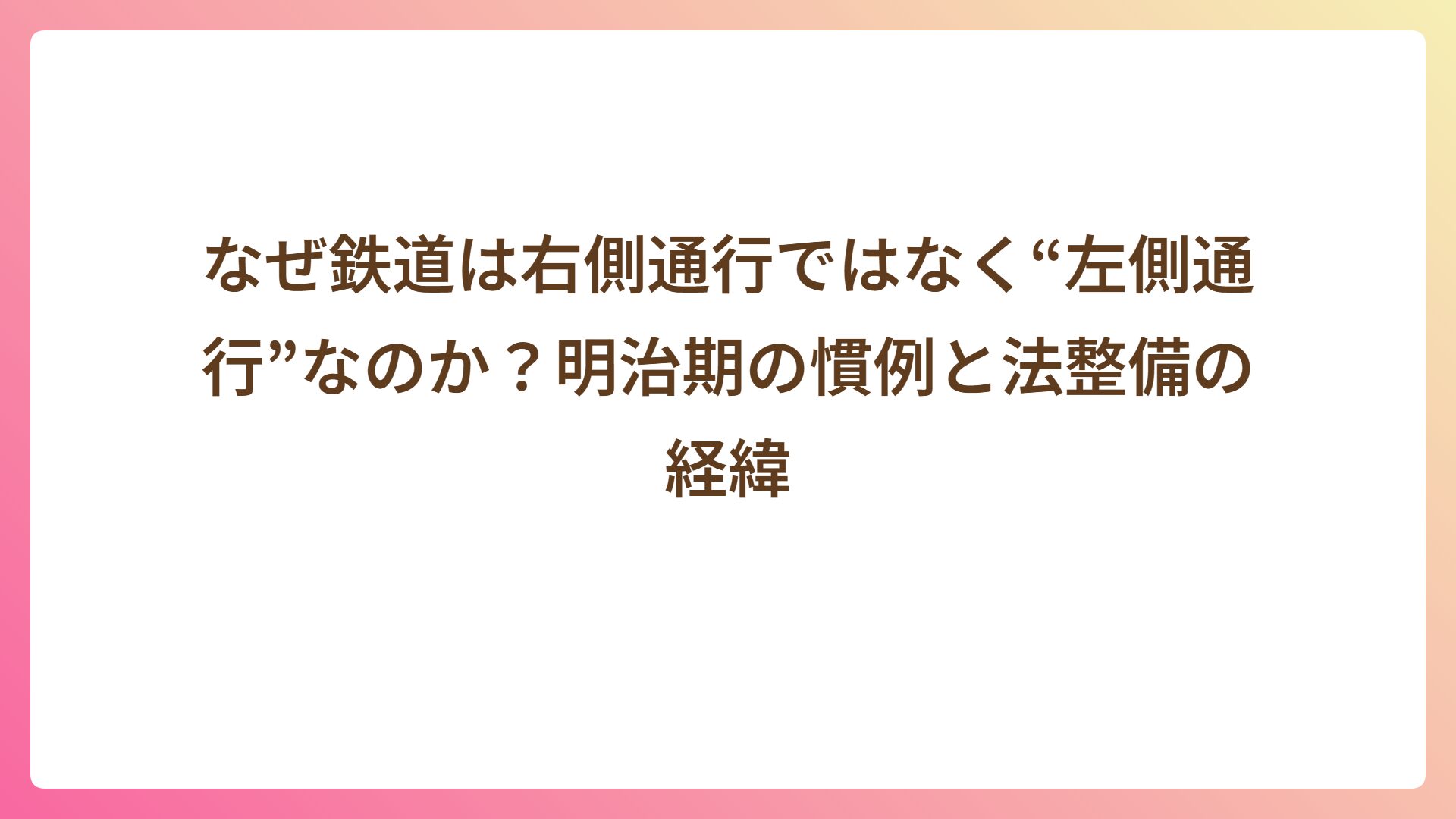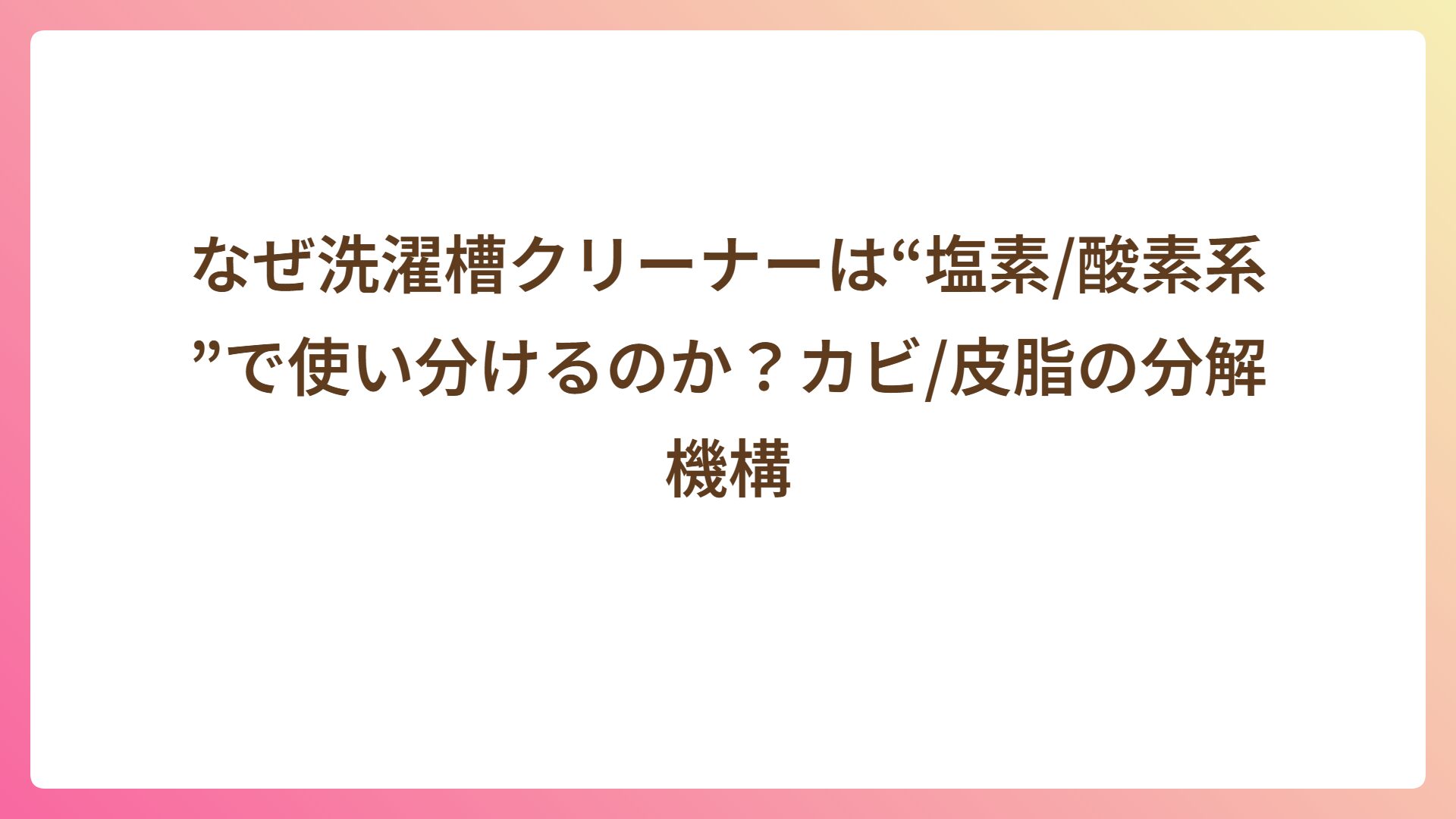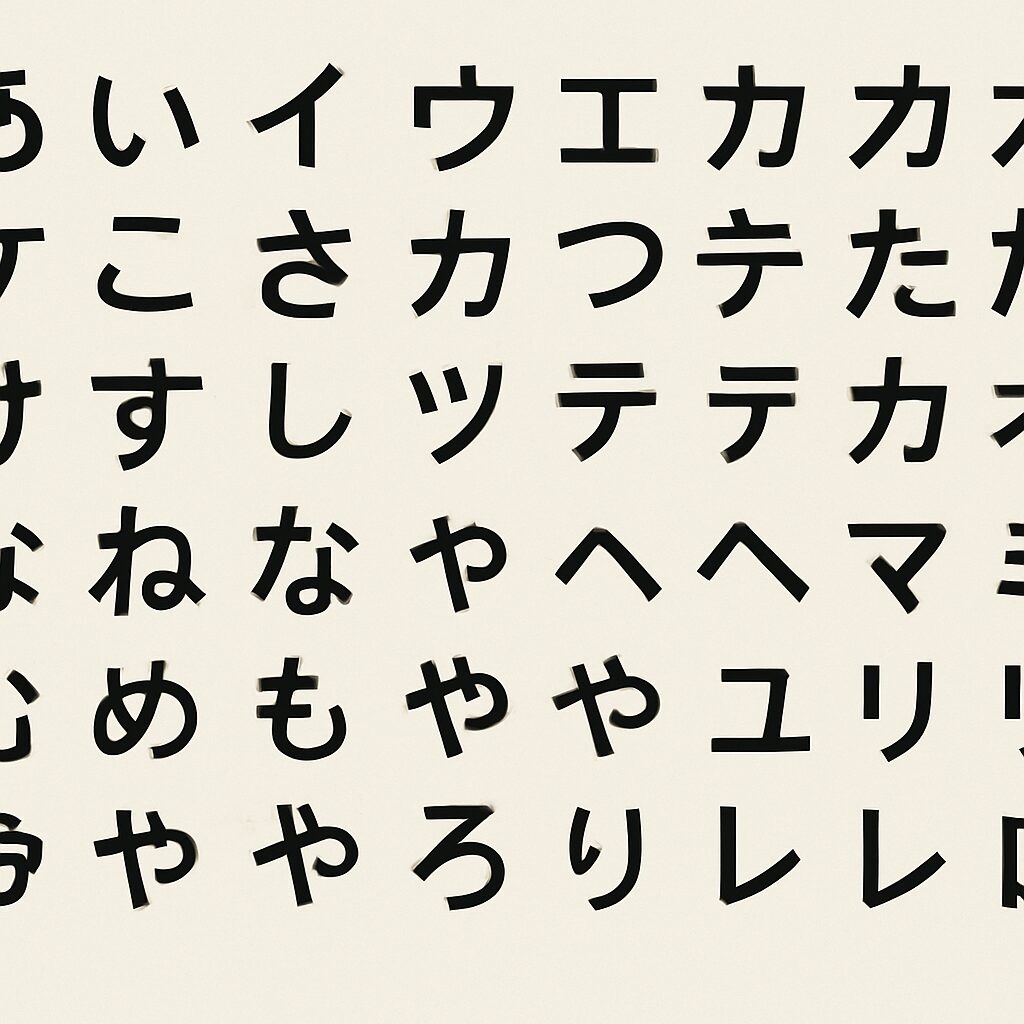なぜ「フィギュア」スケート?名前の由来は氷上に描く図形だった!

みなさんは「フィギュアスケート」という名称に、ふと疑問を持ったことはありませんか?
「フィギュア=人形?」とイメージする人も多いかもしれませんが、実は全く違う意味なのです。
「フィギュア」は図形を意味する
フィギュアスケートの「フィギュア」は、英語の figure=図形・形 に由来しています。
その理由は、もともとのフィギュアスケートが「氷の上に図形を描く競技」だったからです。
スケート靴の刃で氷に跡(トレース)を描き、その正確さや美しさを競う競技でした。
氷上に図形を描く競技”コンパルソリー”
この図形を描く技術を競う種目は「コンパルソリー(compulsory figures)」と呼ばれ、かつては世界選手権やオリンピックでも正式な競技種目でした。
- 正確な円を描く
- 刃の角度や重心移動を丁寧にコントロールする
- 複数の図形を連続して描く
こうした精密な滑りこそが「フィギュアスケート」の原点です。
その名残として、今日の自由演技(フリースケーティング)も「フィギュアスケート」と呼ばれ続けているのです。
バレエの動きが導入されたきっかけ
フィギュアスケートにダンス的な要素を取り入れた最初の人物が、アメリカ出身のバレエ教師ジャクソン・ヘインズだと言われています。
彼はバレエの指導でヨーロッパを訪れた際、氷上で図形を描くスケートに出会い、
「これに音楽と踊りを融合させたら素晴らしいのでは?」と考えました。
彼のアイデアは新たなスタイルとして広まり、現在のような演技重視のフィギュアスケートの基礎が築かれていきました。
「図形の競技」から「演技の競技」へ
オリンピックや世界選手権では、当初は「コンパルソリー」と「フリースケーティング」の両方で成績を競う形式がとられていました。
しかし、コンパルソリーはテレビ映えしづらく、「地味すぎる」という理由もあり、1990年代に競技種目として廃止されました。
現在では、音楽に合わせた演技が中心となった「フリースケーティング」が主流ですが、実はその滑りの基礎技術の多くは、かつての図形描写の技術に根ざしているのです。
氷上に描かれる「目に見えない図形」に注目してみよう
フィギュアスケートの“フィギュア”が「図形」であるという事実は、今も競技の本質に根強く残っています。
演技中の選手の動きを俯瞰アングルで見ると、美しいカーブや螺旋が見えてくることがあります。
それらは、かつてのコンパルソリーの技術を受け継ぐ“見えない図形”でもあるのです。
次にテレビでフィギュアスケートを見るときには、ぜひその軌道にも注目してみてください。競技の奥深さが、より一層伝わってくるかもしれません。