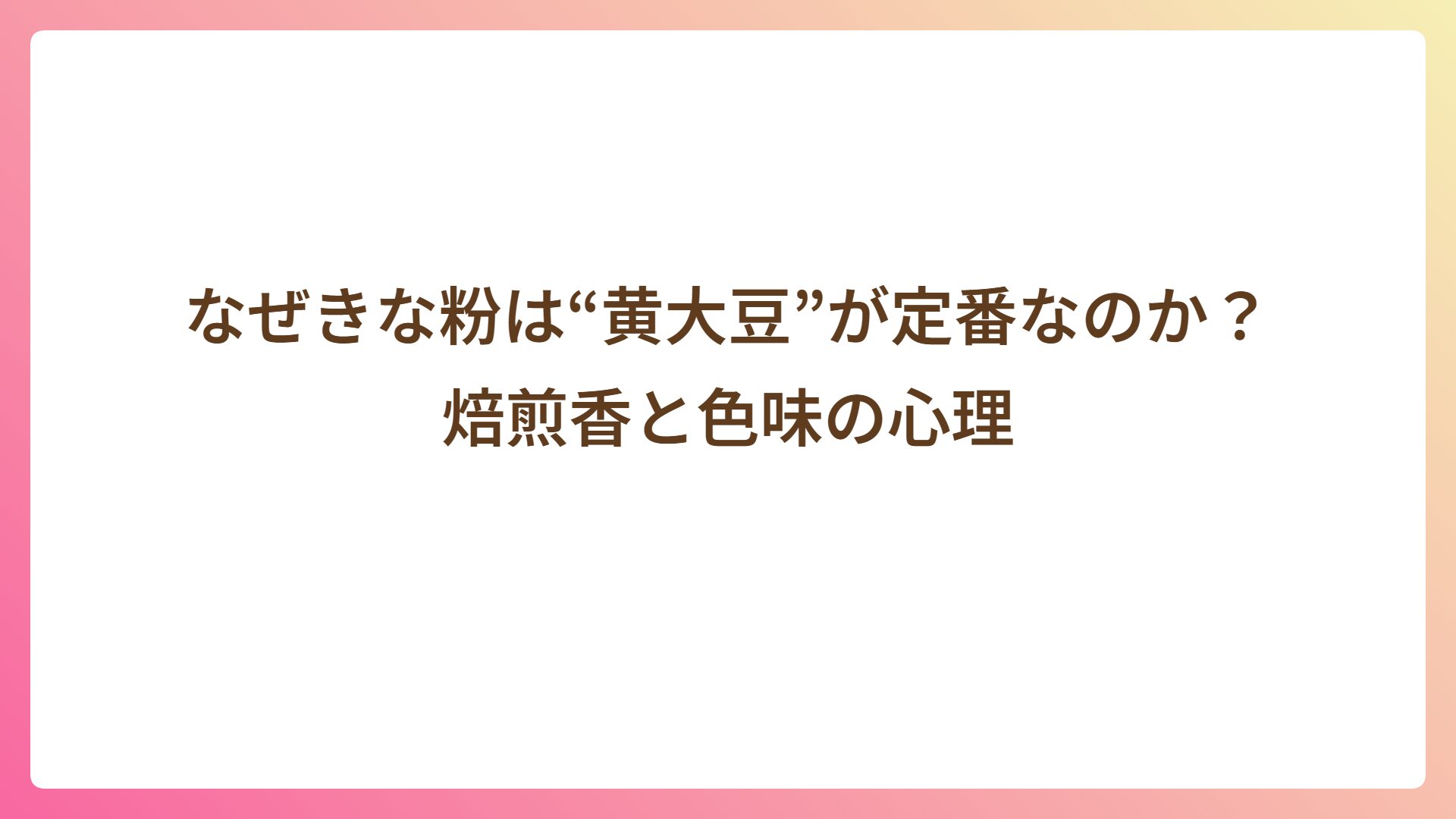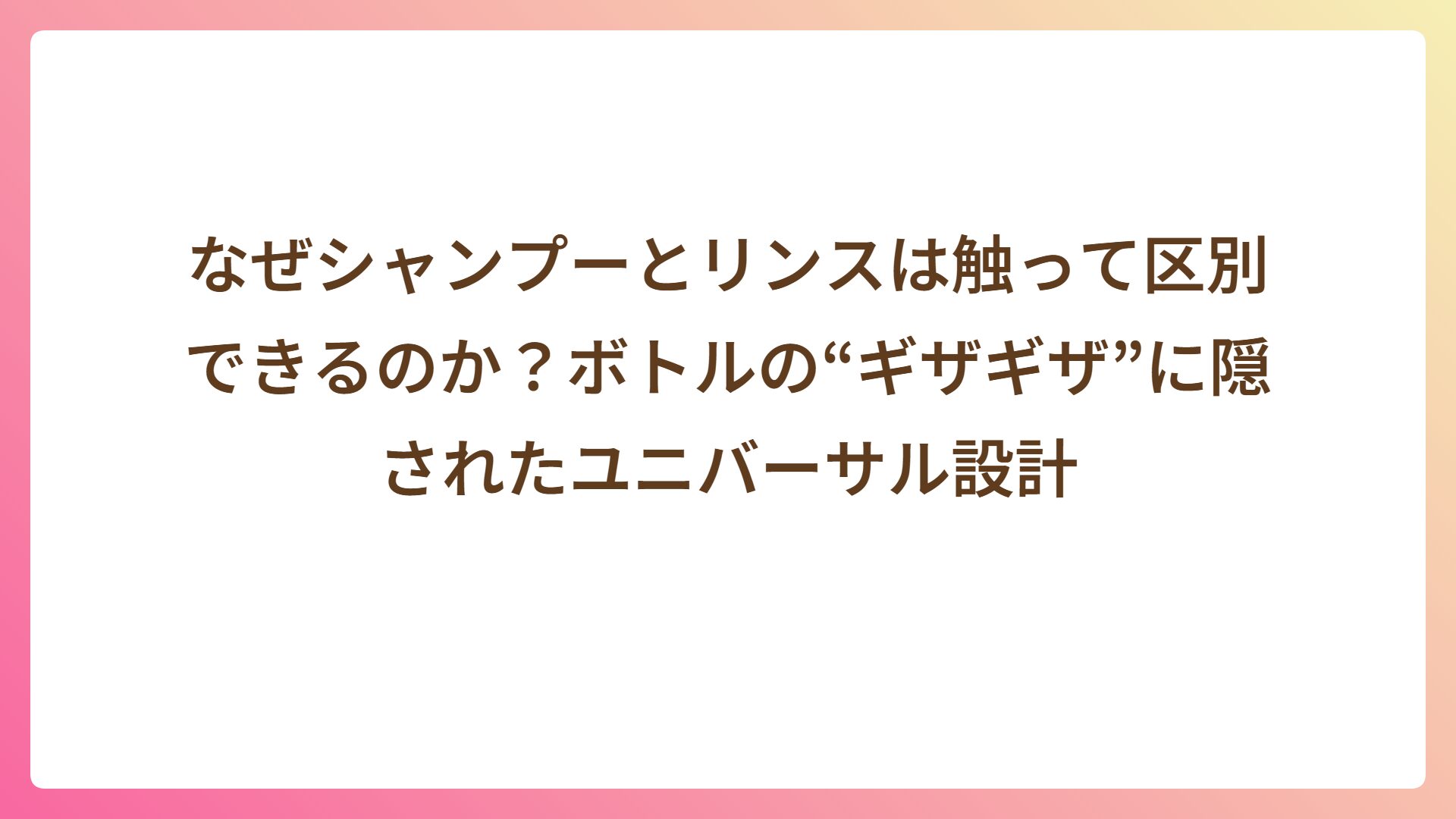楽譜はなぜ「五線」なの?歴史をひもとくと意外な理由があった

楽譜といえば「五線譜」を思い浮かべる方が多いでしょう。でもなぜ線は5本なのか、考えたことはありますか? 実は五線が選ばれた理由にははっきりとした答えがなく、時代や楽器によって線の本数は増えたり減ったりしていたのです。今回は、五線譜が世界標準になった歴史をひもといてみましょう。
世界最初の楽譜は?
現存する最古の楽譜のひとつは古代ギリシアのもので、文字や記号を用いたタブラチュア譜(奏法を記す記譜法)でした。
また、9〜10世紀ごろにはネウマ譜と呼ばれる記譜法が登場します。これは点や曲線で旋律の動きを示したもので、『グレゴリオ聖歌』などに使われました。ただし正確な音程やリズムまでは表せず、曖昧さの残る書法でした。
線は増えたり減ったりしていた
中世からルネサンスにかけて記譜法は発展し、白符定量記譜法やタブラチュア譜が広まります。この頃には五線だけでなく、六線や七線の譜も使われていました。
また、楽器の性質に合わせて線を調整することもあり、右手と左手で線の本数を変える楽譜も存在しました。つまり、「五線」は絶対ではなく、必要に応じて増減していた のです。
五線が標準化した理由
15〜16世紀ごろ、鍵盤楽器用の譜面に五線が多く使われるようになりました。やがてピアノやオルガンといった鍵盤楽器がヨーロッパ音楽の中心となり、その記譜法が標準化していきます。
なぜ線が「ちょうど5本」に落ち着いたのかは明確ではありません。ただ、音域や可読性のバランスから便利だったため、広く定着したと考えられています。
五線譜が国際的に標準になった背景には、西洋音楽が世界的に広まったこと が大きく影響しています。
五線以外の楽譜もある
現代でも五線譜だけが使われているわけではありません。
- 日本の箏の伝統的な譜面は漢字やカタカナで弦を表す。
- 打楽器用には三線や一線などシンプルな譜面が用いられる。
- ギターの「タブ譜」も五線ではなく、弦の番号を記す記法。
つまり、五線譜は数ある楽譜の一形態にすぎない のです。
まとめ
- 五線譜が「なぜ5本か」という明確な答えはない
- かつては6本や7本の線、文字譜など多様な記譜法が存在した
- 鍵盤楽器の普及と西洋音楽の影響で五線が国際標準に
- 今も楽器や文化によって五線以外の楽譜も使われている
五線譜は音楽を伝えるための最適解のひとつにすぎません。歴史を知ると、楽譜の多様さや音楽文化の奥深さをより感じられますね。