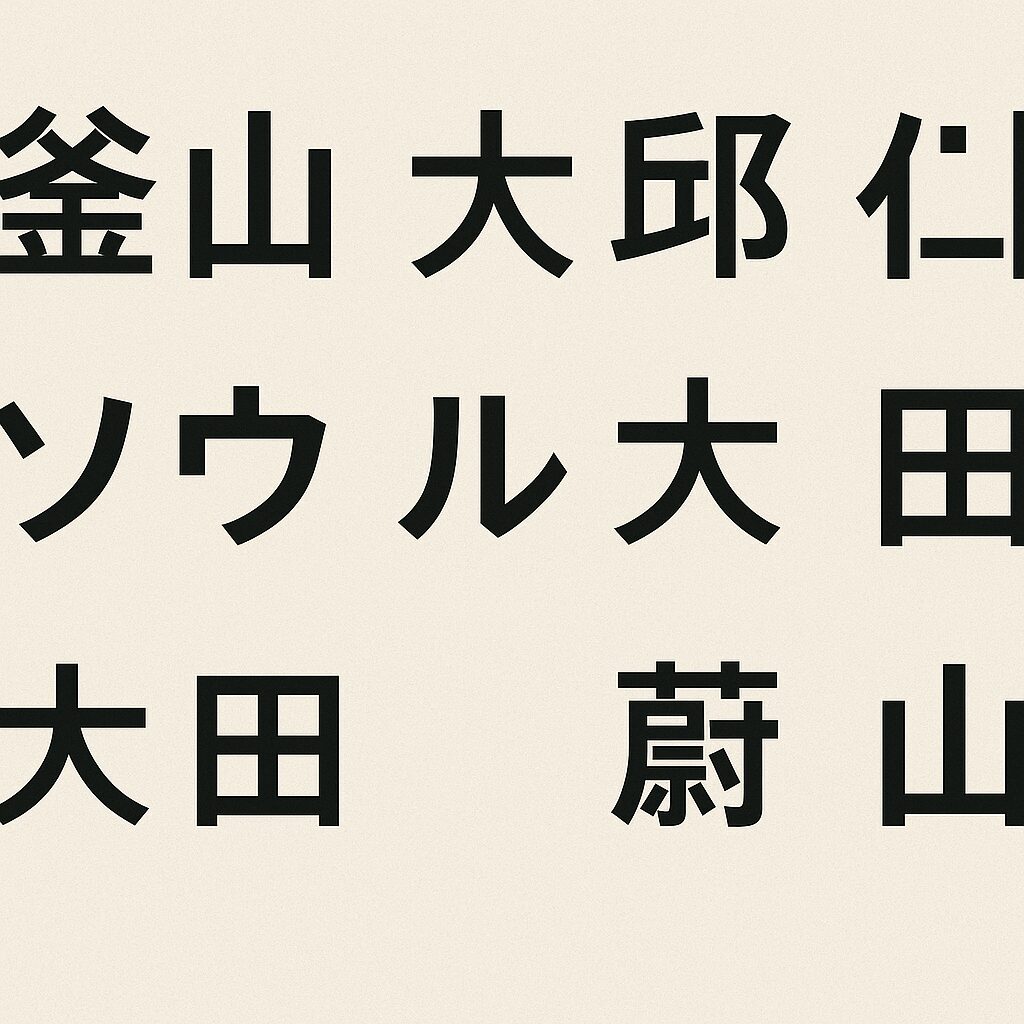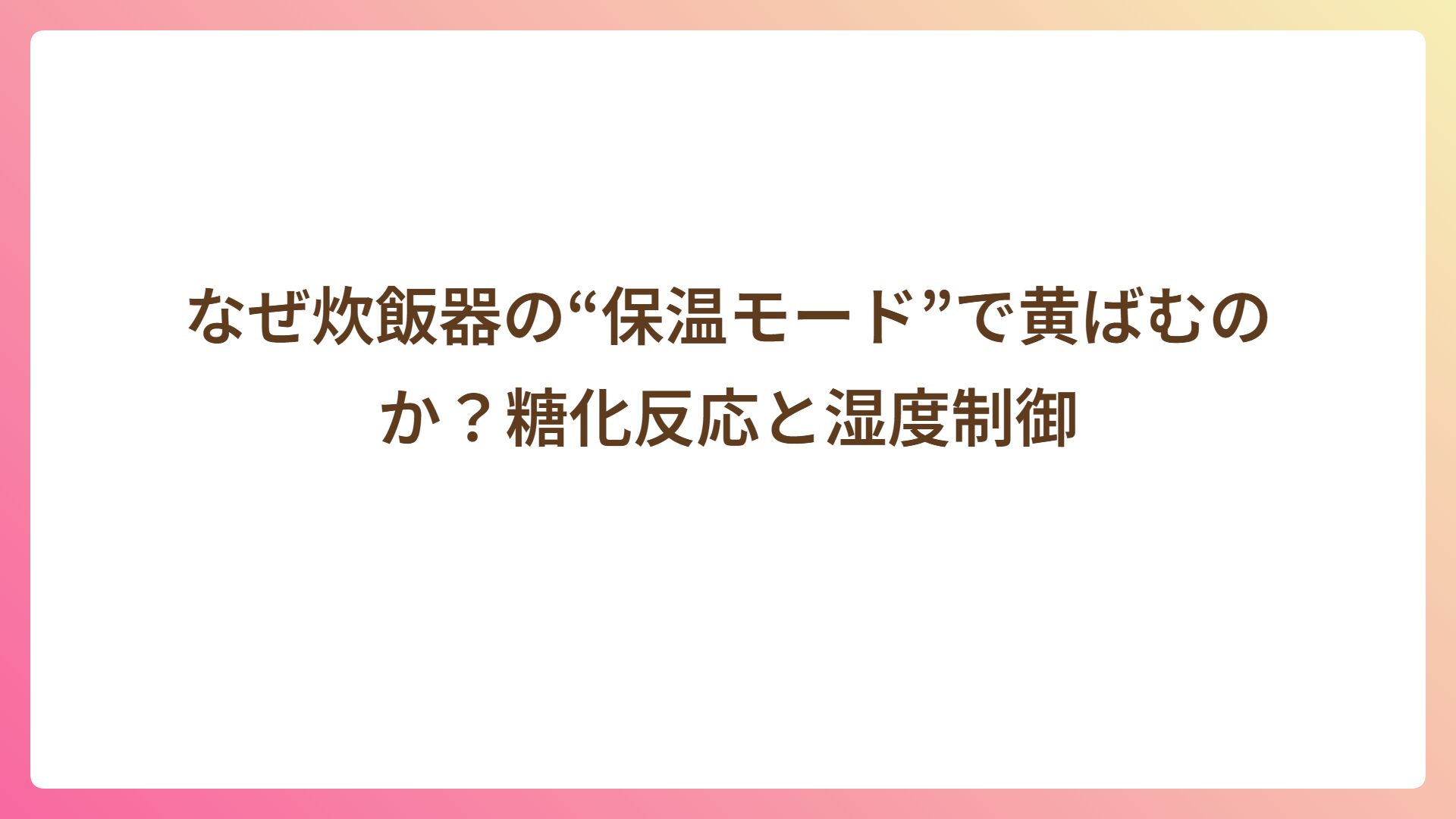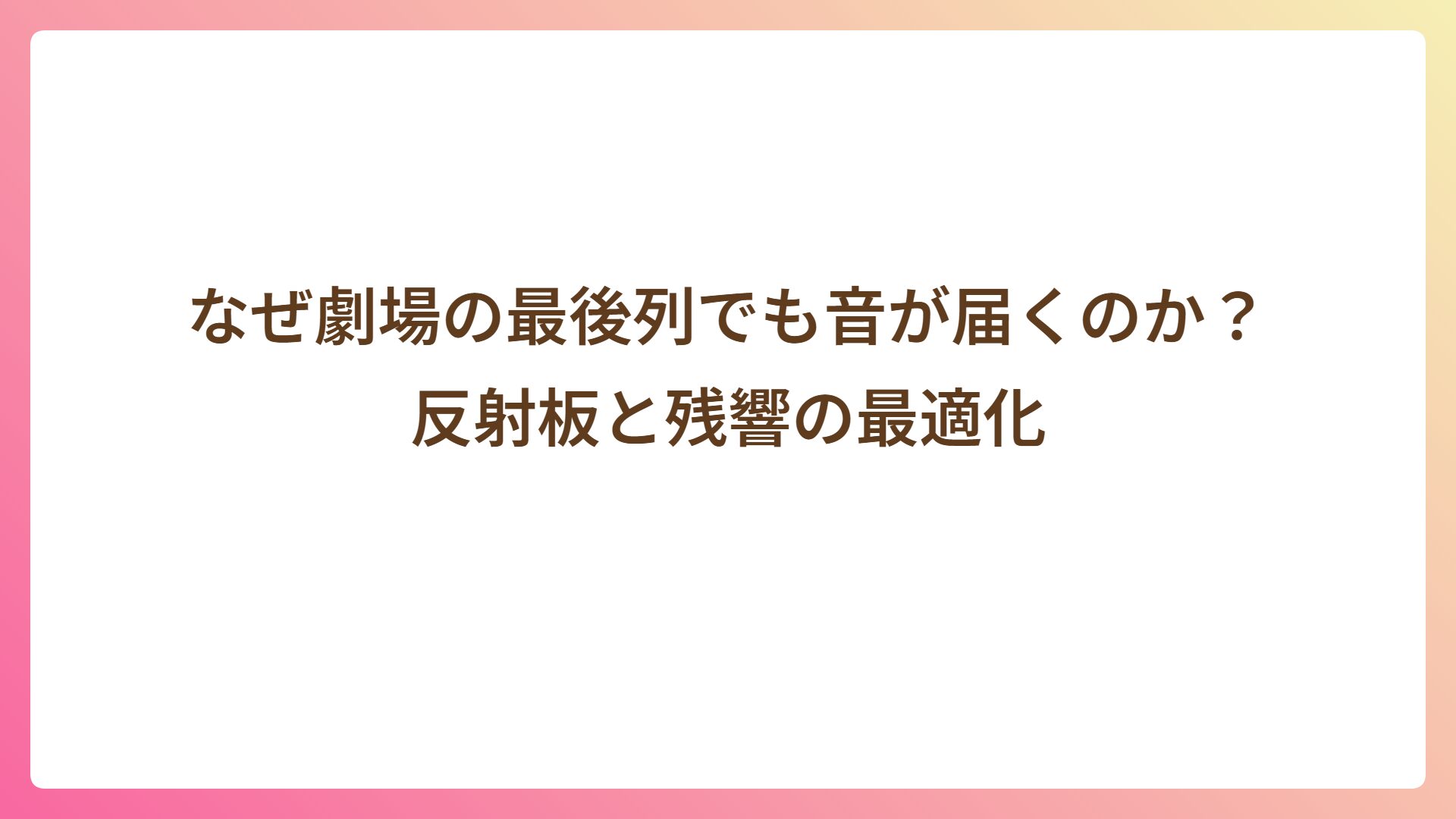ブルーチーズのカビはなぜ食べても大丈夫?安全な理由を解説
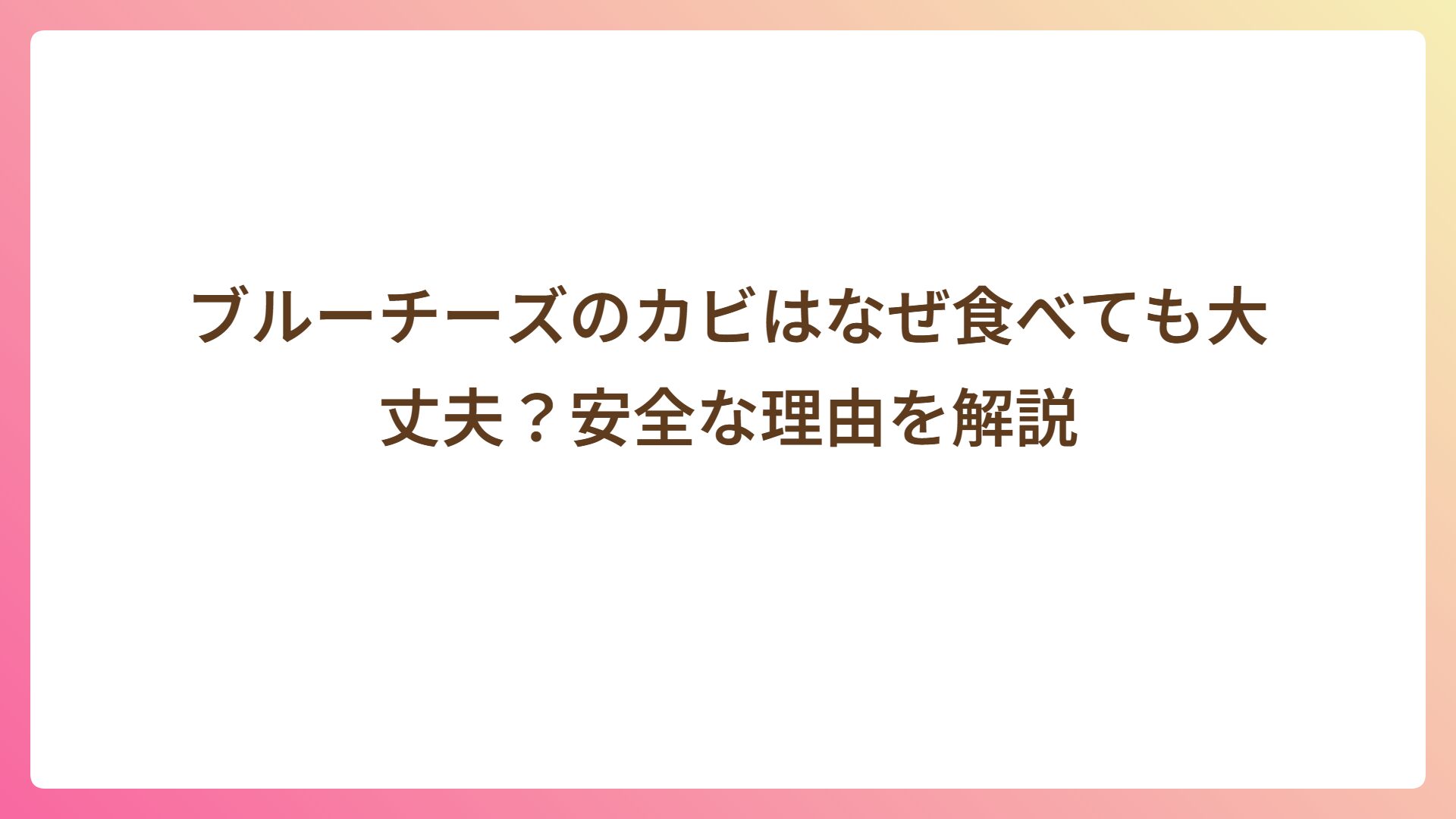
パンやご飯にカビが生えたらすぐに捨てるのに、ブルーチーズやカマンベールのカビはなぜか安心して食べられますよね。この記事では、ブルーチーズを例に「食べられるカビ」と「食べられないカビ」の違いをわかりやすく解説します。
ブルーチーズは意図的にカビを加えて作る
ブルーチーズの青い部分は偶然生えたものではなく、製造工程で人為的に加えられたカビです。
使われるのは Penicillium(ペニシリウム)属 のカビで、ロックフォールなら Penicillium roqueforti、ゴルゴンゾーラなら別の種類……というように、チーズの種類ごとに異なる青カビが用いられます。
また、製造環境も厳密に管理されています。温度10℃前後、湿度80%以上という条件下で、数か月かけて熟成されることで安全なチーズができあがるのです。
なぜチーズのカビは食べられるのか
同じ青カビでも、パンやご飯に自然に生えたものとは安全性が大きく違います。
- 管理された環境で育てられている → 雑菌や有害カビの混入を防ぐ
- チーズのタンパク質が毒素を発生しにくくする → 偶発的な有害物質の生成が起こりにくい
このため、ブルーチーズのカビは人体に害を与えることなく、安全に食べることができます。
青カビとペニシリンの関係
実は、ブルーチーズに使われるカビは医学の歴史とも深い関わりがあります。
1928年、イギリスのアレクサンダー・フレミングが青カビから ペニシリン を発見しました。これは世界初の抗生物質として病気治療に大きな革命をもたらし、その功績により1945年にノーベル生理学・医学賞が授与されています。
つまり、ブルーチーズを彩る青カビは「食品」としてだけでなく「医学の発展」にも貢献してきた存在なのです。
世界のブルーチーズ文化
フランスのロックフォールは「世界三大ブルーチーズ」のひとつとして有名です。町の専門店には何種類ものブルーチーズが並び、食文化として根付いています。
ブルーチーズの独特な風味を楽しめるのは、安全に管理されたカビのおかげ。今度食べるときには、その科学的な背景や歴史にも思いを馳せてみると、より味わい深いかもしれません。