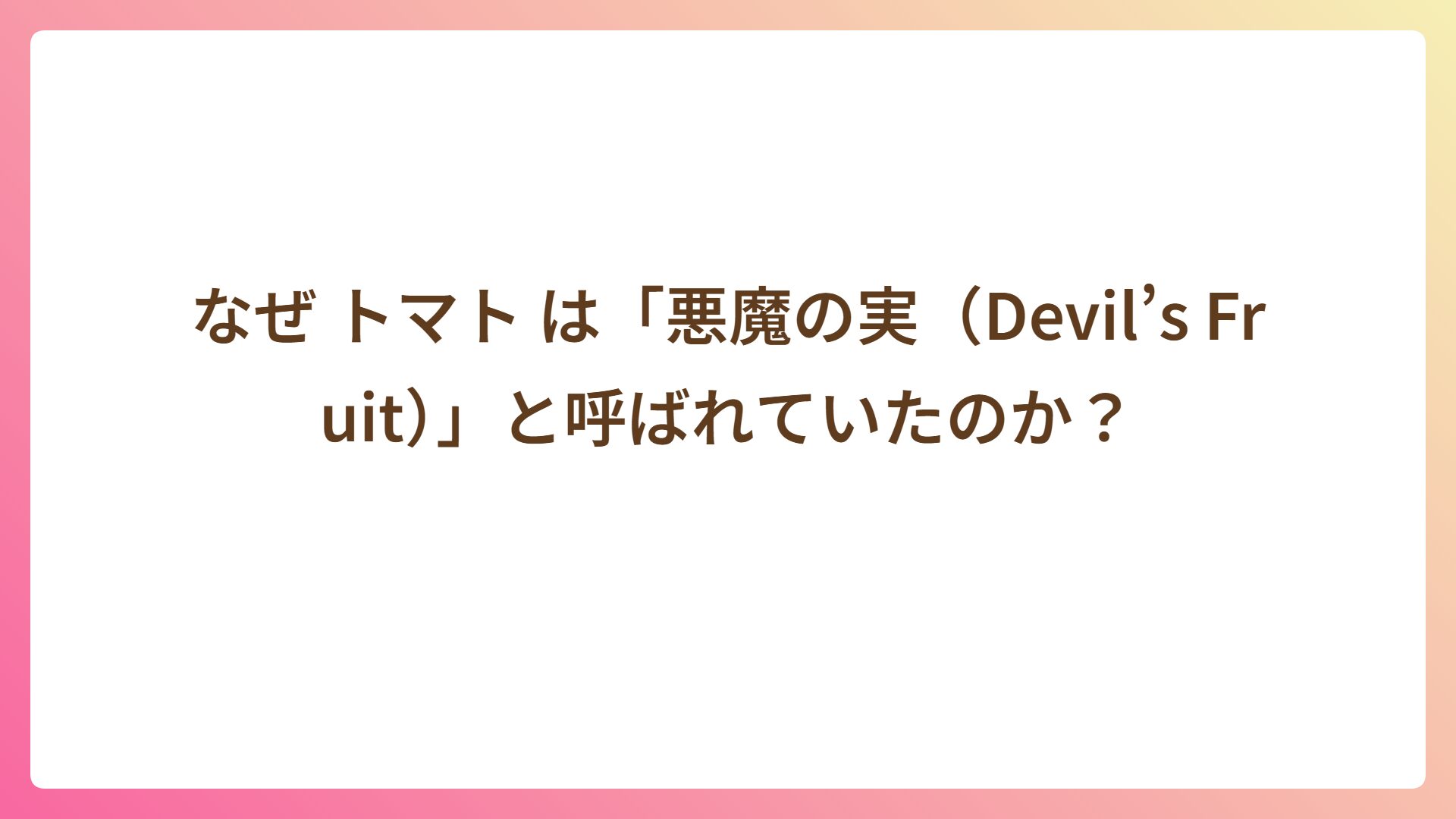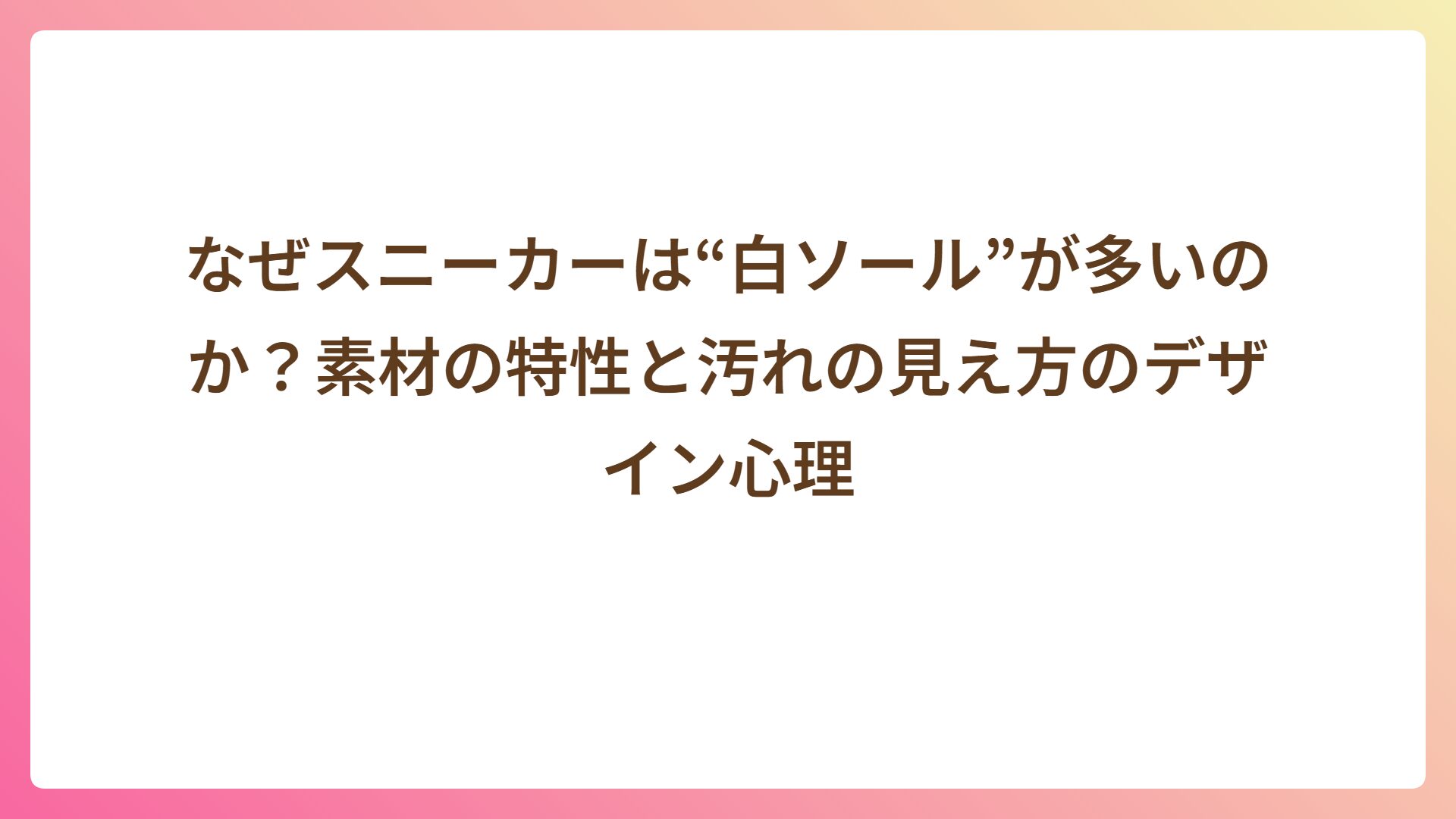なぜ「時差ボケ」が起こるのか?体内時計と光がもたらすズレのメカニズム

海外旅行の初日、「眠れない」「日中なのに眠い」と感じた経験はありませんか?
それは体内時計が現地時間にまだ順応していないために起こる現象――つまり「時差ボケ」です。
この記事では、体内時計と光の関係、そしてなぜ体がすぐ現地時間に合わせられないのかを、科学的にわかりやすく解説します。
体には“24時間の時計”がある
私たちの体には、脳の中に体内時計(生体リズム)が備わっています。
その中枢は、脳の視床下部にある視交叉上核(しこうさじょうかく)という部位。
ここが「体の司令塔」として、睡眠・食事・体温・ホルモン分泌などを24時間周期でコントロールしています。
ただし、この体内時計の周期は正確な24時間ではなく、平均で約24.2時間。
そのため、放っておくと少しずつズレていくため、毎日「外の光」でリセットされる必要があるのです。
光が体内時計をリセットする
体内時計を調整する最大の要素が「光」です。
朝、太陽の光を浴びることで、網膜の奥にあるメラノプシン(光受容体)が刺激され、視交叉上核に信号を送ります。
これにより、
- 「今は朝だ」と脳が認識
- メラトニン(眠気を誘うホルモン)の分泌がストップ
- 体温や代謝が上昇して活動モードに切り替え
といった反応が起こります。
逆に夜になると光刺激が減り、再びメラトニンが分泌され、眠くなる――これが自然な1日のリズムです。
時差ボケの正体は「体内時計と現地時間のズレ」
海外に行くと、現地の昼夜のリズムが日本とズレます。
ところが、体内時計はすぐには追いつかないため、脳と環境の時間にギャップが生じます。
このズレこそが時差ボケ(jet lag)の正体です。
| 移動方向 | 体への影響 | 理由 |
|---|---|---|
| 東へ移動(日本→アメリカ) | 眠れない・早朝に目が覚める | 1日の周期が短くなり、体内時計を“早める”必要があるため |
| 西へ移動(日本→ヨーロッパ) | 日中眠くなる・集中できない | 1日の周期が長くなり、体内時計を“遅らせる”必要があるため |
体内時計は1日に約1時間ずつしか調整できないため、
7時間の時差なら1週間程度かけてようやく順応します。
メラトニンが眠気のカギを握る
時差ボケの主要症状である「眠気」「だるさ」「集中力の低下」には、ホルモンのメラトニンが関係しています。
メラトニンは「夜になると増える」「朝に光を浴びると減る」ホルモン。
旅行先で昼間に眠気が残るのは、まだメラトニンの分泌リズムが日本時間のままになっているからです。
つまり、体は「昼なのに夜だと勘違いしている」状態なのです。
時差ボケを軽くするための3つのコツ
体内時計を早く現地に合わせるには、光と行動のタイミングがポイントです。
- 朝日をしっかり浴びる
現地の朝の光を浴びることで、体内時計が“朝モード”にリセットされやすくなります。 - 寝る時間・起きる時間を少しずつずらす
出発の数日前から、現地時間に近い生活リズムにしておくと適応が早まります。 - メラトニン分泌を妨げない
寝る前のスマホや強い光を避けることで、自然な眠気が出やすくなります。
これらを意識することで、時差ボケの症状を最小限に抑えることができます。
まとめ:時差ボケは「体内時計のリズム調整中」
時差ボケとは、
- 体内時計が環境の昼夜とズレる
- 光の刺激が新しいリズムを作るまで時間がかかる
- メラトニン分泌が混乱する
という一連のプロセスによって起こる現象です。
つまり、時差ボケは体が新しい時間に順応しようとする自然な反応なのです。
体をリセットするには、無理に我慢せず「光を味方につけること」が最も効果的です。