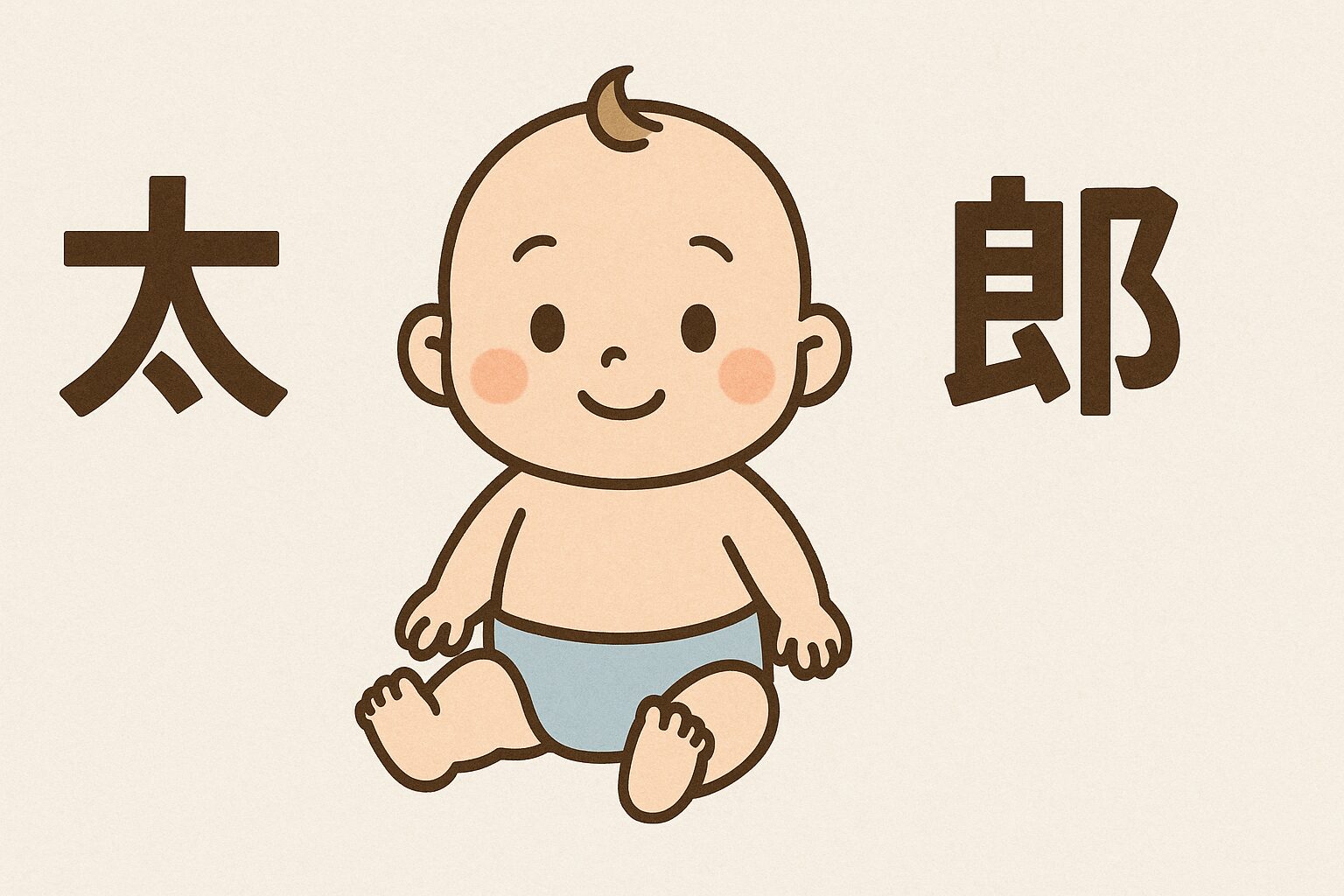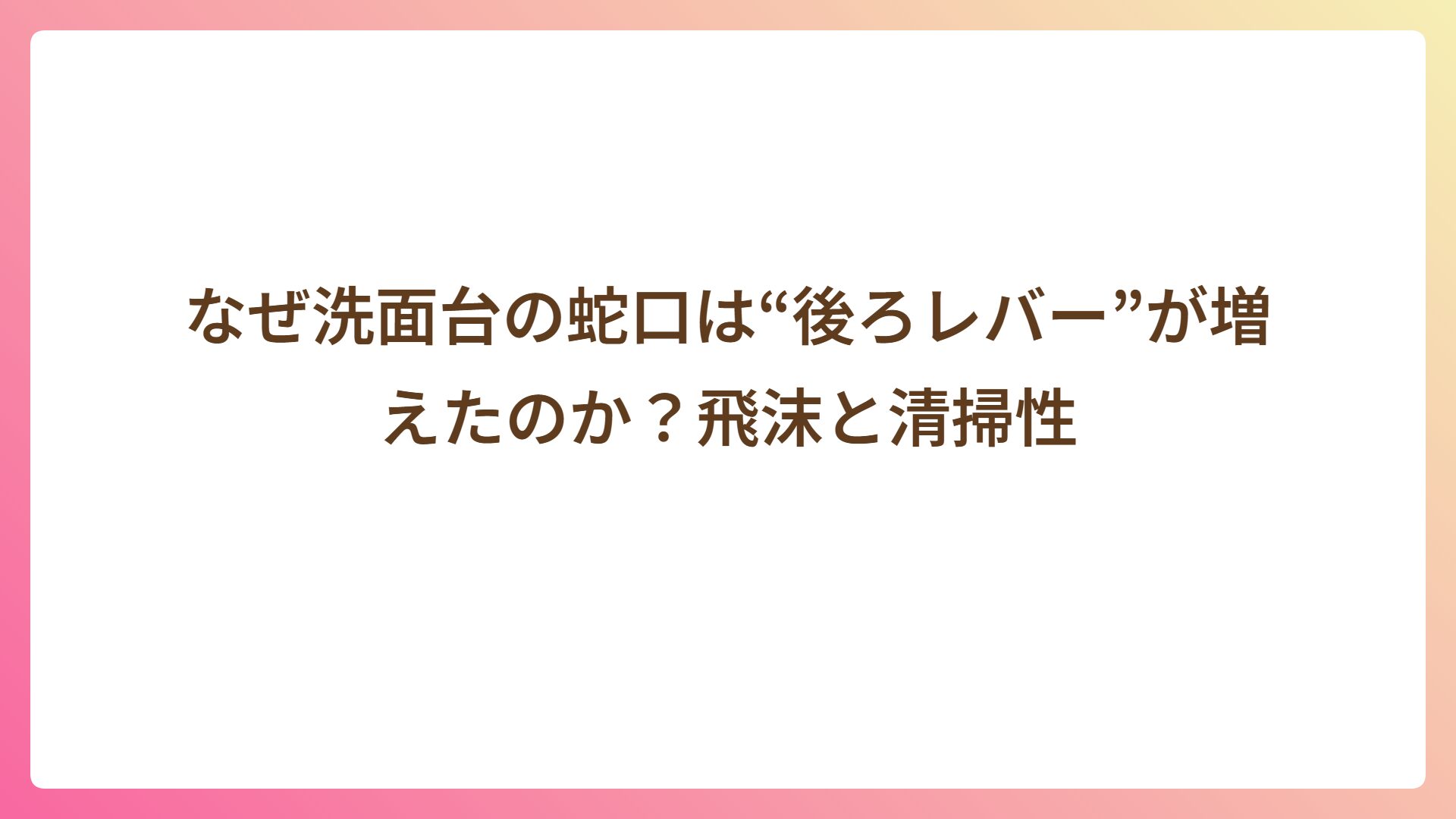なぜシャンプーとリンスは触って区別できるのか?ボトルの“ギザギザ”に隠されたユニバーサル設計
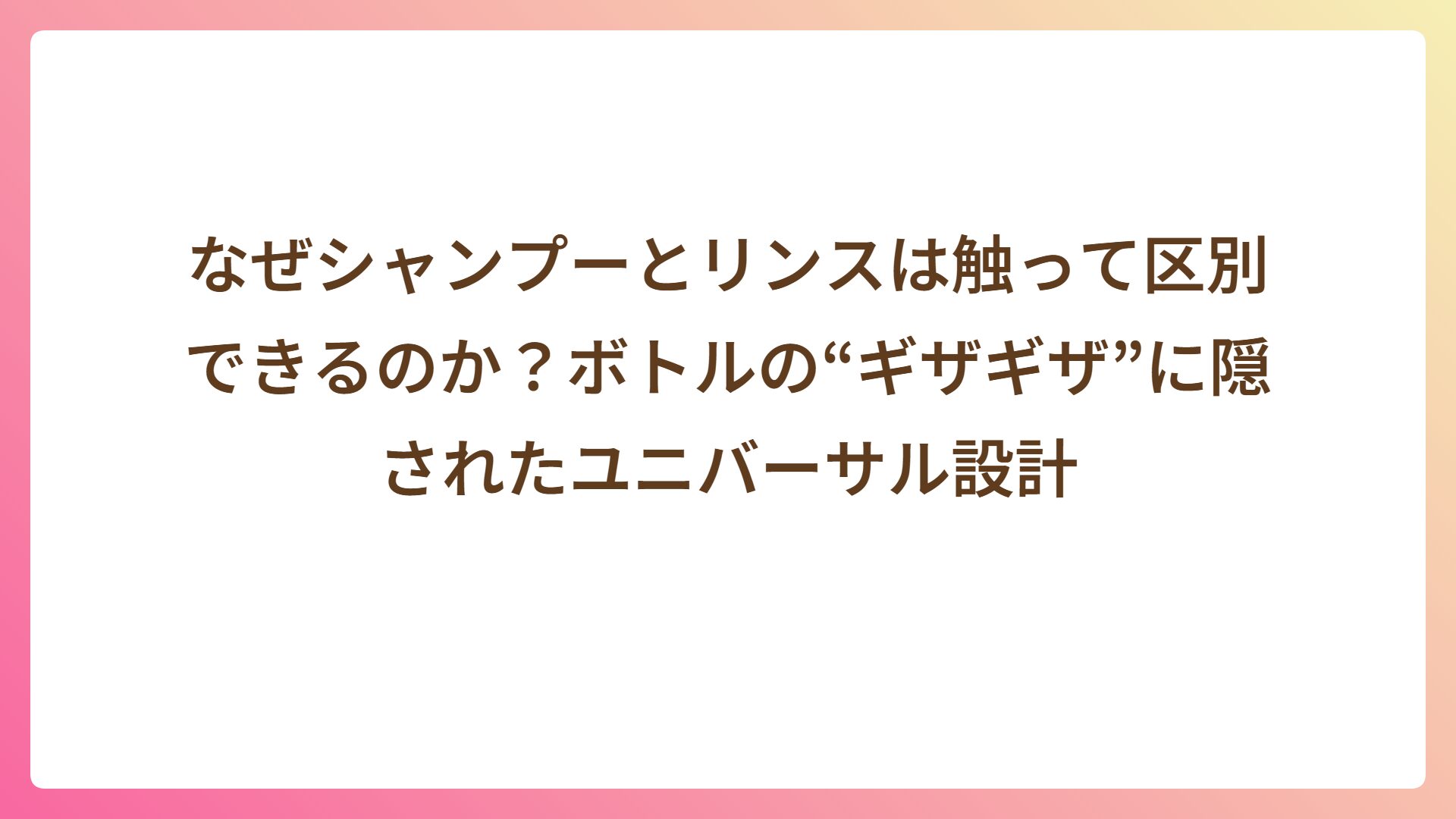
お風呂でシャンプーとリンスを間違えた経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか。
実はその“うっかりミス”を防ぐために、多くのボトルには触ってわかる小さなギザギザが付けられています。
これは単なるデザインではなく、目の不自由な人も安心して使えるように設計されたユニバーサルデザイン。
この記事では、シャンプーとリンスのボトルを触って区別できる仕組みと、その誕生の背景を解説します。
理由①:シャンプーボトルには“ギザギザの目印”がある
日本で販売されている多くのシャンプーボトルには、
上部や側面に縦のギザギザ(突起ライン)が付いています。
この突起は、
- 視覚に頼らずに触覚だけで識別できる
- 目をつぶったままでも手探りで判断できる
ようにするための工夫です。
一方で、リンス(コンディショナー)やボディソープには基本的にギザギザはありません。
つまり、「ギザギザ=シャンプー」という共通ルールで統一されているのです。
理由②:日本では“JIS規格”で定められている
このギザギザは、実はメーカーの自主判断ではなく、
JIS(日本工業規格)によって正式に定められたルールです。
具体的には、
JIS S 0021「高齢者・障害者配慮設計指針-消費生活製品編」
において、次のように定められています:
- シャンプーには「触って分かる突起」を付けること
- 突起の位置はボトル上部またはポンプ上面とすること
- リンスやボディソープは突起を付けないこと
この規格は2000年代に制定され、以後、国内メーカーのほぼすべてが準拠しています。
つまり「触って区別できるシャンプー」は、法律に近いレベルで標準化された安心設計なのです。
理由③:視覚障がい者だけでなく“誰でも”使いやすい
ギザギザの突起は、視覚障がい者のためだけの配慮ではありません。
目を閉じたまま使う入浴中という環境そのものが、誰にとっても「視覚が制限される状況」です。
そのため、
- シャンプーとリンスを間違えずに済む
- 子どもや高齢者でも直感的に使える
- 泡でラベルが見えなくても安心
といった、すべての人にとって便利なユニバーサルデザインになっています。
この考え方は「バリアフリー」より広く、“誰もが使いやすい社会”を目指す設計思想の代表例です。
理由④:海外では“色や形状”で区別することが多い
日本では触覚による識別が重視されていますが、
海外では「色やパッケージ形状」で区別することが一般的です。
たとえば:
- シャンプー=透明・明るい色
- コンディショナー=乳白色・不透明ボトル
- ボトルの形を微妙に変える
しかしこれらは視覚に頼る設計のため、
お風呂の蒸気や照明環境では見分けにくいという欠点があります。
その点、日本の「触覚識別方式」は、視覚情報がなくても確実に判別できるという点で、
世界的にも高く評価されているのです。
理由⑤:製造ラインでも識別しやすい実用的メリット
この突起は、利用者の利便性だけでなく、メーカー側にも利点があります。
同じ形状のボトルを大量生産する中で、
ラベル貼付前でも内容物を区別できるため、製造ミスを防ぐことができます。
つまり、ギザギザはユーザーのためだけでなく、
生産・流通現場での品質管理にも役立つ構造なのです。
理由⑥:リフィル文化の普及で“統一デザイン”が重要に
詰め替え用(リフィル)が一般化した今、
消費者は自分で中身を入れ替える機会が増えています。
そのため、ボトル自体に識別構造があることが極めて重要です。
ラベルを剥がしても、ギザギザがあれば間違えることはありません。
この物理的な違いが、「詰め替え間違い」を未然に防いでいるのです。
まとめ:ギザギザは“小さな突起に宿る大きな配慮”
シャンプーとリンスを触って区別できるのは、
- シャンプーのみに“突起付きボトル”を採用するJIS規格
- 視覚が制限される状況でも安心して使える設計
- リフィル・製造・安全面すべてに配慮された構造
という、人に寄り添うユニバーサルデザインの成果です。
つまり、あの小さなギザギザは、
「見えなくても安心して暮らせる社会を作る」日本のデザイン哲学そのもの。
私たちが無意識に触れているその突起には、誰もが使いやすい世界を支える静かな技術が詰まっているのです。