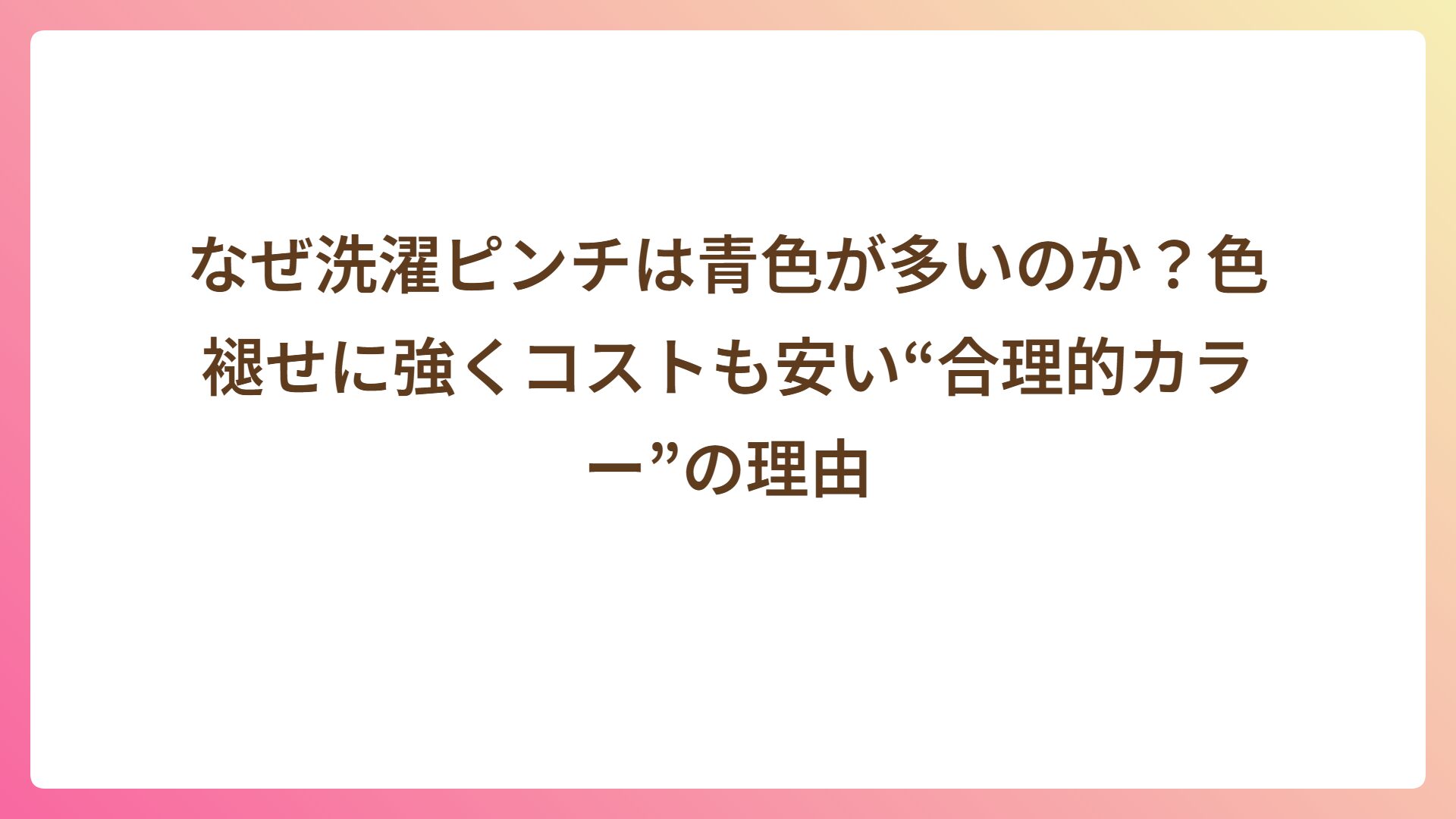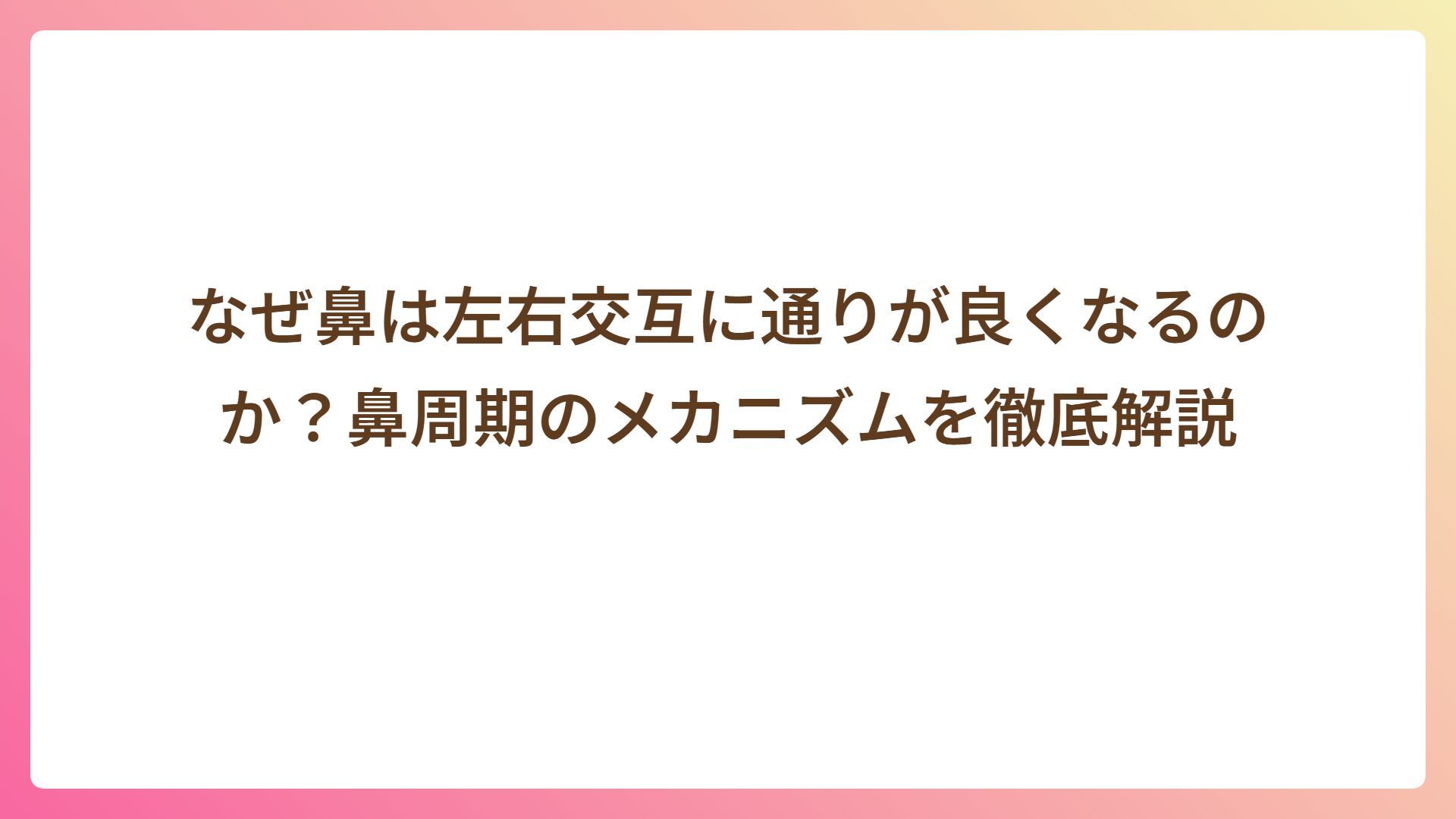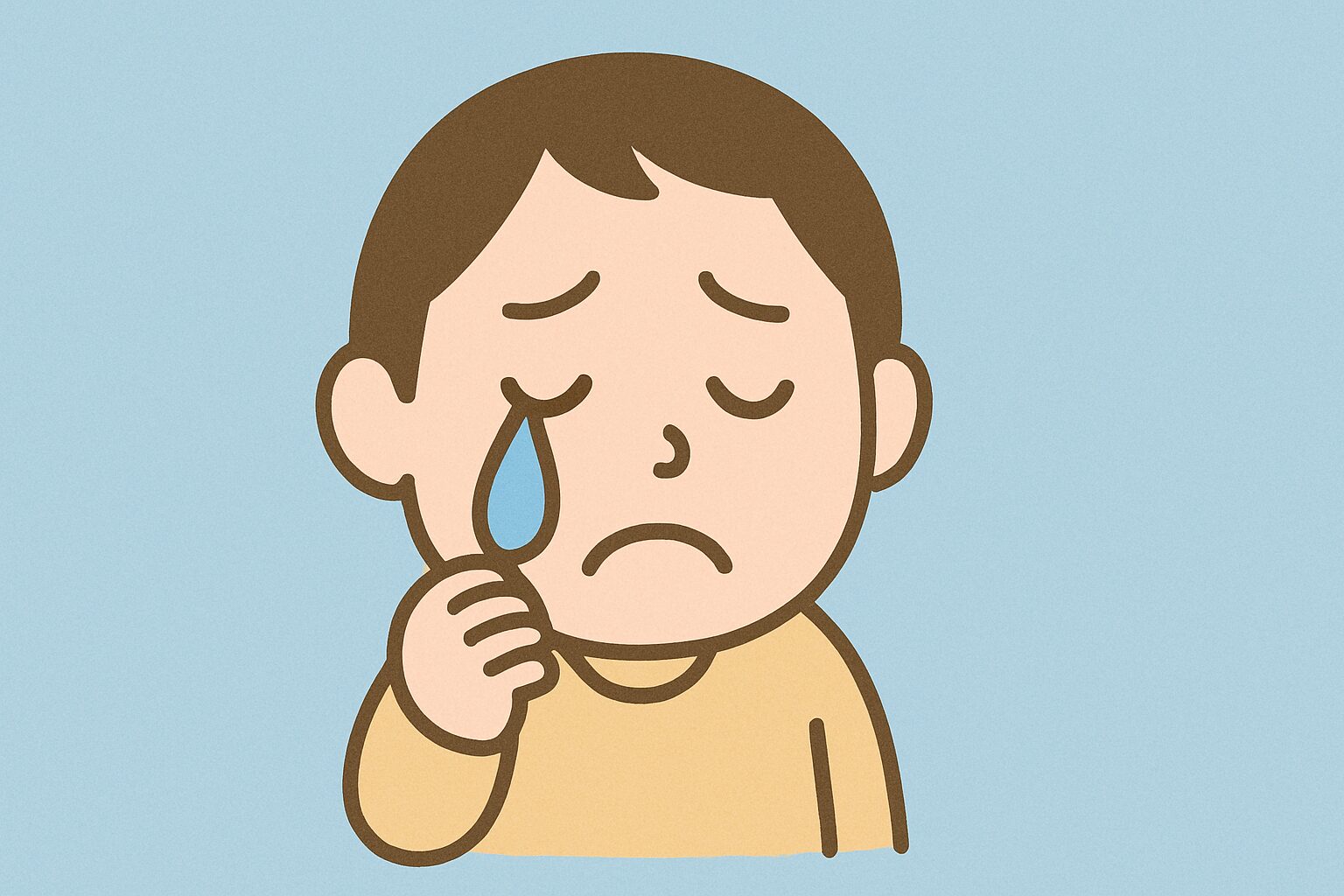なぜ登山道の階段ピッチは“短め”なのか?疲労曲線と転倒リスク
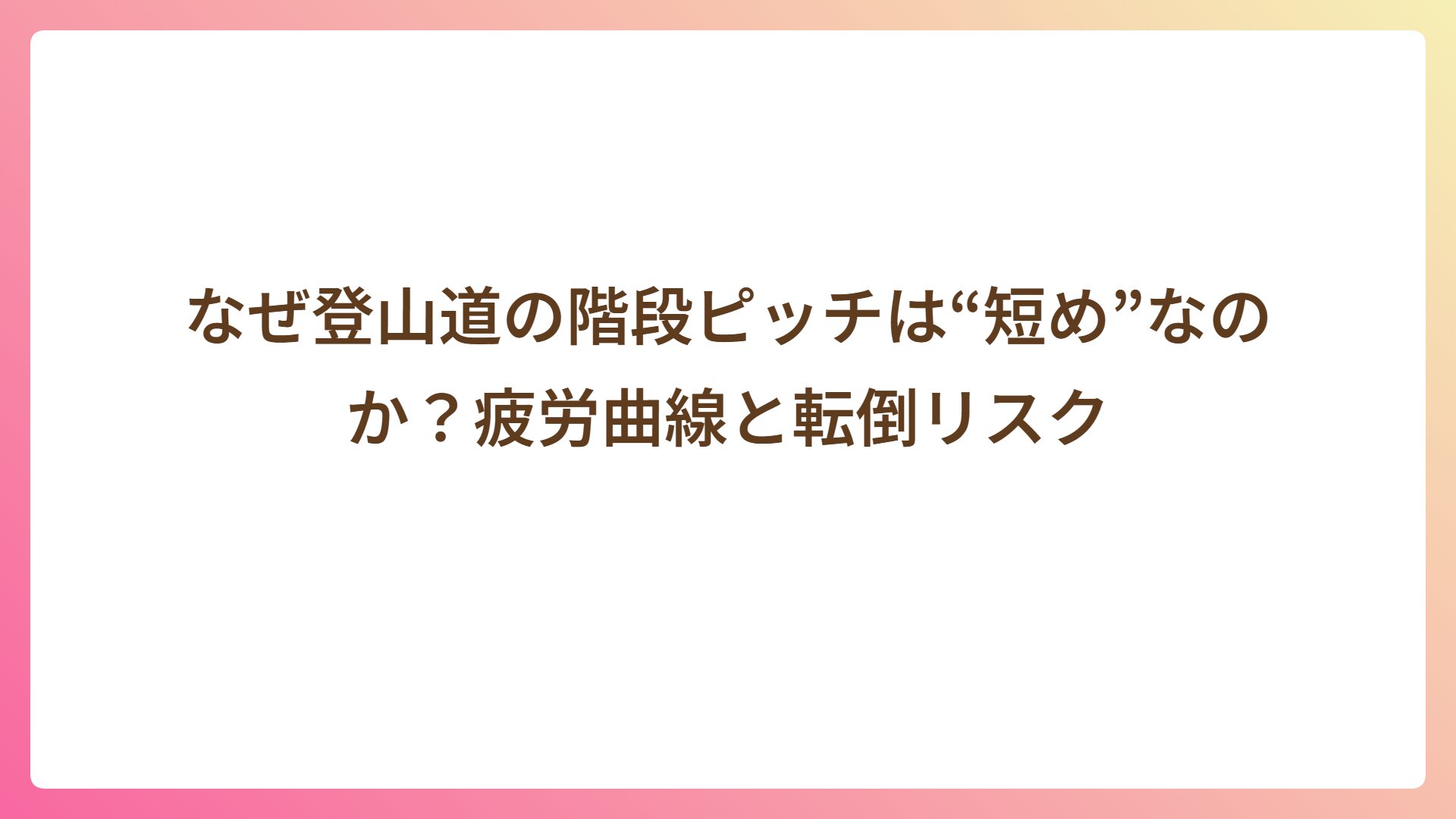
山道を歩いていると、木の階段や丸太の段差が思ったより短いと感じることがあります。
「もう少し高くしてくれたら登りやすいのに」と思うかもしれませんが、あれには明確な理由があります。
実は登山道の階段は、人の筋肉疲労と転倒リスクを最小限に抑えるための“短め設計”になっているのです。
登山道の階段ピッチは「住宅階段」よりも低い
一般的な住宅の階段は、1段の高さ(蹴上げ)が約18〜20cm、奥行き(踏面)が約25cm前後です。
一方で登山道の階段は、蹴上げが10〜15cm、踏面が40cm以上とかなり緩やかに作られています。
これは「登山」という運動が、日常生活とは違って長時間・反復的な動作を伴うためです。
高い段差を何百段も登り続けると、太ももの大腿四頭筋に強い負荷がかかり、
筋疲労が蓄積してバランスを崩しやすくなります。
そのため、段差を低く・奥行きを広くして、筋力よりも体重移動で登れるように設計されているのです。
疲労曲線から見た「最適ピッチ」
人間の脚は、1回の上げ下げに必要なエネルギーが段差の高さに比例して増えます。
研究では、段差が2倍になるとエネルギー消費は約1.6〜1.8倍に増えることが分かっています。
登山のように数千段にも及ぶ環境では、わずか数センチの違いが全体の疲労曲線を大きく左右します。
つまり、登山道の階段を短めにすることで、1段ごとの負荷を下げ、
結果的に長距離を歩いても「息が上がりにくく、転倒しにくい」状態を保てるのです。
下山時の“転倒リスク”にも関係
短めピッチは登りだけでなく、下山時の安全にも関わります。
段差が高いと、体重が前方にかかりやすく、膝関節やかかとに衝撃が集中します。
これが疲労や転倒の原因になるため、段差を低く設定して重心を安定させる構造にしているのです。
また、登山靴はソールが厚く滑りにくい反面、つま先の感覚が鈍くなりやすいため、
段差が浅いほうがつまずきを防ぎやすいという利点もあります。
木段・丸太階段の「施工上の理由」
登山道では、土留めや浸食防止のために丸太や角材を用いた階段が設置されます。
これらの材木の直径は10〜15cm前後が一般的で、自然と段差も同程度に落ち着く構造になります。
つまり、素材の標準寸法=人に優しい段差という、自然と合理的な設計になっているのです。
さらに、ピッチを短くすることで雨水の流れを分散でき、
土砂流出や階段崩落を防ぐという保全上のメリットもあります。
視覚的リズムと心理効果
段差が低くピッチが一定だと、歩くリズムが安定し、心理的にも疲れを感じにくくなります。
逆に段差がバラバラだと、一歩ごとにペースが乱れ、集中力の低下や転倒リスクの増加につながります。
登山道整備では、こうした「歩行リズム」も考慮して設計されているのです。
まとめ
登山道の階段ピッチが短めなのは、脚の疲労を抑え、下山時の転倒リスクを防ぐためです。
自然の地形や木材寸法を活かしつつ、人の歩行リズムと筋肉負荷を最適化することで、
安全かつ快適に登れる道が保たれています。
一見何気ない“段の高さ”にも、人間工学と自然保全の知恵が息づいているのです。