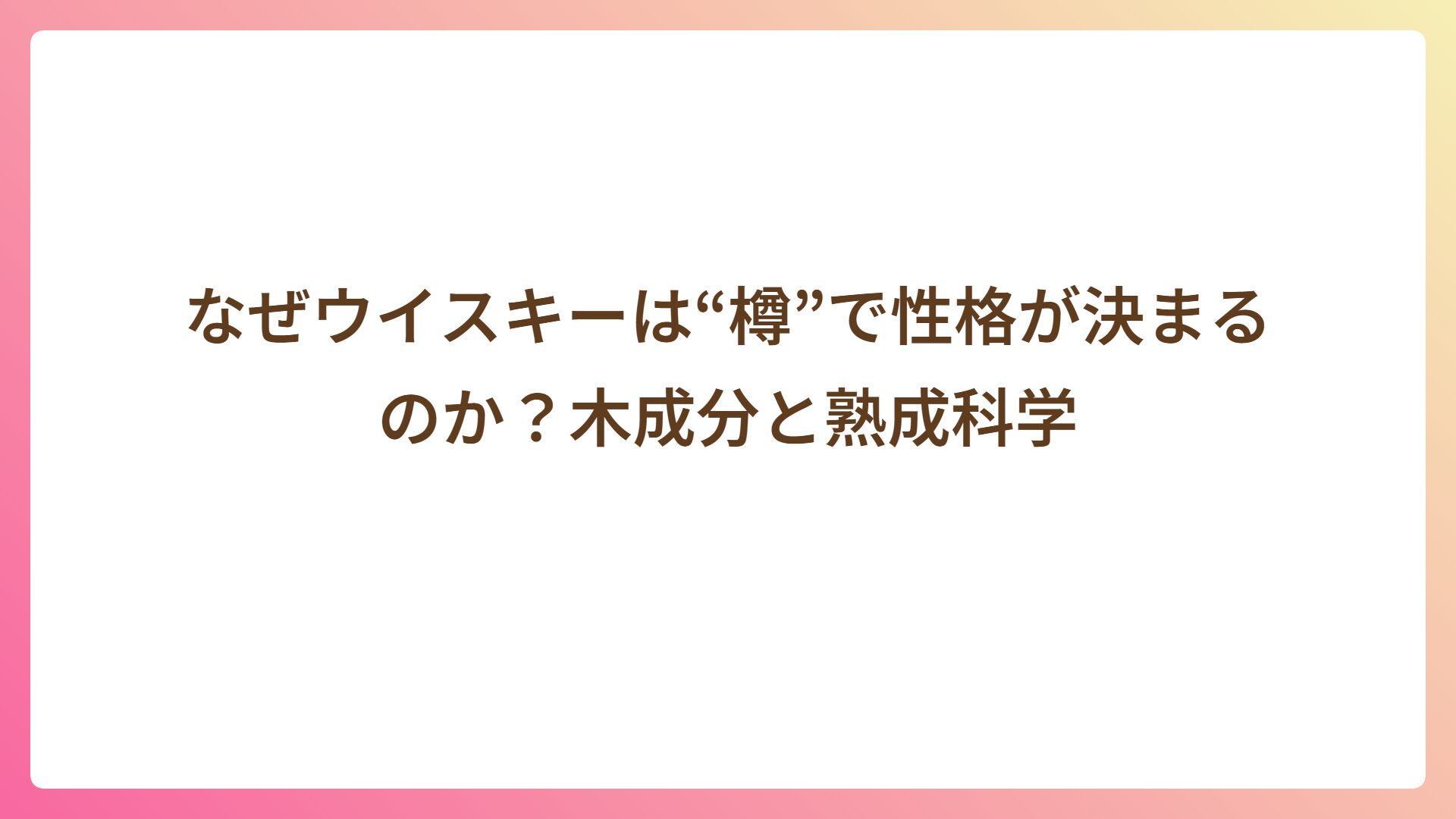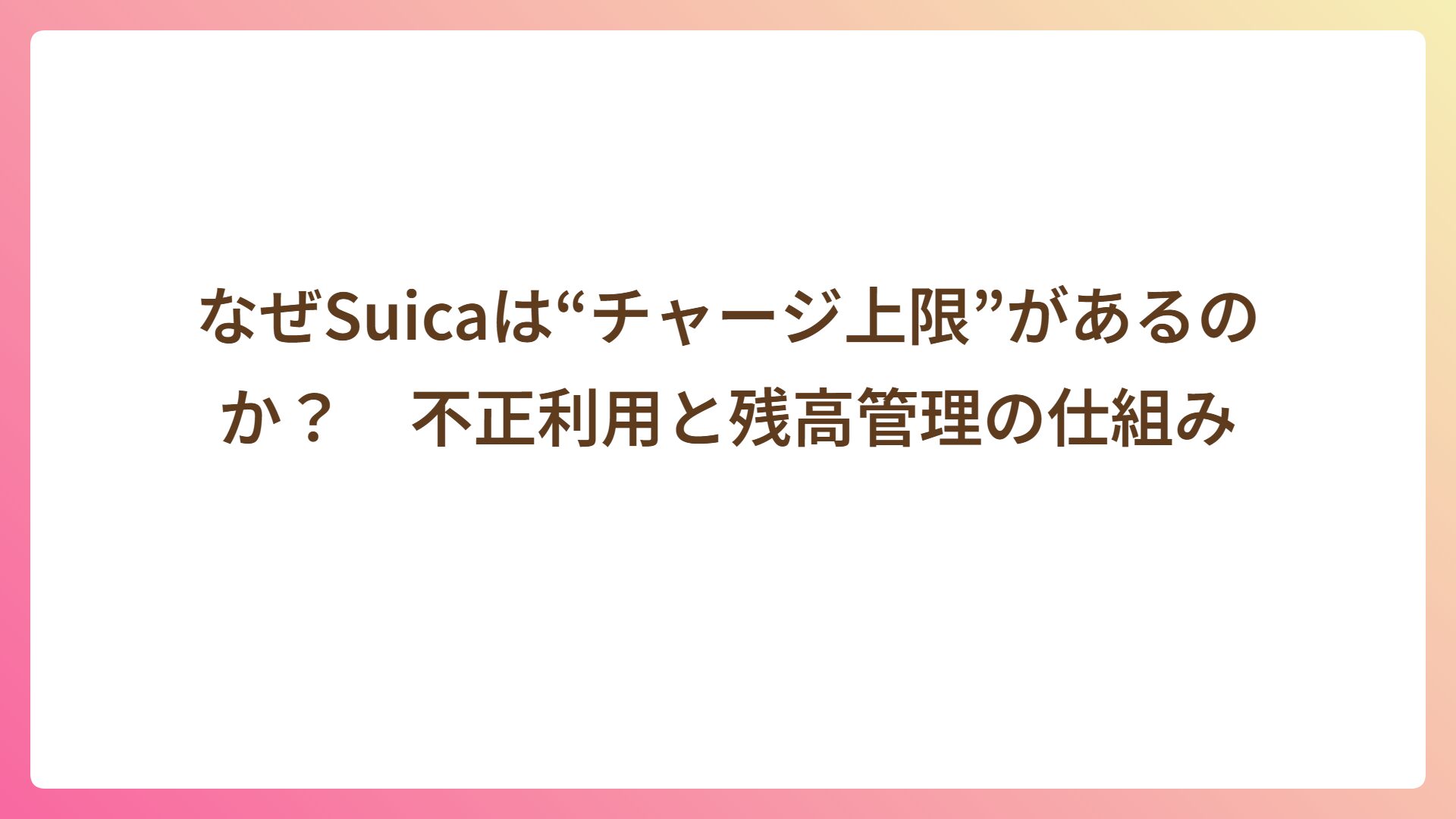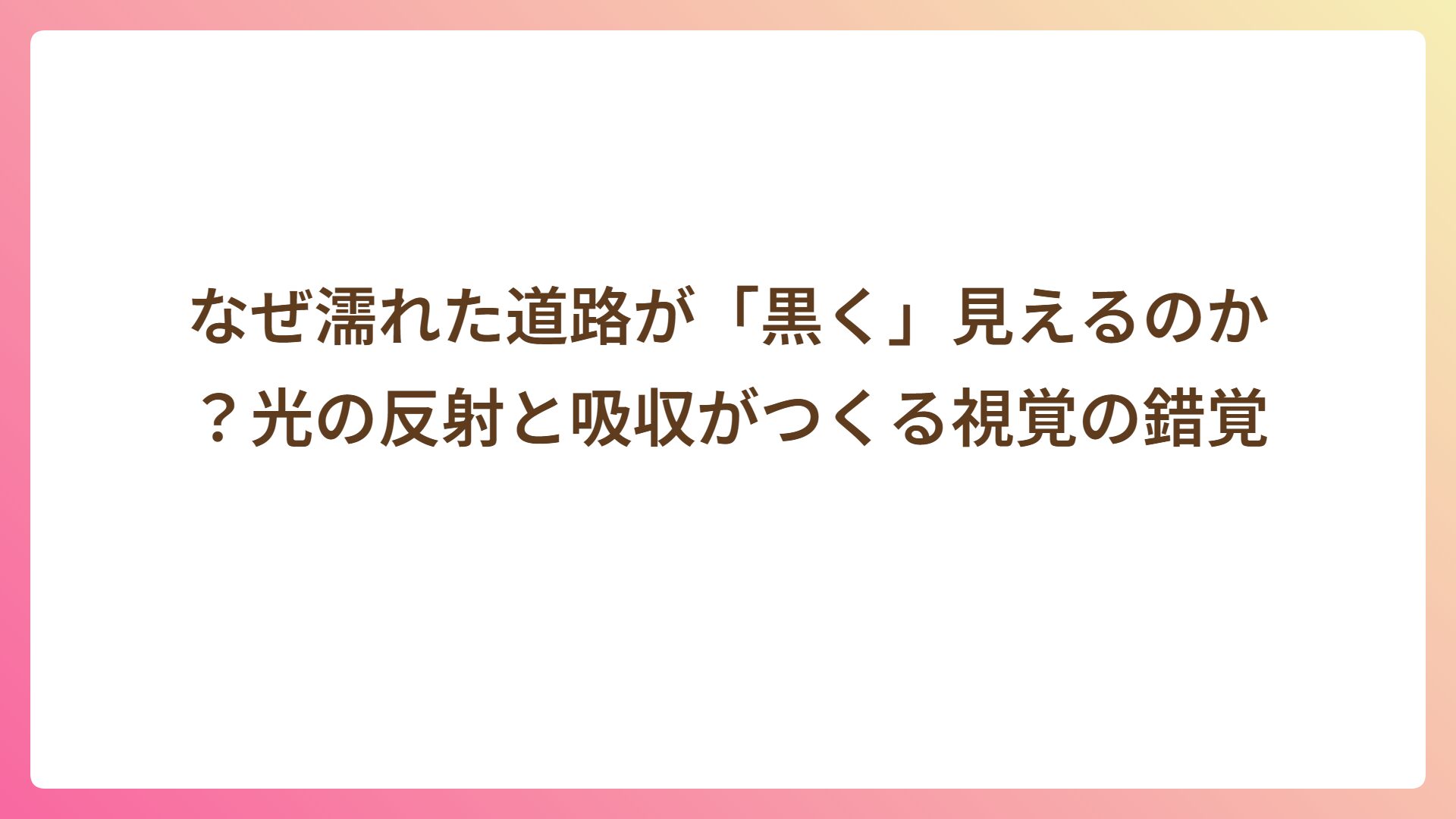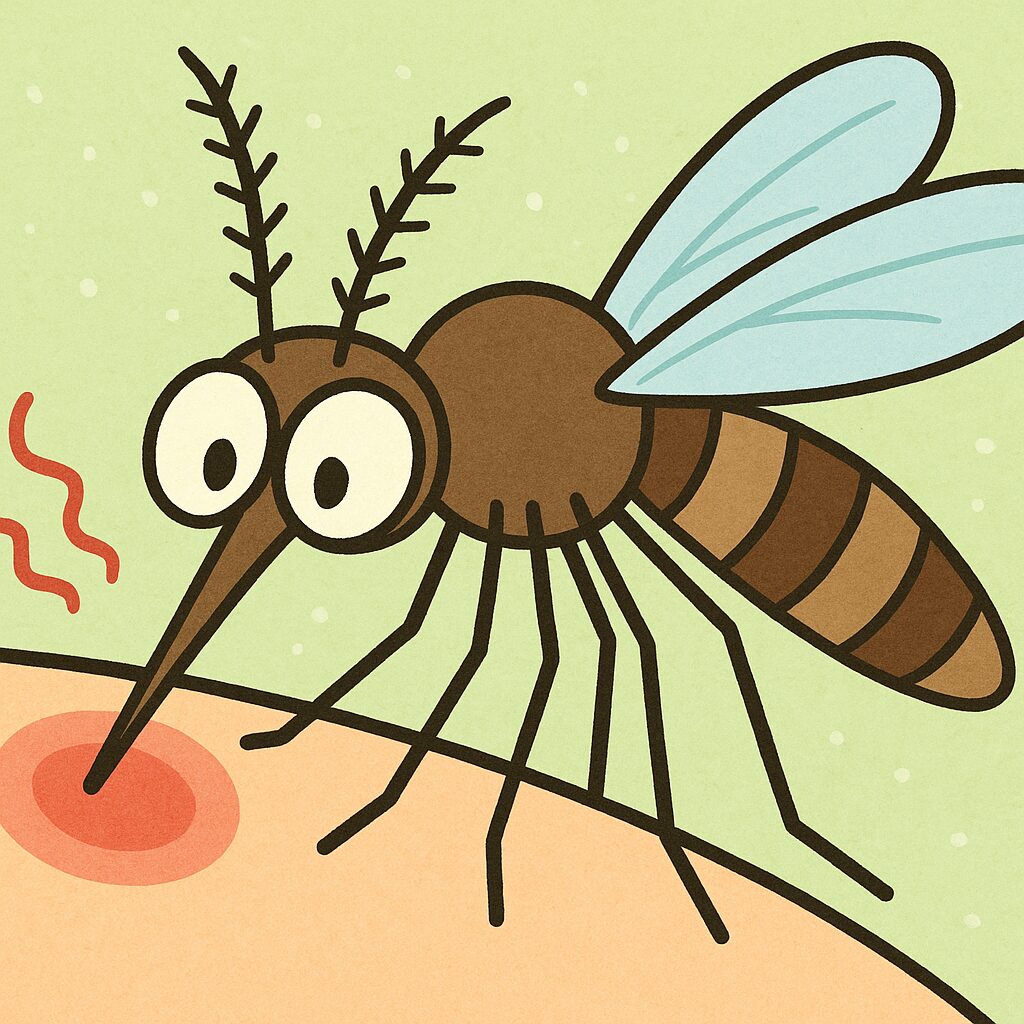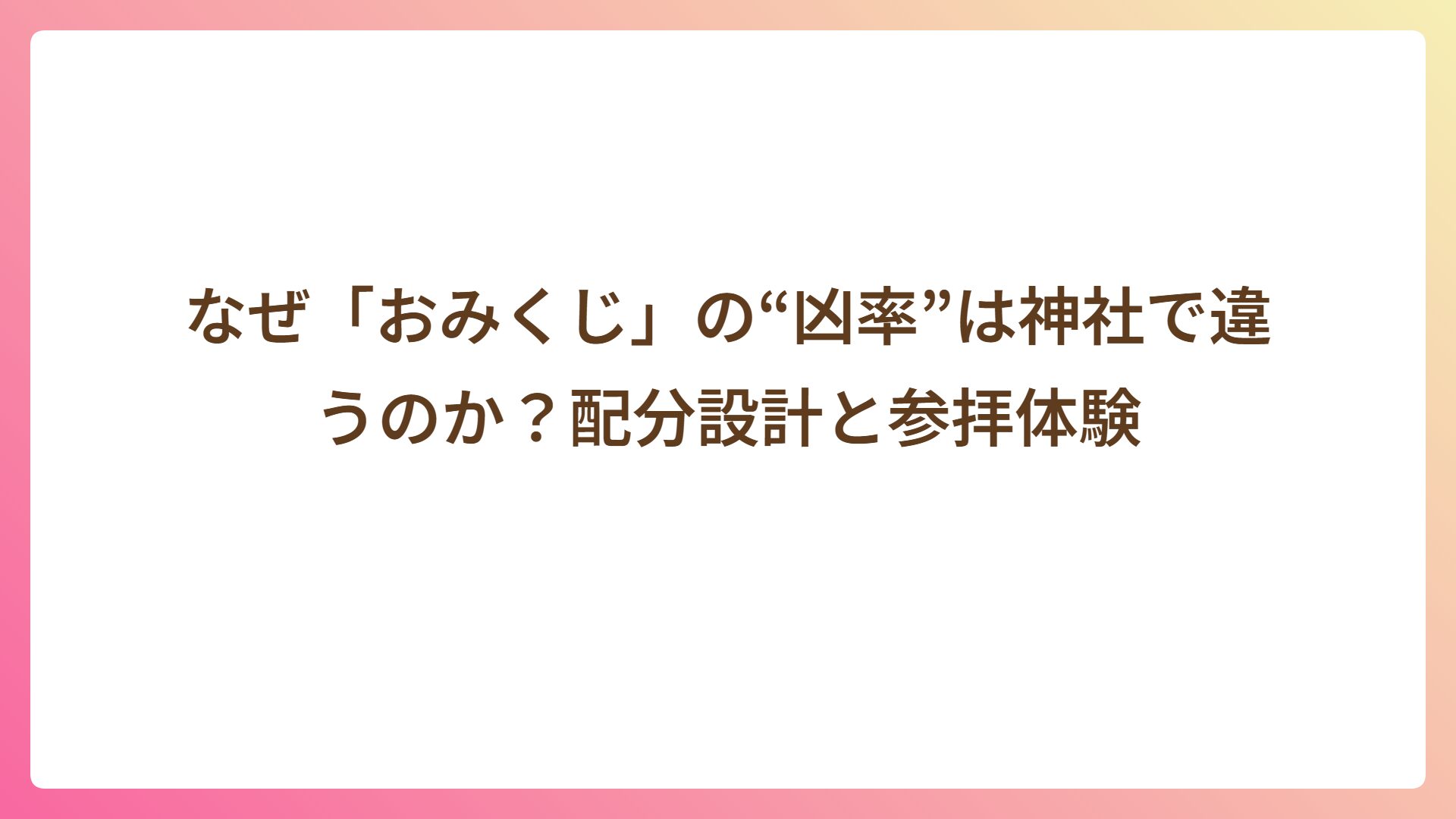鹿肉のことを「もみじ」というのはなぜ?隠語に込められた色と文化の由来
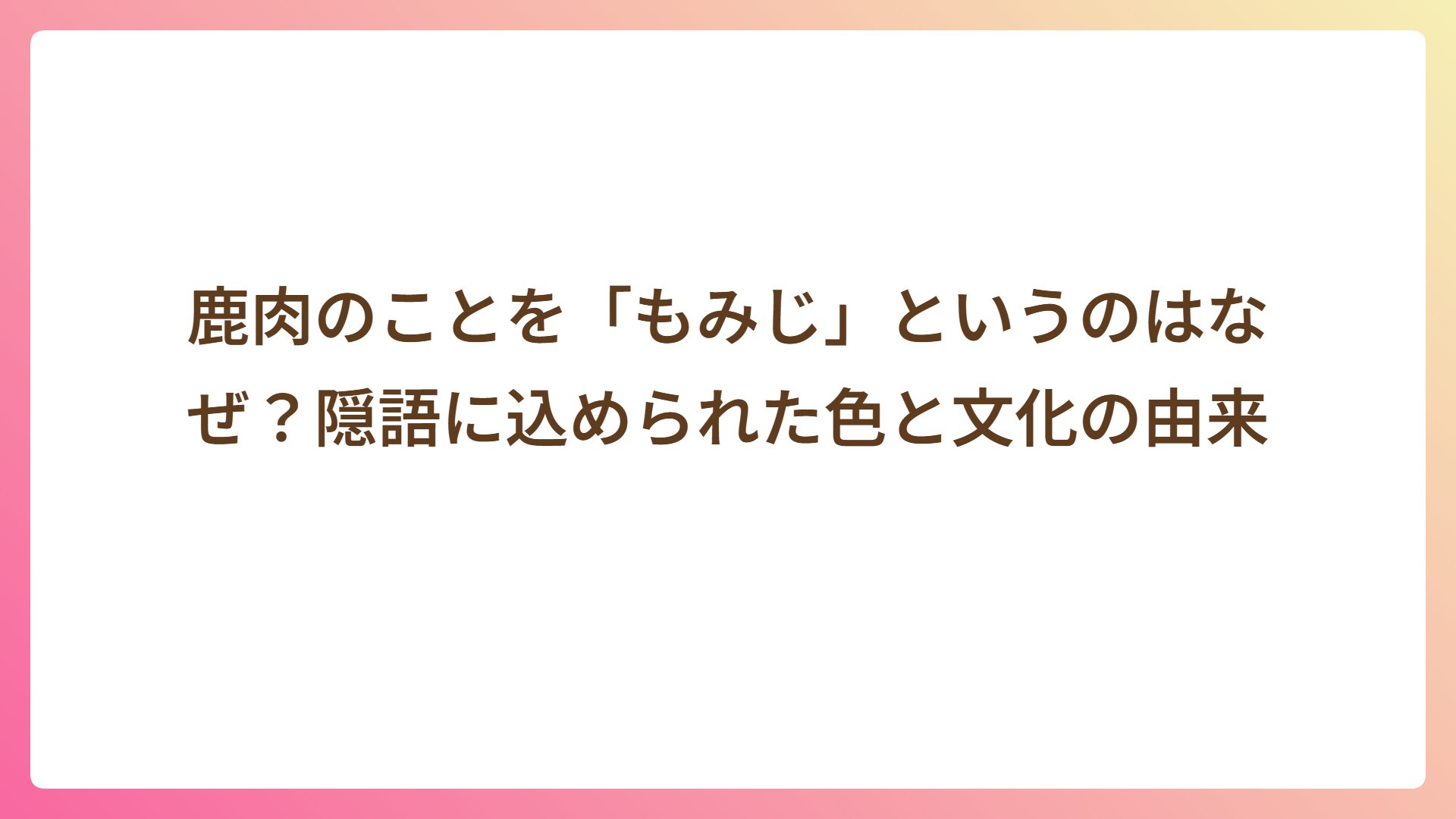
居酒屋のメニューなどで見かける「もみじ鍋」や「もみじ肉」という言葉。
実はこれ、鹿肉を指す隠語ですが、なぜ“紅葉”を意味する「もみじ」が鹿と結びついたのでしょうか?
その背景には、肉食が禁じられた時代の言葉の工夫と、自然の色に込められた象徴的な意味が隠されています。
肉食禁止の時代に生まれた「隠語」
「もみじ」という呼び名が使われるようになったのは、江戸時代の肉食禁止令が背景にあります。
当時の日本では、仏教の影響により「殺生はよくない」とされ、牛や馬、鹿などの肉を食べることが公には禁じられていました。
しかし実際には、人々は密かに野生動物の肉を食べており、その際に直接的な動物名を避けるための隠語を使っていたのです。
例えば、
- 馬肉 → さくら
- 猪肉 → ぼたん
- 鹿肉 → もみじ
というように、季節の花や植物にたとえて表現していたのです。
「もみじ」と鹿の関係は“紅葉の色”から
鹿肉が「もみじ」と呼ばれるようになった最大の理由は、肉の色が紅葉のように赤いことです。
鹿肉は脂肪が少なく、鮮やかな深紅色をしており、その色合いが秋の紅葉に似ていることから「もみじ」と呼ばれるようになりました。
また、古くから日本では「紅葉と鹿」はセットで詩や絵に描かれることが多く、
「紅葉に鳴く鹿」という情景が秋の象徴として親しまれてきました。
この文化的な結びつきも、鹿=もみじという連想を自然に定着させたと考えられます。
「花札」にも見る自然の連想
花札の絵柄でも、10月の札には「紅葉に鹿」が描かれています。
このように、紅葉と鹿が一対の存在として日本文化に根づいていたことが、言葉としての「もみじ肉」を後押ししました。
単なる隠語以上に、「季節」「自然」「情緒」を感じさせる表現として広まったのです。
現代にも残る「花の肉文化」
現在でも、地域によってはこれらの隠語が使われています。
たとえば、熊肉を「やまくじら」と呼ぶ地域があるように、花や自然を使った肉の言い換え文化は今も受け継がれています。
その中でも「さくら」「ぼたん」「もみじ」の3つは特に有名で、鍋料理や居酒屋メニューの名称として定着しています。
まとめ:紅葉の色と文化が生んだ“美しい隠語”
鹿肉を「もみじ」と呼ぶのは、紅葉のような肉の色と、秋の風物詩としての鹿のイメージが重なったことが由来でした。
肉食が禁じられた時代に人々が編み出した美しい言葉の工夫が、現代まで受け継がれているのです。
「もみじ肉」という言葉には、食文化の知恵と日本的な美意識の両方が息づいています。