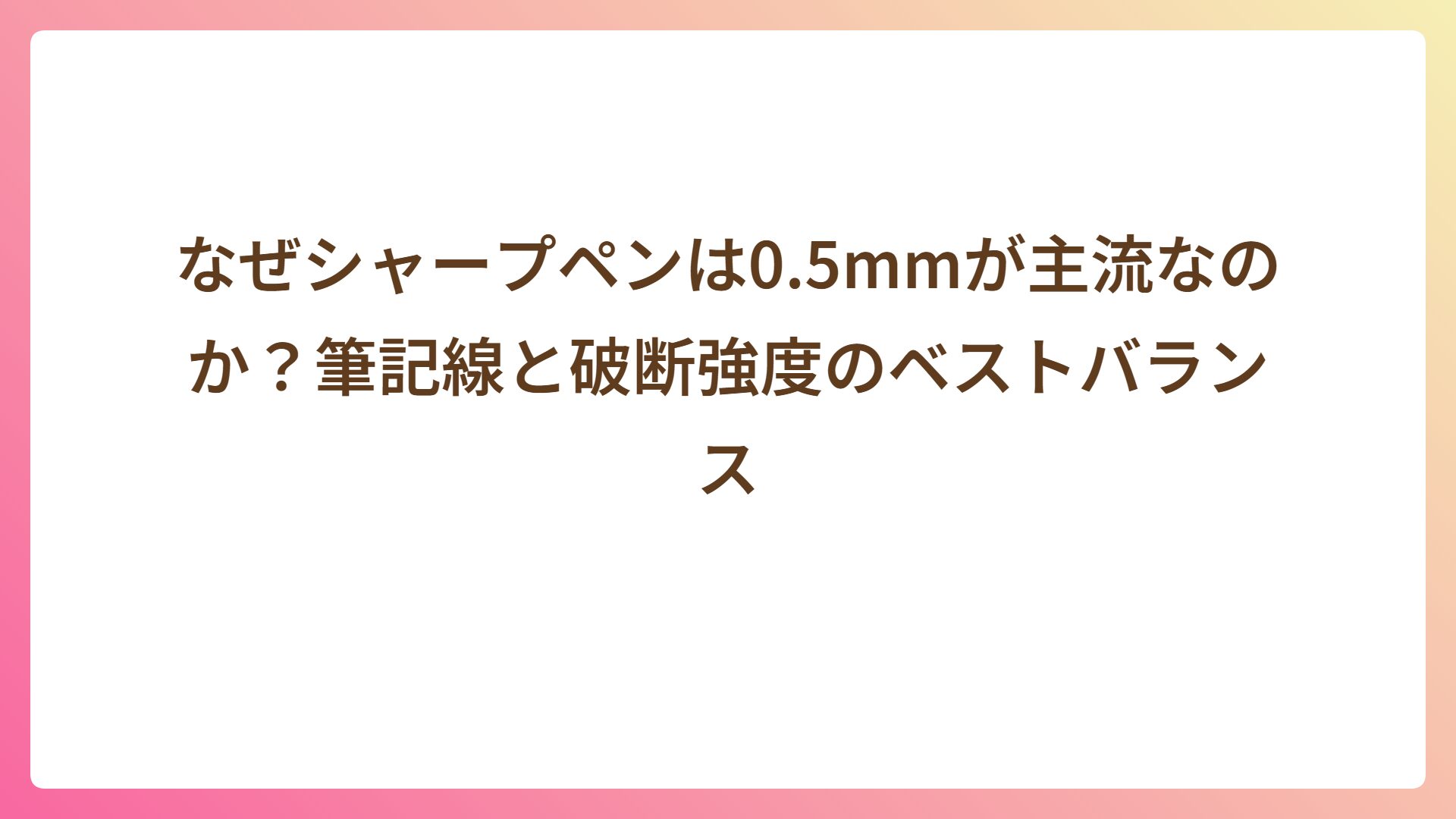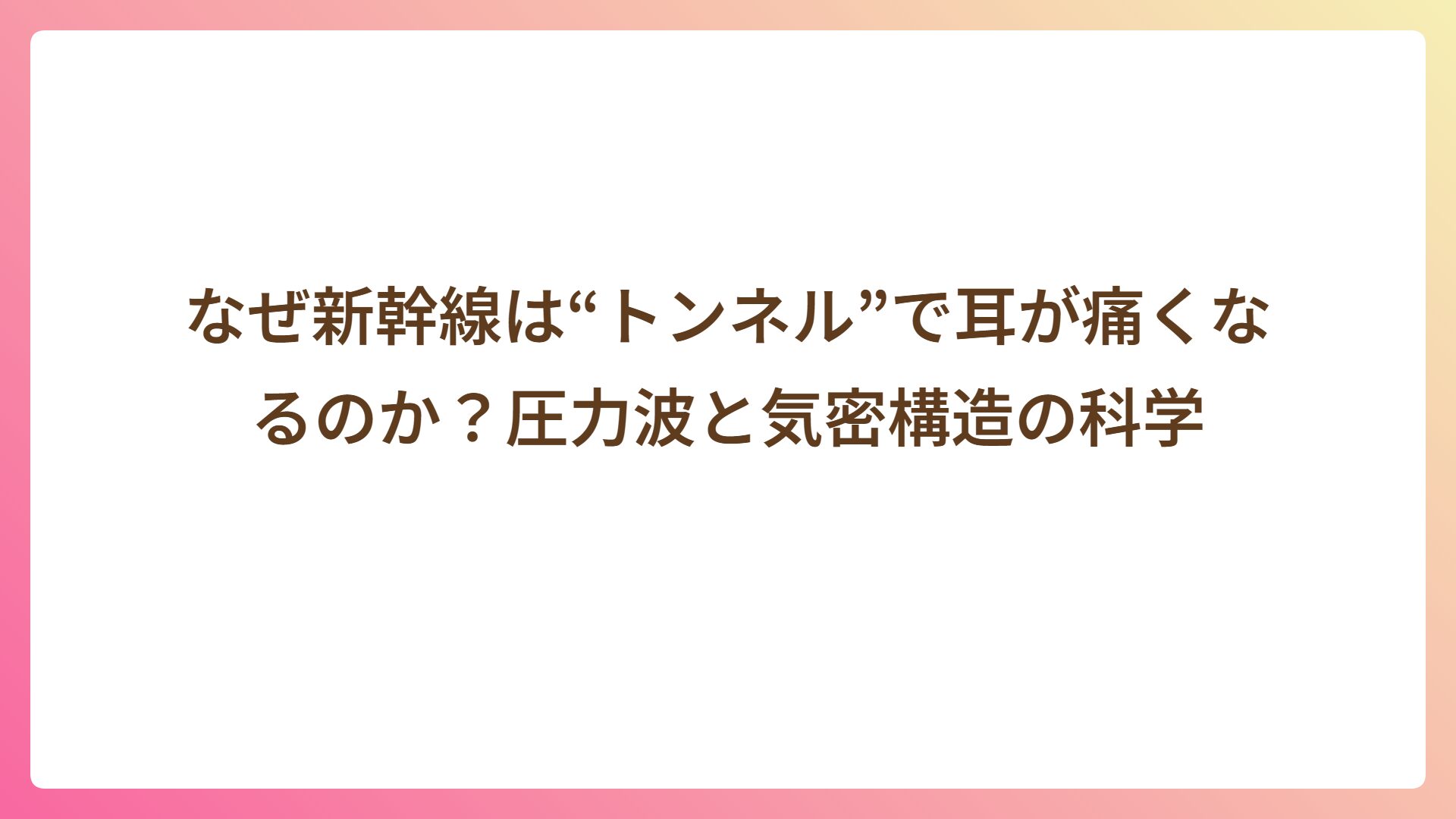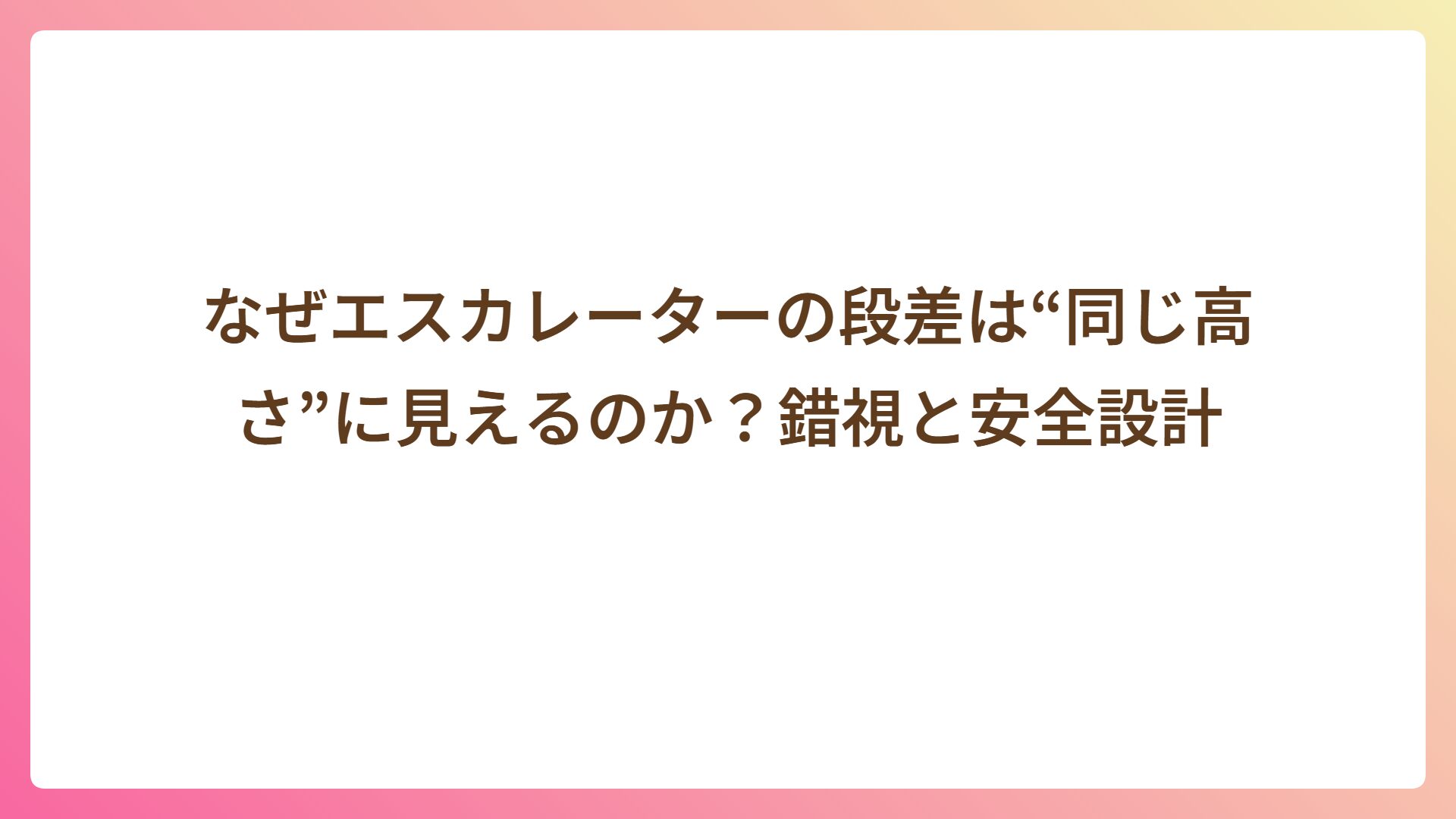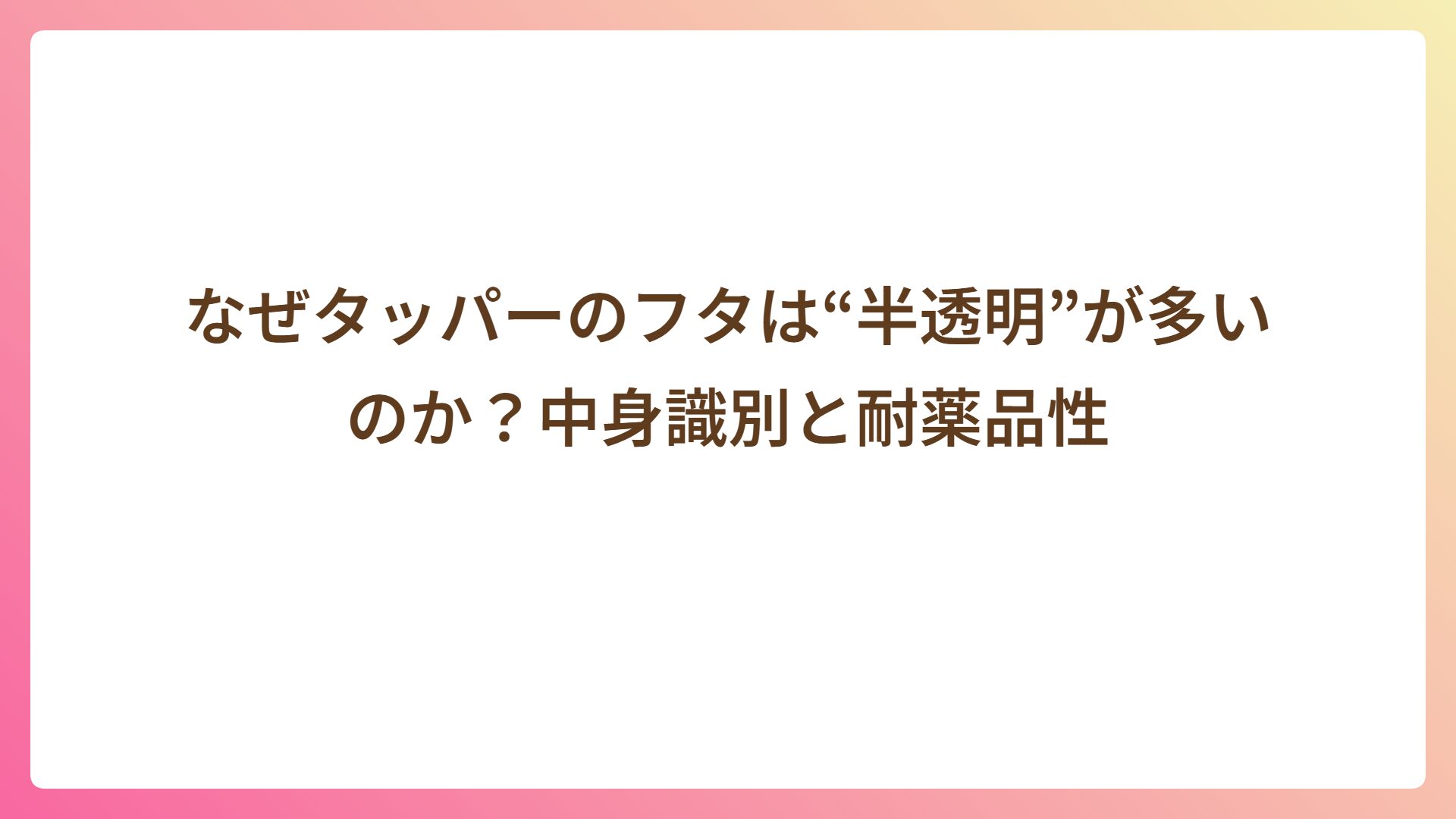なぜ相撲場の土俵は“丸い”のか?形状規定と力士の動線
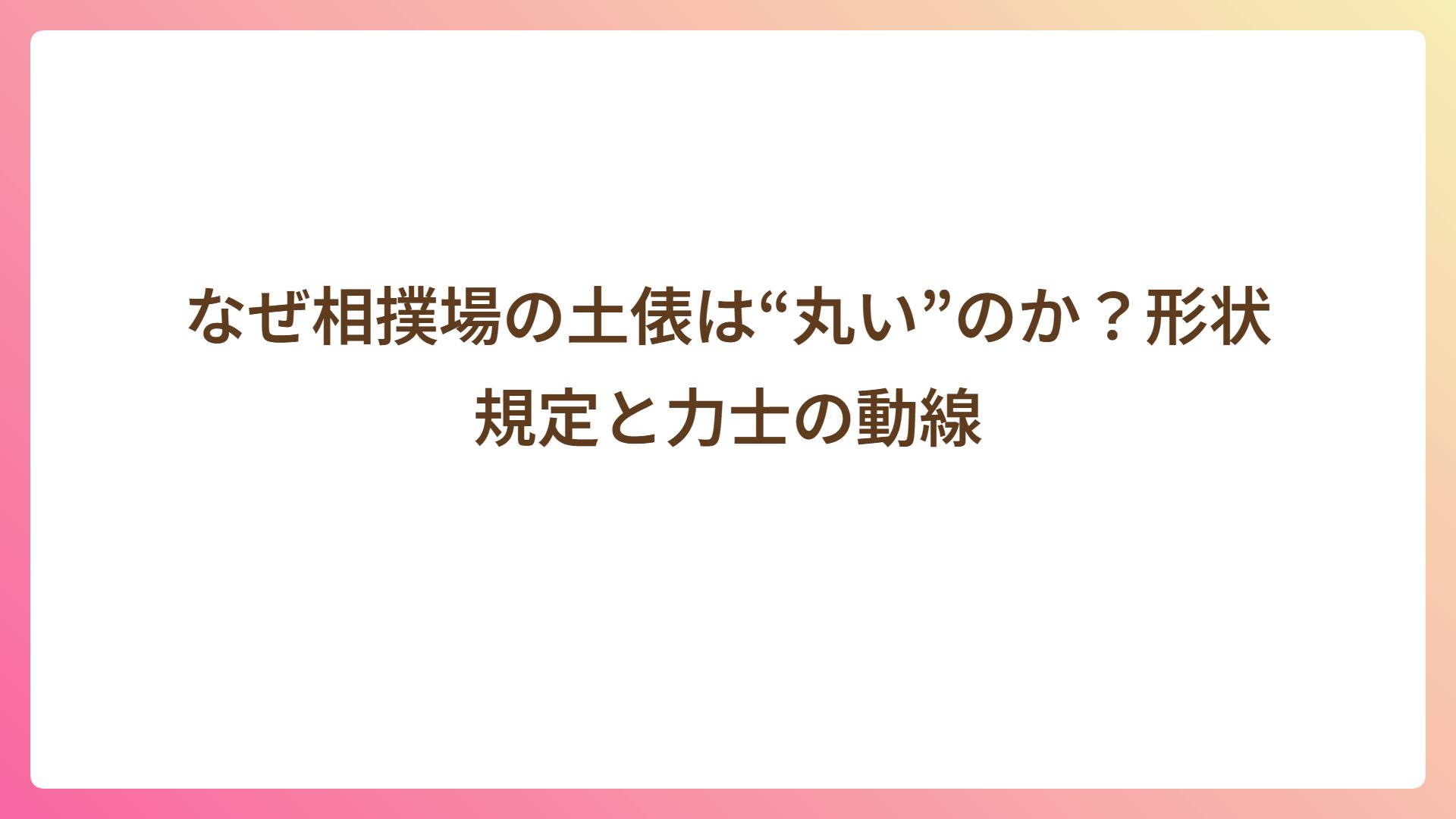
相撲といえば、円形の土俵。その中央で力士がぶつかり合う姿は日本の国技の象徴です。
しかし、なぜ四角ではなく「丸い」形なのでしょうか?
実はこの形には、力士の動線・安全・観客視点のすべてを両立させる合理的な理由があります。
現在の土俵は「直径4.55メートルの円」
現在の大相撲の土俵は、直径4.55メートル(15尺)と規定されています。
円の境界線(俵)はわらで作られ、埋め込まれているため見た目にもはっきりわかります。
この円形は江戸時代中期に定まり、勝敗を明確にするための基準形として全国に統一されました。
もし土俵が四角形や多角形であれば、角の位置で「出た」「残った」の判断が曖昧になります。
しかし円であれば、どの方向に動いても境界までの距離が一定なため、公平かつ明快な勝敗判定が可能になります。
力士の動きを受け止める「最適な形」
相撲は、力士が押し合い・回り込み・投げるといった立体的な動きを行う競技です。
円形の土俵は、これらの動きを自然に中央へ誘導し、激しいぶつかり合いの中でもバランスを保ちやすくしています。
特に投げ技の際、四角形だと角に向かって危険に転倒する可能性がありますが、円なら衝突方向が分散され、安全性が高まるのです。
観客から「どの方向からも同じように見える」
土俵が丸いもう一つの理由は、観客席からの視認性です。
相撲場は360度を観客が取り囲む構造になっており、円形の土俵であればどの位置からでも均等に取り組みが見えます。
角がないことで審判(行司・審判員)も立ち位置を自由に調整でき、
どの角度からでも土俵際の動きを確認しやすくなっています。
神事としての「円=調和・永続」の意味
相撲の起源は神事にあり、土俵もその神聖な場として扱われます。
円は古来より「完全」「調和」「永遠」を象徴する形とされ、
神を招く場・祈りの場として最もふさわしい形と考えられてきました。
つまり、円形は合理性だけでなく、宗教的・象徴的意味も持っているのです。
まとめ
相撲場の土俵が丸いのは、
勝敗を明確にし、安全性と視認性を高め、神事としての象徴性を守るためです。
円は、力士・観客・神々のすべてをつなぐ調和の形。
その完璧なバランスこそ、相撲が千年以上受け継がれてきた理由のひとつなのです。