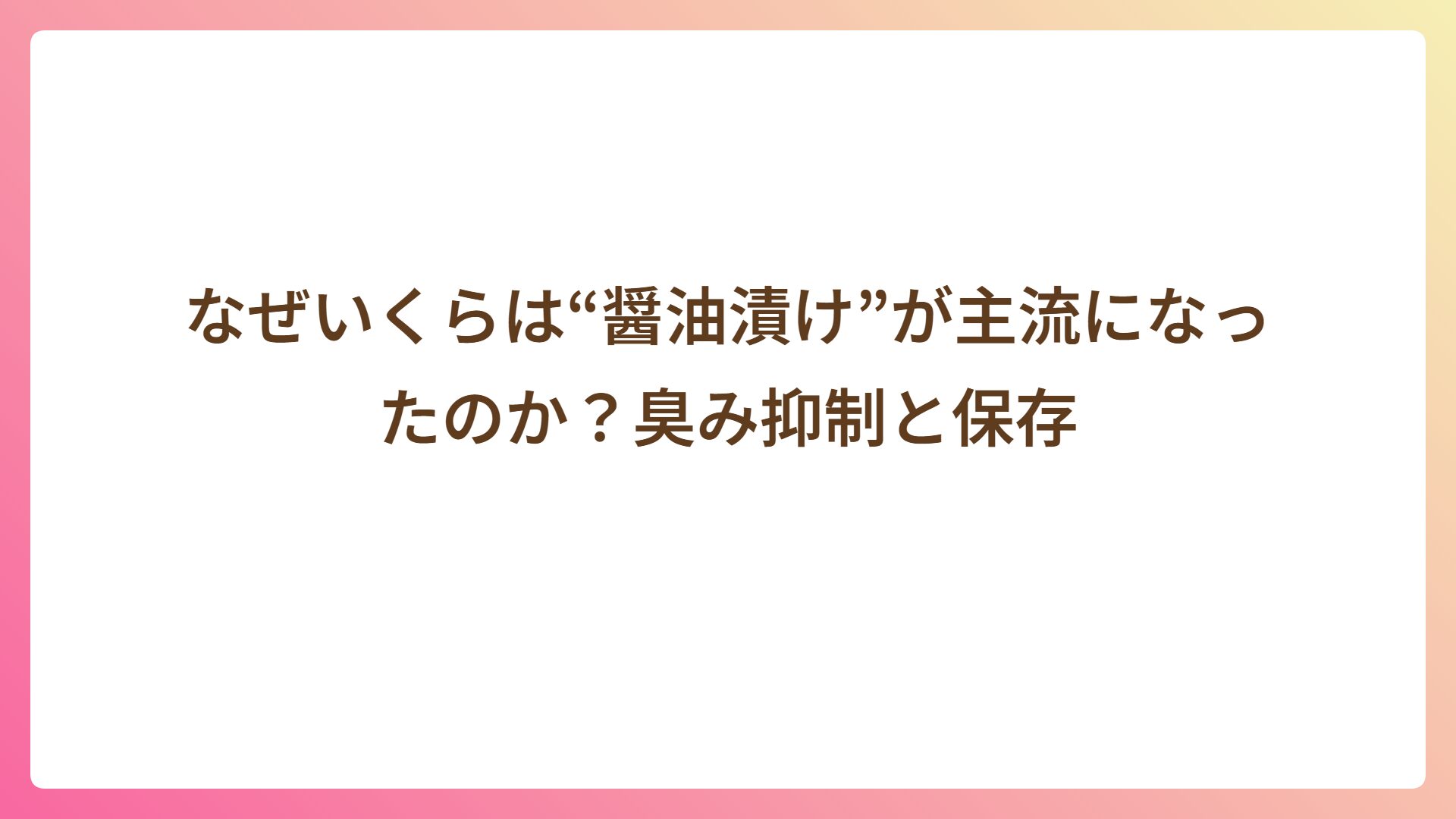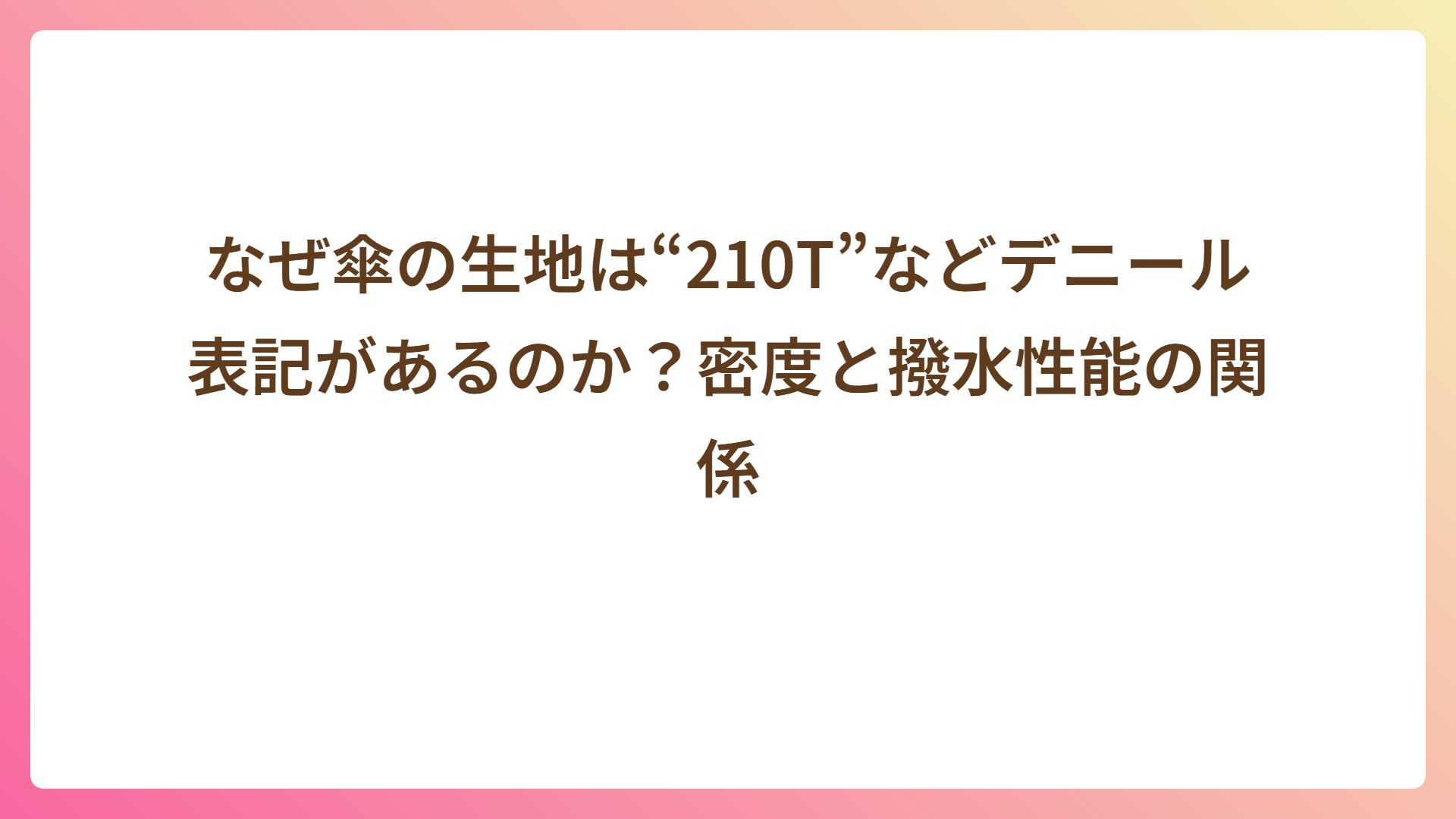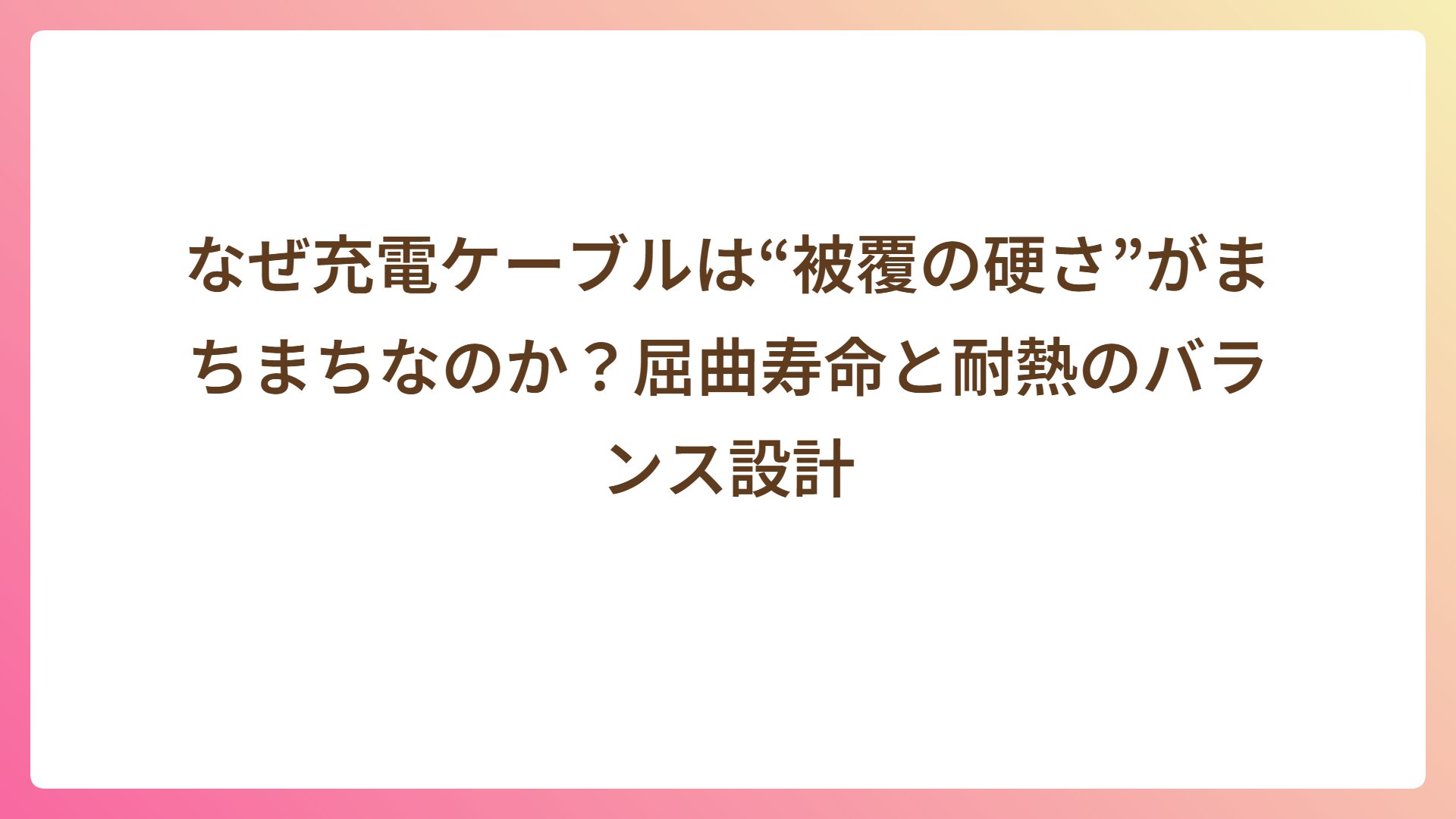なぜおでん種に“ちくわぶ”があるのか?東京独自食材の正体
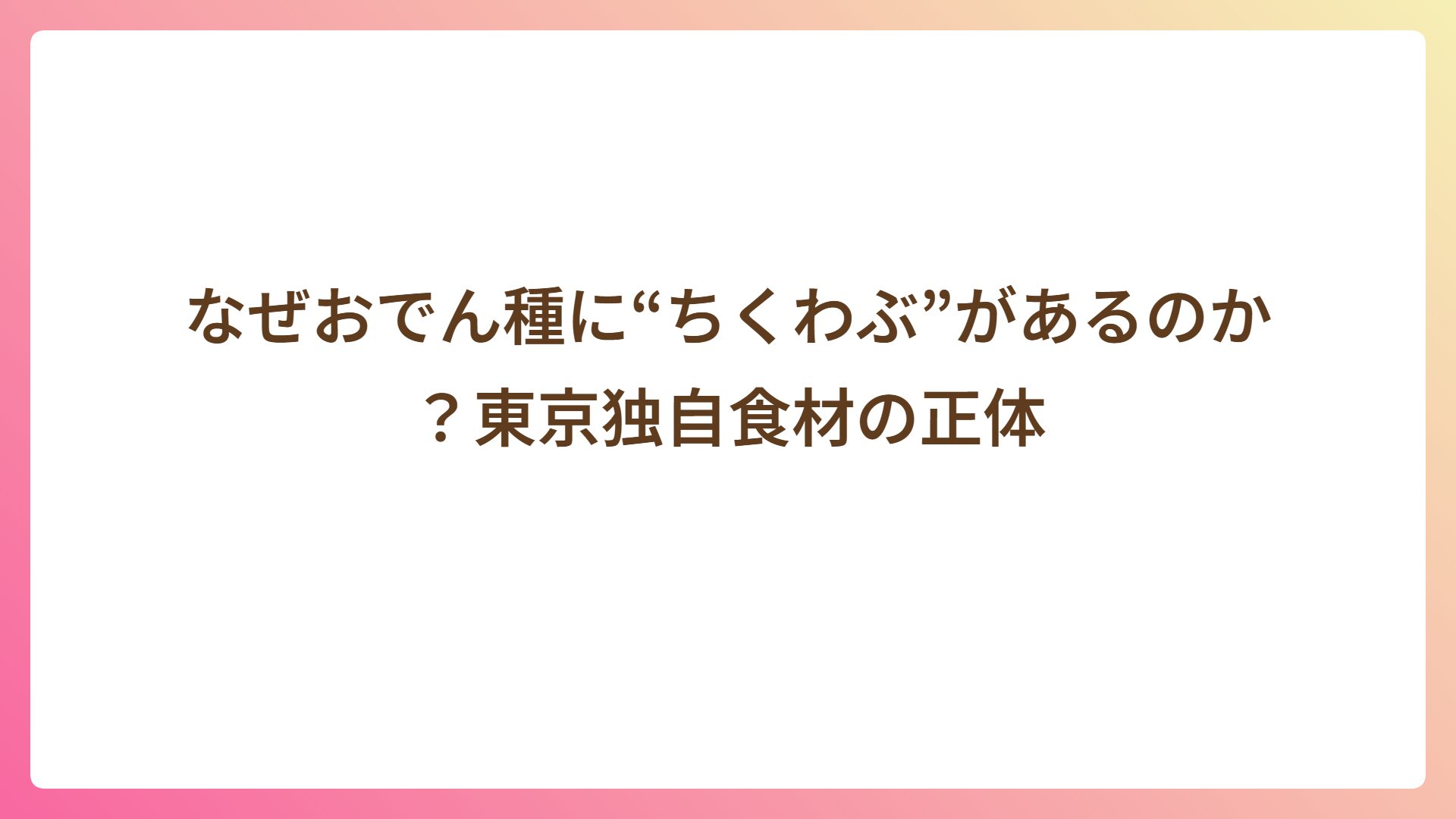
おでんの具といえば、大根、卵、こんにゃく、そして——ちくわぶ。
だがこの「ちくわぶ」、関西ではほとんど見かけません。
見た目はちくわ、でも中身は魚ではなく小麦粉。
なぜ関東だけで愛される独特の食材が生まれたのでしょうか?
その答えは、江戸の食文化と流通事情にあります。
ちくわぶは「ちくわ+麩(ふ)」のハイブリッド
名前の由来は「ちくわ」と「麩(ふ)」を合わせたもの。
魚肉ではなく、小麦粉を水で練って棒に巻きつけ、茹でて作ります。
つまり「ちくわの形をしたグルテン食品」で、
**魚のちくわを模した“代用品”**として誕生しました。
焼くのではなく茹でるため、もっちりとした弾力があり、
汁をよく吸って柔らかくなるのが特徴です。
魚が高価だった江戸で生まれた「粉の代用品」
江戸時代の江戸(東京)は、人口が急増した巨大都市でした。
一方で、内陸部では魚介が高価で手に入りにくく、
庶民にとって魚のすり身を使った練り物は贅沢品。
そこで考え出されたのが、
安価で入手しやすい小麦粉を主原料とした“なんちゃって練り物”。
これがちくわぶの原型とされています。
つまり、ちくわぶは「魚のちくわを食べたいけれど高いから粉で代用しよう」
という江戸庶民の知恵と節約精神の産物だったのです。
小麦文化が発達していた関東だからこそ
関東では古くからうどんや焼き麩など、小麦粉を主食に使う文化が根づいていました。
寒冷な気候のため米の収穫量が少なく、
代わりに麦の栽培が盛んだったためです。
そのため、小麦粉を練って加熱・加工する技術が進んでおり、
自然と「粉もの」を使った独自の食材が生まれやすい土壌がありました。
関西では魚のすり身(はんぺん・ごぼう巻など)が豊富にあったため、
わざわざ粉で代用する必要がなかったのです。
おでんとともに定着した“東京の味”
江戸時代後期、**おでん(当時は田楽系の煮込み料理)**が屋台で流行します。
関東では濃口醤油を使っただしが好まれ、
しっかりした味が染みるちくわぶが相性抜群でした。
やがて「おでん=ちくわぶ入り」というイメージが東京で定着。
昭和に入ってからも関東地方ではスーパーに必ず並ぶ定番具材として定着しました。
一方、魚介が豊富な関西では受け入れられず、
ちくわぶは“東京ローカル食品”として独自進化を遂げたのです。
もっちり食感と“汁のスポンジ”
ちくわぶの魅力は、何といってもだしを吸い込むスポンジ構造にあります。
小麦グルテンがネット状になっており、
内部に無数の気泡を抱えることで、煮込むほどに味が染みる。
その食感は、他の具材にはないもっちりとした満足感を生み出し、
「主食に近いおでんの具」として存在感を放っています。
まとめ
ちくわぶは、魚が貴重だった江戸で生まれた小麦製のちくわ代用品。
庶民の知恵と粉食文化が融合した、まさに東京発のソウルフードです。
おでん鍋の中で静かに味を吸い込み、
噛むほどにだしが染み出すちくわぶ。
その素朴な一片には、江戸の暮らしと工夫の歴史が今も息づいているのです。