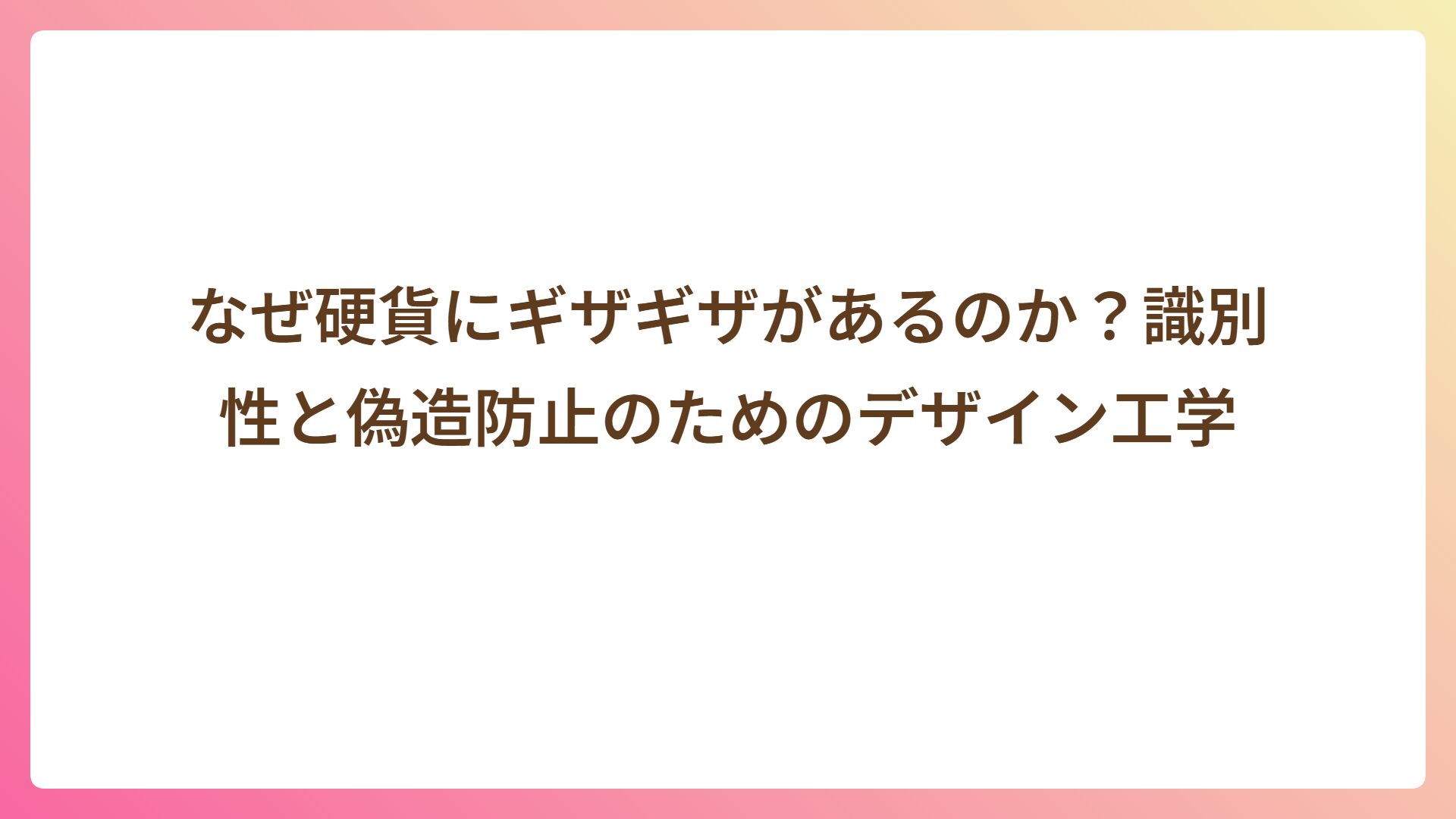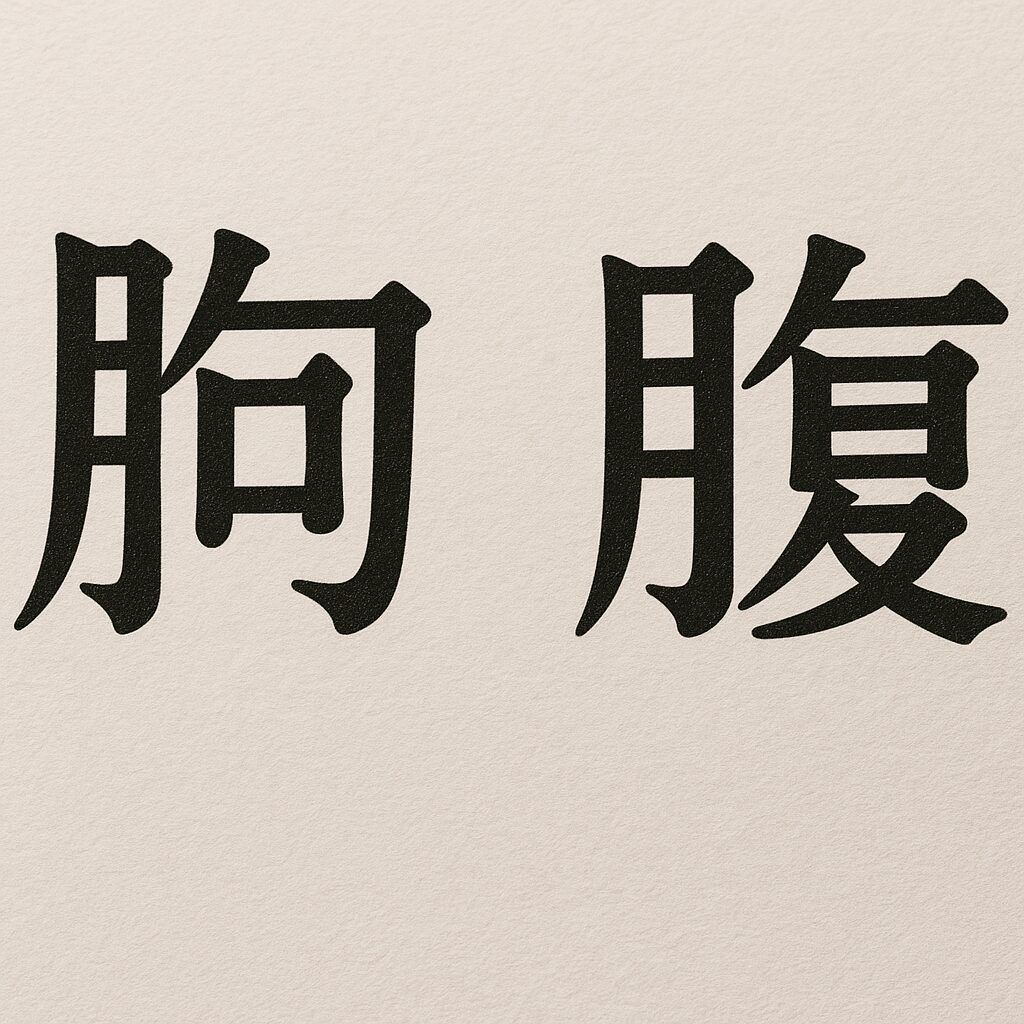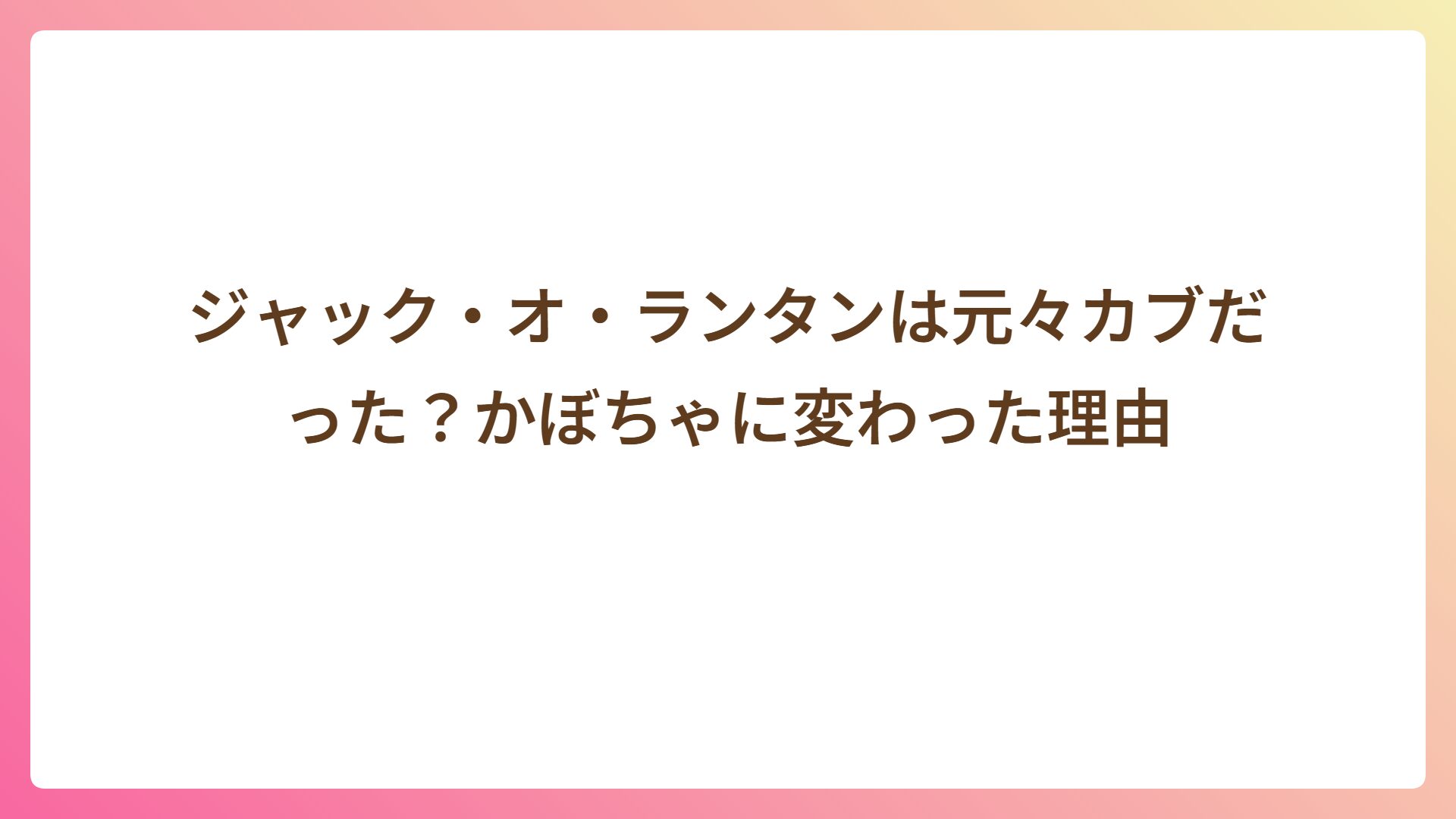なぜガードパイプは“黄色黒ストライプ”なのか?注意喚起のJIS配色
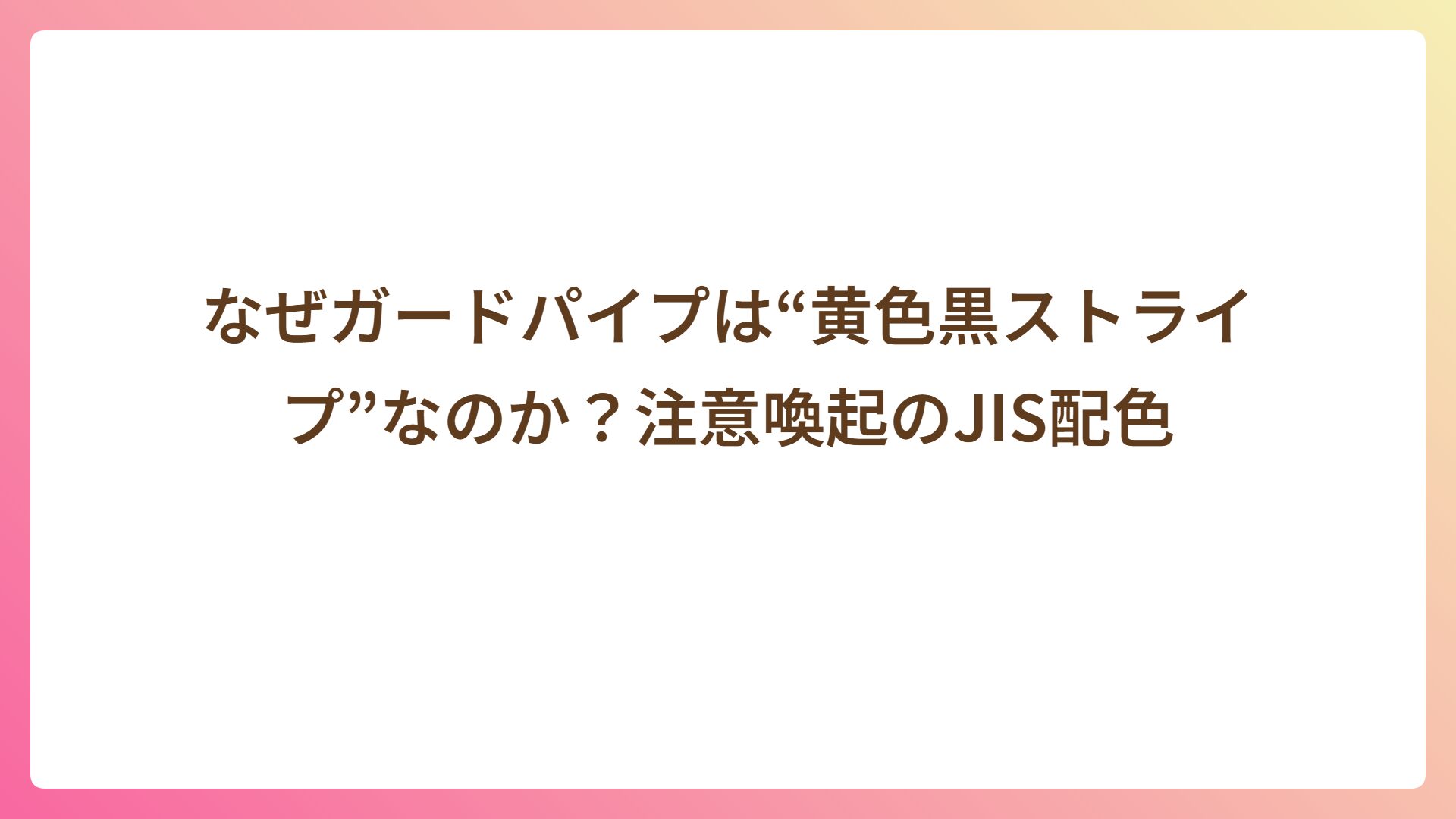
駐車場や歩道の端などで見かける、黄色と黒のストライプ模様のガードパイプ。
なぜあの色なのでしょうか?ただ目立つように塗られているわけではありません。
実はこの配色は、**日本工業規格(JIS)に基づいた「注意喚起色」**として正式に定められた、安全設計の一部なのです。
黄色と黒は「危険・注意」を示す標準配色
JIS Z 9103(安全色及び安全標識)では、作業現場や公共空間で使う安全色が明確に定義されています。
その中で「黄色と黒の斜線模様」は、注意を促すための警戒表示として指定されており、
人が視覚的に最も強く“危険”を感じやすい配色とされています。
黄色は明度が高く、昼夜を問わず視認性が高い色。
黒を組み合わせることでコントラストが最大化され、遠くからでも目立ちやすくなります。
つまりあの模様は、**「ここに障害物があります」「ぶつかるかもしれません」**という警告を、直感的に伝えるための信号なのです。
なぜ「ストライプ」なのか?
単色ではなくストライプになっているのは、どの方向から見ても視覚的に認識しやすくするためです。
線の傾斜(おおむね45°)は、静止していても「動き」を感じさせ、視線を自然に引きつける心理効果があります。
また、斜線のパターンが光の反射や汚れによって一部欠けても、模様全体が警告として機能し続けるという利点もあります。
ガードパイプに使われる理由
ガードパイプは、車や自転車が誤って突っ込むのを防ぐ物理的なバリアです。
しかしそれ以前に、まず「ここに障害物がある」と事前に気づかせる視覚的警告である必要があります。
黄色黒ストライプはその役割に最も適しており、
・運転者の視野に入りやすい
・夜間でも街灯の光でコントラストが残る
・汚れても判別しやすい
といった特徴から、全国的に採用されています。
海外でも通用する「共通認識」
黄色と黒の警告模様は、国際的にも共通する安全サインです。
ISO(国際標準化機構)でも、黄色=注意、赤=危険、緑=安全という色体系が採用されており、
工場や空港、港湾設備などでも**「警戒すべき場所」として同じ色使いがされています。
そのため、外国人利用者が多いエリアでも直感的に理解できるデザイン**として機能します。
素材や塗装の工夫
ガードパイプは屋外設置が多いため、塗装には耐候性と耐摩耗性が求められます。
粉体塗装や樹脂コーティングを施し、紫外線や雨水による色あせを防いでいます。
また、夜間の視認性を高めるために反射材入りフィルムを貼るタイプもあり、
「見えること」自体が安全の第一条件として設計されています。
まとめ
ガードパイプが黄色と黒のストライプ模様なのは、JIS規格で定められた注意喚起の標準配色だからです。
黄色が「注意」を、黒が「危険の境界」を示し、ストライプの形状が視線を強く引きつける。
それは単なるデザインではなく、人の心理と安全工学に基づいた、“ぶつからないための色”なのです。