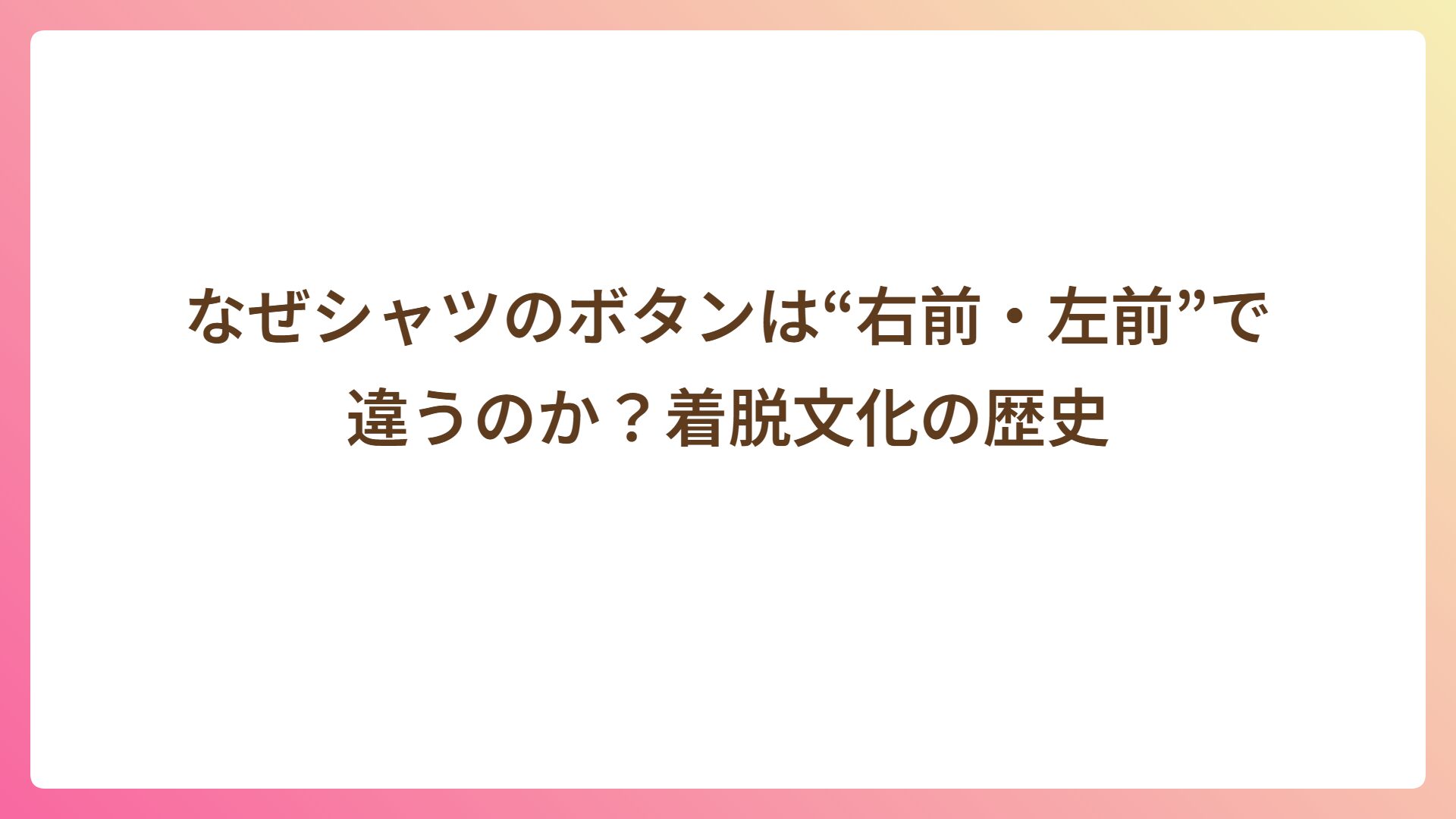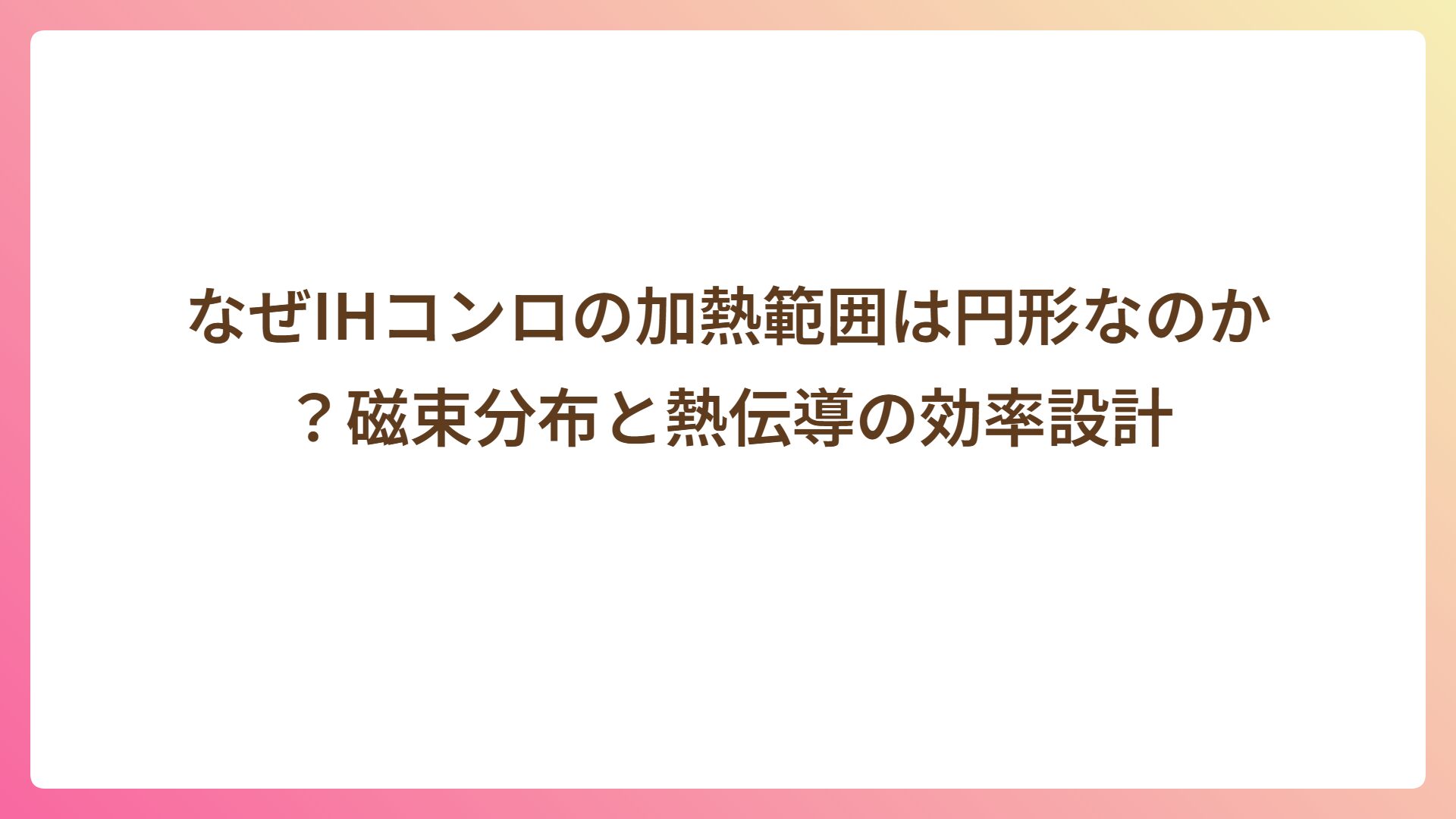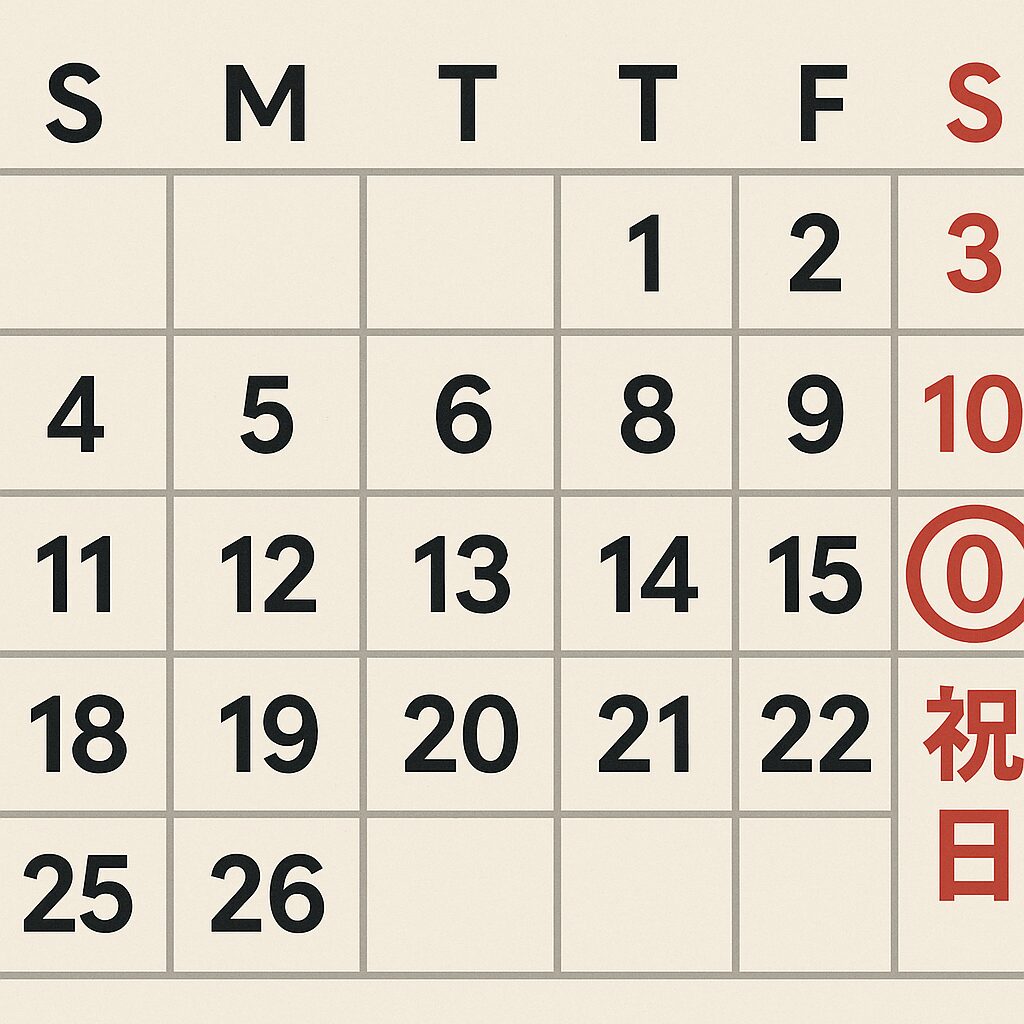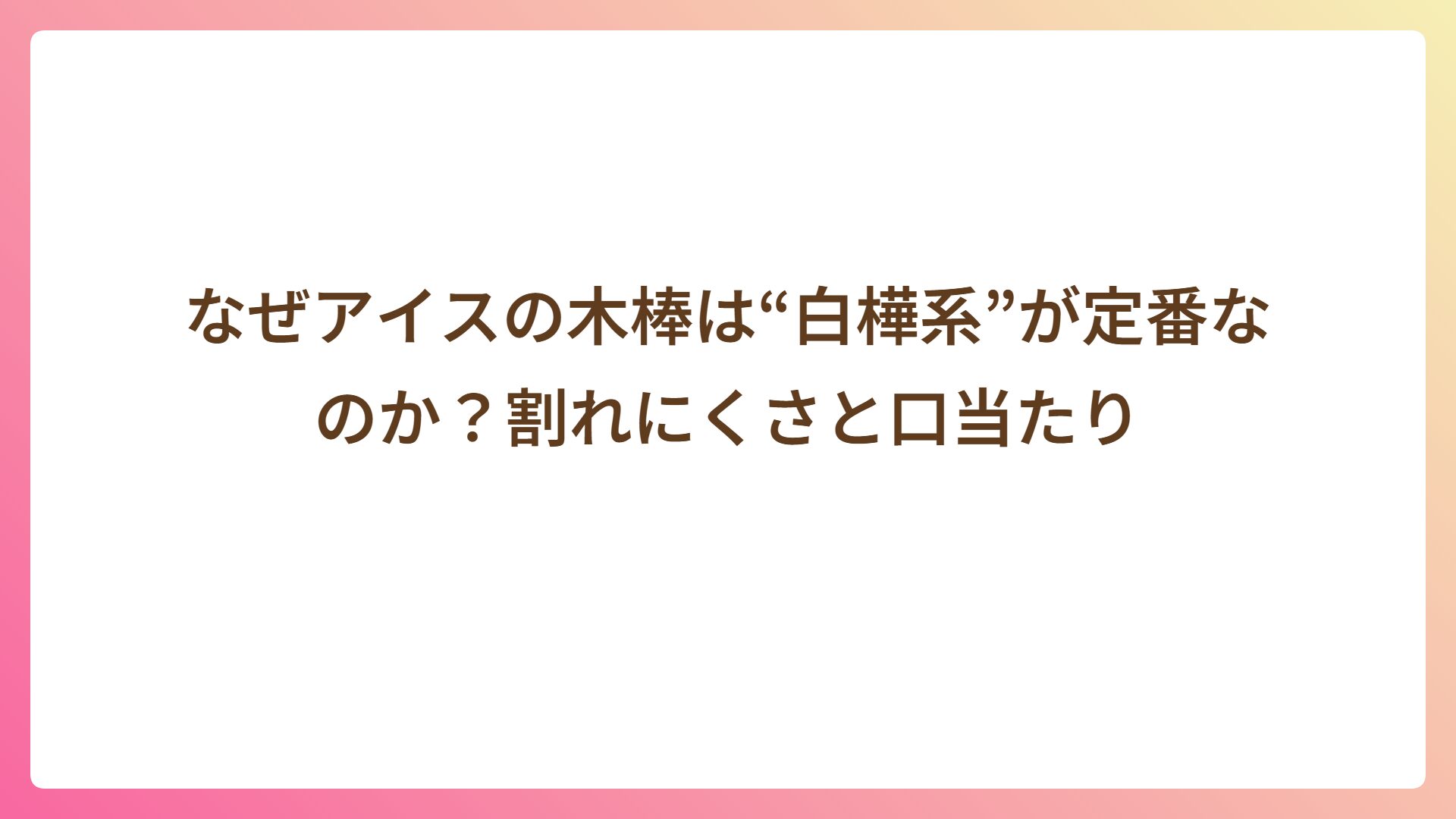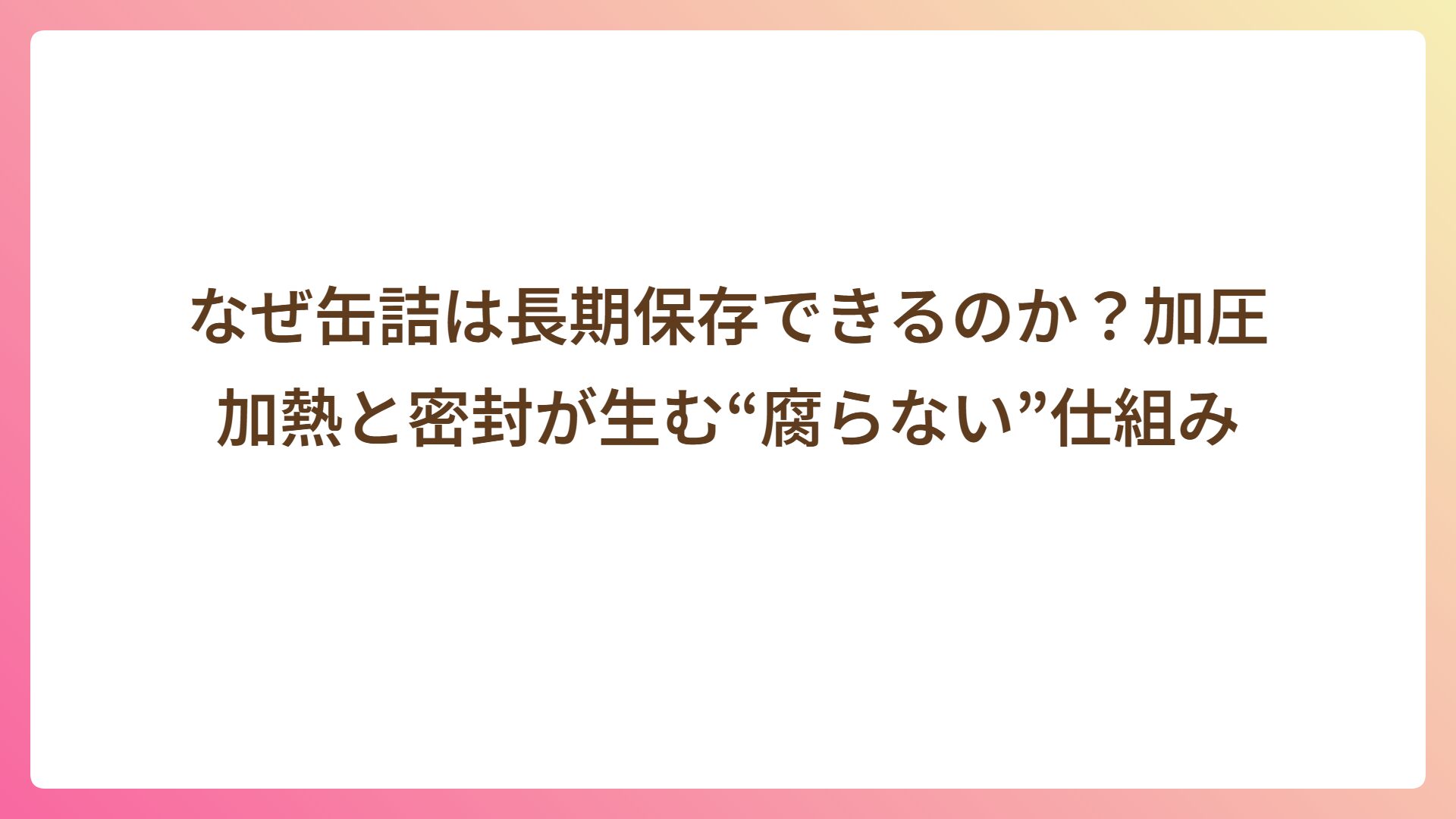なぜ羊乳や山羊乳は普及しにくいのか?風味・流通・法規の壁
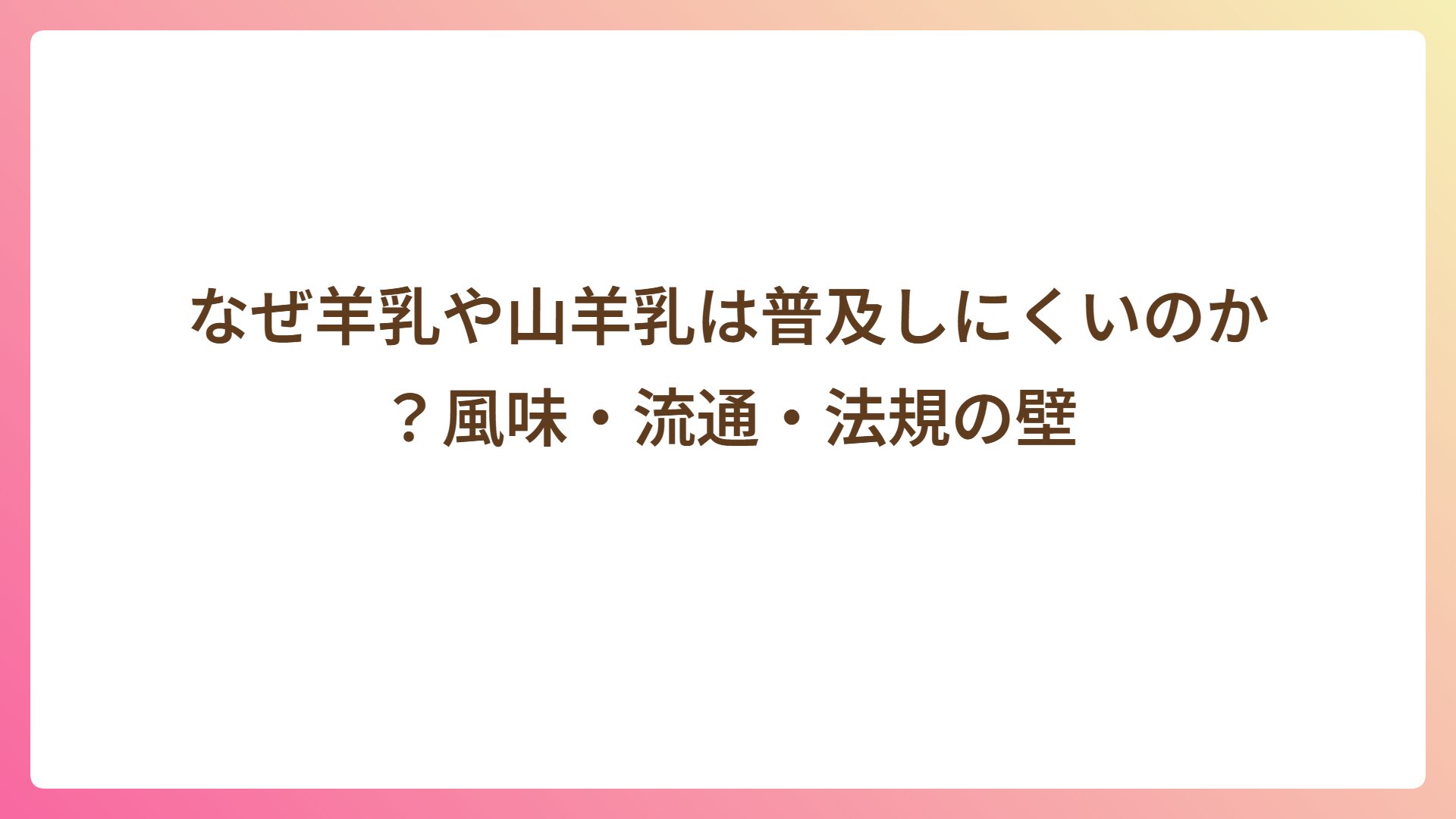
「羊乳」や「山羊乳」は栄養価が高く、チーズの原料にも多く使われています。
しかし、日本のスーパーで見かけるのはほとんど牛乳ばかり。なぜ他の乳は広く普及しないのでしょうか?そこには風味だけでなく、生産・流通・法制度の複合的な理由が関わっています。
風味の個性が強く“飲みづらい”と感じる人が多い
まず最も大きいのが、独特の風味です。
羊乳や山羊乳には、脂肪球が細かく溶け込むためクリーミーで栄養価も高い一方、特有の“獣臭さ”を感じる人が少なくありません。
この香りの正体は、脂肪酸の一種であるカプリル酸(C8)やカプリン酸(C10)など。
これらは山羊(goat=Capra)に由来する名前が付けられており、香り成分としては非常に特徴的です。
冷やして飲めば比較的マイルドになりますが、日本人は牛乳の“無臭でまろやか”な風味に慣れているため、風味の差が心理的なハードルになっています。
生産頭数と乳量が圧倒的に少ない
次に、生産面での制約があります。
牛に比べて、山羊や羊は体が小さく、1頭あたりの乳量が少ないのが特徴です。
- 乳牛(ホルスタイン種):年間約8,000〜10,000リットル
- 山羊:年間約400〜600リットル
- 羊:年間約100〜200リットル
このように、単位あたりの生産効率が10分の1以下。
そのため、規模の経済が働きにくく、1リットルあたりのコストが高くなります。
さらに搾乳期が季節限定で、通年供給が難しいという点も流通面での大きなネックです。
日本の流通網は牛乳前提で最適化されている
牛乳は全国の酪農地帯から集荷・低温輸送され、コンビニやスーパーに並ぶまでのコールドチェーン(低温流通網)が確立しています。
一方、羊乳や山羊乳は生産量が少なく、同規模の流通網を構築するだけでコストが跳ね上がるのが現実です。
特に小規模牧場から都市部への輸送では、単価あたりの輸送費が牛乳の数倍に達することもあります。
また、需要の少なさも物流上の障壁になります。販売量が安定しないと、流通業者も取り扱いをためらうため、市場流通が成立しにくい構造になっているのです。
法規制と衛生基準が高いハードルに
牛乳と同様に、山羊乳や羊乳も「生乳」として扱うには食品衛生法・乳等省令の厳しい基準を満たす必要があります。
日本では、これらの基準が牛乳を基準に設計されているため、少量多品種の生産体制には過剰な負担となるケースもあります。
特に、搾乳設備や殺菌装置を導入するには高額な投資が必要で、小規模牧場では採算が取れないのが現状です。
結果として、商品化できるのはチーズやヨーグルトなど日持ちする加工品に限定されがちです。
海外では一般的でも“文化の定着”が違う
ヨーロッパでは、羊乳チーズ(ペコリーノ、ロックフォール)や山羊チーズ(シェーブル)などが伝統的に食文化に根づいています。
しかし日本では、牛乳中心の酪農体系が戦後から一貫して続いており、他乳への親しみが薄いまま今日に至っています。
つまり、単に風味やコストの問題だけでなく、「食文化としての基盤がない」ことも大きな要因なのです。
まとめ:合理性より“慣習の強さ”が勝っている
羊乳や山羊乳は栄養価の面では牛乳を上回る部分もあります。
それでも普及しにくい理由は次の通りです。
- 特有の香りが好みを分ける
- 生産量が少なくコスト高
- 流通網・法規制が牛乳前提
- 日本では食文化として根づかなかった
こうした要因が重なり、「牛乳の独占的地位」が維持されているのが現状です。
ただし、アレルギー対応や高栄養食としての注目も高まりつつあり、今後は“個性派ミルク”として新たな市場を開く可能性もあります。