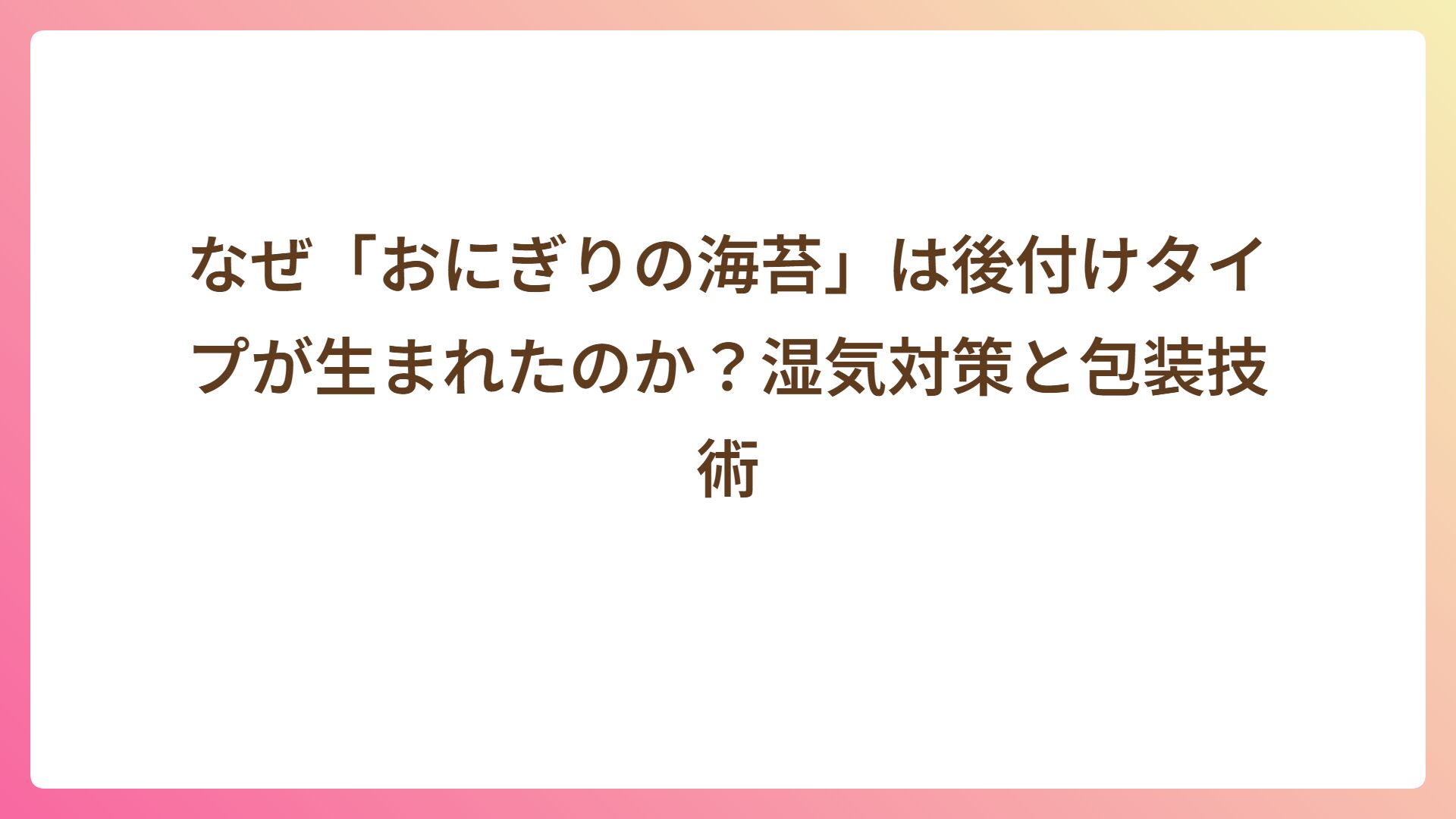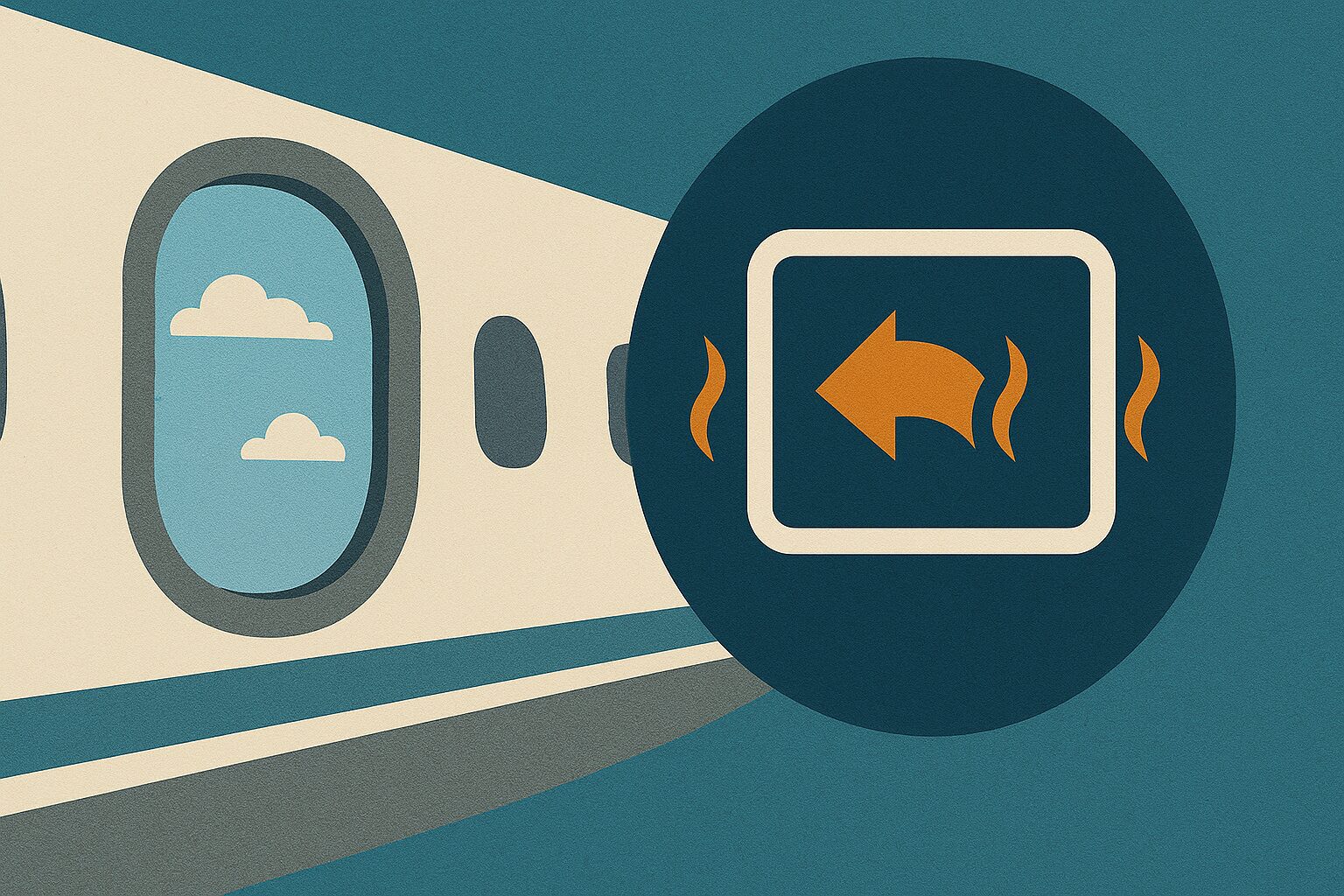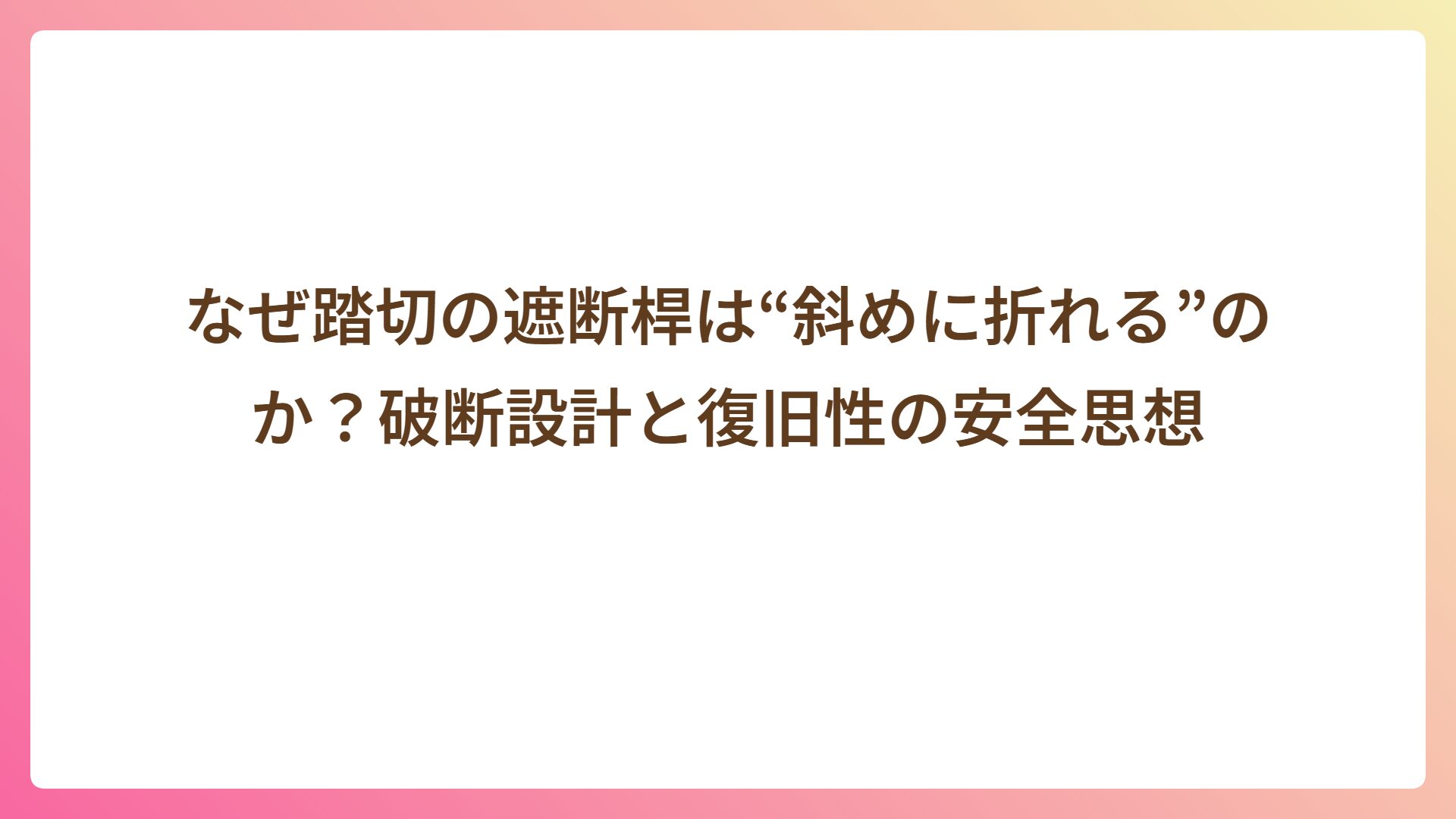「おしぼりそば」の名前の由来とは?別名「ねずみそば」と呼ばれる理由
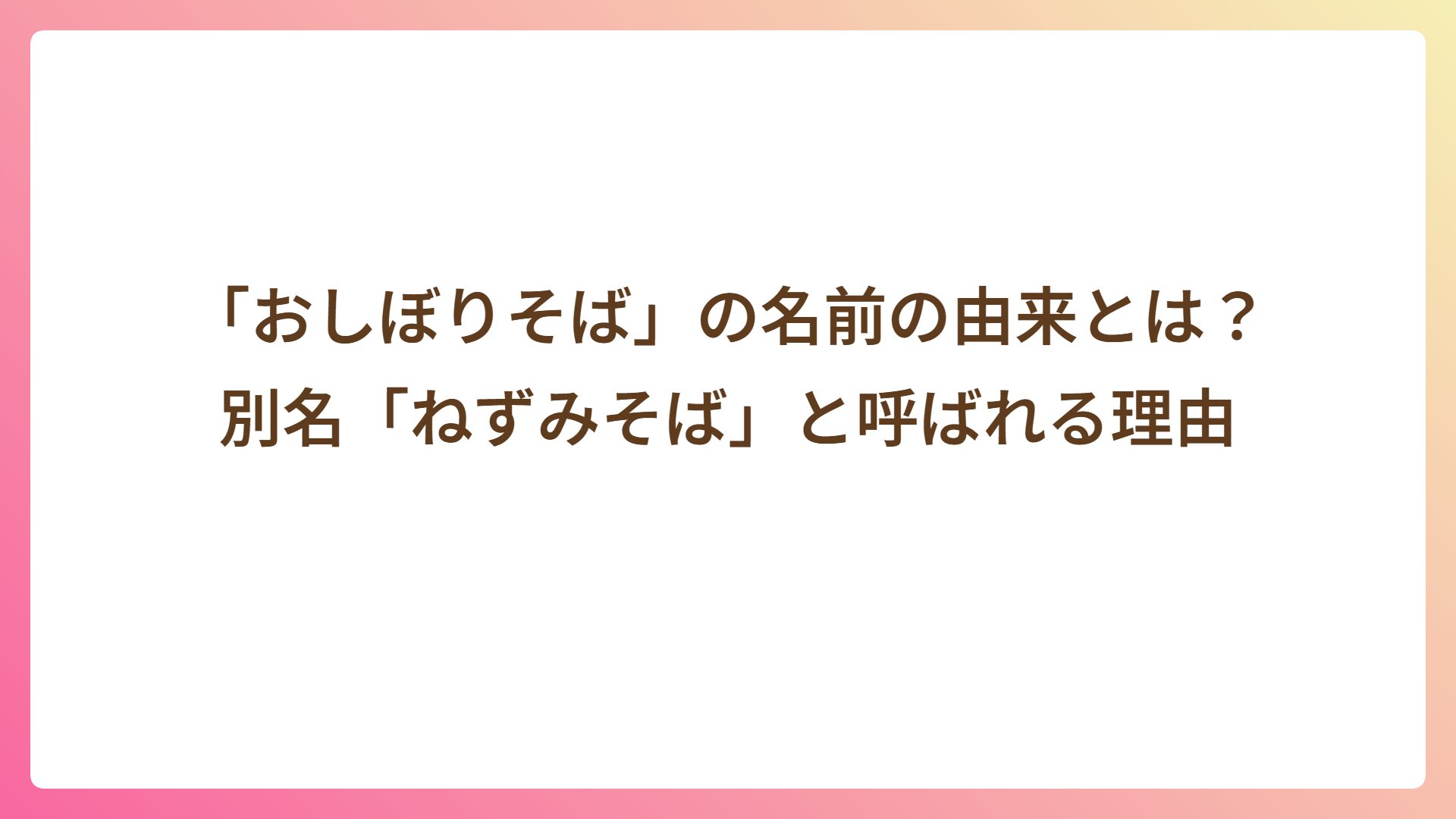
長野県を中心に親しまれる郷土料理「おしぼりそば」。すりおろした辛味大根の絞り汁につゆを加えて食べる独特のそばですが、なぜ“おしぼり”という名前がついたのでしょうか?また、なぜ一部地域では「ねずみそば」とも呼ばれるのでしょうか?その名前の由来をたどると、信州の食文化の知恵が見えてきます。
「おしぼりそば」は大根を“しぼる”ことから
「おしぼりそば」の語源は、辛味大根をおろして絞るという調理工程にあります。
このそばでは、まず辛味の強い地大根をすりおろし、布や手ぬぐいでぎゅっと絞り、その絞り汁にそばつゆを加えていただきます。
つまり、「おしぼり」とは手を拭くおしぼりではなく、大根をしぼる動作そのものを指しているのです。
この食べ方は江戸時代の信州地方で生まれたとされ、冬場でもそばをさっぱりと楽しめる方法として定着しました。
「ねずみそば」と呼ばれるもう一つの理由
同じ料理が「ねずみそば」と呼ばれるのは、見た目の色合いに由来します。
辛味大根の絞り汁はやや濁った灰色をしており、その上に白いそばが盛られると、全体がねずみ色のように見えるのです。
そのため、地元では「ねずみそば」と呼ぶ地域もあり、特に長野県東御市や坂城町などでは両方の呼び名が併用されています。
つまり「おしぼりそば」と「ねずみそば」は同じ料理の別名であり、呼び方の違いは地域の言葉や見た目の印象によるものなのです。
大根の辛味が生む“信州らしさ”
おしぼりそばに使われる辛味大根は、信州の冷涼な気候で育つため、通常の大根よりも辛味と香りが強いのが特徴です。
この辛味がそばの甘みを引き立て、つゆの味を引き締める役割を果たします。
地元では、酒の肴としても親しまれ、そばの本来の香りを楽しむ通の食べ方として愛されています。
まとめ:しぼり方と色が生んだ二つの名
「おしぼりそば」という名前は、大根をしぼる調理法から生まれた言葉。
そして「ねずみそば」という別名は、大根汁の灰色がかった見た目に由来します。
どちらも信州そば文化を象徴する呼び名であり、地域の風土と味覚の知恵が詰まった一杯なのです。