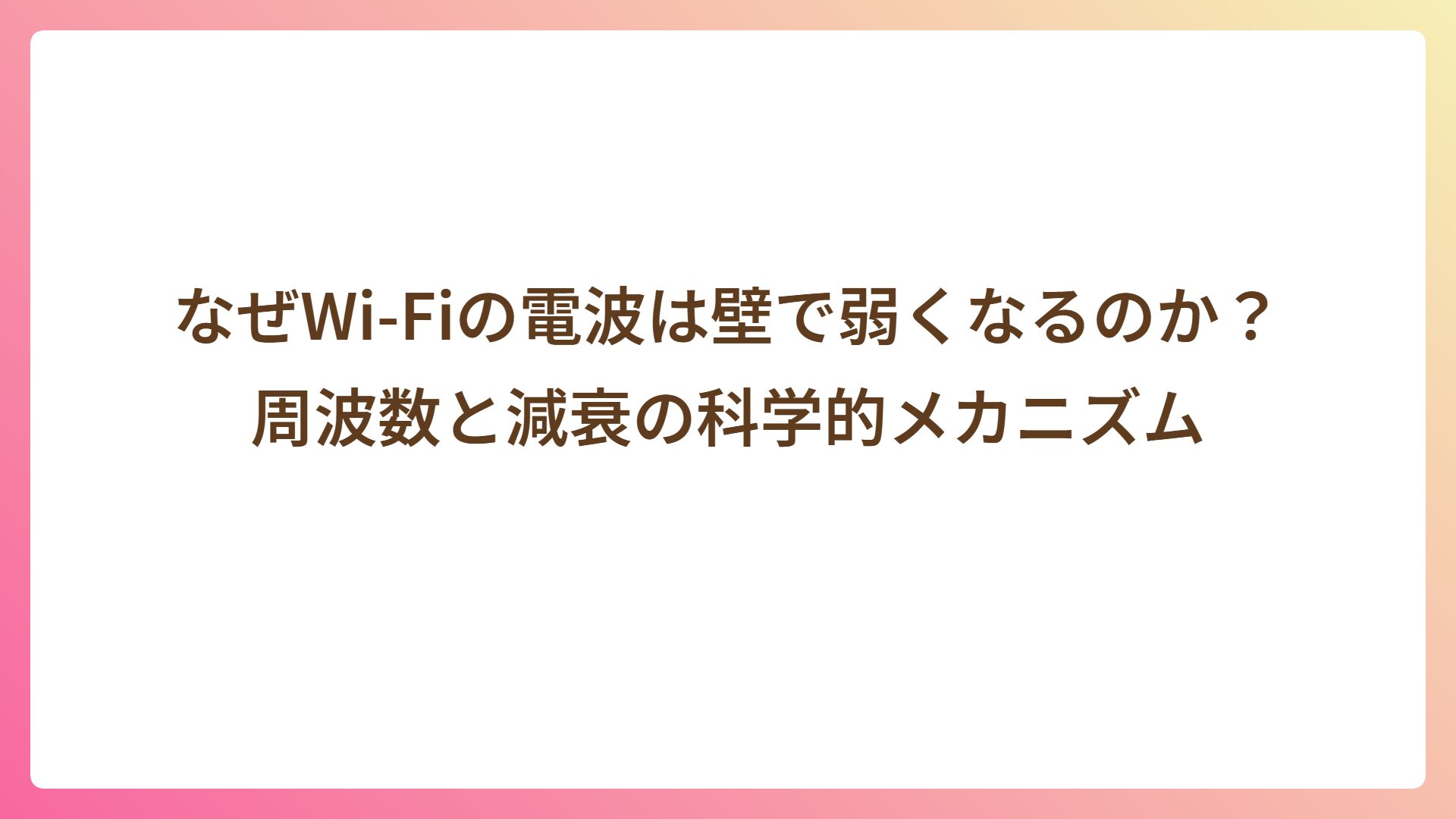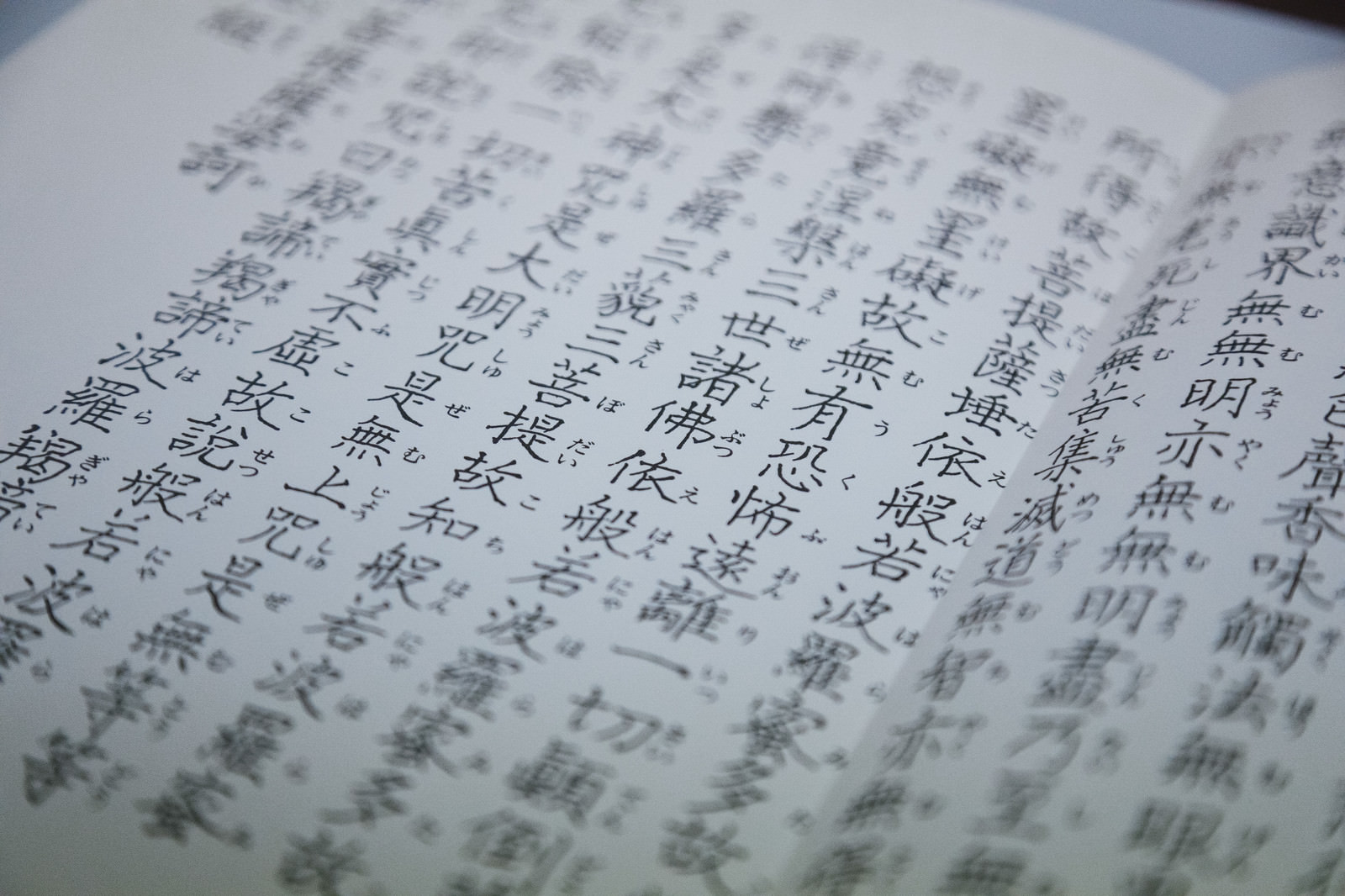「サバを読む」の語源とは?なぜサバで年齢をごまかすのかを解説!

「サバを読む」という表現を聞いたことがある人は多いでしょう。
たとえば、年齢や身長などを少しごまかすとき、「サバを読んだ」と言ったりしますよね。
「あの芸能人、実は2歳サバを読んでるらしい」など、ニュースや会話でもよく登場するこの慣用句ですが、改めて考えてみると「なぜ“サバ”なの?」という疑問が湧いてきます。
マグロやホッケ、イワシではなく、なぜサバ?
その由来には、サバの鮮度の落ちやすさと、魚市場の事情が関係していました。
サバは鮮度が落ちやすく、ごまかしやすい魚だった
サバは非常に鮮度の落ちるのが早い魚として知られています。
見た目は新鮮そうでも、実際には腐敗が始まっていることもあるため、「サバの生き腐れ」という言葉まであるほどです。
しかも、サバは大量に漁獲されるため、市場ではスピード勝負で数を数える必要がありました。急いで数える中で、実際の数がズレたり、ごまかされたりすることも珍しくなかったのです。
こうした背景から、「サバを読む」=「数をごまかす」という意味が生まれたとされています。
「読む」は本来「数える」という意味
「読む」という言葉は、ふつう「本を読む」「文章を読む」などのように使われますが、もともとの意味は「数を数えること」でした。
たとえば、選挙の際に票の数や動向を予測することを「票読み」と言いますね。
このように、「読む」には「計算する・予測する・数える」といった意味があるのです。
つまり、「サバを読む」の「読む」は、単純に“数を数える”の意味。
そこに“ズレ”や“ごまかし”が加わることで、「実際の数字とは違うことを言う」という意味合いになったわけです。
他にもある「サバを読む」語源の説
「サバを読む」の語源には他にも複数の説があります。
- 魚市場のことを昔は「いさば」と言った →「いさばを読む」が転じた説
- サバを数える際、2尾で1刺しとして計算していた → 実数とのズレが生じた説
いずれも共通するのは、数をざっくり計算する/ごまかす場面があったことです。
これが語源として定着したのでしょう。
サバが傷みやすいのはなぜ?
補足として、サバがなぜ傷みやすいかについても触れておきましょう。
サバの筋肉にはヒスチジンというアミノ酸が多く含まれています。
このヒスチジンは死後すぐに酵素によってヒスタミンという物質に変化し、それがアレルギーや蕁麻疹(じんましん)などの食中毒を引き起こす原因になります。
昔は保存技術も乏しく、サバはとくに注意が必要な魚でした。
現代では冷凍や冷蔵技術が発達したため、安全に食べられるようになっています。
しかもサバには、DHAやEPAといった脳や血管に良い成分も豊富に含まれています。
「サバを読む」どころか、サバを食べて健康になるほうが賢明かもしれませんね。
「サバを読む」は魚市場から生まれたリアルな言葉
「サバを読む」という表現は、もともと市場での不正確な数え方や、ごまかしの場面から生まれたものでした。
- サバの鮮度の問題
- 大量の取引における数のズレ
- 「読む」=「数える」という本来の意味
これらが合わさって、今のような慣用句として定着したのです。
普段何気なく使っている表現にも、こんな歴史や背景があると知ると、ちょっと面白くなりますよね。