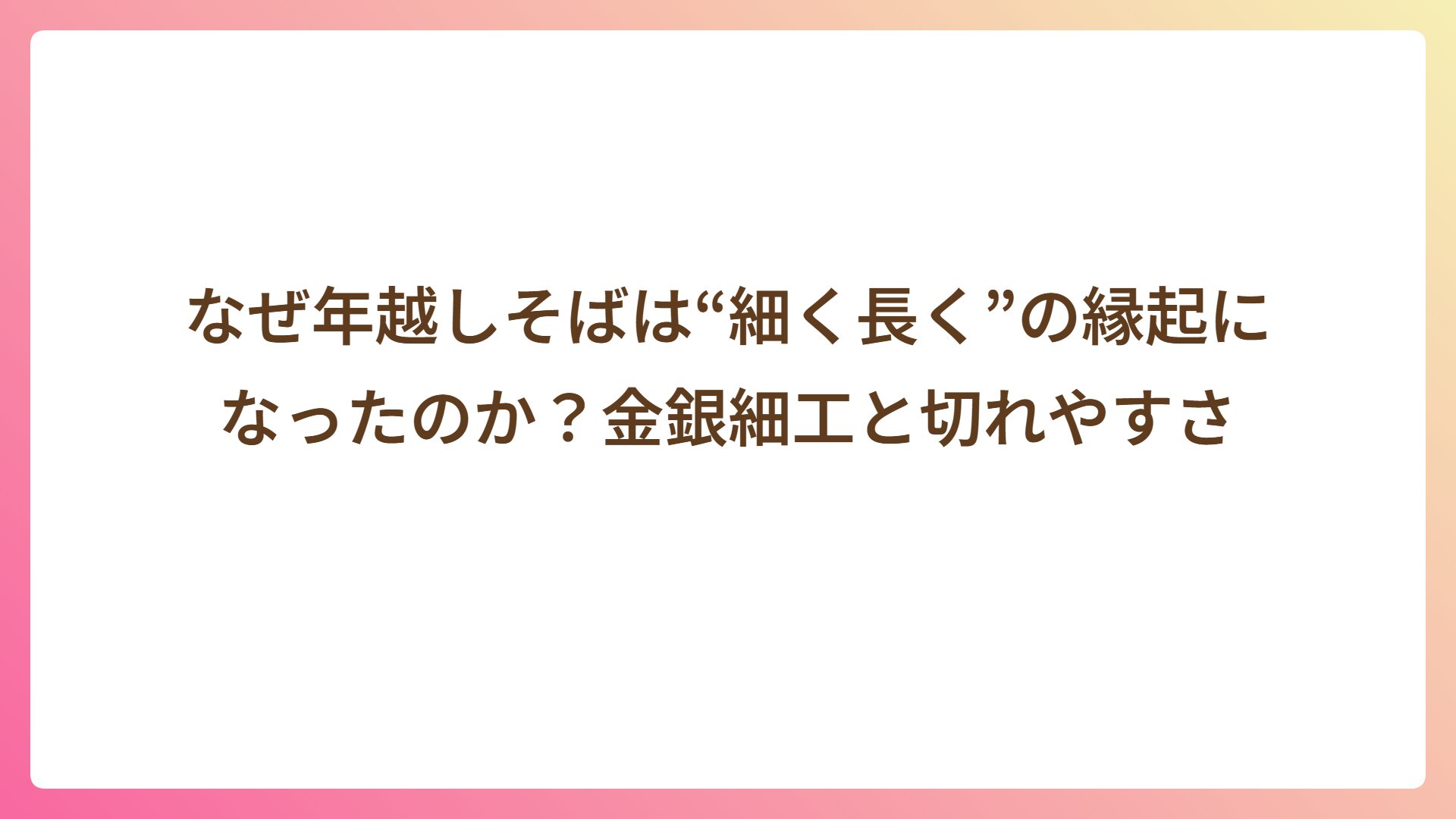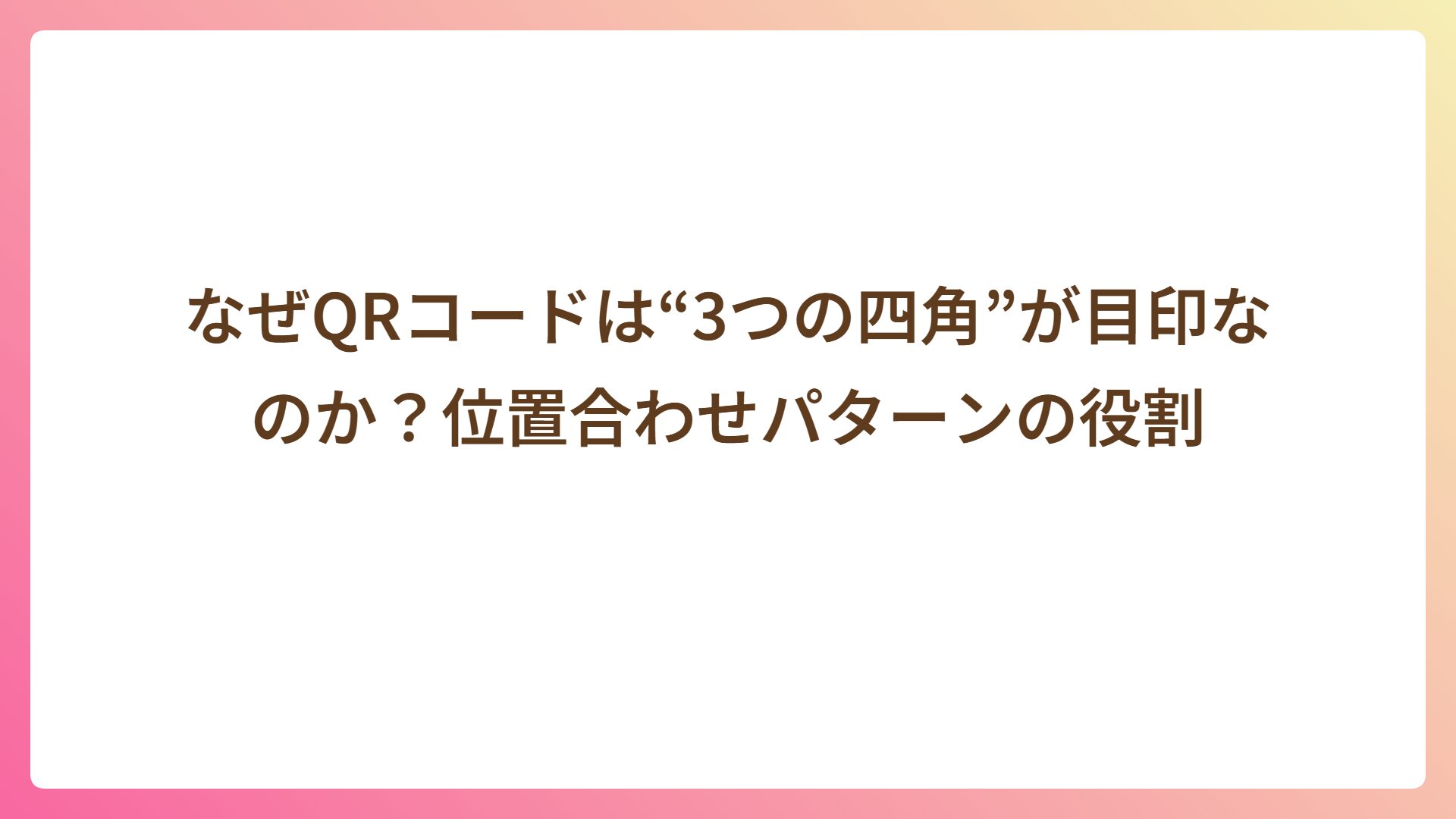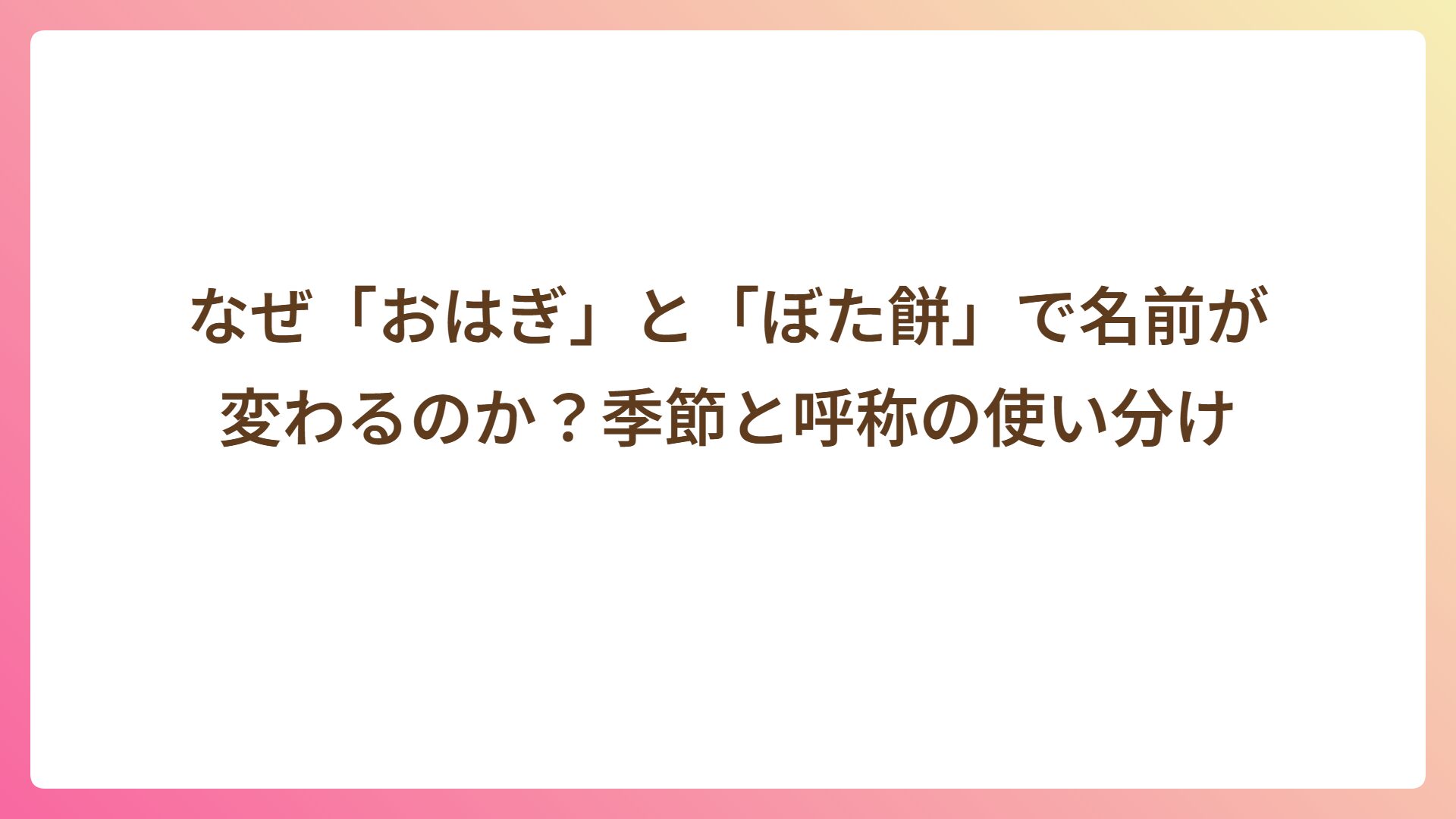現存する最古の自動販売機は切手やハガキを売っていたって本当?日本に残る“自販機の原点”の物語
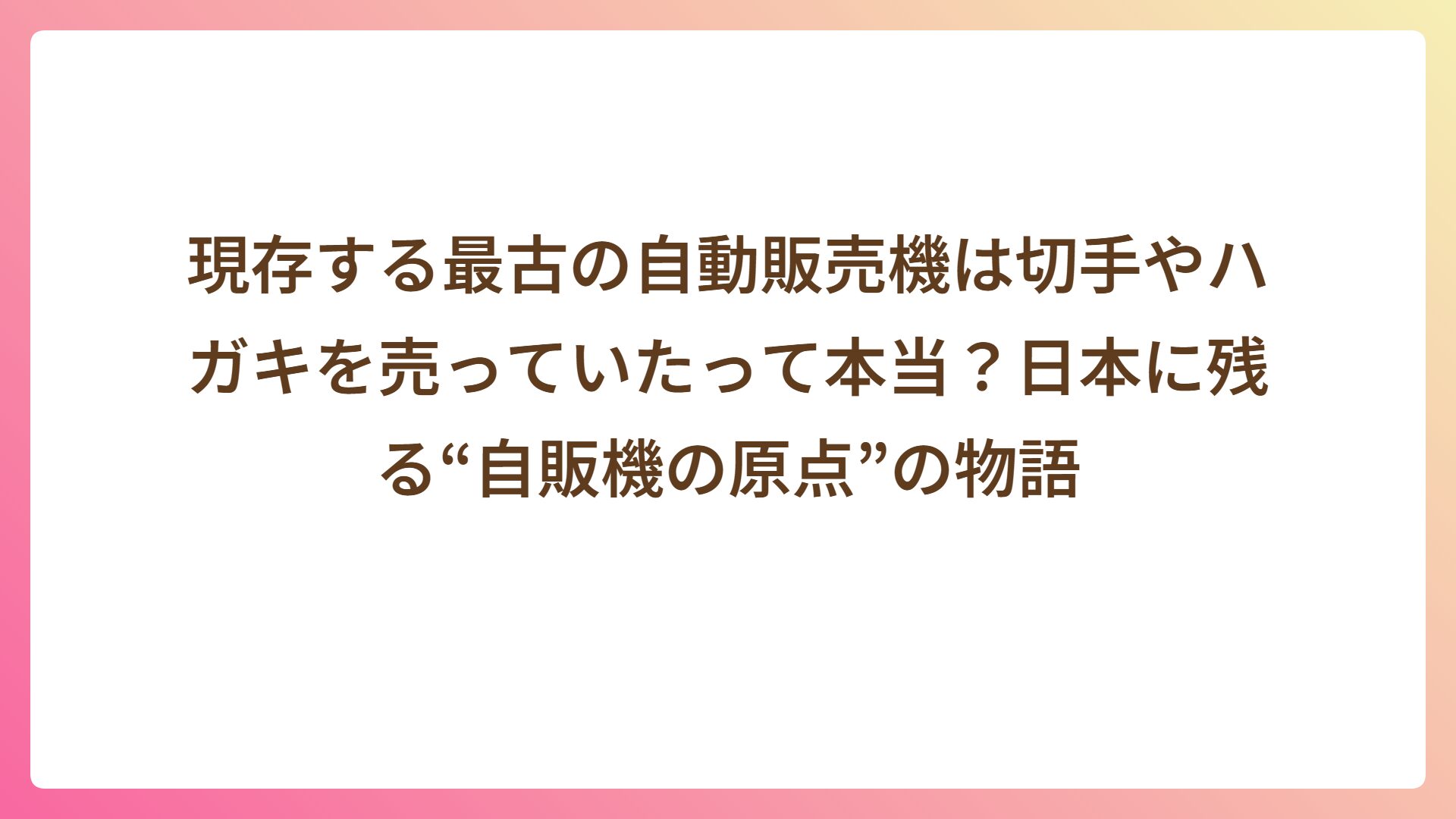
清涼飲料やお菓子など、今や日本の街角に当たり前に並ぶ自動販売機。
しかし、その起源をたどると、最初に売られていたのは切手やハガキだったのをご存じでしょうか?
現存する最古の自販機は、飲み物でもタバコでもなく、郵便用品を売るために作られたものでした。
現存する最古の自販機は「郵便切手葉書自働販売機」
日本国内で現存する最古の自動販売機は、1904年(明治37年)に製造された「郵便切手葉書自働販売機」です。
この機械は、当時の逓信省(現在の日本郵便)によって導入され、郵便局の窓口が閉まっていても切手やはがきを購入できるようにするために設置されました。
硬貨を入れると、一定の重さや大きさを感知して作動し、内部の仕組みが回転して切手やはがきを1枚ずつ排出する――という、極めてシンプルなメカニズムです。
現在は、逓信総合博物館(ていぱーく)の後継施設や、郵政資料館などに実物が保存されています。
世界的にも非常に古い“自販機”
この「郵便切手葉書自働販売機」は、世界的に見ても極めて初期の自販機にあたります。
世界最古の自販機は、古代エジプトの神殿に設置された“聖水を出す装置”(ヘロンの自動販売機)とされていますが、近代的なコイン式の自販機としては19世紀末のイギリスが最初期。
日本でこの仕組みが導入されたのはそのわずか十数年後であり、世界でもトップクラスに早い導入例だったのです。
つまり日本の郵便局は、当時すでに自動化・省人化を意識した先進的な試みを行っていたことになります。
なぜ切手やはがきが最初に選ばれたのか
明治時代の郵便利用は急速に拡大しており、窓口業務が非常に混雑していました。
特に夜間や休日にも郵便を出したい人が多く、「人がいなくても買える仕組み」が求められていたのです。
そこで選ばれたのが、常に一定のサイズ・価格・需要がある切手とハガキ。
こうして日本最古の自販機は、便利さと効率化を両立する郵便サービスの一環として誕生しました。
技術的にも先進的だった明治の自販機
この自販機は完全に機械式で、電力を使わずに動作していました。
投入された硬貨の重みを利用して内部の歯車が回転し、正しい金額であれば商品が出る仕組み。
不正防止のための仕掛けも備わっており、単なる箱ではなく精密な機構を持つ装置でした。
その構造は、現在の自販機にも通じる“硬貨認識+機械的分配”の基本原理を先取りしていたといえます。
まとめ:自販機のルーツは“郵便の便利化”から
現存する最古の自動販売機は、飲み物ではなく切手やハガキを売るための装置でした。
それは単なる機械ではなく、郵便サービスを24時間使えるようにするという明治時代の合理化の象徴でもあります。
今や世界中に広がった自販機文化の原点は、意外にも“手紙を出す便利さ”を追求した日本の郵便から始まっていたのです。