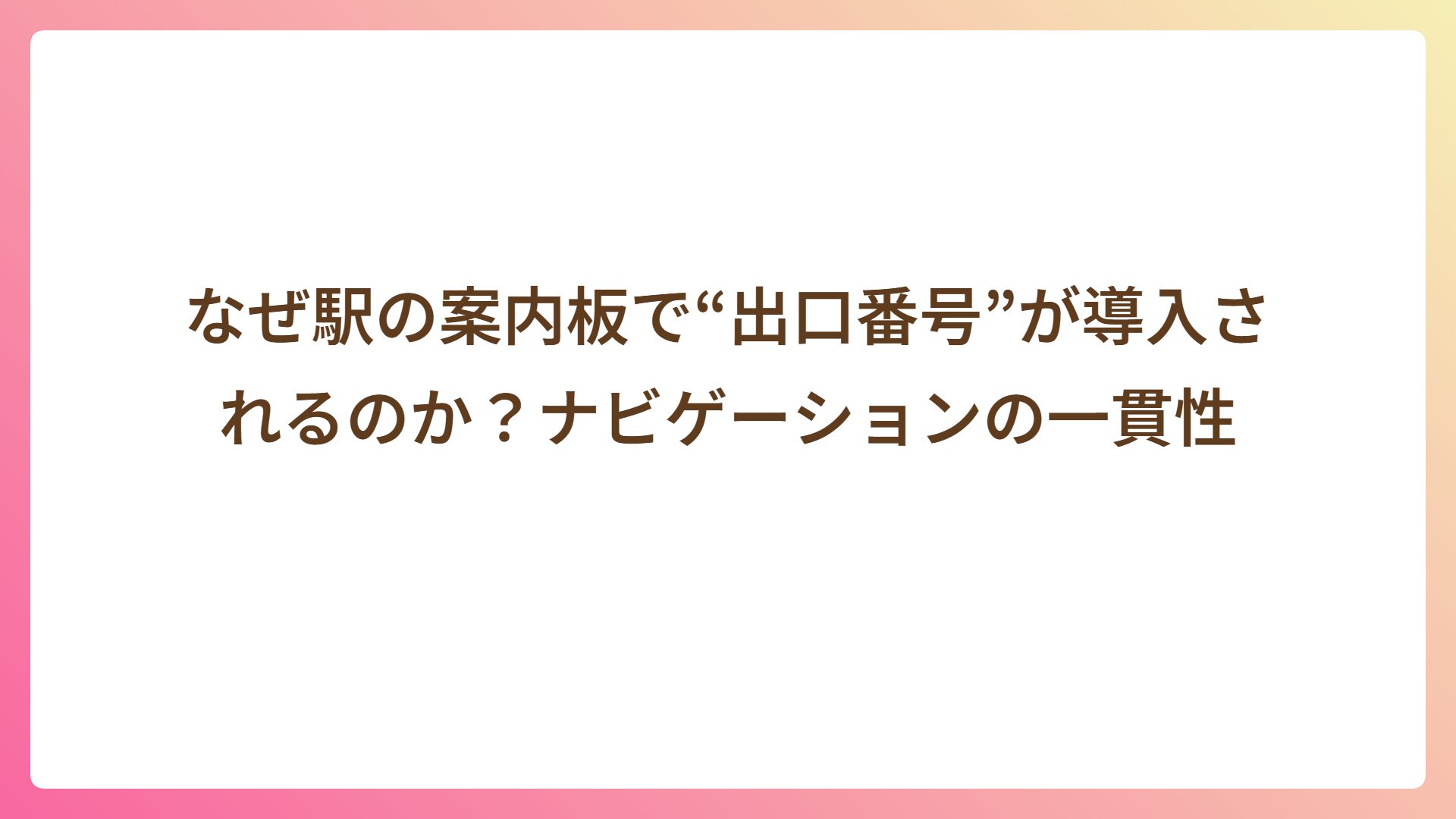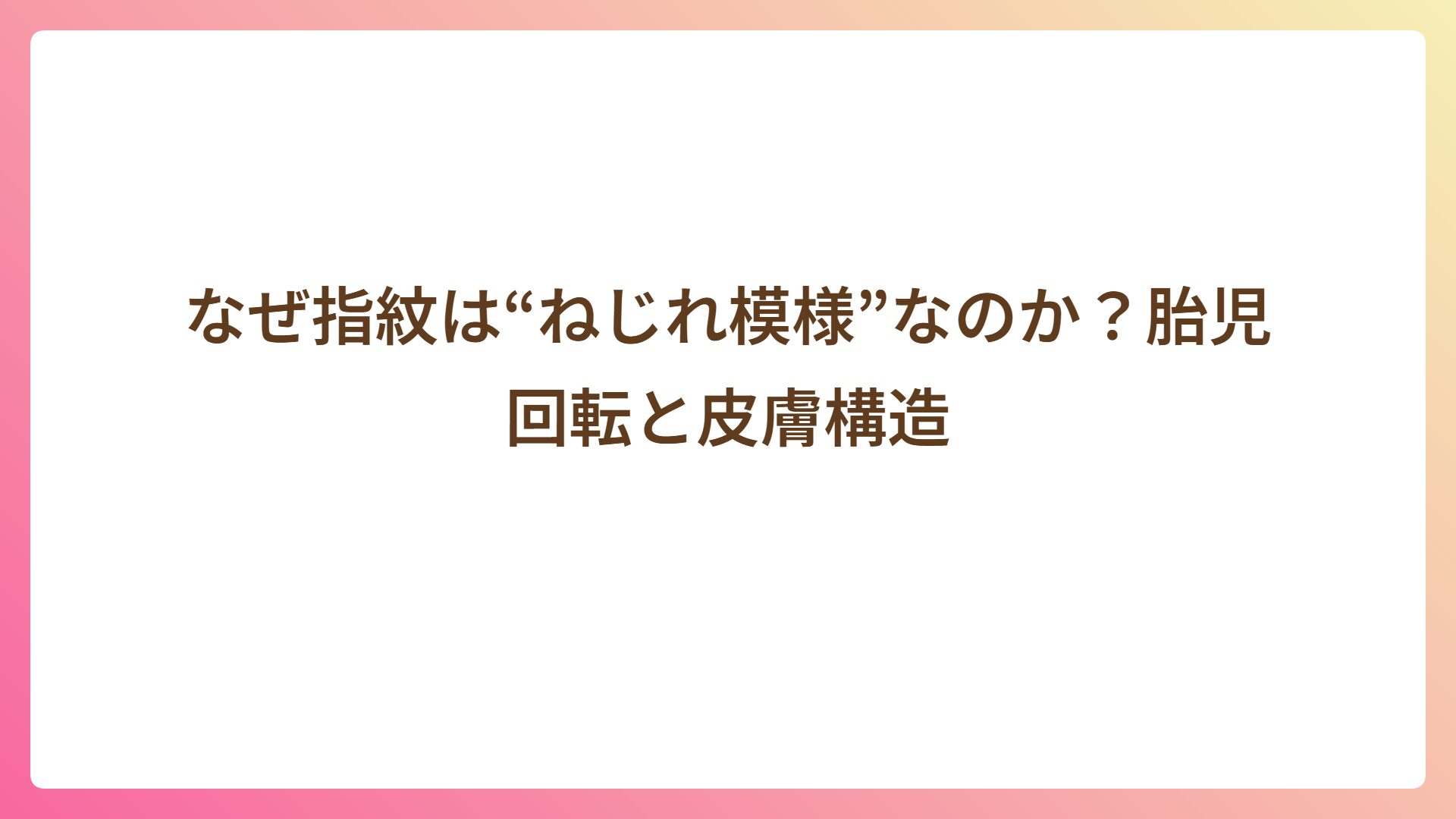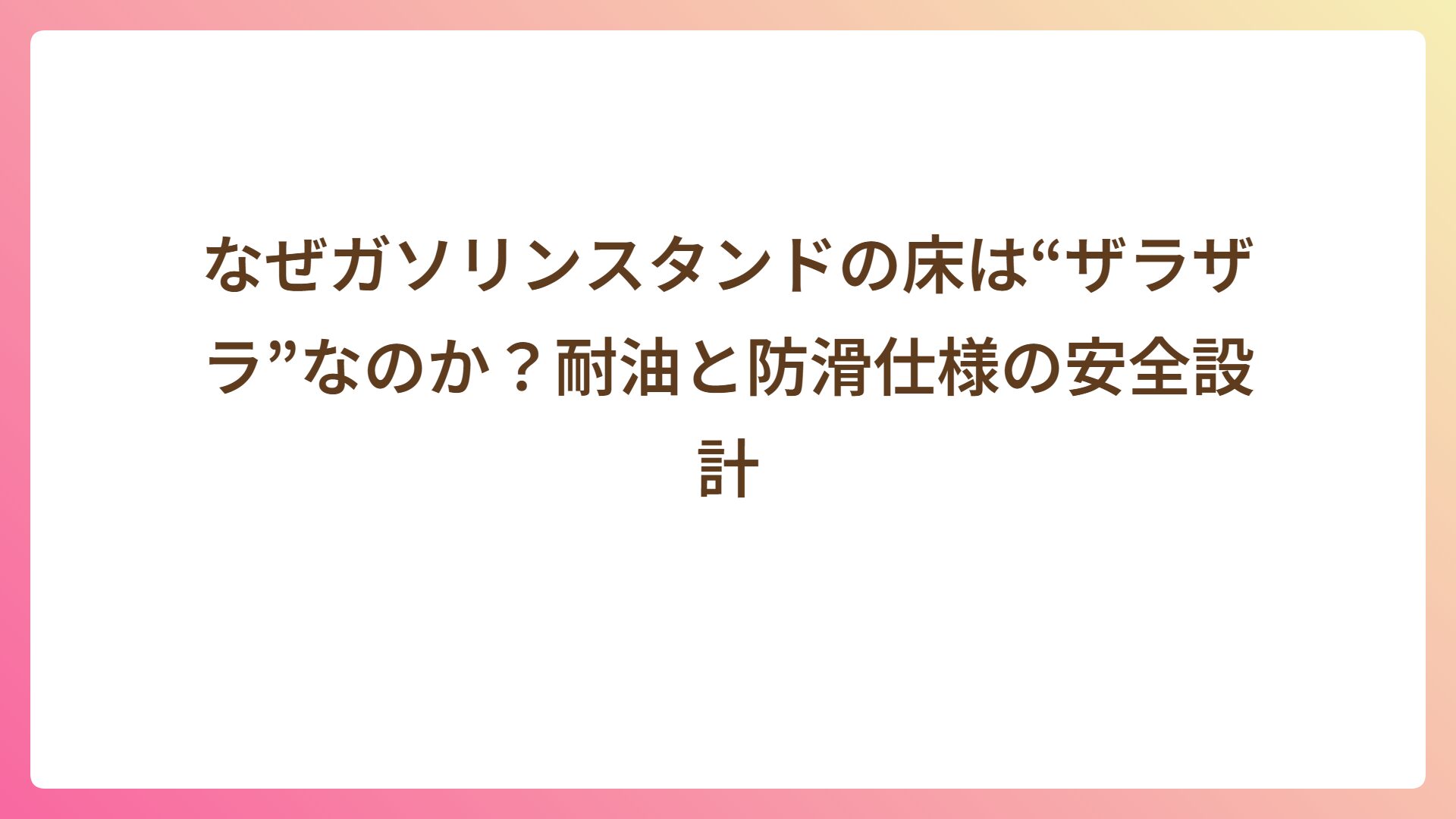なぜたくあんは“黄色”なのか?色づけの歴史と現在
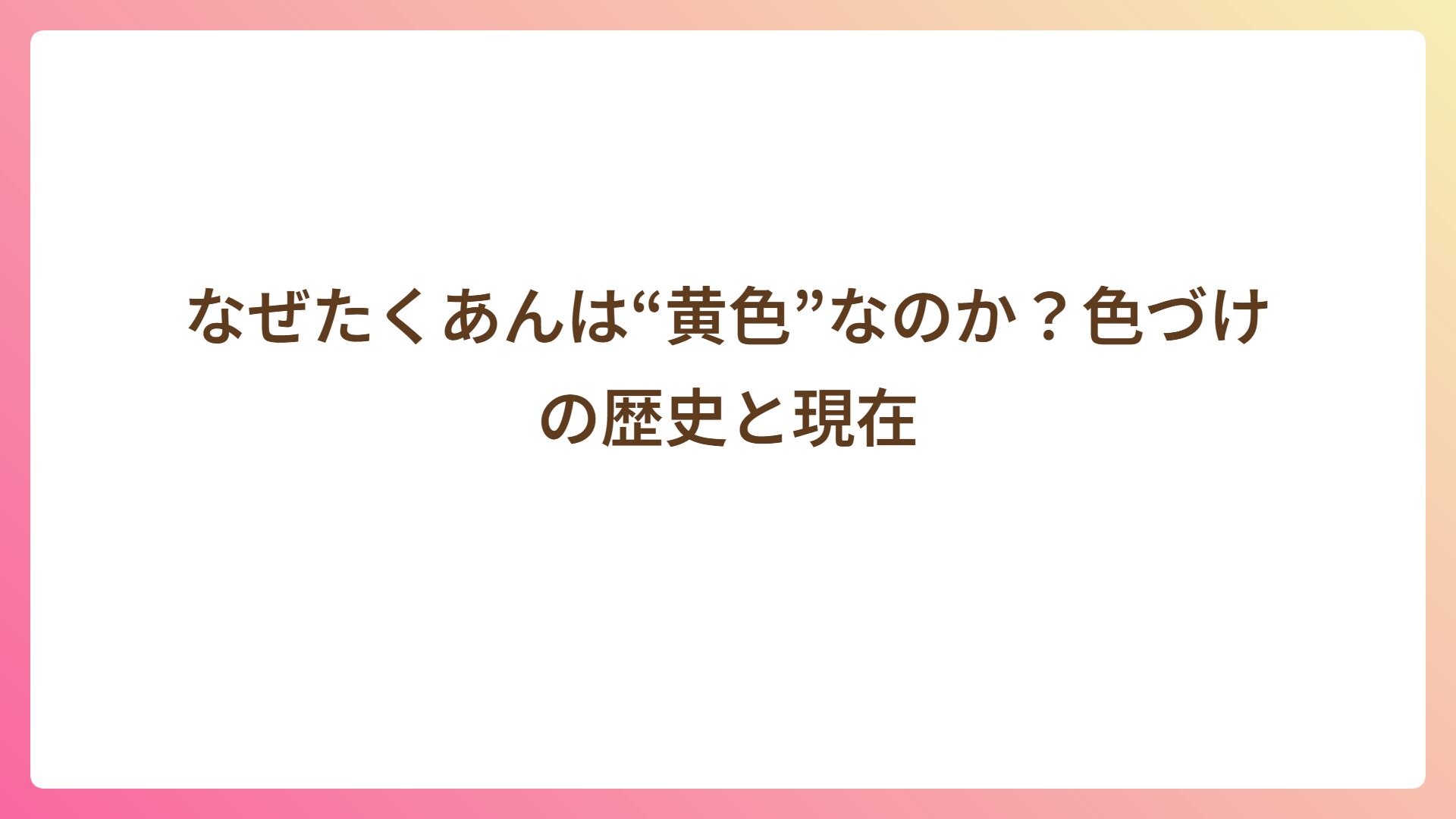
お弁当や定食の端に添えられる「黄色いたくあん」。
見慣れた色ですが、なぜ漬け物がここまで鮮やかな黄色をしているのでしょうか?
実はこの色、自然発酵・伝統色・食品加工技術の三つの時代を経て作られてきたものなのです。
たくあんはもともと“白っぽい漬物”だった
たくあんは、干した大根を米ぬか・塩・こんぶなどで漬け込んだ保存食。
その名前は、江戸初期に沢庵和尚が考案したとされることから来ています。
漬け上がり直後の伝統的なたくあんは、白〜薄い黄土色。
これは、
- 米ぬか中のアミノ酸や糖分が発酵によって褐変する
- 大根の成分と酸素が反応して黄味を帯びる
といった自然発酵による色づきによるものでした。
つまり、もともとのたくあんは現在のような“鮮やかな黄色”ではなく、
もっと地味で素朴な色合いだったのです。
江戸後期〜明治期に“見栄え”が求められる
江戸時代後期になると、商業的に大量のたくあんが作られるようになります。
このとき「見た目が良いほうが売れる」として、
より明るく美しい黄色を出す工夫が始まりました。
その代表がくちなしの実による天然色づけ。
くちなしの果実に含まれるカロテノイド系色素「クロシン」が、
漬け込むことで大根にやわらかな黄金色を与えます。
この天然の黄色が「食欲をそそる」「日持ちが良さそう」と評判になり、
やがて“たくあん=黄色”というイメージが定着しました。
戦後の“合成着色料時代”
戦後、食品産業が大量生産化すると、
天然色素では色ムラやコストの問題が出てきます。
そこで登場したのが、タール系合成着色料(食用黄色4号・5号など)。
これらは少量で鮮やかな発色が得られ、
保存中も退色しにくいため、
1950〜1980年代にかけて多くのたくあんが人工的な黄色で着色されました。
コンビニや駅弁で見られる“レモンのような黄色”のたくあんは、
この時代の名残なのです。
現代は“無着色・自然派”へ回帰
しかし、1980年代以降、
食品添加物への意識が高まるにつれて、
「着色料を使わないたくあん」が再び注目され始めました。
現在では、
- くちなしやウコンなどの植物由来色素を使用
- 無着色・自然発酵色のたくあんを販売
といった、健康志向・自然志向の潮流が主流になっています。
特に昔ながらのぬか漬けや干し大根仕込みのたくあんは、
時間をかけて熟成させることで、
自然な黄褐色と深い旨味が生まれます。
黄色には“保存”と“心理効果”の両面も
黄色は古来から「太陽・豊穣・幸福」を象徴する色であり、
食卓でも食欲を増進させる暖色とされています。
発酵食品であるたくあんにこの色をまとわせることで、
「元気」「健康」「保存の安心感」を視覚的に伝える効果もあったのです。
つまり、黄色は単なる見た目ではなく、
長期保存食としての信頼と明るい印象を兼ね備えた色だったのです。
まとめ
たくあんが黄色いのは、
発酵の自然な黄化 → 天然色素 → 合成着色 → 無添加回帰という歴史の積み重ねによるもの。
- 米ぬか発酵で自然に黄ばむ
- くちなしで彩りを強調
- 合成着色料で鮮やかさを量産
- 現代は自然色・無着色へと回帰
その黄色には、
時代ごとの美意識・技術・安全志向の変遷が映し出されているのです。