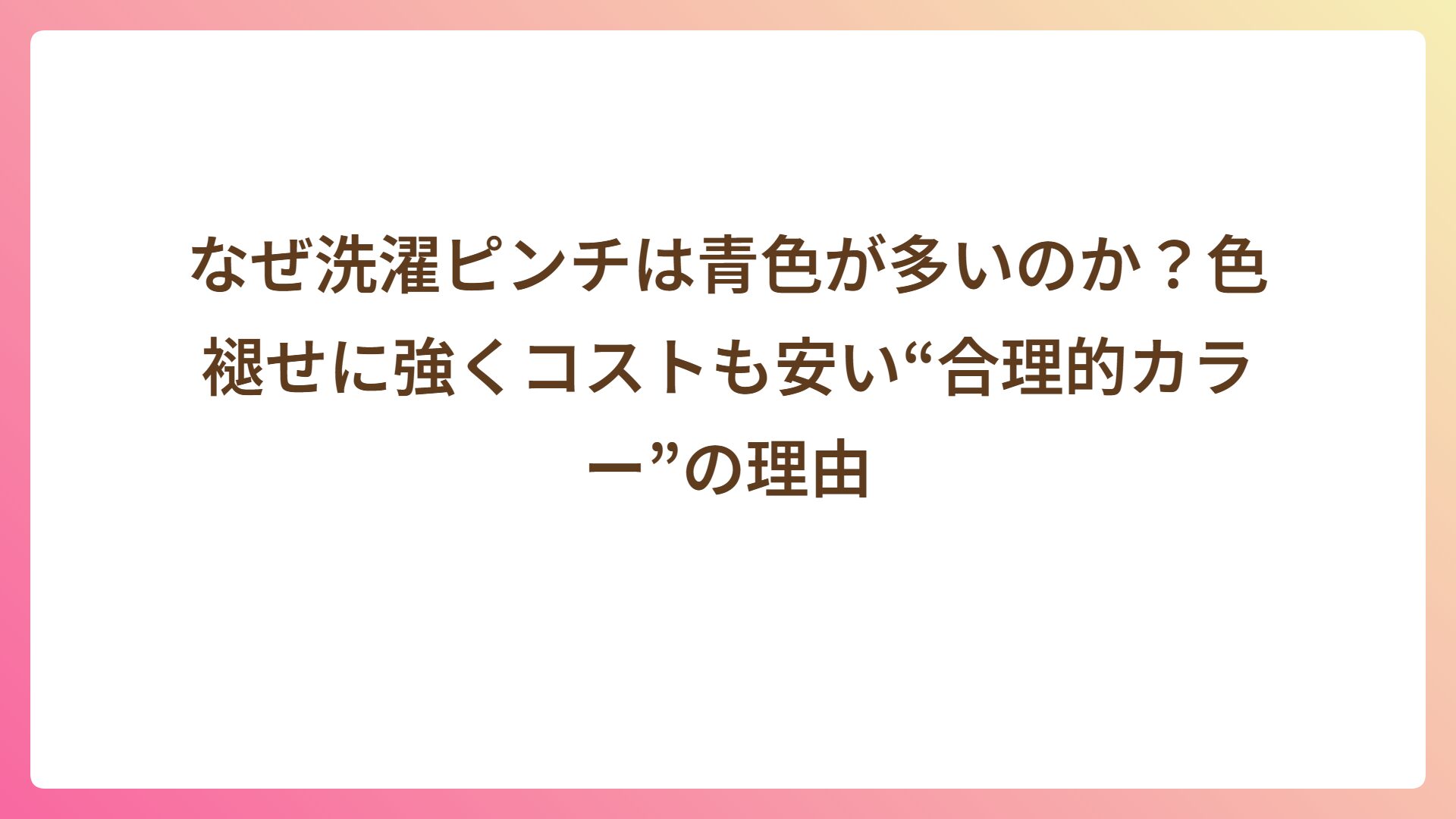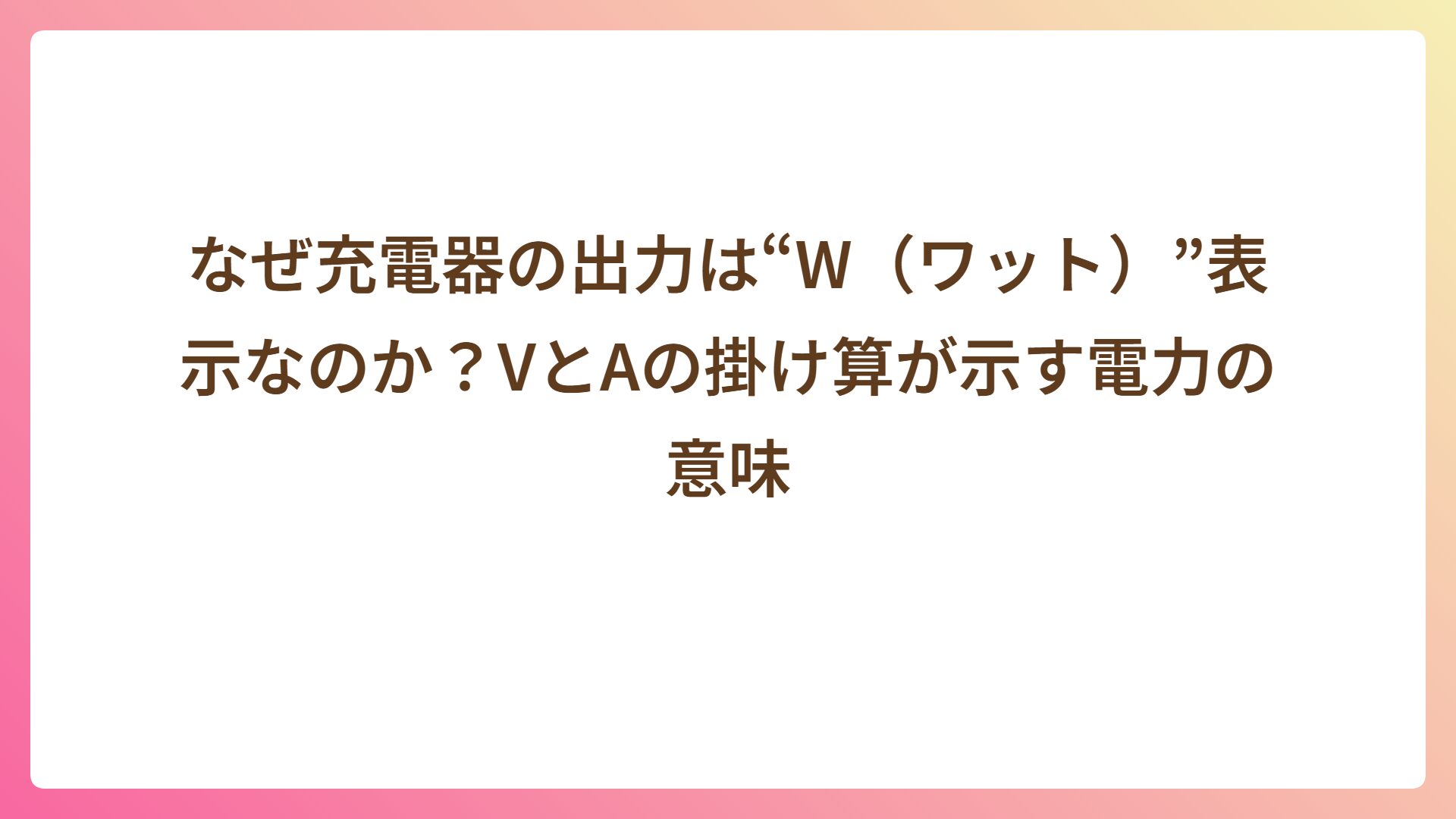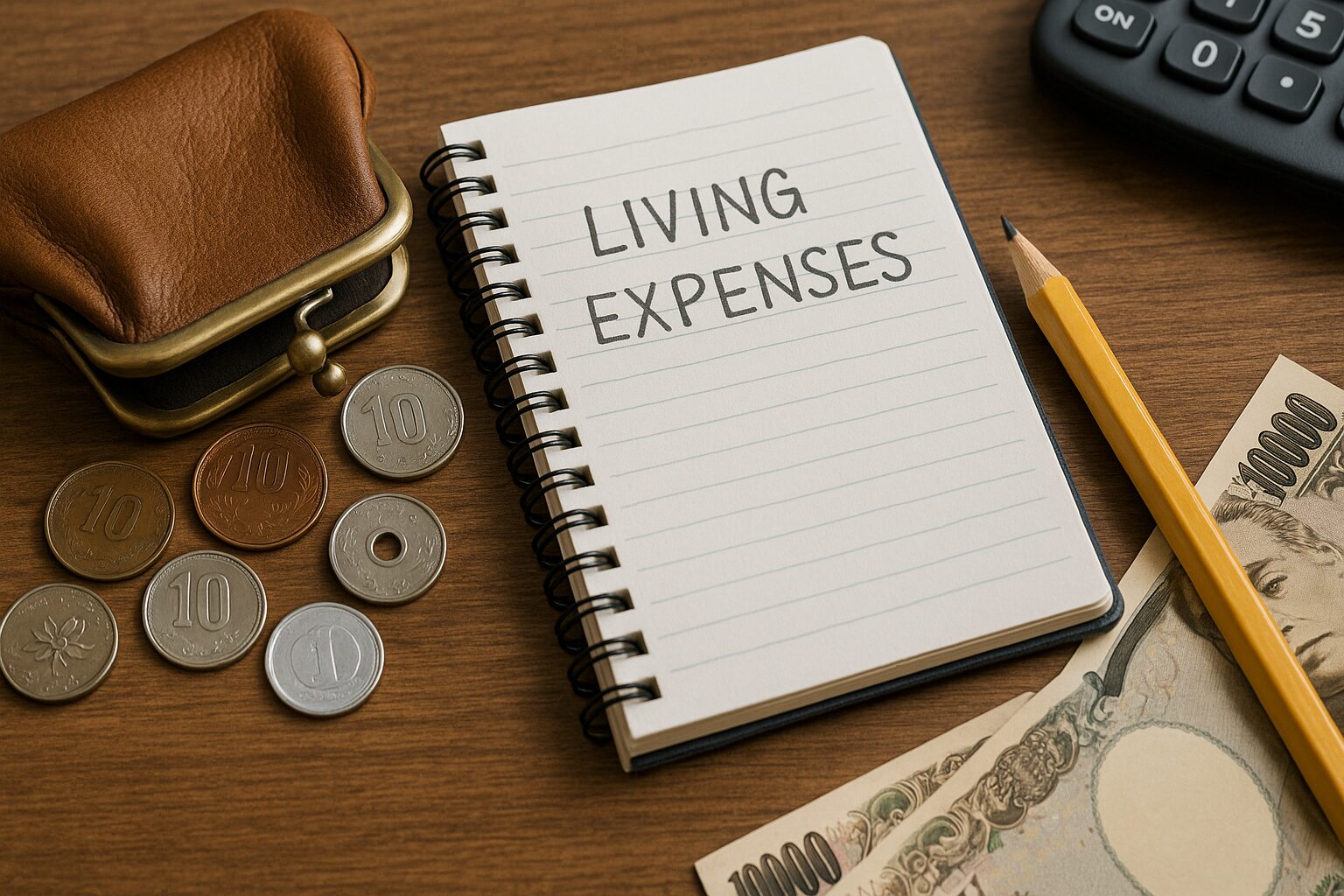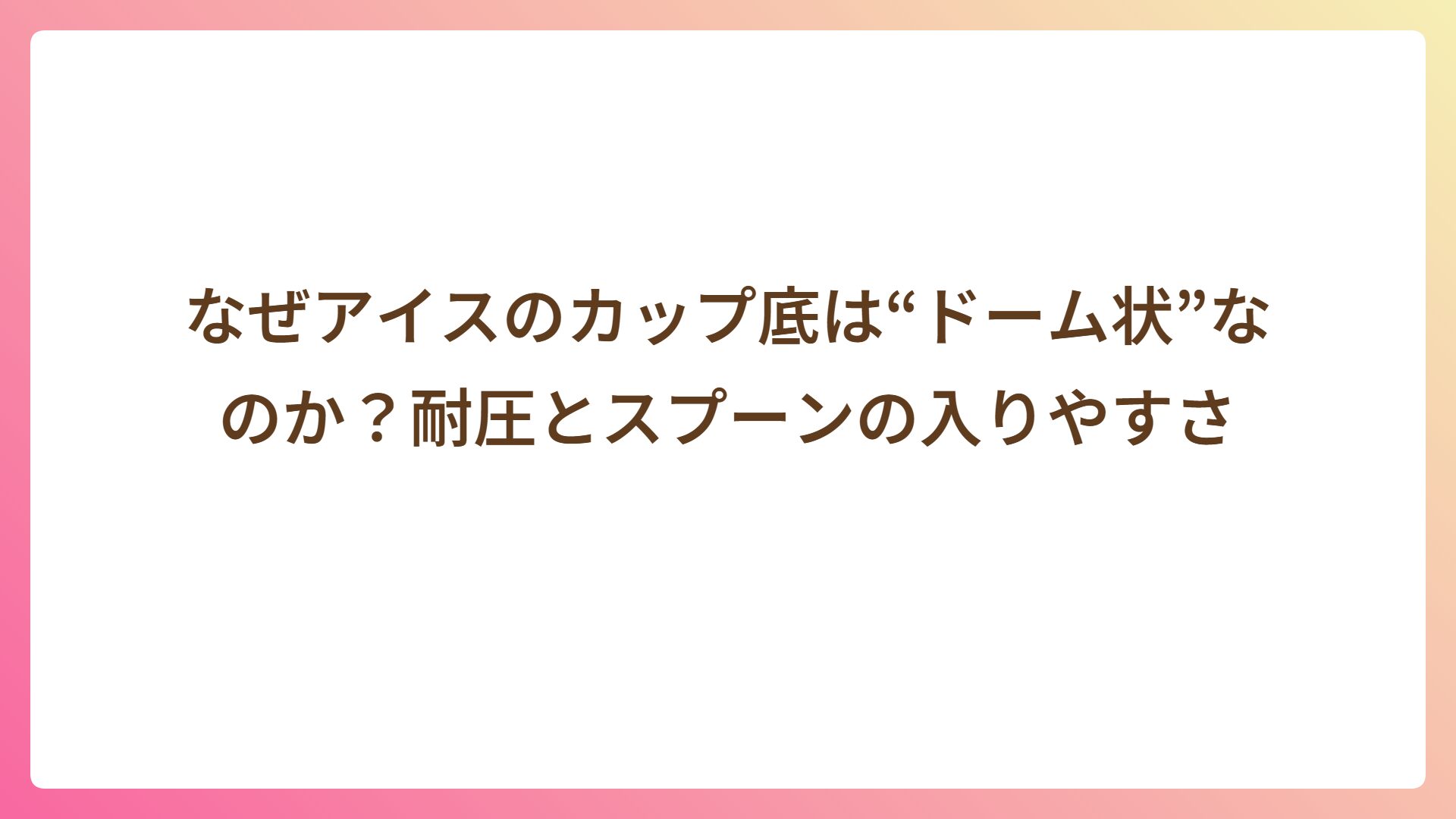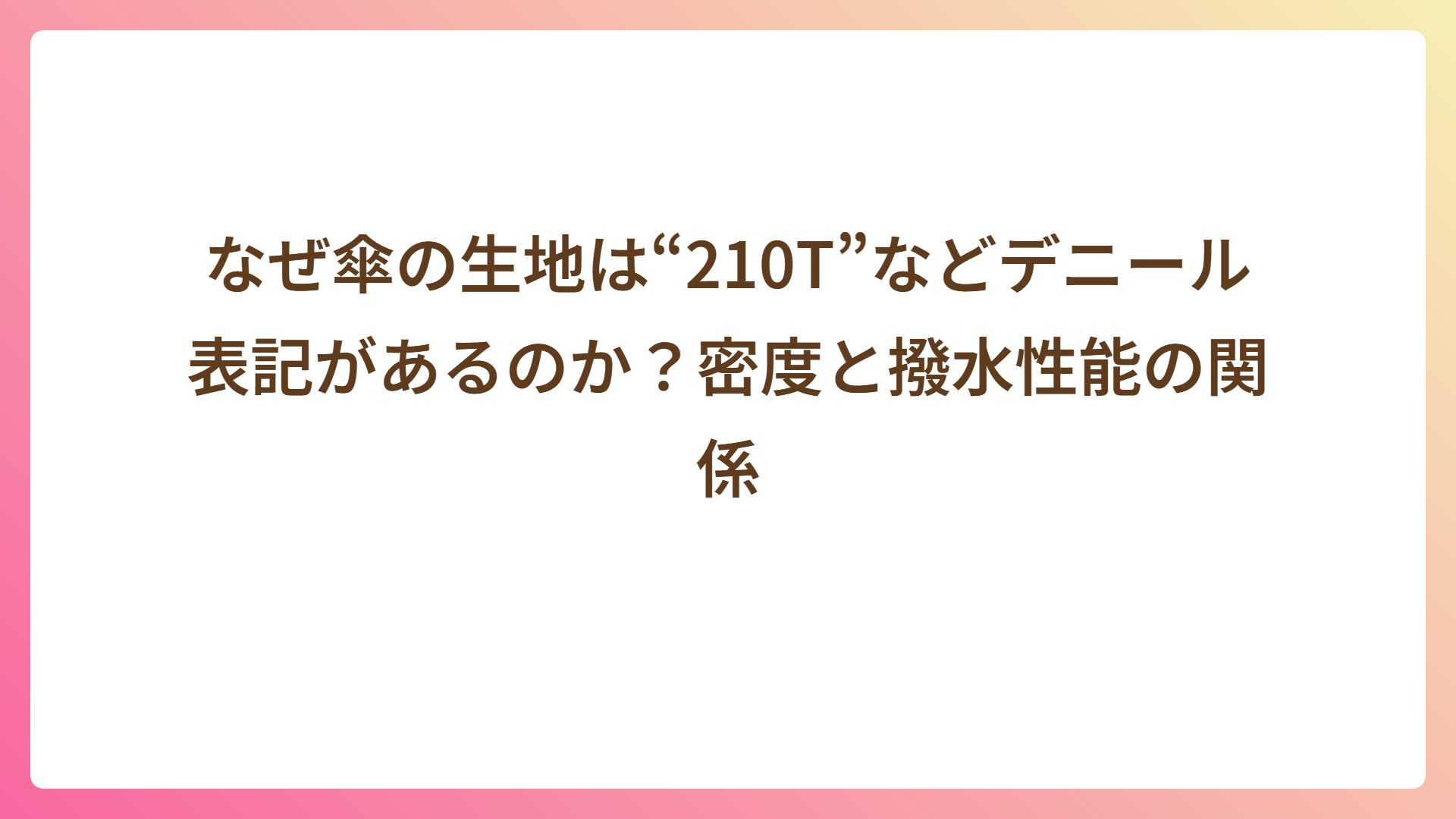都道府県の違いは何?「府」や「道」が存在する理由とその歴史とは?

日本の行政区分は「1都1道2府43県」、計47都道府県で構成されています。
ですが、「全部まとめて“県”でいいのでは?」と感じたことはありませんか?「都」や「府」「道」といった区分は、なぜ今も残っているのでしょうか。
今回は、都道府県の違いや由来について、歴史をもとに解説していきます。
明治初期は「府」と「県」の違いがあった
現在のような都道府県制度が始まったのは、明治時代に入ってからのことです。
明治元年(1868年)、新政府は旧幕府の直轄地を行政区分として整理するにあたり、重要な都市は「府」、それ以外は「県」と定めました。
このとき誕生した「府」は以下の10か所です。
- 箱館府(北海道)
- 東京府
- 神奈川府
- 越後府
- 甲斐府
- 京都府
- 大阪府
- 奈良府
- 度会府(三重県南部)
- 長崎府
しかし翌年には、東京・京都・大阪の3府以外はすべて県に格下げされ、以後、府として残ったのはこの3つだけとなりました。
廃藩置県で県が爆発的に増加
明治4年(1871年)には、廃藩置県が実施されました。
これは、全国の「藩」を廃止し、代わりに「県」を設置するという制度改革です。これにより、日本全国には一時的に3府302県という大量の行政区画が存在することになります。
その後、県の整理や統合が進められ、明治16年(1883年)には3府44県にまで整理されました。
北海道は最初「道」ではなかった?
北海道は今でこそ「道」として分類されていますが、もともとは「函館県・札幌県・根室県」という3つの県が存在していました。
しかし明治19年(1886年)に「北海道庁」が設置され、それら3県は統合されて「1庁」となります。
このとき日本は「3府41県1庁」という区分になり、北海道はまだ“道”とは呼ばれていなかったのです。
「東京都」と「北海道」が誕生した経緯
現在の「東京都」が生まれたのは昭和18年(1943年)。
それまで存在していた東京府と東京市が統合・廃止され、「東京都」として一本化されたのがはじまりです。これにより、特別な自治体としての「都」が誕生しました。
さらに昭和22年(1947年)には、「北海道庁」が「北海道」と改称され、ここでようやく“道”という区分が成立しました。
結局、全部「県」ではダメなの?
結論から言えば、行政機能的にはすべて「県」に統一することも可能です。
しかし、「都」「道」「府」にはそれぞれ歴史的・文化的な背景があるため、今日でもその呼称が尊重され、維持されているのです。
たとえば、東京都は首都としての象徴的意味を持ち、北海道は他県と異なる広大な地理的条件と開拓の歴史を背負っています。大阪府と京都府も、明治初期から「重要な都市」として扱われてきた歴史があり、今でも府のままとなっています。
おわりに
「都・道・府・県」は一見ややこしく感じるかもしれませんが、それぞれにしっかりとした歴史的理由があります。
単なる行政用語ではなく、日本の歩んできた歴史の一部として知っておくと、より身近に感じられるかもしれませんね。