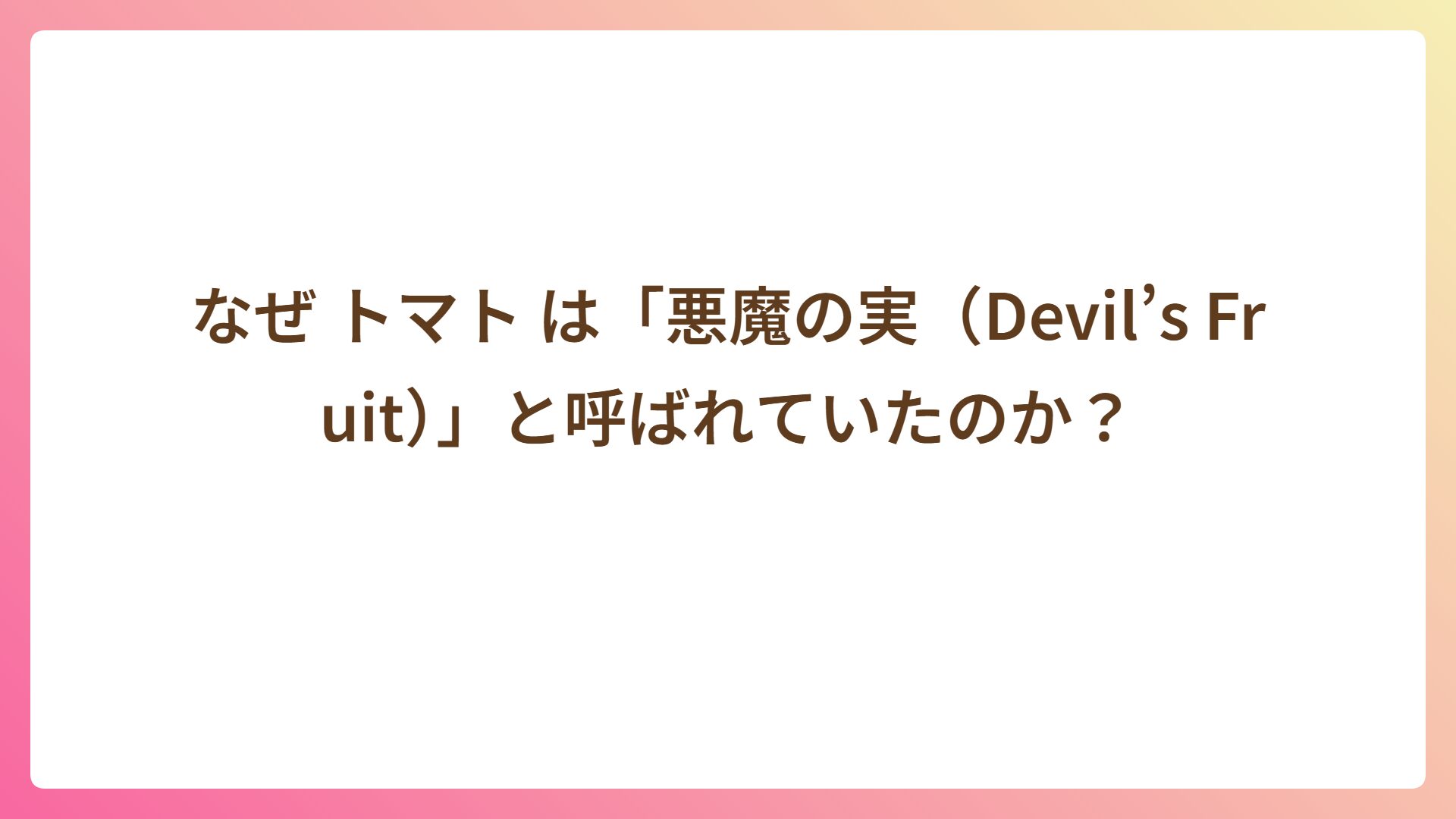赤くて丸いトマト。現代ではサラダに、パスタに、ピザにと大活躍ですが、実はかつてヨーロッパでは 「毒リンゴ」「悪魔の実(Devil’s Fruit)」 とさえ呼ばれていました。なぜ、人類の食卓にこれほど自然に溶け込んだ野菜が、最初は“忌避される”存在だったのでしょうか?
その背景には、植物分類・食器の材質・文化的恐れなどが複雑に絡んでいます。
主な理由とその経緯
以下、トマトが「悪魔の実」と呼ばれた主な理由を整理します。
- 分類上“危険とされた植物の仲間”だった
トマトは ナス科 に属しており、同科には有毒とされた植物(例:ベラドンナなど)も含まれています。MOLD :: Designing the Future of Food+2Laidback Gardener+2
新大陸から渡来した当初、欧州の人々にはこの属の植物は「観賞用・薬用」などが多く、食用として受け入れられるのに時間がかかりました。
- 「毒りんご/悪魔の実」という呼称の由来
・英語史料では、“globes of the devil” “devil’s fruit”といった記述があります。ウィキペディア+1
・また、トマトを盛った貴族が鉛を多く含むピューター(錫合金)製皿を使っており、酸性のトマトが鉛を溶出させて鉛中毒を起こしたという錯誤も影響しています。Laidback Gardener+1
こうした複数の要因が合わさって、「この赤い果実は怪しい」「悪魔の仕業ではないか」というイメージが生まれました。
- 視覚的・文化的な印象も影響
トマトの鮮やかな赤色、未熟果の緑色、丸い形状などが、当時の人々には「見慣れぬ果実」「毒草っぽい」と映った可能性があります。Medium
また、「りんご=誘惑」「りんご=原罪」のイメージがリンゴ以外の赤い果実へも転用され、トマトが類似の象徴と見なされたという分析もあります。ウィキペディア
- 受容への転換と「黄金のりんご」呼び名
一方で、イタリア語ではトマトを “pomodoro(ポモドーロ)=金のりんご” とも呼び、好意的な呼称も出ています。Cesta na talíř+1
つまり、トマトの評価は「恐れ→試行→受容」という文化的変遷をたどったわけです。
なぜ「悪魔の実」という言葉が残ったのか?
- 科学的・医学的な誤解(ナス科=毒草)
- 食器・食文化・社会階層が絡んだ事故と噂(ピューター皿+酸=鉛溶出)
- 見慣れぬ新種植物への不信と象徴的な赤色
これらが重なり合って、トマトには「危険」「異物」「悪魔的」というレッテルが貼られ、長い間食用として広まらなかったのです。現代では栄養価や調理法で人気を博していますが、その歴史を知ると、「悪魔の実」と呼ばれた過去があるからこそ今があるということが見えてきます。
まとめ
トマトが「悪魔の実」と呼ばれたのは、単なる誇張ではなく、当時の植物分類・食器材質・文化的信仰が背景にあった「合理的な恐れ」でもありました。
今日、私たちが安心してトマトを食べられるのは、先人たちの試行錯誤と受容があったからこそ。次にトマトを味わうときは、その赤い果実に刻まれた“恐れから受容への旅”を思い出してみてはいかがでしょうか。