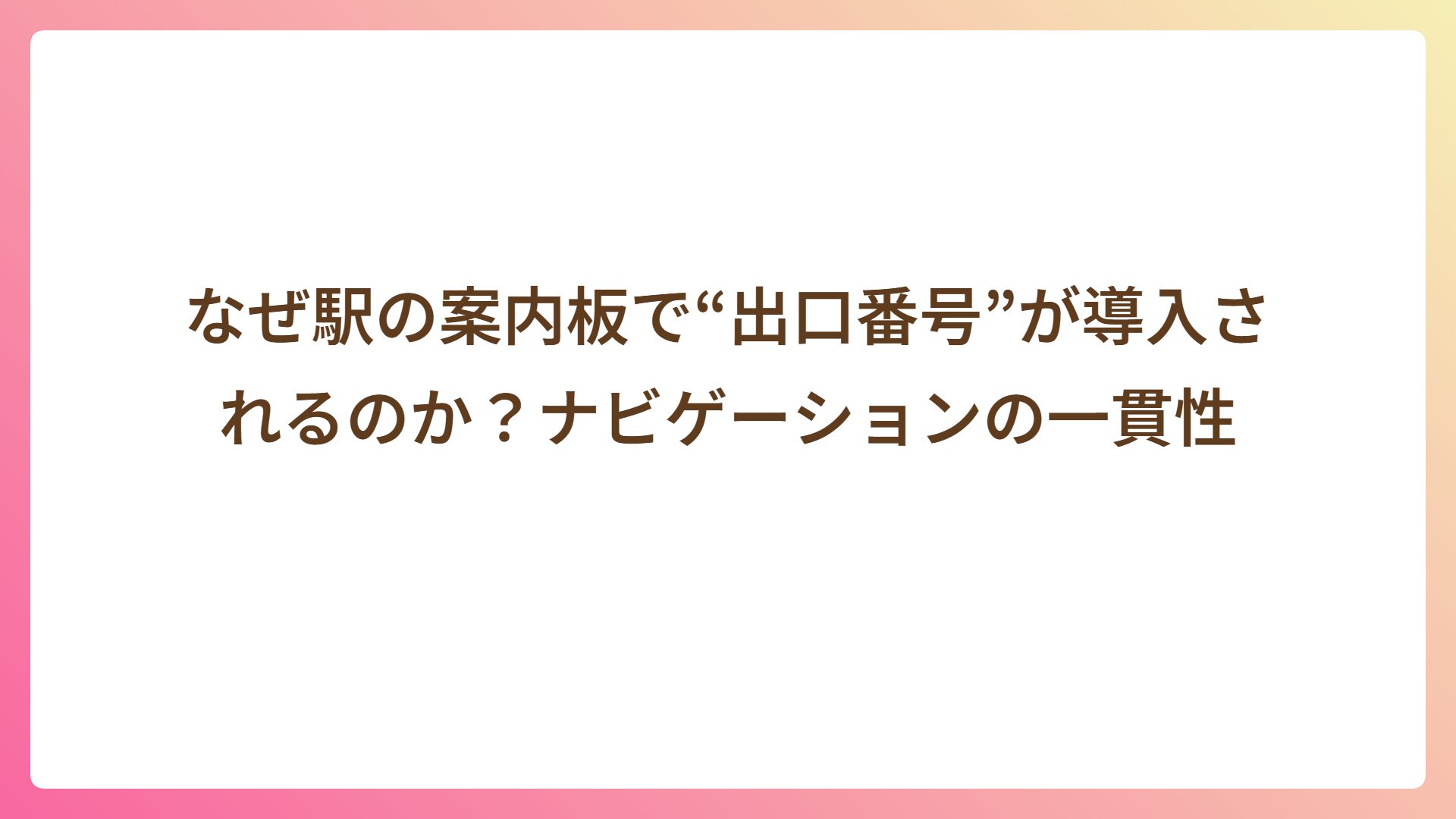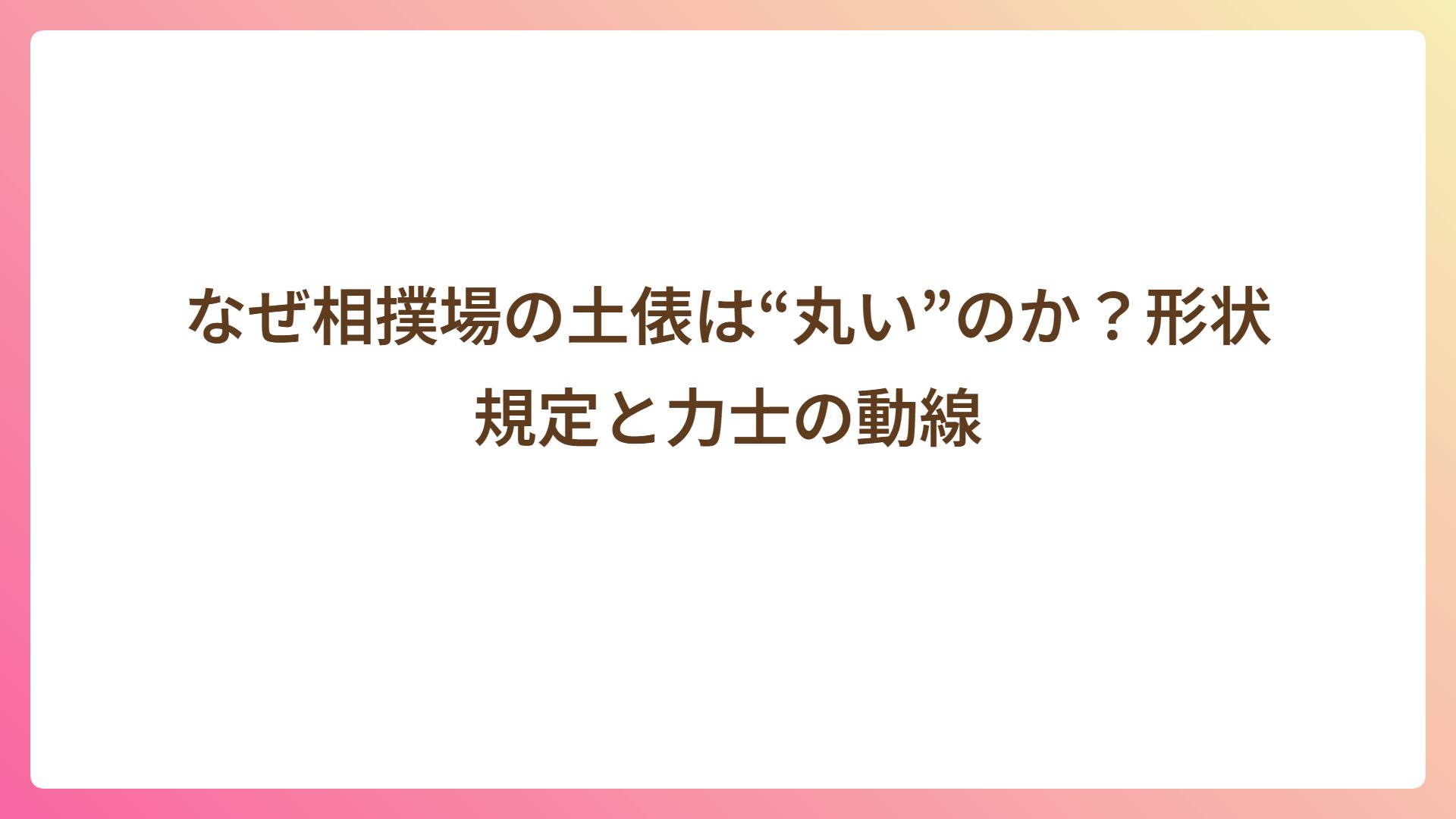なぜ鳥は電線に止まっても感電しないのか?電位差でわかる安全の仕組み
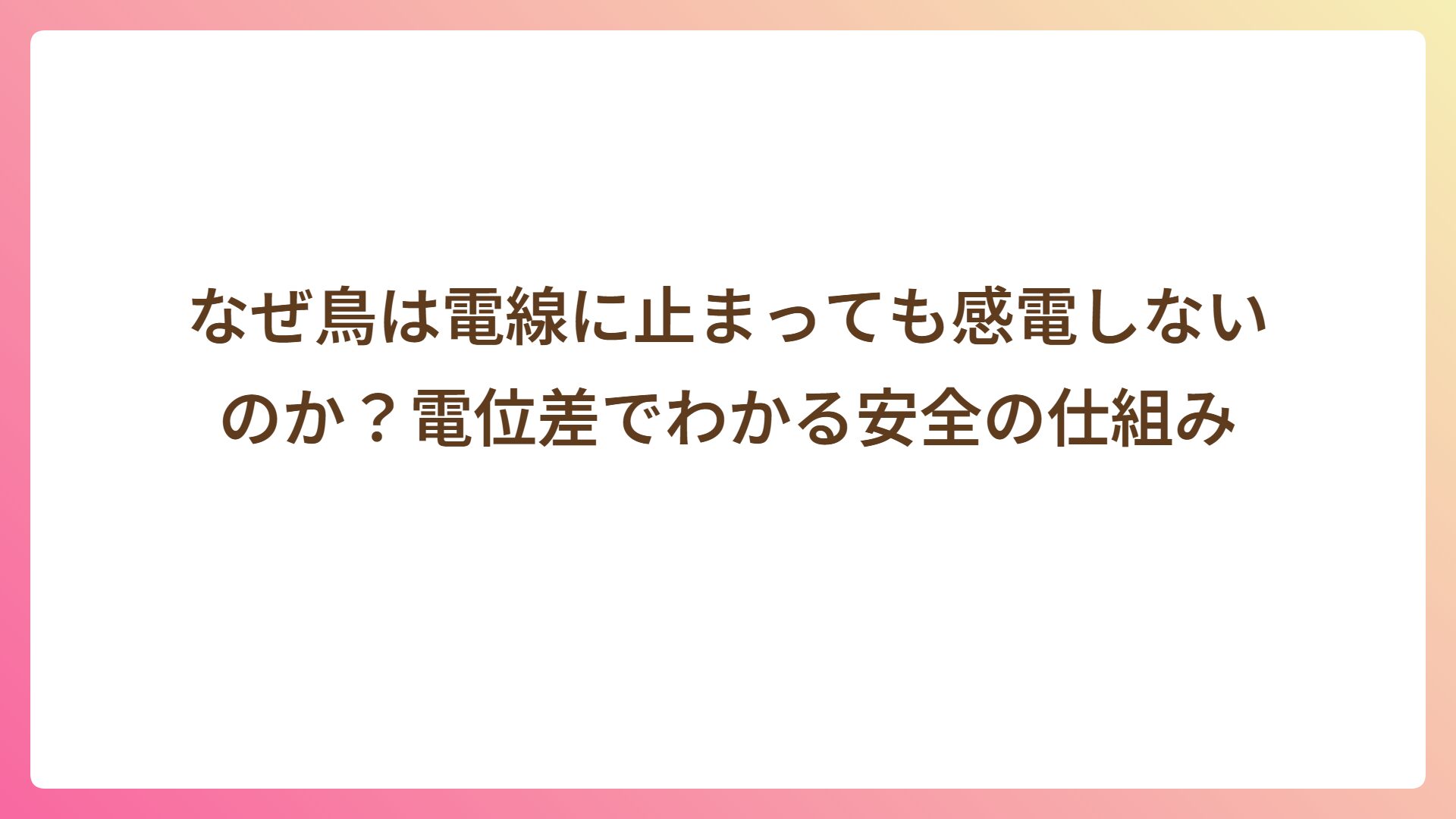
街を見上げると、電線に小鳥が並んで止まっている光景をよく見かけます。
しかし、あの電線には高電圧(数千ボルト)が流れています。
「なぜ鳥は感電しないの?」──誰もが一度は疑問に思う現象です。
実は、感電を防ぐカギは“電位差”と“電流の通り道”にあります。
感電とは「電気が体を通り抜ける」こと
まず前提として、感電は「電気が体の中を通り抜ける」ときに起こります。
電気(電流)は、電位の高い場所から低い場所へ流れる性質を持っています。
つまり、体の両端に電位差が生じたときにだけ電流が流れるのです。
| 状況 | 電流の流れ | 感電する? |
|---|---|---|
| 電位差がある(例:片手が電線・もう一方が地面) | 電流が流れる | 〇 感電する |
| 電位差がない(例:両足が同じ電線上) | 電流が流れない | ✕ 感電しない |
つまり、電流が“入口”と“出口”を見つけられなければ、
電気は体の中を通り抜けられず、感電は起こらないのです。
鳥は電線上で“同じ電位”の上にいる
鳥が電線に止まるとき、両足は同じ1本の電線に接しています。
そのため、両足の間に電位差がほとんどありません。
電線全体はたしかに高電圧ですが、
電線の上の任意の2点間で生じる電位差はごくわずか。
結果として、鳥の体内には電流が流れず、感電しないのです。
つまり鳥は「高電圧の空間」にいるけれど、
電気的には電線と一体化した状態になっているということです。
感電するのは「2つの異なる電位に触れたとき」
では、鳥でも感電してしまう場合はあるのでしょうか?
答えは「2本の電線や地面に同時に触れたとき」です。
高圧線は電線ごとに異なる電位(数千〜数万Vの差)を持っています。
もし翼やくちばしが誤って隣の線に触れると、
高電位から低電位へ強い電流が体を通過し、即座に感電死します。
同じように、人間が電線に触れた場合も、
地面に立ったまま電線をつかめば地面との電位差(約0V)が生じて電流が流れ、
危険な感電となるわけです。
電線を扱う作業員が安全なのも同じ原理
電線工事の作業員が高所で電線に触れても感電しないケースがあります。
これは、作業員が絶縁装備をしており、
かつ他の電位(地面など)に接触していないからです。
作業員自身が電線と同じ電位に“浮いた状態”になっているため、
鳥と同様に電流が通る経路がない=感電しないのです。
ただし、安全帯や工具が別の線や鉄塔に触れると、
一瞬で感電する危険があるため、厳重な管理が行われています。
高電圧でも「電位差がなければ安全」という事実
このように、電気の危険性は電圧の高さそのものではなく、
電位差の有無によって決まります。
たとえ10万ボルトの電線に触れても、
完全に電気的に浮いていて他と接していなければ感電しません。
逆に、100ボルトでも両手で触れれば電位差が生じ、感電します。
つまり、重要なのは“電圧の値”ではなく、
電流が通る道があるかどうかなのです。
まとめ:鳥が感電しないのは「電流の通り道」がないから
鳥が電線に止まっても感電しない理由は、
- 両足が同じ電線上にあり、電位差がない
- 電流が体を通り抜ける経路が存在しない
- 電線と同じ電位になっているため、電気的に安定している
というシンプルな物理法則によるものです。
つまり、電線の上の鳥は危険な高電圧の中にいながら、
「電気的には安全な島」に乗っているような状態なのです。