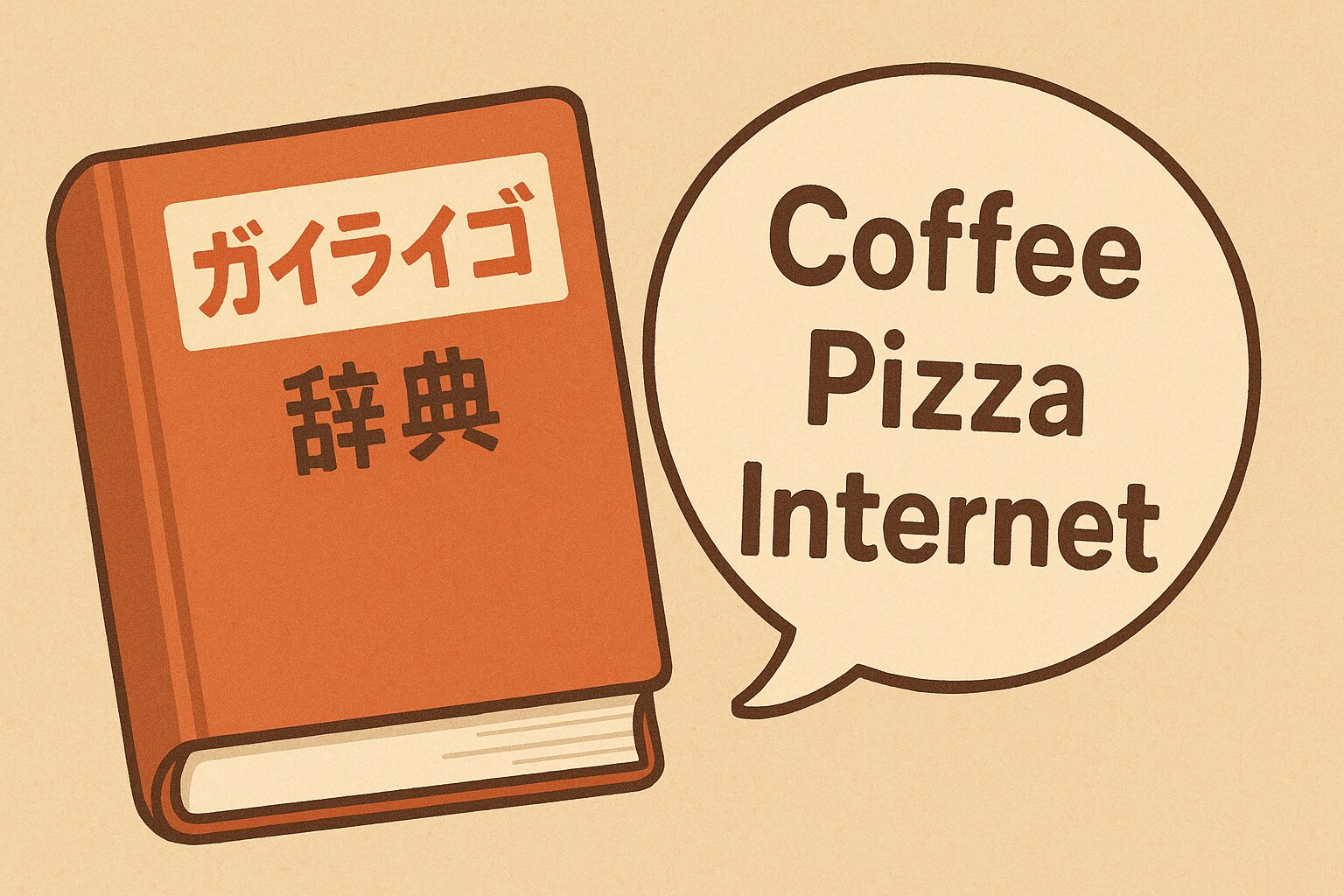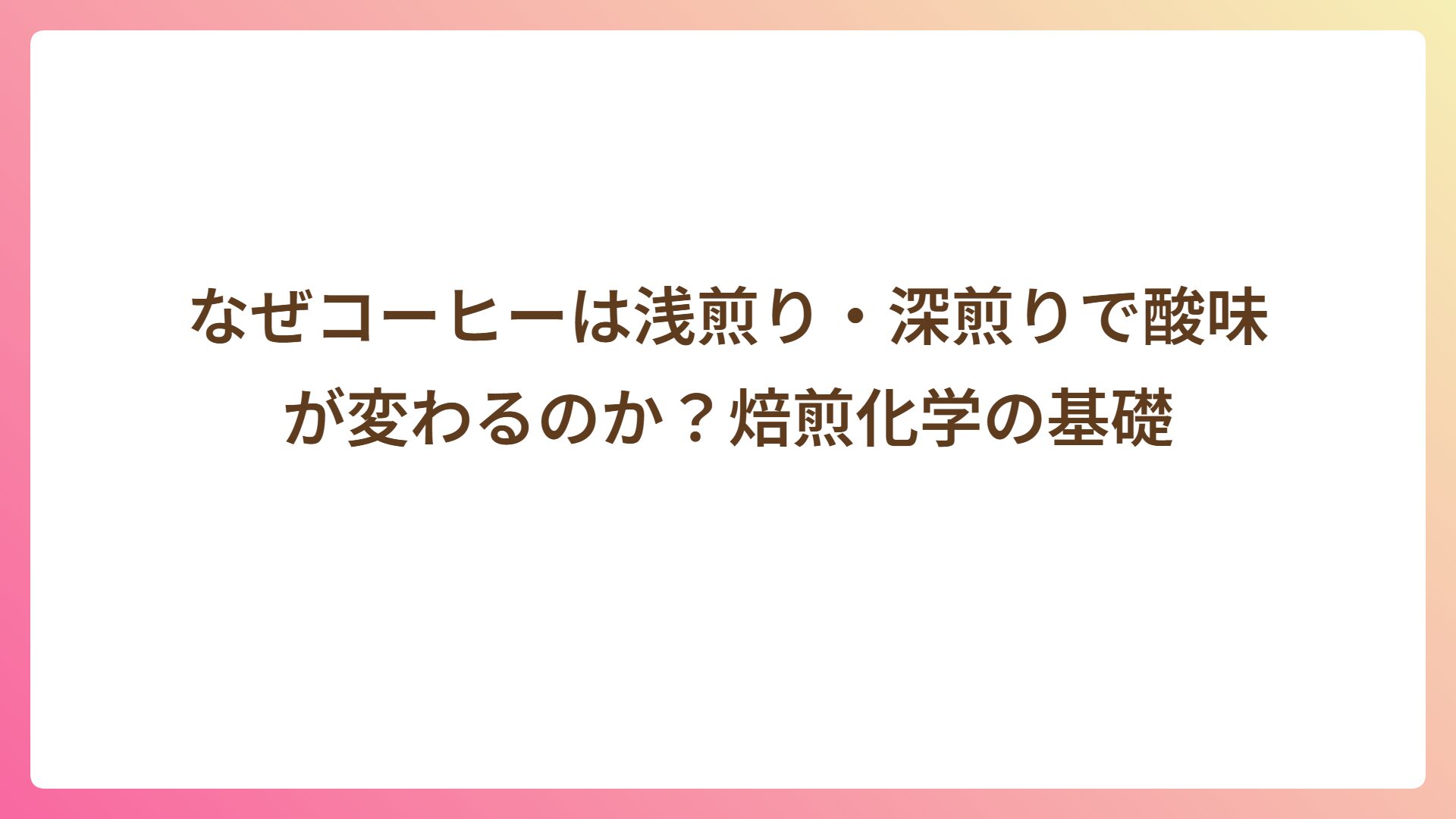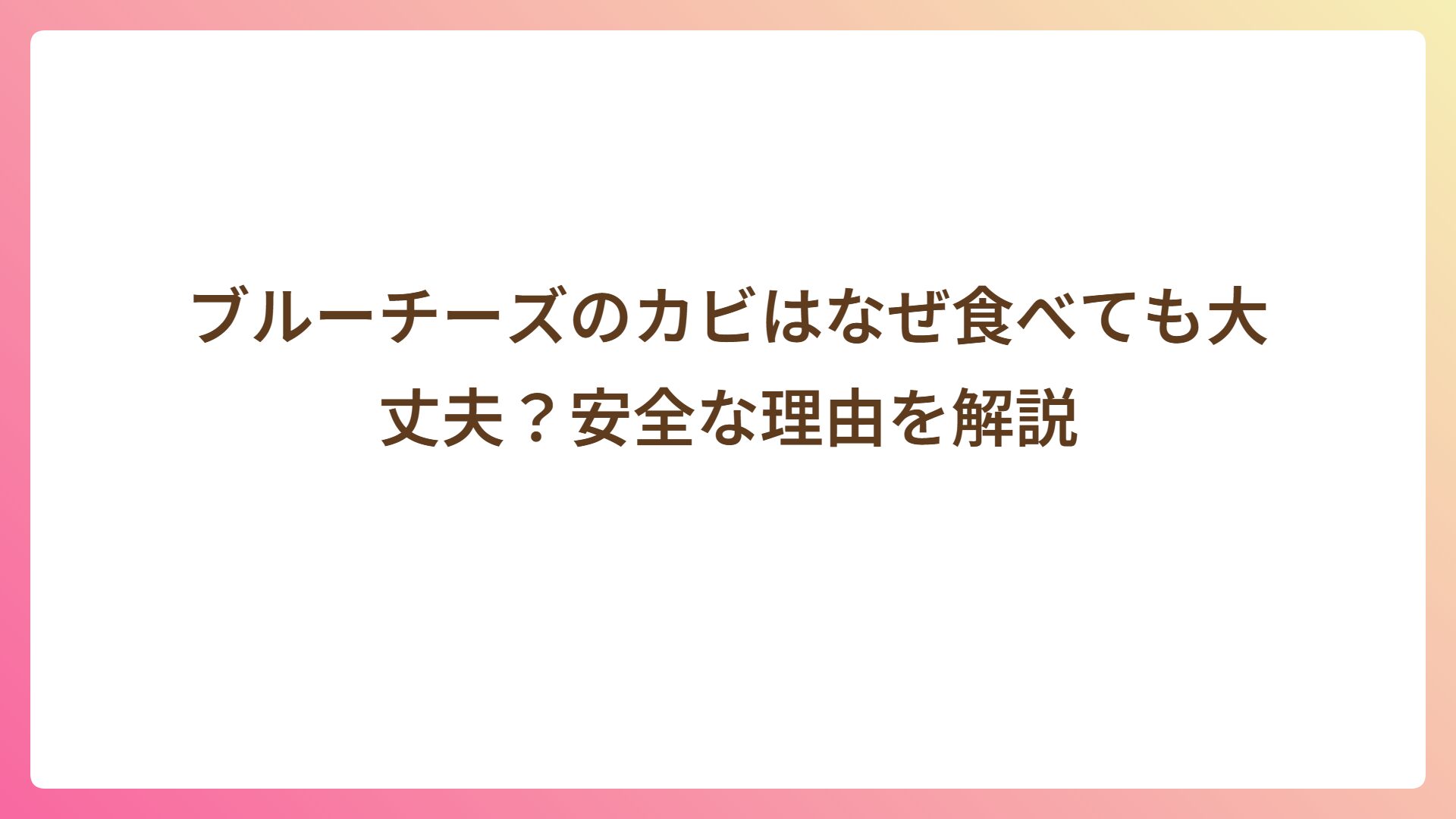なぜ観光地の“ご当地マンホール”が増えたのか?地域PRと蓋の耐久性の関係
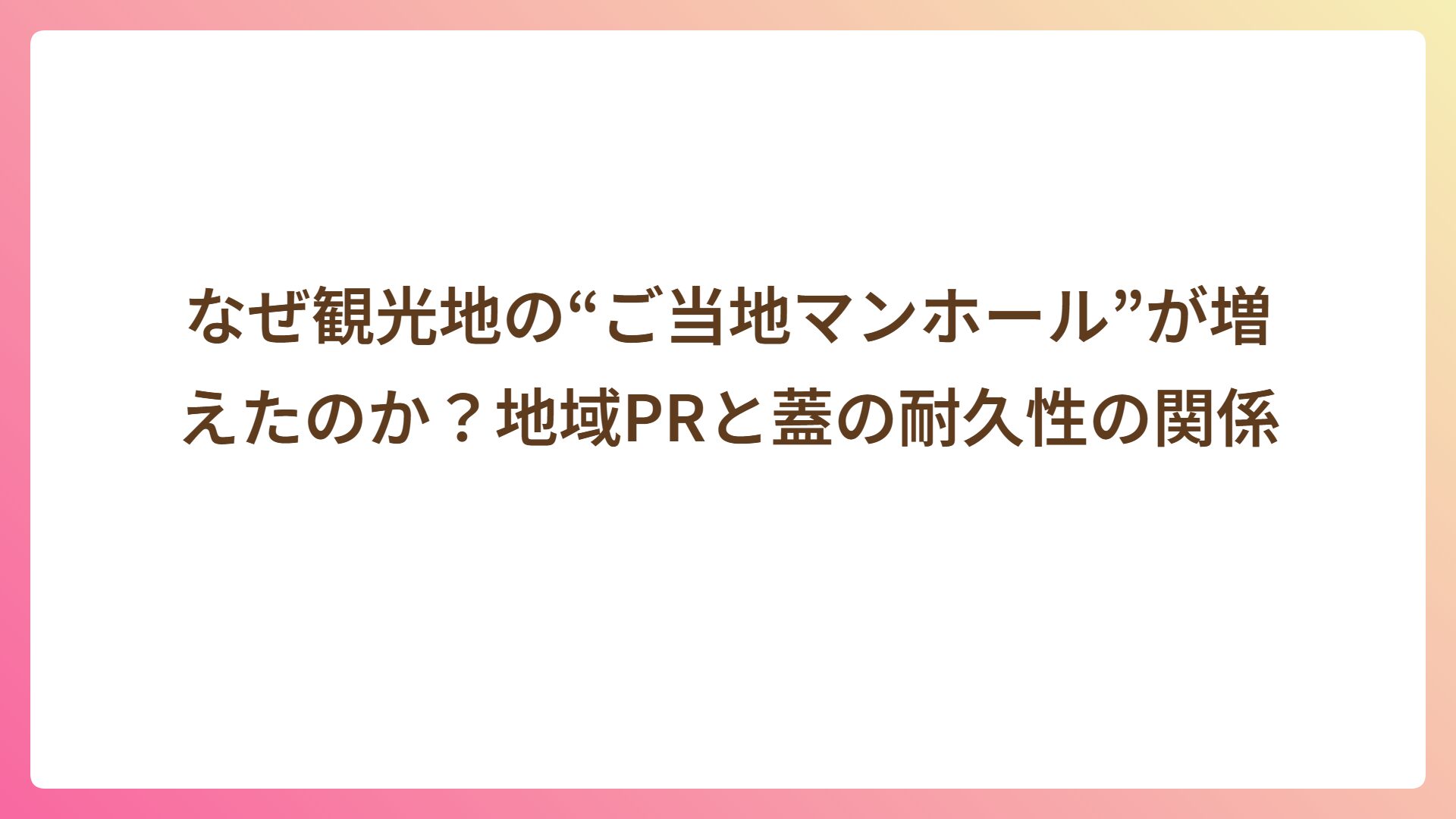
観光地の道を歩いていて、キャラクターや名所が描かれたカラフルなマンホールを見かけたことはありませんか?
「こんなところまで凝ってる!」と写真を撮る人も多く、今や立派な観光資源のひとつ。
しかし、なぜ全国で“ご当地マンホール”が急増しているのでしょうか?
この記事では、地域PRの戦略と、蓋そのものの耐久性向上という2つの観点からその理由をひもときます。
ご当地マンホールとは?全国で広がる“路上アート”
ご当地マンホールとは、各自治体が地域の特色をデザインした装飾付きのマンホール蓋のことです。
図柄には、市の花や木、名所、ゆるキャラ、アニメ作品などが描かれ、
「歩く人に楽しんでもらう」「地域への愛着を深めてもらう」目的で設置されています。
特にSNS時代に入ってからは、
「マンホール巡り」や「マンホールカード」といった文化も生まれ、
観光のきっかけや街歩きのモチベーションとして注目を集めています。
理由①:地域PR・観光振興のためのデザイン活用
ご当地マンホールが広がった最大の理由は、地域のPRツールとしての効果です。
1980年代、下水道普及率がまだ低かった時期に、建設省(現・国土交通省)が
「市町村ごとに個性的なデザインを導入してもいい」と推奨したことがきっかけでした。
その狙いは、住民に下水道への理解を深めてもらうこと。
無機質なインフラに「親しみ」や「誇り」を感じてもらうため、
各地で地元の花やシンボルをデザインに取り入れる動きが始まりました。
そこから時代が進み、SNSやスマートフォンの普及によって、
今では「写真映えする観光素材」としても注目されるようになりました。
特にアニメ・特撮とのコラボマンホールは、“聖地巡礼”効果で多くの観光客を呼び込んでいます。
理由②:カラーデザインを支える高耐久塗装技術
近年のご当地マンホールがカラフルに進化した背景には、素材と塗装技術の向上があります。
従来のマンホールは黒一色の鋳鉄製でしたが、現在は次のような技術が導入されています。
- 耐熱性・耐候性のあるウレタン系塗料で長期間色落ちしにくい
- サンドブラスト加工で塗料の密着度を高める
- 紫外線や酸性雨への耐性を持つ表面処理
これにより、直射日光や雨にさらされても10年以上鮮やかさを保てるようになりました。
デザイン性だけでなく、メンテナンスコストの抑制にもつながっています。
理由③:鋳物メーカーの参入と“産業の活性化”
ご当地マンホールの普及は、地場産業との連携にも大きく貢献しています。
多くのマンホール蓋は、長野県や埼玉県などの伝統的な鋳物メーカーが手がけています。
これらの企業は高精度の鋳造技術を持ち、近年では3Dデータやレーザー加工を活用して
細部まで緻密なデザインを再現できるようになりました。
その結果、自治体からの発注が増え、地域の鋳物産業そのものの活性化にもつながっています。
“街の顔”としてのマンホールが、実は地元企業の技術のショーケースになっているのです。
理由④:観光×インフラという新しい価値づくり
観光地では、風景や建物に手を加えずに新たな魅力を生む方法として、
「地面をデザインする」アプローチが注目されています。
マンホールは設置場所が公共空間であり、追加の用地や施設を必要としないのが強みです。
街歩きの中で自然に目に入り、写真を撮るだけでSNS拡散にもつながります。
自治体にとっては、
- 観光客が街を歩く導線を作れる
- 下水道事業への理解を広められる
- 維持費も抑えられる
という“一石三鳥”の施策なのです。
まとめ:ご当地マンホールは「街の広告塔」
ご当地マンホールが増えた理由は、
- 地域PR・観光促進のためのデザイン戦略
- 耐久性を支える素材・塗装技術の進化
- 地場産業の活用と経済波及効果
という3つの要素が組み合わさった結果です。
かつては下水道の“蓋”だったものが、いまや街の個性を発信するメディアへ。
何気なく踏んでいる足元に、その地域の文化と技術が詰まっているのです。