なぜ高速道路の照明はオレンジ色が多いのか?ナトリウム灯と雨天時の視界確保
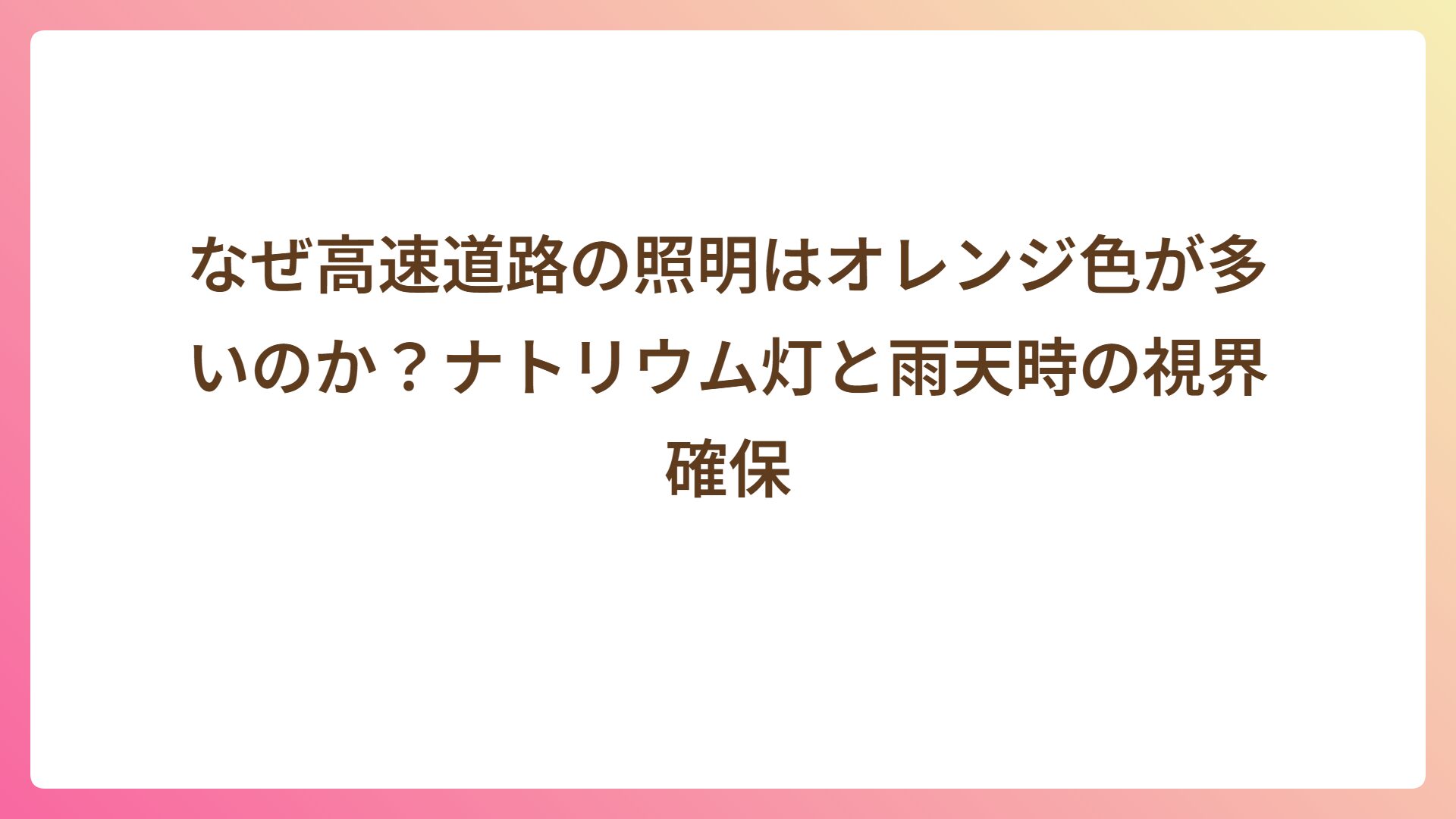
夜の高速道路を走っていると、街灯が白ではなくオレンジ色であることに気づく人も多いでしょう。
街中の白いLED照明と違い、高速道路では温かみのあるオレンジ光が長く使われています。
実はこの色には、霧・雨・スピード・省エネといった条件を満たすための明確な理由があるのです。
この記事では、高速道路の照明がオレンジ色(ナトリウム灯)である理由を、光の波長と安全設計の観点から解説します。
理由①:オレンジ色の光は“霧や雨に強い”
オレンジ色の照明が選ばれた最大の理由は、悪天候時の視認性にあります。
光は波長によって散乱しやすさが異なり、
- 青や白(短波長) → 水滴や霧で散乱しやすい
- 赤やオレンジ(長波長) → まっすぐ届きやすい
という性質を持っています。
つまり、オレンジ色の光は霧・雨・雪などで減衰しにくく、遠くまで届くのです。
高速道路では時速100km前後で走るため、遠方まで視認できることが何より重要。
そのため、短波長の白色光よりも長波長のオレンジ光が採用されています。
理由②:ナトリウム灯は“非常に高効率”な光源だった
高速道路で長く使われてきたのは、高圧ナトリウムランプ(HPS:High Pressure Sodium Lamp)と呼ばれる照明です。
特徴は以下の通り:
- 発光効率:100〜150 lm/W(蛍光灯の約2倍)
- 寿命:1〜2万時間と長寿命
- 発熱が少なく寒冷地でも安定点灯
つまり、広範囲を少ない電力で照らせる理想的な街灯だったのです。
高速道路のように何十kmにもわたって照明を設置する場所では、
エネルギー効率とメンテナンス性の高さが特に重視されます。
理由③:運転中の“眩しさ”を抑えるため
白色光は波長が短く、眩しさ(グレア)を感じやすいという特性があります。
夜間運転では、明るすぎる照明がかえって視認性を下げることも。
オレンジ色の光は、
- コントラストを保ちながらも柔らかい光
- 照らされた路面の反射が穏やか
- 対向車ドライバーの目に優しい
といった視覚的な快適性をもたらします。
長距離運転でも目の疲れを抑えられるため、
オレンジ照明は「夜間運転に優しい光」として選ばれてきました。
理由④:ナトリウム灯の“単色性”でコントラストが際立つ
ナトリウムランプの光は、主に589nm付近の黄橙色単一波長を発します。
この単色性によって、
- 路面標示(白線や矢印)がはっきり浮かび上がる
- 対象物の輪郭が見やすい
- 路面の凹凸が陰影として強調される
といった視界の明瞭化効果が得られます。
夜間のドライバーにとっては、明るさよりも「コントラストの見やすさ」が重要。
オレンジ光はその点で非常に理想的な光なのです。
理由⑤:高圧ナトリウム灯は“冬季・霧地域”でも安定点灯
ナトリウム灯は気温の影響を受けにくく、
−20℃前後でも安定して点灯します。
そのため、東北・北陸・山岳地帯の高速道路では長年重宝されてきました。
また、霧が発生しやすい地域では、
白色光よりオレンジ光のほうが反射しにくく視界が確保しやすいため、
安全上の理由でも採用が続けられています。
理由⑥:近年は“白色LED化”が進行中
とはいえ現在では、ナトリウム灯から白色LED照明への置き換えが進んでいます。
LED化の理由:
- 消費電力がさらに低い(効率150 lm/W以上)
- 寿命が長い(約5万時間)
- 照射方向を制御できる
ただし、LEDは青白い光が霧で散乱しやすいため、
最近の道路照明は中間色(電球色や中白色)に調整されるケースが増えています。
理由⑦:LEDでも“オレンジ寄り”の色が選ばれる傾向
最新のLED照明でも、高速道路では完全な白ではなく、
色温度2700〜3500K程度の暖色系が採用されることが多くなっています。
これは、
- 眩しさを抑える
- 雨天でも見やすい
- 従来のナトリウム灯と違和感がない
といった理由から、「ナトリウム灯の特性を受け継いだLED照明」として設計されているためです。
まとめ:オレンジ光は“悪天候と長距離運転に強い光”
高速道路の照明がオレンジ色なのは、
- 霧・雨・雪でも見やすい長波長の光だから
- ナトリウム灯が省エネで高効率だったから
- 眩しさを抑えて長時間運転でも疲れにくいから
- 白線や標識を際立たせる単色性があるから
といった安全性・効率性・快適性のすべてを兼ね備えているためです。
つまり、あのオレンジの光は単なる「昔の照明」ではなく、
高速道路を安全に走るために計算された“機能色”なのです。






